大川興業のお芝居、Lock'n Roll、は、「暗闇演劇」という、本来ならば「視覚芸術」であるところの演劇を、視覚表現をほとんど排除して、音声表現を中心として成立させたものである。
ふだんでも、小さな芝居小屋に入ると、隣同士がくっつきあっており、体を自由に動かせない。
また大半の芝居は開演前に一度暗転し、私たちは、ほんの一瞬であるとはいえ、視覚を奪われる経験も、少なくとも芝居小屋においては、していなくもない。
しかしこの「暗闇演劇」は、暗転が常態であり、そのままほとんど最後まで暗転したまま物語は進む。
芝居の世界へと参入するためのイニシエーション(通過儀礼)ではなく、そのまま暗闇が舞台となって、芝居が続く。
もちろん日常において、そういった体験はめったにない。
2時間近く、何も見えない。基本的に、体を移動することもできない。そういう状態にいる観客は、すでに、この作品の主人公と近い状態に自分がいることに、気づかされる。
大川興業は、これまでも、視力を失った人を主人公にしたり、匂いに焦点をあてたり、音のもつ可能性を探ってみたり、とさまざまな実験的作品を世に問うてきたが、今回の「Lock'n Roll」は、「閉じ込め症候群」になった人物が主人公である。
モロ師岡演ずる主人公は、芝居の最初から、病院のベッドに寝たままで、しかも、視覚が奪われた状態で登場する。
そのため、私たち観客もまた、最初から真っ暗な舞台をみつめながら、声だけを聞く。
注:本来のこの「閉じ込め症候群」は、眼とまぶただけは動かせる場合もあるが、本作品では、それもできない状態であるという前提で物語は進む。
つまり、この芝居の巧みなところは、こうした視覚や身体動作の不自由さを、観客が不可避的に共有する点にある。
観客は他人事ではなく、自分自身の感覚の状態を主人公と分かち合いつつ、物語にかかわるわけである。
主人公は、動くことも、見ることもできないが、耳は聞こえている。
聞こえているが、それに反応することができない。完全なる受身の状態である。
そして私たち観客も、主人公と同じように、ただ、まわりの登場人物の声が聞こえるなか、同時に、主人公が発した独り言を、聞くだけである。
つまり、主人公は、まったく周囲の人たちのコミュニケーションには一人だけ参加していないのである。いや、少なくとも言語コミュニケーションとしては、何も成立していないのである。
まわりは勝手に推測し、一方的に語り、自分だけで納得して会話ならぬ会話を続ける。
これは、とても歯痒い。
そうだ、とも、違う、とも言えない。何もリアクションできない。
おそらく、本作品のような閉じ込め症候群の患者のみならず、互いに言語を理解していない外国人や赤子や動物、さらには植物などと対したときにも、やや似たような経験は、起こりうるだろうから、誰でも似たような経験はあると思われる。
相手に通じているかどうか分からなくても、自分の意志や感情を伝えるときは、とても心もとない。
話が通じない、気持ちが伝わらないというのは、とても、もどかしい。
しかし、逆説的であるが、私たちは、言葉が通じる相手のほうが、かえってうまく通じない、という経験もしていることだろう。
最初から通じないと思っている方が、かえって、相手の真意を理解しようと努力することもある。
少なくともこの寝たきりの主人公のまわりに集まってくる人たちは、みな、主人公とこれまで以上に、何かを伝えようとしている。または、相手を理解しようとする。
その際に、自然(=盆栽)と最先端技術(=脳波の運動によって動くモビルスーツ)の両極を持ちだしたところが、また、興味深かった。
ちなみに、ちらしの表紙は、「盆栽カー」が疾走している写真である。この、やはりここでも、自然と技術が融合している。
この芝居を見て、個人的には、二つのことを思い出した。
一つは、昨年永眠した我が家のネコ「シナモン」との、「死」という「点」をはさんだその前後のプロセスのこと。
足腰が立たなくなり、目の輝きがぼんうやりとし、力が弱くなり、にもかかわらず、最後に体が伸ばされ、そして、呼吸が止まり、身体が次第に冷たくなり、硬直しはじめ、排泄物や涙などが流れ出た。
それでもまだ3日ほど、一緒にいた。
「看取る」ということは、生前のみならず死後にも続く。
反応のない亡骸にも、声をかけるし、なでもする。
それが自然に思えた。
そのときの自分の感情とこの芝居にただよう感覚が、かなり近いと自分では思っている。
「死」とは「点」ではなく、プロセスである、というのが私の思いである。
また、もう一つは、この体験の理論的な裏付けのようなものであるが、修士論文でテーマにした「自然死」と「脳死」の問題である。
これについては、明日あらためて書こうと思う。
*主人公を演ずるモロ師岡と、総裁である大川豊による本芝居についてのショート・トークがYouTubeにアップされている。
↓
こちら
ふだんでも、小さな芝居小屋に入ると、隣同士がくっつきあっており、体を自由に動かせない。
また大半の芝居は開演前に一度暗転し、私たちは、ほんの一瞬であるとはいえ、視覚を奪われる経験も、少なくとも芝居小屋においては、していなくもない。
しかしこの「暗闇演劇」は、暗転が常態であり、そのままほとんど最後まで暗転したまま物語は進む。
芝居の世界へと参入するためのイニシエーション(通過儀礼)ではなく、そのまま暗闇が舞台となって、芝居が続く。
もちろん日常において、そういった体験はめったにない。
2時間近く、何も見えない。基本的に、体を移動することもできない。そういう状態にいる観客は、すでに、この作品の主人公と近い状態に自分がいることに、気づかされる。
大川興業は、これまでも、視力を失った人を主人公にしたり、匂いに焦点をあてたり、音のもつ可能性を探ってみたり、とさまざまな実験的作品を世に問うてきたが、今回の「Lock'n Roll」は、「閉じ込め症候群」になった人物が主人公である。
モロ師岡演ずる主人公は、芝居の最初から、病院のベッドに寝たままで、しかも、視覚が奪われた状態で登場する。
そのため、私たち観客もまた、最初から真っ暗な舞台をみつめながら、声だけを聞く。
注:本来のこの「閉じ込め症候群」は、眼とまぶただけは動かせる場合もあるが、本作品では、それもできない状態であるという前提で物語は進む。
つまり、この芝居の巧みなところは、こうした視覚や身体動作の不自由さを、観客が不可避的に共有する点にある。
観客は他人事ではなく、自分自身の感覚の状態を主人公と分かち合いつつ、物語にかかわるわけである。
主人公は、動くことも、見ることもできないが、耳は聞こえている。
聞こえているが、それに反応することができない。完全なる受身の状態である。
そして私たち観客も、主人公と同じように、ただ、まわりの登場人物の声が聞こえるなか、同時に、主人公が発した独り言を、聞くだけである。
つまり、主人公は、まったく周囲の人たちのコミュニケーションには一人だけ参加していないのである。いや、少なくとも言語コミュニケーションとしては、何も成立していないのである。
まわりは勝手に推測し、一方的に語り、自分だけで納得して会話ならぬ会話を続ける。
これは、とても歯痒い。
そうだ、とも、違う、とも言えない。何もリアクションできない。
おそらく、本作品のような閉じ込め症候群の患者のみならず、互いに言語を理解していない外国人や赤子や動物、さらには植物などと対したときにも、やや似たような経験は、起こりうるだろうから、誰でも似たような経験はあると思われる。
相手に通じているかどうか分からなくても、自分の意志や感情を伝えるときは、とても心もとない。
話が通じない、気持ちが伝わらないというのは、とても、もどかしい。
しかし、逆説的であるが、私たちは、言葉が通じる相手のほうが、かえってうまく通じない、という経験もしていることだろう。
最初から通じないと思っている方が、かえって、相手の真意を理解しようと努力することもある。
少なくともこの寝たきりの主人公のまわりに集まってくる人たちは、みな、主人公とこれまで以上に、何かを伝えようとしている。または、相手を理解しようとする。
その際に、自然(=盆栽)と最先端技術(=脳波の運動によって動くモビルスーツ)の両極を持ちだしたところが、また、興味深かった。
ちなみに、ちらしの表紙は、「盆栽カー」が疾走している写真である。この、やはりここでも、自然と技術が融合している。
この芝居を見て、個人的には、二つのことを思い出した。
一つは、昨年永眠した我が家のネコ「シナモン」との、「死」という「点」をはさんだその前後のプロセスのこと。
足腰が立たなくなり、目の輝きがぼんうやりとし、力が弱くなり、にもかかわらず、最後に体が伸ばされ、そして、呼吸が止まり、身体が次第に冷たくなり、硬直しはじめ、排泄物や涙などが流れ出た。
それでもまだ3日ほど、一緒にいた。
「看取る」ということは、生前のみならず死後にも続く。
反応のない亡骸にも、声をかけるし、なでもする。
それが自然に思えた。
そのときの自分の感情とこの芝居にただよう感覚が、かなり近いと自分では思っている。
「死」とは「点」ではなく、プロセスである、というのが私の思いである。
また、もう一つは、この体験の理論的な裏付けのようなものであるが、修士論文でテーマにした「自然死」と「脳死」の問題である。
これについては、明日あらためて書こうと思う。
*主人公を演ずるモロ師岡と、総裁である大川豊による本芝居についてのショート・トークがYouTubeにアップされている。
↓
こちら
- 日本インディーズ候補列伝(DVD付)/扶桑社
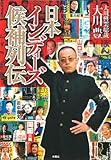
- ¥1,700
- Amazon.co.jp
- 金なら返せん! 天の巻 (幻冬舎アウトロー文庫)/幻冬舎
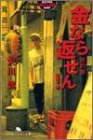
- ¥520
- Amazon.co.jp
