調べものをしていたところ、昨年5月に大阪高裁で、高齢者の方が入浴中に溺死し、損害保険会社などの傷害保険が支払われるか否かが争われた判決が出されたことを知りました(大阪高裁平成27年5月1日判決)。
厚生労働省の統計によると、1年間に約5000人もの方が風呂において溺死してしまっている実態があるとのことです。
また、この事案は保険法における「不慮の事故」の3要件のうちのひとつの「外来性」をどう考えるかという近年極めてホットな分野のひとつでもあります。

2.事実の概要
(1)D株式会社は、Y1(日本中小企業福祉事業財団)との間で、平成17年7月にDを共済契約者、代表取締役であったAを被共済者、受取人をD、死亡共済金を1000万円とする災害共済契約を締結した。
また、平成20年1月にDはY2(AIU損害保険)との間で、Dを保険契約者、Aを被保険者、保険金受取人をD、死亡保険金1000万円とする傷害保険契約を締結した。
(2)Y1の災害共済契約の共済約款には、「次の事由によって生じた災害については補償費を支払わない」との免責事由のひとつとして、「被共済者の疾病、脳疾患又は心神喪失」との、いわゆる「疾病免責条項」が規定されていた。
Y2の傷害保険契約の普通保険約款には、免責事由のひとつとして、「被保険者の脳疾患、疾病又は心神喪失」との、これもいわゆる「疾病免責条項」が規定されていた。
(3)平成23年2月6日午前3時ごろ、A(78歳)が、自宅の浴槽で43度に設定された湯に仰向けに浸かり死亡しているところをAの妻であるBにより発見された。
同日、死体を検案したC医師は、死体検案書に、直接の死因を溺死、溺死の原因を虚血性心疾患、虚血性心疾患の原因を高血圧症と記載したほか、糖尿病等がこれらの傷病経過に影響をおよぼした旨を記載した。
なお、Aの司法解剖は実施されなかった。
D社は平成23年9月21日、大阪地裁において破産手続開始の決定を受け、Xが破産管財人に選任された。
XはY1に対して災害共済契約に基づく保険金1000万円および遅延損害金の支払いを請求し、また、Y2に対して傷害保険契約に基づく保険金1000万円および遅延損害金の支払いを請求したのが本件訴訟である。
(4)地裁の審理において、Yらは、Aの直接の死因は溺死であることを認めた上で、本件は疾病免責条項が適用されると主張した。
つまり、Aは事故当時78歳と高齢であり、高血圧症や糖尿病等に罹患していたことから、血管内皮細胞が加齢に伴う程度を超えて著しく損傷し、虚血性心疾患の発症のリスクが高まっていたところ、冬の夜に43度という高温の風呂の湯につかったため、血圧が急激に変動し、体を動かした際に心臓への還流血液量が低下する虚血性心疾患という「疾病」が発症し、脳虚血による意識障害が発生し、溺死したものと認めるのが相当と主張した。
またYらは、入浴中の急死に関する統計データなども提示して、Aに入浴時に循環血液量の減少を機序とする虚血性心疾患や低酸素脳症を発症した可能性も主張した。
これに対してXは、Aについて司法解剖が行われていないため、虚血性心疾患を発症したと断定することはできないこと、Aは事故当時、高血圧症や糖尿病は重度のものでなかったのであるから、虚血性心疾患を発症したと認められないなどとして、本件には疾病免責条項は適用されないと主張した。
(5)第一審判決(大阪地裁平成26年6月10日判決)は、A死亡の翌日のC医師のBへの説明内容などから、Aの直接の死因は溺死であり、Aが疾病を原因として溺死したことをYらは立証できていないとして、Xの請求を一部認容した。そのためYらが控訴。
3.判旨(大阪高裁平成27年5月1日判決・控訴棄却【確定】)
高裁判決はつぎのように判示し、結論として疾病免責条項の適用を認めず、Yらに対して保険金の支払いを命じました。
『Aが虚血性心疾患を発症したと認められるか検討する。(略)、(高血圧症および糖尿病について)主治医からも、特に危険な状態ではなく、むしろ、比較的良くコントロールされた状態であるなどと評価されていた(略)すると、Aの死亡当時、高血圧症および糖尿病の症状が重度の状態であったとまでは認められ(ない。)』
『したがって、Aが高血圧症や糖尿病に罹患していた事実や同人の喫煙歴から、直ちに同人が虚血性心疾患を発症したとの事実を推認することはできないというべきである。』
『次に、入浴中の事故に関する統計報告等について検討する。(略)(東京都監察医務院などの)報告によっても、入浴中急死について外因死と判断された例や、虚血性心疾患以外の原因が死因とされた例は、いずれも相当程度あることが認められる(略)以上によれば、入浴中の事故に関する上記の統計報告等を根拠としてAが虚血性心疾患を発症したと推認することはできない。』
『入浴中急死の機序は未だ解明されておらず、(略)専門家の間でも意見が分かれているのが現状である。』
『本件全証拠によってもAの溺水の原因を特定することは困難であるといわざるを得ず、Aが、Yらの主張する機序で虚血性心疾患を発症したことにより溺水したものと認定するには十分ではないものというべきである。したがって、Aが疾病を原因として溺水したことが立証されたとはいえないから、本件に疾病免責条項を適用することはできない。』
4.検討
(1)外来性と疾病免責条項に関する裁判所の判断枠組み
(a)従来の裁判例・通説
本件のような外来性と疾病免責条項の適用に関する事例、つまり、被保険者の死亡などの発生にあたり、事故などの外因性のものと疾病などの内因性の両方が重なり合って原因となっている悩ましい事案について、従来の学説はつぎのように整理していました。
つまり、傷害保険契約上、発生した傷害は外因性のものか内因性のものかのいずれであって、両者は理論的に両立しえないとの理解に立ち、疾病免責条項は、疾病と相当因果関係にある傷害が偶然性・外来性に欠け、傷害の原因とならないことを確認した当然の規定であり、したがって、保険金請求権者側は、傷害が外来のものであることだけでなく、傷害が被保険者の疾病によるものでないことまで立証しなくてはならないとする学説が多数説でした(請求原因説・西島梅治『保険法[第3版]』381頁、山下友信・竹濱修・洲崎博史・山本哲生『有斐閣アルマ保険法(1999)』271頁など)。
この時期の下級審判決もこれと同じ考え方を採用していました(てんかん発作を原因とする頭部打撲による脳挫傷等による死亡について外来性を否定した東京地裁平成8年11月21日判決、東京地裁平成12年9月19日判決、神戸高裁平成18年1月18日判決など)。
この従来の裁判例・通説においては、保険金請求者側の主張・立証のハードルが高すぎるという問題がありました。
(b)最高裁平成19年判決
しかしこのような裁判例・通説の大きな転換点となった最高裁判決が平成19年に現れました。
この判例(最高裁平成19年7月6日)は、パーキンソン病に罹患していた高齢(83歳)の被共済者が、もちをのどにつまらせて窒息、低酸素症による後遺症が残ったという事案です。
この最高裁平成19年判決は、「外来の事故とは、その文言上、被共済者の身体の外部からの作用による事故」とし、「請求者は、外部からの作用によって事故と被共済者の傷害との間に相当因果関係があることを主張、立証すれば足り、被共済者の傷害が被共済者の傷害が被共済者の疾病を原因として生じたものではないことまで主張、立証する責任を負うものではない」と判示し、請求者側の請求を認容しました。
つまり、保険金受取人側は外部からの作用によって事故と被保険者の傷害との間に相当因果関係があることを主張、立証すれば足り、一方、保険会社側は被保険者の傷害が被保険者の疾病に基づくものであることを立証しない限り、疾病免責条項は認められず、保険金を支払う義務を負うことになります(抗弁説・潘阿憲『保険法概説』297頁、最高裁平成19年7月6日、最高裁平成19年10月19日)
本件においても、Y保険会社らはAの直接の死因は溺死であることは認め、そのうえで疾病免責条項に該当すること、すなわち、Aの疾病を原因として本件の溺死が発生したことを主張・立証しようと試みており、Yらも抗弁説に立っています。
(c)高齢者の入浴中の溺死に関する最高裁平成25年判決
なお、高齢者が風呂で溺死をした事例については、最高裁平成25年7月11日判決が出されています。こちらは今回取り上げた事件とは逆に、被保険者の疾病性を認め、保険会社側の疾病免責を認める結論となっています。
すなわち、当該事案では死亡した被保険者に対して医師による死体検案および解剖が実施され、死体検案書が作成されています。
その結果、溺死した被保険者は心疾患を疑わせる胸痛、高血圧などの既往症があり、心肥大、心筋内の小繊維化、右冠動脈の約30%の狭窄などの病変があり、また事故当時被保険者は軽度の酩酊状態であったことなどが明らかになったとされています。
そのため、同人は虚血性心疾患を発症する状態にあったと裁判所は認定し、保険会社側の疾病免責条項の適用を認めています。
(深澤泰弘「浴槽内での溺死における傷害保険契約等の保険金等請求に対して、いわゆる疾病免責条項の適用を認め請求を棄却した事例」『損害保険研究』76巻2号311頁)
(2)立証の困難さ・立証の容易さ
ところで本件の溺死の事例をみると、司法解剖が実施されていない事案では、Aの疾病が虚血性心疾患を発症したと推認できるほど重篤なものであったこと、他の機序による可能性が合理的根拠をもって排除されること、などの条件を満たさないと保険会社側の立証は成功し難いように思われます。
保険会社側は本件の審理で、統計情報や医学的見解などを提示していますが、未だ未解明な部分が多い高齢者の溺死については、これらは裁判所の心証形成に対して説得力が低いようです。
このように、高齢者の風呂での溺死の問題は、平成19年の2件の最高裁判決以降は、保険会社側にとっては立証のハードルがかなり高く、その一方、保険金受取人など消費者側にとっては、従来より主張、立証の困難さがかなり緩和されたように思われます。
(3)生命保険会社の傷害保険について
ここまで取り上げてきたのは、損害保険会社の傷害保険と、それに類似する共済の傷害保険でした。
ところで、生命保険会社各社も傷害保険を扱っていますが、疾病免責の規定が損保と異なっています。
つまり、保険金の支払いの対象の原因となる「不慮の事故」の定義として「急激」「偶発」「外来」の3要件をあげたうえで、「外来」の定義で、「疾病や疾病に起因する外因等身体の内部に原因があるものは該当しません。」と規定するのが通常です。

(第一生命保険「傷害特約D条項」より)
ここで今回取り上げた損保型の傷害保険における疾病免責条項の考え方が生保型の傷害保険にもダイレクトにおよぶとする考え方もあるようです(白井正和『法学協会雑誌』125巻11号247頁)。
しかしこの点は、上であげた最高裁平成19年7月6日判決に関する最高裁の調査官解説は、同判決が約款の文言を重視していること、生保型傷害保険には損保型のような疾病免責条項がないことなどから、その射程がおよぶものではないとしています(中村心『最高裁判所判例解説民事編 平成19年度(下)』550頁)。
■参考文献
・石田清彦「入浴中の溺死と疾病免責」『保険事例研究会レポート』291号1頁
・山下友信・永沢徹『論点体系 保険法2』295頁、300頁
・潘阿憲『保険法概説』297頁
・西島梅治『保険法[第3版]』381頁
・山下友信・竹濱修・洲崎博史・山本哲生『有斐閣アルマ保険法(1999)』271頁
・深澤泰弘「浴槽内での溺死における傷害保険契約等の保険金等請求に対して、いわゆる疾病免責条項の適用を認め請求を棄却した事例」『損害保険研究』76巻2号311頁
・中村心『最高裁判所判例解説民事編 平成19年度(下)』550頁
・山下友信・竹濱修・洲崎博史・山本哲生『有斐閣アルマ保険法[第3版補訂版]』351頁
■関連するブログ記事
・吐物誤嚥が傷害保険の「外来の事故」にあたるか(最高裁平成25年4月16日判決)
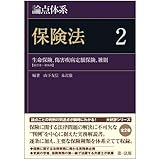 |
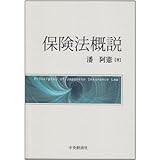 |
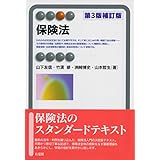 |
法律・法学 ブログランキングへ
にほんブログ村