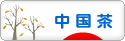台湾の秋も深まりつつあります。
飲水思縁のブログでは、昨年の秋に東京で出会ったことを振り返ります。ひとつ前の記事(→☆)では、昨年の秋、上海から茶友馮娟さんの来日を耳にしたら、急遽、昨年11月上旬に馮さんの「一杯の茶を淹れるには」講座をコーディネートしたことを記録しました。
講座の余韻に浸った馮さんと私の間は、また成り行きで、講座2日後の「自然茶会」を設けました。今度は集客にそこまで拘りませんでしたけど、たった1日中を使った集客期間にやはりドキドキしました。

「一杯の茶を淹れるには」講座の2日後に開いた「自然茶会」の場所は三軒茶屋の桜樺苑にしました。当日、オーナー何さんの臨機応変に感謝しています。
では、馮さんよりもらった「自然茶会の誘い」文面を振り返ります。
「自然茶会は、たまたま茶を飲んだ一つの体験より生み出しました。それで、2019年の始めに、ご縁に恵まれる100名の方に、丁寧に中国茶を淹れることを願いました。この一杯の茶が、ご縁のある方に、少しでも静けさをお届けすることができれば、幸いです。
このようなスタイルの茶会は今まで、17回を数え、計92名さまのご参加がありました。
自然という言葉は、フリースタイルのことも意味しています。事前準備は要らず、心より一杯の茶を飲みたい方なら歓迎しています。
東京の旅道中に、一杯の茶を飲みたいという方に出会えれば幸いです。」
中国語の文面を、急いで日本語訳にしたせいか、今読むと、微妙に直したい言葉遣いもありました(笑)当時の雰囲気を伝えるための資料として、ここで記録します。
たった1日だけの宣伝にもかかわらず、結果的に私を含めて計4名の参加者がいました。馮さんはお茶を淹れながら、参加者と感想を交わし、今でも振り返れば、私にとって濃密な時間でした。
そして、「自然茶会」の日は夜に国立の新井先生(新井先生を紹介した記事→
☆)宅の茶室までハシゴしました。一昨年に初めて新井先生のことを馮さんに紹介し、今度も是非、ということでアレンジしました。
その日は冬の初めに、新井先生に壺荘り(つぼかざり)のことも教えていただきました。
愛おしい和菓子にもいつも目がありませんw
何かの牽引で、新井先生は次から次へとお宝をだしてくださいました。中国茶を飲むための湯呑を見ても目から鱗でした。
馮さんは自ら中国茶をサーブすることに挙手。新井先生に感謝の意も込めながら、勉強熱心な彼女は柄杓の持ち方も色々質問したり練習していました。
最後に新井先生自作の茶杓も色々見せていただいて、茶杓のあるべき作法なども教えていただきました。
あの日の円相図は還暦という60年の循環に相当する話も心に留まりました。
新井先生宅には遅くまでお邪魔しました。深夜の国立駅までの帰り道に、馮さんがこの景色を撮ることに夢中でしたw彼女の美しくて凛とした心象風景を見たようです。
突然アレンジした「自然茶会」で、馮さんのパフォーマンスも私の想像を超えました。あの日、彼女の淹れる茶で、その懐の深さと環境への適応能力の高さに、私は脱帽しました。
彼女を見て、日々の暮らしを丁寧にし、茶に対する姿勢も妥協しないけど、堅実ながら柔らかく人と接することを覚えました。ただし、それから馮さんのような人間になろうとしませんでした。今も我ながらあんな境地に近づける道を試行錯誤しています。人の成功例は完全にコピペできないものでしょうし、自らの性質も大切にしつつ歩むべき道を探っていくべきです。
馮さんと密着する経験は実り多い秋の思い出として、心に残りました。
そして一年後の最近、馮さんは中国語でいくつか示唆的な茶の文章を書いてくださって、マイペースながらいつかここでその日本語訳を紹介できれば、と考えています。
【メモリーズ】 馮さんと
【メモリーズ】新井宗利先生と
2015年、国際茶会は出会い→☆
2015年、初茶室→☆
2016年、国際茶会→☆
2017年、一緒の芸大茶会→☆
2017年、国際茶会→☆
2018年、茶室でのコラボ茶事→☆
2019年、「而立の年 茶の写真展」小堀遠州流抹茶席紹介→
☆
ランキングに参加しております。
よろしければ、応援クリックお願いいたします!