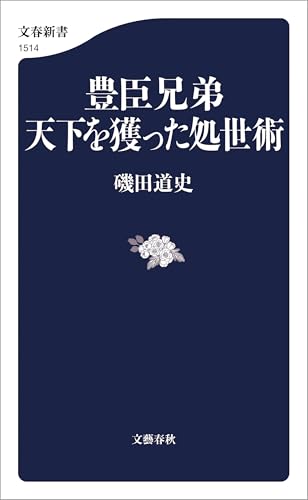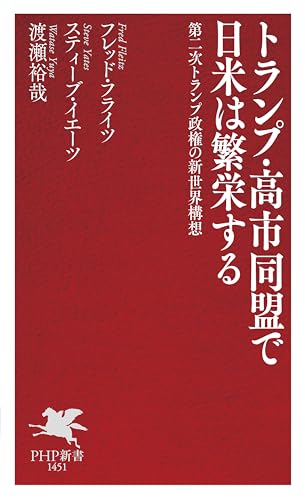◆磯田道史『豊臣兄弟。天下を獲った処世術』を読み解く
★要旨
・誤字を厭わず「即レス」を貫く実務力
・永禄年間には、秀吉は細々とした事務を精力的にこなし、
あちこちに手紙を書いているのですが、秀吉の手紙には誤字、当て字が多い。
・権威ある醍醐寺の「醍(だい)」がわからぬ書記には「大」と書かせて、素早く書状を出すのです。
大納言でさえ「大なんこ」と秀吉は書いています。
・秀吉は形式にこだわりません。
スピードにはこだわりました。
漢字は書きたがらず、ひらがなが早く書けるので好きでした。
・秀長が織田家に仕えるようになった時期は、
まさに織田家の高度成長期だったと考えられます。
・秀長が厚遇されていたと考えられる理由は、その名乗りです。
実は秀長は、はじめ長秀と名乗っているのです。
・この「長秀」が非常に重要なのです。
というのも、織田家において、信長の「長」を勝手に名乗ることはできません。
信長が小一郎に「長」の一字を使うことを許したと考えるのが自然です。
・いつ長秀は秀長となったのか。
これも非常に面白い。時は下って1584年9月、小牧・長久手の戦いの最中なのです。
・よく知られるように、この戦いは秀吉と、
徳川家康と信長の次男である織田信雄の連合軍との戦いでしたが、ここで初めて「美濃守 秀長」と署名しています。
・この改名には秀吉の明確な意向が込められていると思います。
織田家由来の「長」と羽柴家の「秀」を入れ替える。
・それによって、「もう俺たち(羽柴家)は織田家の下には立たないぞ」と宣言した、とも考えられるのです。
・翌年、秀吉は従一位(じゅいちい)関白になって信長の官位をこえました。
信長は正二位(しょうにい)右大臣です。
・このように、秀吉の政治発想力はすごい。
信長より上だと、弟の名前を変えて天下に広告したのです。
・天下の武将たちが、秀吉と家康・信雄のどっちが勝つのか注目しているときに、これをやりました。
実際、天正12年の11月に織田信雄から和睦を求め、家康とも和議を成立させて、小牧・長久手の戦いは終わります。
★コメント
豊臣兄弟から学ぶことは多い。
仕事力をアップさせたい。