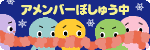それでは今その私を見ている私は何だろう・・・・・・やはり私である。
一体私が二人いてはいけないなんて誰がきめた。
新潮文庫 大岡昇平『野火』173ページ
以前武田泰淳の『ひかりごけ』で扱われたあまりにも重いテーマ
「カニバリズム」が描かれている小説、として有名だが、それ以
上に人間の存在の根源まで深く押し入った大岡昇平の傑作である。
それは戦争文学の金字塔といっても決して大げさではない。
煙は比島のこの季節では、収穫を終った玉蜀黍(とうもろこし)
の殻を焼く煙であるはずであった。それは上陸以来、我々を取り
巻く眼に見えない比島人の存在を示して、常に我々の地平を飾っ
ていた。
歩哨はすべて地平に上がる煙の動向に注意すべきであった。ゲリ
ラの原始的な合図かも知れないからである。事実不要物を焚く必
要から上がる煙であるか、それとも遠方の共謀者と信号する煙で
あるかを、煙の形から見分けるという困難な任務が、歩哨に課せ
られていた。
(16~17ページ)
この野火こそが、敵の存在を象徴的に示していて、すでに追い詰
められた状態にあった日本兵を恐怖へと駆るものであった。火を
焚く者がフィリピンの一般市民であろうが、ゲリラであろうが、
すでに上陸しているアメリカ兵であろうが、すべてが敵なのであ
る。このような極限状態にあっては、すでに日本兵であっても純
粋な「味方」とは言えない状況である。それが、主人公である田
村一等兵の軍内部での扱いからも示唆されているのだ。
警戒は私から瞑想を奪った。
(21ページ)
この言葉はとても印象的である。想像や空想する力を奪う、それ
が戦争の重要な一面ではないだろうか。人を殺すということはど
のような意味を持つのか。戦地においてこのような想像を巡らす
余裕はない。ないばかりかそれは危険である。自分の生命に対す
る危険である。戦地では0.1秒の躊躇いによって命を落としてしま
う可能性だってある。「この兵士には故郷に母や妻や娘がいるか
も知れない」などと想像してはいけないのである。
今私があの空に焦がれるのは、及び難いと私が知っているからで
あろう。私は自分が生きているため、生命に執着していると思っ
ているが、実は私は既に死んでいるから、それに憧れるのではあ
るまいか。
この逆説的な結論は私を慰めた。私は微笑み、自分は既にこの世
の人ではない、従って自ら殺すには当たらない、と確信して眠り
に落ちた。
(48~49ページ)
田村一等兵は自殺するなら今だと考える。彼は結核を病み、原隊
の服することも、病院に入ることも許されない存在であったのだ。
上官からは「死ね」と言われる。田村一等兵は想像する。彼はイ
マジンする。何とか自分の道徳心と自分の行為との折り合いを付
けることに腐心する。そこにはどうしても正当な理由が必要であ
った。多くの知識人が戦地にかり出された。そして多くの兵士が
このようなことに悩んでいただろう。
戦地では想像力を働かせてはいけない。田村一等兵にはそれがで
きなかった。だから彼はある部分で救われ、ある部分で悲劇的で
あったのだ。
廃墟と化した教会に田村は食料を探して入る。そこで事件が起き
る。彼は意図せず、偶然教会に入ってきた恋人たちに銃を向ける。
そして女性が死ぬ。田村は現地の女性を射殺してしまう。それは
戦闘行為ではない。このことが田村の上に重くのし掛かるのであ
る。田村がこの教会で得た物は「塩」であった。
田村が持つ倫理観はキリスト教によるものであろう。キリスト教
において「塩」とは特別な物である。それは新約聖書の福音書を
読めばたちまち理解できる。キリストの「山上の垂訓」(マタイ
による福音書5章13節以下)の場面で出てくる。
何故私は射ったか。女が叫んだからである。しかしこれも私に引
金を引かす動機ではあっても、その原因ではなかった。これは事
故であった。しかし事故なら何故私はこんなに悲しいのか。
(84~85ページ)
銃は国家が私に持つことを強いたものである。こうして私は国家
に有用であると同じ程度に、敵にとって危険な人物になったが、
私が孤独な敗兵として、国家にとって無意味な存在となった後も、
それを持ち続けたということに、あの無辜の人が死んだ原因がある。
私はそのまま銃を水に投げた。
(86ページ)
田村一等兵を突き動かすものとは何だろうか。それは生き残ろう
とする力なのだろうか。一見するとそれは明らかに違うように思
える。生き残ろうとする人間が自分を守る銃を捨てるはずがない。
しかし彼は銃を捨てる。これによって「違う人間」として生きよ
うとした。そんな深い決意を見る。状況によっては、一見矛盾し
たことが、反対に正当性を持つことがあり得るのだ。
その時変なことが起った。剣を持った私の右の手首を左の手が握
ったのである。この奇妙な運動は、以来私の左手の習慣と化して
いる。私が食べてはいけないものを食べたいと思うと、その食物
が目の前に出される前から、私の左手は自然に動いて、私の匙を
持つ方の手、つまり右手の手首を、上から握るのである。
(132ページ)
田村が積極的な食人を避けたのはもはや道徳心という理性の働き
ではなくて、むしろ習慣的で反射的な動きであった。私はわから
ない。どちらが人間的だと言えるのか。そして、その答えを見つ
けることが私がこの本を最初に読んだときから、私に課せられた
使命であると勝手に思い込むようになった。今もわからない。し
かし、私は習慣的で反射的な田村の「奇妙な運動」を持って、人
間的であると信じている。
田村は人肉を食べたのだろうか。
田村は三人の日本兵による壮絶な殺し合いを生き残った後に意識
と記憶を失い、「狂人」となった。想像する力を失った瞬間に田
村は救出される。生き残り、戦後を迎えることになる。
田村は「猿の肉」を食したが、人肉を食べるという行為にコミッ
トしなかった。この「コミットメント」が重要であり、「コミッ
トする能力を失した」ことで田村の戦争が終わったということは、
兵士としての田村一等兵が生き残ったという「敗北」を、人間と
しての死「勝利」によって得るという理解が可能であろう。
戦前における日本人の価値観の皮肉な運命を、私はこの作品に見
る。それは戦後の日本および日本人が未だに解決できずにいる様
々な問題の、出発点であるという理解を私はしている。
野火 (新潮文庫)/大岡 昇平

¥340
Amazon.co.jp


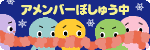
一体私が二人いてはいけないなんて誰がきめた。
新潮文庫 大岡昇平『野火』173ページ
以前武田泰淳の『ひかりごけ』で扱われたあまりにも重いテーマ
「カニバリズム」が描かれている小説、として有名だが、それ以
上に人間の存在の根源まで深く押し入った大岡昇平の傑作である。
それは戦争文学の金字塔といっても決して大げさではない。
煙は比島のこの季節では、収穫を終った玉蜀黍(とうもろこし)
の殻を焼く煙であるはずであった。それは上陸以来、我々を取り
巻く眼に見えない比島人の存在を示して、常に我々の地平を飾っ
ていた。
歩哨はすべて地平に上がる煙の動向に注意すべきであった。ゲリ
ラの原始的な合図かも知れないからである。事実不要物を焚く必
要から上がる煙であるか、それとも遠方の共謀者と信号する煙で
あるかを、煙の形から見分けるという困難な任務が、歩哨に課せ
られていた。
(16~17ページ)
この野火こそが、敵の存在を象徴的に示していて、すでに追い詰
められた状態にあった日本兵を恐怖へと駆るものであった。火を
焚く者がフィリピンの一般市民であろうが、ゲリラであろうが、
すでに上陸しているアメリカ兵であろうが、すべてが敵なのであ
る。このような極限状態にあっては、すでに日本兵であっても純
粋な「味方」とは言えない状況である。それが、主人公である田
村一等兵の軍内部での扱いからも示唆されているのだ。
警戒は私から瞑想を奪った。
(21ページ)
この言葉はとても印象的である。想像や空想する力を奪う、それ
が戦争の重要な一面ではないだろうか。人を殺すということはど
のような意味を持つのか。戦地においてこのような想像を巡らす
余裕はない。ないばかりかそれは危険である。自分の生命に対す
る危険である。戦地では0.1秒の躊躇いによって命を落としてしま
う可能性だってある。「この兵士には故郷に母や妻や娘がいるか
も知れない」などと想像してはいけないのである。
今私があの空に焦がれるのは、及び難いと私が知っているからで
あろう。私は自分が生きているため、生命に執着していると思っ
ているが、実は私は既に死んでいるから、それに憧れるのではあ
るまいか。
この逆説的な結論は私を慰めた。私は微笑み、自分は既にこの世
の人ではない、従って自ら殺すには当たらない、と確信して眠り
に落ちた。
(48~49ページ)
田村一等兵は自殺するなら今だと考える。彼は結核を病み、原隊
の服することも、病院に入ることも許されない存在であったのだ。
上官からは「死ね」と言われる。田村一等兵は想像する。彼はイ
マジンする。何とか自分の道徳心と自分の行為との折り合いを付
けることに腐心する。そこにはどうしても正当な理由が必要であ
った。多くの知識人が戦地にかり出された。そして多くの兵士が
このようなことに悩んでいただろう。
戦地では想像力を働かせてはいけない。田村一等兵にはそれがで
きなかった。だから彼はある部分で救われ、ある部分で悲劇的で
あったのだ。
廃墟と化した教会に田村は食料を探して入る。そこで事件が起き
る。彼は意図せず、偶然教会に入ってきた恋人たちに銃を向ける。
そして女性が死ぬ。田村は現地の女性を射殺してしまう。それは
戦闘行為ではない。このことが田村の上に重くのし掛かるのであ
る。田村がこの教会で得た物は「塩」であった。
田村が持つ倫理観はキリスト教によるものであろう。キリスト教
において「塩」とは特別な物である。それは新約聖書の福音書を
読めばたちまち理解できる。キリストの「山上の垂訓」(マタイ
による福音書5章13節以下)の場面で出てくる。
何故私は射ったか。女が叫んだからである。しかしこれも私に引
金を引かす動機ではあっても、その原因ではなかった。これは事
故であった。しかし事故なら何故私はこんなに悲しいのか。
(84~85ページ)
銃は国家が私に持つことを強いたものである。こうして私は国家
に有用であると同じ程度に、敵にとって危険な人物になったが、
私が孤独な敗兵として、国家にとって無意味な存在となった後も、
それを持ち続けたということに、あの無辜の人が死んだ原因がある。
私はそのまま銃を水に投げた。
(86ページ)
田村一等兵を突き動かすものとは何だろうか。それは生き残ろう
とする力なのだろうか。一見するとそれは明らかに違うように思
える。生き残ろうとする人間が自分を守る銃を捨てるはずがない。
しかし彼は銃を捨てる。これによって「違う人間」として生きよ
うとした。そんな深い決意を見る。状況によっては、一見矛盾し
たことが、反対に正当性を持つことがあり得るのだ。
その時変なことが起った。剣を持った私の右の手首を左の手が握
ったのである。この奇妙な運動は、以来私の左手の習慣と化して
いる。私が食べてはいけないものを食べたいと思うと、その食物
が目の前に出される前から、私の左手は自然に動いて、私の匙を
持つ方の手、つまり右手の手首を、上から握るのである。
(132ページ)
田村が積極的な食人を避けたのはもはや道徳心という理性の働き
ではなくて、むしろ習慣的で反射的な動きであった。私はわから
ない。どちらが人間的だと言えるのか。そして、その答えを見つ
けることが私がこの本を最初に読んだときから、私に課せられた
使命であると勝手に思い込むようになった。今もわからない。し
かし、私は習慣的で反射的な田村の「奇妙な運動」を持って、人
間的であると信じている。
田村は人肉を食べたのだろうか。
田村は三人の日本兵による壮絶な殺し合いを生き残った後に意識
と記憶を失い、「狂人」となった。想像する力を失った瞬間に田
村は救出される。生き残り、戦後を迎えることになる。
田村は「猿の肉」を食したが、人肉を食べるという行為にコミッ
トしなかった。この「コミットメント」が重要であり、「コミッ
トする能力を失した」ことで田村の戦争が終わったということは、
兵士としての田村一等兵が生き残ったという「敗北」を、人間と
しての死「勝利」によって得るという理解が可能であろう。
戦前における日本人の価値観の皮肉な運命を、私はこの作品に見
る。それは戦後の日本および日本人が未だに解決できずにいる様
々な問題の、出発点であるという理解を私はしている。
野火 (新潮文庫)/大岡 昇平

¥340
Amazon.co.jp