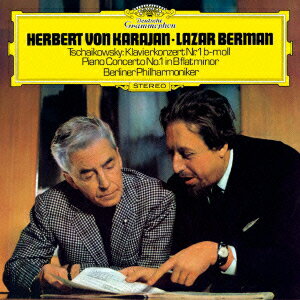Non Stop West
Al Caiola & Leroy Holmes Orchestra
曲目/
1.The Good, The Bad And The Ugly-続・夕日のガンマン 2:53
2.A Professional Gun-ジャガー 2:12
3.True Grit -トゥルー・グリット 3:53
4.A Fistful Of Dollars-荒野の用心棒 2:00
5.Ole Turkey Buzzard-マッケンナの黄金 3:26
6.Hang 'Em High-奴らを高く吊るせ 2:25
7.The Big Gundown-復讐のガンマン 2:45
8.The Magnificent Seven-荒野の七人 2:00
9.For A Few Dollars More-夕日のガンマン 2:20
10.Bonanza-ボナンザ 2:16
11.The Big Country-大西部 2:23
12.Wagons Ho! -ワゴン・トレイン 3:44
13.Return Of The Seven-続荒野の七人 2:15
14.High Chaparral- シャパラル高原 2:13
演奏/ルロイ・ホルム・オーケストラ 1-6
アル・カイオラ楽団 7-14
発売/1972
英SUNSET SLS 50312
英SLSはユナイテッド・アーティスト系の再発専門の廉価版レーベルでした。サントラ版はこのレーベルで結構集めました。これまでには下記のアルバムを取り上げています。
前半を担当しているのはルロイ・ホームズです。このルロイ・ホームズ(1913年9月22日 - 1986年7月27日)は、アメリカの作詞家、作曲家、編曲家、オーケストラ指揮者、そしてレコードプロデューサーでした。そして、ホームズはハリウッド高校を卒業後、イリノイ州エバンストンのノースウェスタン大学とニューヨークのジュリアード音楽院で音楽を学び、1930年代から1940年代初頭にかけて、エルンスト・トック、ヴィンセント・ロペス、そしてハリー・ジェイムズといった多くのバンドリーダーと共演しました。
第二次世界大戦中はアメリカ海軍でパイロットと飛行教官、そして中尉を務めた後、ハリウッドに移り、MGMミュージック・スタジオに専属編曲家兼指揮者として採用されました。1950年にニューヨークに移り、MGMでレコードプロデューサーとして活動を続け、後にユナイテッド・アーティスツに移籍しました。1960年代初頭にユナイテッド・アーティスツ・レコードに移籍し、数多くの映画テーマ曲のコンピレーション・アルバムに楽曲を提供し、自身の名義でアルバムをリリースするとともに、コニー・フランシス、グロリア・リン、シャーリー・バッシー、そしてプエルトリコ出身のティト・ロドリゲスやチューチョ・アヴェジャネットといった歌手のバックオーケストラを務めています。
今回このアルバムを取り上げたのは今月までNHK-FMで放送中の「✖️クラシック」で特集中のエンリオ・モリコーネがらみということで考えました。まあ、アル・カイオラにしてもウェスタンをテーマにしたアルバムを服末発売していましたからねぇ。必然的にエンリオ・モリコーネもたくさん含まれています。このアルバムでいうと1.2.4.7.9とモリコーネの作品が並びます。
冒頭は「続・夕日のガンマン」です。ユナイテッド・アーティストで活躍していましたから、映画音楽は得意なものです。いいアレンジで原曲の雰囲気を掴んでいます。日本とはヒットの基準が違いますから2曲目の「ジャガー」はあまり知られていません。3曲目はジェフ・ブリッジェス主演の西部劇で音楽はエルマー・バーンスタインが書いています。
後半のアル・カイオラはギター奏者でしたが自らのオーケストラを率いて勢力的に1960-70年第二活躍しました。彼の演奏した「荒野の七人」はベストセラーになりましたし、テレビドラマの主題歌としての「ボナンザ」も大ヒットしました。あまり知られていない「ワゴン・トレイン」の主題歌、「ワゴン・ホー」も彼がヒットさせました。まあ、楽しいアルバムですが、日本ではこういうアルバムはリリースされていません。