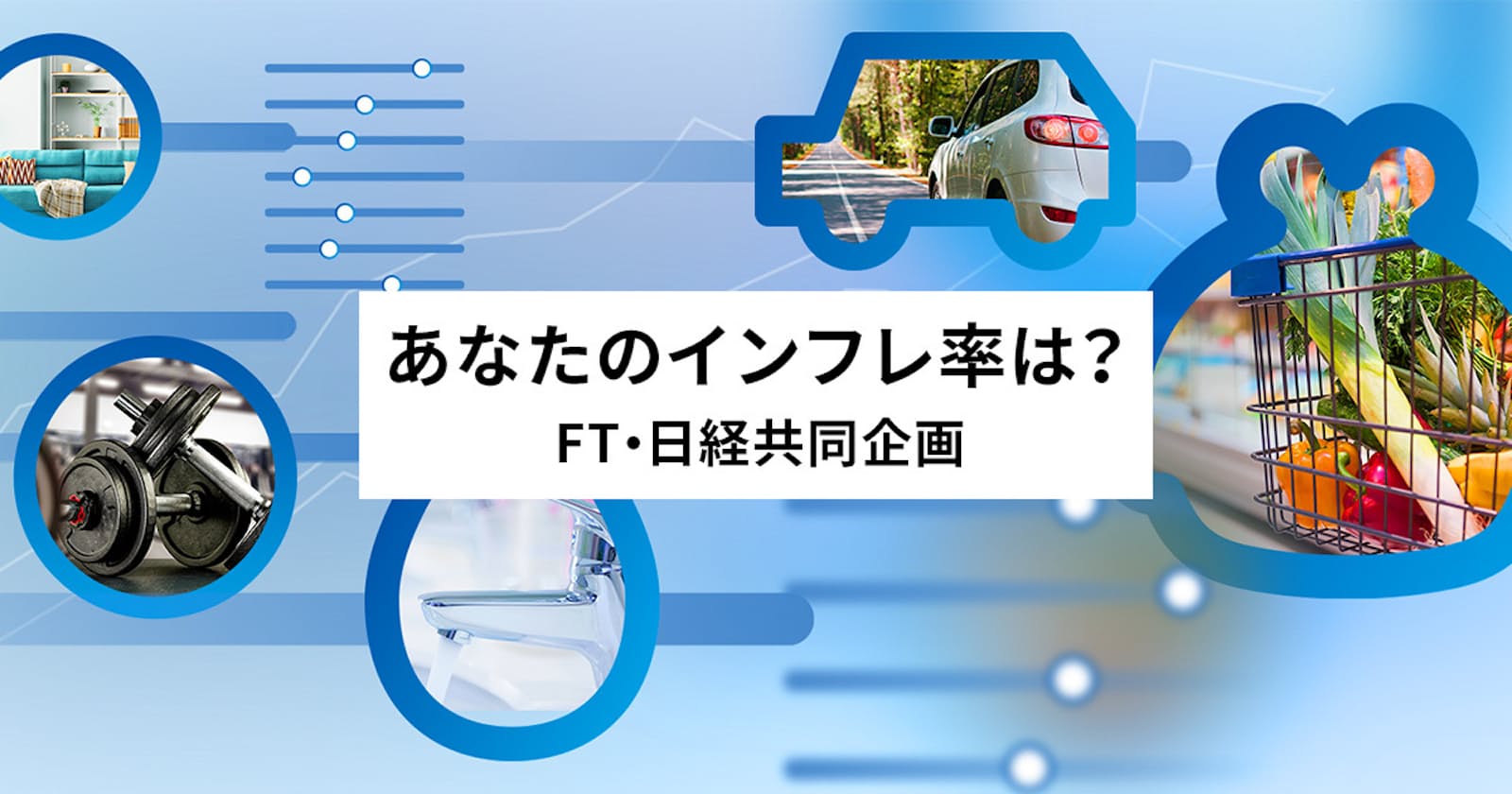8年間続いた日本のマイナス金利政策が解除となり
「金利のある世界」が復活し、家計にも影響を及ぼし始めています。
あなたの家計にはどんな影響が出ていますか?
みずほリサーチ&テクロノジーズ社のリサーチによると
全世帯平均では最大で差し引き7.7万円/年のメリットが生じる
※預金・有価証券といった金融資産からの所得が増加
30~39歳世帯では差し引き55.5万円/年のデメリットが生じると試算される
※対象を負債保有世帯に限ると、若年層や低中所得層を中心に利払い負担増の悪影響が大きい為
という結果が出ています。
つまり負債がなく資産をある程度お持ちの世帯にとっては金利のある世界の方が家計にプラスであり
資産がまだ少なく住宅ローンが重くのしかかっている30代では
資産効果があまり得られない上に、負債の利息負担が増えるマイナス面がかなり大きくなるという試算だ。
今まで以上に
・無理な住宅ローンを組まない
・貯めるチカラをしっかりつけてから住宅を買う
・将来的に資産運用の効果が住宅ローンの利息負担を上回るような投資を取り入れる(理想)
といったことが大切で
もちろん
・人生設計をしっかり作り定期的に見直しする
ことをお忘れなく。
これらを若いうちから実現できれば40代のうちに住宅ローン残高以上の金融資産が作れて
住宅ローンの利息負担分以上に投資効果が得られることも夢ではありません。
住宅ローン残高4000万円 年間の利払いが40万円
①資産運用残高1000万円 年間の投資効果50万円
②資産運用残高4000万円 年間の投資効果200万円
このような①②の状態が平均的に達成できたなら
余裕資金は繰上げ返済よりも投資に回した方が良いと考えるでしょう。
お金が貯まったら繰上げ返済
また貯まったら繰上げ返済
を繰り返していると、手元資金が少ないというリスクがありますし
家計としては効率が悪いです。
金利のある世界は、金利のない世界以上に金融リテラシー(お金の知識や判断力)が重要で
知識があるか・ないかでの格差がより広がっていくことになります。
専門家のアドバイスを適切に活用する力をお持ちかどうかも、大きな差を生みます。
金利のある世界でも家計にプラスの影響となるように
しっかり金融リテラシーを上げていきましょう。