『銀河鉄道999』(劇場版)
- 本じゃないけど、まあ。
私が『銀河鉄道999』が好きだということはこのブログで何度かお話してきましたが、まあそうなんです。ですが、私にとっての「999」はあくまでも原作のマンガで。テレビ版も、それほど強く記憶にないし、最初や最後は全然覚えてないです(最初はこないだケーブルTVで見た )。
そんなわけで、実は映画版の「999」は、今まで見たことがなかったのです。あ、98年の「エターナル編」は劇場で見ました。…感想?「なんだかなあ」です。(^^;;
それを、先日、観たんですね。なんで今更観る気になったかというと、ちょっと前に、たまたまレンタルCD屋で、久々にゴダイゴのCDを借りたんですね(結構好き*^^*。詳しくないけど)。で、あらためて、「999」の主題歌はいいなあ、と思いまして(『西遊記』も好きなんですが。結構海外でも流行ってるんですよね、いま)。それで気になっているところへ、たまたまアニメDVDを100円で借りられる日に遭遇してしまい、映画版が1枚残っていたもので、イキオイで借りた、と。
で。
…あ~、そーゆーことだったのか~っ!!! と叫びたいことが何度か。
どーゆーことかというと、いままで999の話を友人などとしていても、どうも話が噛み合わないことがあったんですよね(皆さんマニアではありません)。で、その原因がわかったと。どうも、映画版の設定の方が、世間では流通しているらしい。なんで999でトチローの話が?とか、え?エメラルダス?え?メーテルの****?なんだそりゃ?とか、とか、とか…。
それと、マンガの方も、「エターナル編」の設定が、どうも微妙に劇場版を受け継いでいるらしいということもわかって。
でさっき wikipedia を見てみたら、うん、そうだったのか、と。
なんか色々な疑問が氷解しちゃったなあ。
でもですね。私としては、やはり「999」はマンガなのですよ。劇場版は、どうも底が浅く感じられてしまう。まあそりゃあれだけの長編を2時間に詰めこみ、さらに見せ場をいくつも作るのだから、仕方ないといえば仕方ないのですが。だけど、原作では最後の最後まで機械の体をもらうかどうか悩む鉄郎が、映画ではあっけなく結論出しちゃうし…マンガで出てくる最後の一つ手前の星、「最後の晩餐」の話良かったのになあ。機械伯爵が機械化人の英雄ってのもなあ…。
「まあ」だらけですが、まあそんな気持ちで観てました。
でも、ラストシーンは良いですね。あそこでゴダイゴの曲がかかるのはもう最高です。だいぶ前、たまたま見てたテレビで、松本零士が語っていたんですが、彼としては、最後は荘厳なクラシックの曲がかかるのをイメージしてたそうです(クラシック好きなので)。ところが、蓋を開けてみればゴダイゴの曲。最初はだいぶ抵抗があったそうなのですが、いざ完成版を見てみたら、ああ、こういうのもいいもんだなあ、と思ったとか(もう随分昔見た番組なので、うろ覚えですが)。あそこは観ててゾクゾクしますね。
そうそう、アニメつながりでもう一つ。
ひと月ほど前になりますか、あの『ヤッターマン』も観に行きました。それなりに楽しめたのですが、一番の感想は、「小原乃梨子ってスゲエなあ」でした(本人もちょっと出演してましたね)。(^^;;
最初は「深田恭子もイマイチだなあ、フニャフニャしたしゃべり方で」と思ってたんですが、そのうち、うーん、いまの若い女優でそれができるのはいないかもしれない、と思い、最後に、ああ、小原乃梨子が凄かったんだな、と。いやまあドロンジョについては若い人がやらなくても良かったんじゃないかとも思うのですが。年齢層外せばもっと適役の人がいるんじゃないかと思ったり。
あ、小原乃梨子は声優です。ドロンジョでのび太でコナンでペーターでひろしの母ちゃんです。(^^)
- 銀河鉄道999 (劇場版) [DVD]

- ¥4,251
- Amazon.co.jp
血液型性格判断・ニセ科学・差別、あるいは「科学」と「価値」
きくちさんのこのインタビュー記事
をきっかけに、あちこちで血液型性格判断に関する議論(というかなんというか)がまきおこっているようですね。私のところへのリンクを貼っていただいたり、あるいはブクマの関連エントリということで飛んで来られる方もそれなりにいらっしゃるようです(というか、ログを見てて気がついた。ちょっとまた忙しくて、こんなにあちこちで騒がれていると気付いてなかった)。
で、ちょびっとだけ見て、いくつか気になったことがあるので、過去エントリへのリンクを示しながら、簡単にコメントしたいと思います。
血液型性格判断はニセ科学でもあるし差別とも絡んでいます。これはTAKESANさんが主張されている通りですね。人によって重点の置き方は違うけれども、でもまあ「差別」であるということはほぼ自明であるので、今更あまり論じられてこなかったのだと思います。それはもちろんネット上でのことで、血液型性格判断を取り上げている(批判的にですよ、もちろん)心理学関係の書物などでは、たいてい差別のことにも触れられています。
いやもちろん「自明」だとは言えないのが残念ながらいまの社会的状況ではあるのでしょうけれどもね。
私も差別に関しては以下のエントリで取り上げたことがあります。
血液型性格判断前史
『AERA』11/19:血液型性格判断を肯定
メディアということでは、これも関係するでしょう。
血液型と性格に強い関係はないことがわかっています
『an・an』の血液型特集:ダメだこりゃ
これらをふまえた上で、では科学的には「血液型と性格」の関係はどうなっているのかについて、以下を見ていただければと思います。
「血液型と性格」論文レビューをするにあたって
「血液型と性格」の正しい理解のために:松井(1991)その1
「血液型と性格」の正しい理解のために:松井(1991)その2
【ニセ科学であることと差別であること】
「血液型と性格」も、ある意味「水伝(水からの伝言)」と似たような面を持っていると言えるでしょう。
「水伝」において、(A)その道徳の部分(あるいは価値判断の部分)である「ありがとうと言いましょう」を導くために、(B)「『良い』言葉をかけると『綺麗な』結晶ができる」、という「ウソ」をついたわけです(提唱者である江本勝が自覚しているかどうかはわかりませんが)。「水伝」の価値判断に関わる部分は、その「ウソ」がウソであると判明した時点で崩れ去ります(論理的には)。
ここで、価値判断の部分は、単に「ありがとうと言いましょう」にとどまりません。「たかが」水に、高度に発達した精神活動を行う人間の意思を従属させるという問題、人間関係から生じ、また人間関係そのものとも言える「言葉」そしてその意味付けを、人間から独立した存在に委ねることの危険性。論理的につきつめて考えていけば、「水伝」の価値判断そのものが、大きな問題を抱えているということに気付くはずです(これらについても多くの議論の蓄積があります)。
そして、この「水伝」の価値判断が問題であるということは、仮に「良い」言葉が「綺麗な」結晶を作ることが本当だったとしても、問題であることは論を待たないでしょう。Bが成り立たなければAは崩れ去りますが、Bが成り立とうが成り立つまいが、AはAとしてそれ自身で問題なわけです。
血液型性格判断においても、社会における受容の仕方を見てみれば、同様に(a)血液型で人物を判断するという「差別」の部分と(b)血液型と性格に強い相関があるという「ウソ」の部分があるわけです。ここで a の中身を見てみれば、就職差別や人事における差別という明らかに問題となることもあれば、人間関係がうまくいかないことを血液型の「相性」のせいにしてしまうという、コミュニケーションの観点からはまさに「退廃」としか言いようのない結論を導くことも含まれるわけです。 a が成り立つためには b が成り立っていないといけないのは自明です。だから、多くの人は b について、つまり血液型性格判断のニセ科学性について言及する。だが、たとえ b がウソではなく、強い相関があったとしても、それを理由にやってはいけないことってのは世の中あるわけです。
「水伝」の場合には、Aの部分の問題が結構入り組んでいて、問題が問題としてあまり気付かれにくいという面がありました。それに比べると、血液型性格判断の場合の a の問題はあまりにもわかりやすく、もはや論じるまでもない、というところでしょうか。
というわけで、血液型性格判断に関しては、「ニセ科学」でありかつ「差別」の問題であると言えるのです。そして、血液型性格判断のニセ科学性を批判する人の多くが、その根底には「差別」という問題があると捉えている、という印象を私は持っています(持ってない人もそりゃいるでしょうけど)。批判することで優越感を持つ人がいるのかどうかは知らないけれど、言ってることが理にかなっているならば、その人が優越感を持ってたって別にいいんじゃないですかね?大事なのは、血液型性格判断がきちんと批判され、この社会において、重要視されなくなるということなんじゃないでしょうか(人に反感を持たれるような優越感があるとすれば、それはちょっと困りものですが)。
【「血液型と性格」と「性格の定義」について】
さて、科学としての血液型の問題の方にいったん焦点を絞りましょう。
そもそも「性格」ってなんでしょうか。定義できるもんなんでしょうか。
無論、それについては色々な議論があります(『モード性格論 』あたりを見るのが良いかと思います)。が、いちおう主流の考えは考えとしてあるわけです(ごく大まかには5つに分類される、という、ビッグファイブ仮説)。もちろん10年後にどうなっているかはわかりません。が、多くのプロの研究者が妥当であろうと「今」考えていることを蔑ろにすることが建設的とはとても思えません。なので、自己評定により性格を定義し、それと血液型の相関について調べるというのは十分に意味があります。
もし、このレベルで相関があるとは言えないということになれば、「自己評定による性格」は血液型との強い相関がないということになります。では、その場合、血液型性格判断が生き残るにはどういう道があるでしょうか?
一つ考えられるのは、本人による評価ではなく、他人による評価でしょう。
しかし、これを調査するのはかなり大変だと思われます。ですので、相関があることを示すということ自体がとても大変になります。そして、そのような調査結果は(私の知る限り)ありません(もしかしたらあるかもしれませんが)。それに、もし他人による評価が本人による評価と強い相関があれば、結論は結局変わらないことになります。
では、そもそも性格など定義できないとしたら?となると、「血液型と性格」の相関を論ずること自体に意味がなくなります。つまり、「血液型と性格に強い関係がある」という言明は事実に反するわけです。事実に反することを、さも科学的根拠があるように主張するわけですから、結局「血液型性格判断はニセ科学だ」ということになりますよね。
こういったことは、kikulogの「血液型と性格」1、2、3 (リンクは「3」にはってあります)の3000コメントに及ぶ議論の中ですでに出されていることでもあります。
【科学と価値】
ここでちょっと視点を変えて、先日「ニセ科学批判」界隈で議論になっていたことに目を転じてみましょう。たとえば反社会的な宗教を科学の立場から(あるいはニセ科学批判の一つとして)批判することはどういう意味があるでしょうか?
オウムのようなカルト集団は、その根本の教義の部分では完全にオカルトであり、事実に即するかどうかという話よりも、いかに教祖に帰依するか、のような「価値判断」そのものがコアになっていると言えるでしょう。しかし、それを根拠づけようとして様々なニセ科学的言説が散りばめられます。
科学(あるいはニセ科学批判)にできるのは、そのような「ニセ科学的言説」を批判することだけです。(客観的な)事実関係とは独立した価値判断については、どうしようもありません。
逆に、どうかできちゃったら困ったこともおきるわけです。つまり、価値判断と科学的真偽が切っても切り離せないものだとしたら、たとえば「ありがとう」と言ったら綺麗な結晶ができるなら、我々は「水伝」に従わないといけないのでしょうか?そしてようやく本題に戻りますが、血液型と性格に強い相関がもしあったとしたら、血液型で差別されることも容認しないといけないのでしょうか?
客観的な事実関係と、価値に基づく判断を分離しておくことは、実は我々人間の「価値」そのものを守ることにもつながるのだと思います。たとえば「体に悪いものほど美味しい」なんて言いますが、体に悪いものを自分の判断で食べるのは「悪」なのか?だとすれば、人間の文化って一体なんなんだ?ということになるでしょう。
たとえ血液型性格判断に科学的根拠があったとしても、血液型で人を判断してはいけないんです。それが人間が長年の経験から産み出してきた智慧であり、文化なのではないでしょうか。
【おわりに】
というわけで、簡単にと言いつつついつい書き過ぎてしまいました。長文すいません。
簡単にコメントするだけのつもりでしたので、今回は「血液型性格判断はエセ科学問題ではなく差別問題だ 」(狐の王国さん)と「血液型性格判断がニセ科学だなんてニセ科学だぜ 」(sonickhedgeさん)のエントリ、及びこれらへのブックマークコメントを見てこのエントリを書きました。
ちなみに「ソース出せ」が出ましたね。「「血液型と性格」論文レビューをするにあたって 」で表明していた懸念が現出しました(苦笑)。具体的にどういう研究がされているかをちょっとでいいので見ていただければと思います。
こんなに長く書くつもりはなかったので、本来参照すべきブログ・エントリがいくつもあるのですが、省略します。すみません。一つだけ、割と最近のエントリで、差別について論じているものがありますので、参考までにそこにだけリンクはらせていただきます(「「血液型性格判断」批判 前編:ニセ科学批判の練習問題 」(みつどん曇天日記);後編もぜひ)。
(追記)TAKESANさんとこのエントリ「色々説明 」が、上記sonickhedgeさんのエントリについての詳しい説明になっていますので、ご覧いただくとわかりよいかと思います。それと、後半には血液型性格判断に関する膨大なリンク集がついています(私も目を通したことがないものもあったりします)。どれだけ膨大な議論の蓄積があるか、感じ取っていただければ…と思います。
で、ちょびっとだけ見て、いくつか気になったことがあるので、過去エントリへのリンクを示しながら、簡単にコメントしたいと思います。
血液型性格判断はニセ科学でもあるし差別とも絡んでいます。これはTAKESANさんが主張されている通りですね。人によって重点の置き方は違うけれども、でもまあ「差別」であるということはほぼ自明であるので、今更あまり論じられてこなかったのだと思います。それはもちろんネット上でのことで、血液型性格判断を取り上げている(批判的にですよ、もちろん)心理学関係の書物などでは、たいてい差別のことにも触れられています。
いやもちろん「自明」だとは言えないのが残念ながらいまの社会的状況ではあるのでしょうけれどもね。
私も差別に関しては以下のエントリで取り上げたことがあります。
血液型性格判断前史
『AERA』11/19:血液型性格判断を肯定
メディアということでは、これも関係するでしょう。
血液型と性格に強い関係はないことがわかっています
『an・an』の血液型特集:ダメだこりゃ
これらをふまえた上で、では科学的には「血液型と性格」の関係はどうなっているのかについて、以下を見ていただければと思います。
「血液型と性格」論文レビューをするにあたって
「血液型と性格」の正しい理解のために:松井(1991)その1
「血液型と性格」の正しい理解のために:松井(1991)その2
【ニセ科学であることと差別であること】
「血液型と性格」も、ある意味「水伝(水からの伝言)」と似たような面を持っていると言えるでしょう。
「水伝」において、(A)その道徳の部分(あるいは価値判断の部分)である「ありがとうと言いましょう」を導くために、(B)「『良い』言葉をかけると『綺麗な』結晶ができる」、という「ウソ」をついたわけです(提唱者である江本勝が自覚しているかどうかはわかりませんが)。「水伝」の価値判断に関わる部分は、その「ウソ」がウソであると判明した時点で崩れ去ります(論理的には)。
ここで、価値判断の部分は、単に「ありがとうと言いましょう」にとどまりません。「たかが」水に、高度に発達した精神活動を行う人間の意思を従属させるという問題、人間関係から生じ、また人間関係そのものとも言える「言葉」そしてその意味付けを、人間から独立した存在に委ねることの危険性。論理的につきつめて考えていけば、「水伝」の価値判断そのものが、大きな問題を抱えているということに気付くはずです(これらについても多くの議論の蓄積があります)。
そして、この「水伝」の価値判断が問題であるということは、仮に「良い」言葉が「綺麗な」結晶を作ることが本当だったとしても、問題であることは論を待たないでしょう。Bが成り立たなければAは崩れ去りますが、Bが成り立とうが成り立つまいが、AはAとしてそれ自身で問題なわけです。
血液型性格判断においても、社会における受容の仕方を見てみれば、同様に(a)血液型で人物を判断するという「差別」の部分と(b)血液型と性格に強い相関があるという「ウソ」の部分があるわけです。ここで a の中身を見てみれば、就職差別や人事における差別という明らかに問題となることもあれば、人間関係がうまくいかないことを血液型の「相性」のせいにしてしまうという、コミュニケーションの観点からはまさに「退廃」としか言いようのない結論を導くことも含まれるわけです。 a が成り立つためには b が成り立っていないといけないのは自明です。だから、多くの人は b について、つまり血液型性格判断のニセ科学性について言及する。だが、たとえ b がウソではなく、強い相関があったとしても、それを理由にやってはいけないことってのは世の中あるわけです。
「水伝」の場合には、Aの部分の問題が結構入り組んでいて、問題が問題としてあまり気付かれにくいという面がありました。それに比べると、血液型性格判断の場合の a の問題はあまりにもわかりやすく、もはや論じるまでもない、というところでしょうか。
というわけで、血液型性格判断に関しては、「ニセ科学」でありかつ「差別」の問題であると言えるのです。そして、血液型性格判断のニセ科学性を批判する人の多くが、その根底には「差別」という問題があると捉えている、という印象を私は持っています(持ってない人もそりゃいるでしょうけど)。批判することで優越感を持つ人がいるのかどうかは知らないけれど、言ってることが理にかなっているならば、その人が優越感を持ってたって別にいいんじゃないですかね?大事なのは、血液型性格判断がきちんと批判され、この社会において、重要視されなくなるということなんじゃないでしょうか(人に反感を持たれるような優越感があるとすれば、それはちょっと困りものですが)。
【「血液型と性格」と「性格の定義」について】
さて、科学としての血液型の問題の方にいったん焦点を絞りましょう。
そもそも「性格」ってなんでしょうか。定義できるもんなんでしょうか。
無論、それについては色々な議論があります(『モード性格論 』あたりを見るのが良いかと思います)。が、いちおう主流の考えは考えとしてあるわけです(ごく大まかには5つに分類される、という、ビッグファイブ仮説)。もちろん10年後にどうなっているかはわかりません。が、多くのプロの研究者が妥当であろうと「今」考えていることを蔑ろにすることが建設的とはとても思えません。なので、自己評定により性格を定義し、それと血液型の相関について調べるというのは十分に意味があります。
もし、このレベルで相関があるとは言えないということになれば、「自己評定による性格」は血液型との強い相関がないということになります。では、その場合、血液型性格判断が生き残るにはどういう道があるでしょうか?
一つ考えられるのは、本人による評価ではなく、他人による評価でしょう。
しかし、これを調査するのはかなり大変だと思われます。ですので、相関があることを示すということ自体がとても大変になります。そして、そのような調査結果は(私の知る限り)ありません(もしかしたらあるかもしれませんが)。それに、もし他人による評価が本人による評価と強い相関があれば、結論は結局変わらないことになります。
では、そもそも性格など定義できないとしたら?となると、「血液型と性格」の相関を論ずること自体に意味がなくなります。つまり、「血液型と性格に強い関係がある」という言明は事実に反するわけです。事実に反することを、さも科学的根拠があるように主張するわけですから、結局「血液型性格判断はニセ科学だ」ということになりますよね。
こういったことは、kikulogの「血液型と性格」1、2、3 (リンクは「3」にはってあります)の3000コメントに及ぶ議論の中ですでに出されていることでもあります。
【科学と価値】
ここでちょっと視点を変えて、先日「ニセ科学批判」界隈で議論になっていたことに目を転じてみましょう。たとえば反社会的な宗教を科学の立場から(あるいはニセ科学批判の一つとして)批判することはどういう意味があるでしょうか?
オウムのようなカルト集団は、その根本の教義の部分では完全にオカルトであり、事実に即するかどうかという話よりも、いかに教祖に帰依するか、のような「価値判断」そのものがコアになっていると言えるでしょう。しかし、それを根拠づけようとして様々なニセ科学的言説が散りばめられます。
科学(あるいはニセ科学批判)にできるのは、そのような「ニセ科学的言説」を批判することだけです。(客観的な)事実関係とは独立した価値判断については、どうしようもありません。
逆に、どうかできちゃったら困ったこともおきるわけです。つまり、価値判断と科学的真偽が切っても切り離せないものだとしたら、たとえば「ありがとう」と言ったら綺麗な結晶ができるなら、我々は「水伝」に従わないといけないのでしょうか?そしてようやく本題に戻りますが、血液型と性格に強い相関がもしあったとしたら、血液型で差別されることも容認しないといけないのでしょうか?
客観的な事実関係と、価値に基づく判断を分離しておくことは、実は我々人間の「価値」そのものを守ることにもつながるのだと思います。たとえば「体に悪いものほど美味しい」なんて言いますが、体に悪いものを自分の判断で食べるのは「悪」なのか?だとすれば、人間の文化って一体なんなんだ?ということになるでしょう。
たとえ血液型性格判断に科学的根拠があったとしても、血液型で人を判断してはいけないんです。それが人間が長年の経験から産み出してきた智慧であり、文化なのではないでしょうか。
【おわりに】
というわけで、簡単にと言いつつついつい書き過ぎてしまいました。長文すいません。
簡単にコメントするだけのつもりでしたので、今回は「血液型性格判断はエセ科学問題ではなく差別問題だ 」(狐の王国さん)と「血液型性格判断がニセ科学だなんてニセ科学だぜ 」(sonickhedgeさん)のエントリ、及びこれらへのブックマークコメントを見てこのエントリを書きました。
ちなみに「ソース出せ」が出ましたね。「「血液型と性格」論文レビューをするにあたって 」で表明していた懸念が現出しました(苦笑)。具体的にどういう研究がされているかをちょっとでいいので見ていただければと思います。
こんなに長く書くつもりはなかったので、本来参照すべきブログ・エントリがいくつもあるのですが、省略します。すみません。一つだけ、割と最近のエントリで、差別について論じているものがありますので、参考までにそこにだけリンクはらせていただきます(「「血液型性格判断」批判 前編:ニセ科学批判の練習問題 」(みつどん曇天日記);後編もぜひ)。
(追記)TAKESANさんとこのエントリ「色々説明 」が、上記sonickhedgeさんのエントリについての詳しい説明になっていますので、ご覧いただくとわかりよいかと思います。それと、後半には血液型性格判断に関する膨大なリンク集がついています(私も目を通したことがないものもあったりします)。どれだけ膨大な議論の蓄積があるか、感じ取っていただければ…と思います。
- 「モード性格」論―心理学のかしこい使い方/サトウ タツヤ
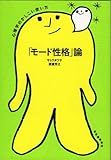
- ¥1,890
- Amazon.co.jp
浮力
(テキトーな物言いをしていたところを微妙に修正しました)
閑話(って何が本題だろう^^;;)。
先日 kikulog のコメント欄 でちょっとだけ出た話題について、若干違和感があったので。
浮力をどう教えるか?という話なのだけれども、まあ元の話の文脈はここではちょっと忘れましょう。
説明が二種類ある。一つは、kikulogでYMNさんという方がリンクしている先 に書いてあり、またきくちさんも述べていることだが、簡単に言うと、水中の「水」の重さをばねばかりで測るとゼロになるから、水中に物体を入れると、おしのけた水の分だけ空気中より軽くなる(ばねばかりの示す値が変化する)というもの(ガモフの説明)。もう一つは、圧力差で説明する、というもの。で、高校では直方体の上下の圧力差で説明しているが、浮力は形に依らないので、いかがなもんでしょう、と。
たしかにそれはそれで問題としてあるのだけれども、ガモフの説明で事足りるかというと、それはどうも納得がいかない。というのは、ガモフの説明では、何がどのように水中に沈めた物体に力を及ぼしているのかがまったく理解できないからだ。
直方体を使った説明の何が問題かといえば、物体の大きさが有限(微小量でない)ということにある。では、きちんと圧力差で説明しようとするとどうなるか。本質的には静水圧平衡(静力学平衡)の概念が必要になる。
まず、水の密度をρ0とし、深さ水槽の底からの高さhでの圧力をP(h)とする。そこからΔhだけ上昇した点での圧力をP(h+Δh)≒P(h)+ΔPとしておく。当然、ΔP<0である(水面に近いほど圧力は減るので)。深さ高さhにおける流体素片の体積をΔV=SΔhとおくと、圧力差と重力が釣り合っているなら全体の力は(上向きを正にとる)、
F = P(h)S-P(h+Δh)S-mg = -SΔP-ρ0 ΔV g = -S ( ΔP + ρ0 g Δh ) = 0
となって、
ΔP = - ρ0 g Δh
が成り立つ。Δh→0 にとれば、
dP/dh = - ρ0 g
となる。平衡状態ではこうなっている。
さて、水中に沈める物体の質量をΔm、密度をρ、体積をΔVとしよう。ここで微小体積を問題にするので、水の場合の流体素片と同様に、物体を微小な高さ方向に対称な形状とし、底面積をS、高さをΔhとする。
この物体についての運動方程式をたてると、
Δm a = P(h)S - P(h+Δh)S - Δm g = -SΔP - ρSgΔh = -S ( ΔP + ρgΔh )
= -S ( -ρ0 g Δh + ρgΔh ) = SgΔh ( ρ0 - ρ)
となって、水の密度との差だけ軽くなることがわかる(密度が水より大きいと加速度が負、つまり沈もうとする)。
あるいは、同じ体積の水の質量を上で書いたように m と置いておくと、
Δm a = mg - Δmg = -(Δm-m)g
となって、まさに物体が押しのけた水の質量 m だけ軽くなっていることが示される。
というわけで、直方体での説明は、力を及ぼす実体のイメージを持たせつつ、微分が使えない高校物理での苦肉の説明だと思う。直方体の大きさを微小としさえすれば水中での圧力を深さの関数として表すことが可能となり、一旦それを認めてしまえば、あとは「物体が押しのけた水の量だけ軽くなる」というのを示すのは容易であるし、なにより水が力を及ぼすことで(上からも下からも、あと今回は省略したけど横からも)浮力が働くというイメージを持ちやすいのではないだろうか。
もちろん、話の入口としてのガモフの説明は大いに結構であると思う。それは、「だってそうじゃなかったら色々矛盾しておかしいじゃん」という、今まで学んできたこと同士の整合性を取り、論理的に非自明なことを導くという良い訓練になっていると思うから。でも、そこで留まるのはどうかなあ、と思うのであった。
あ、notation が妙なのはすんません(mとΔmが並ぶのはキモチ悪いよなあ。でもHTMLだと添字をつけるの面倒だもんで…)。
あともう一つ、kikulogでもリンク先の方も、当然「どっちが悪い」という議論はしておりませんので、念のため。どちらも大切だけど、ガモフ的な考え方が軽視されているのでは、という趣旨です(と私は読みました)。それには賛成です。
ではなんでわざわざこんなエントリあげたかというと、極限操作の厳密性を抜きにすれば、この程度できちんと理解できるから、ということを示したかったわけです。まあ高校ではつらいかもしれんけど。でもさ、静水圧平衡を理解していれば、大気の構造とかも理解できちゃうわけで、コストパフォーマンスの良い教養だと思います。
***
追記。全然関係ないけど、平衡で思い出した。某福岡氏の「動的平衡」ってやつですが、最初見たとき、これって「非平衡定常じゃん」と思った。が、分野によっては「動的」でも「平衡」と言うんですかね。
閑話(って何が本題だろう^^;;)。
先日 kikulog のコメント欄 でちょっとだけ出た話題について、若干違和感があったので。
浮力をどう教えるか?という話なのだけれども、まあ元の話の文脈はここではちょっと忘れましょう。
説明が二種類ある。一つは、kikulogでYMNさんという方がリンクしている先 に書いてあり、またきくちさんも述べていることだが、簡単に言うと、水中の「水」の重さをばねばかりで測るとゼロになるから、水中に物体を入れると、おしのけた水の分だけ空気中より軽くなる(ばねばかりの示す値が変化する)というもの(ガモフの説明)。もう一つは、圧力差で説明する、というもの。で、高校では直方体の上下の圧力差で説明しているが、浮力は形に依らないので、いかがなもんでしょう、と。
たしかにそれはそれで問題としてあるのだけれども、ガモフの説明で事足りるかというと、それはどうも納得がいかない。というのは、ガモフの説明では、何がどのように水中に沈めた物体に力を及ぼしているのかがまったく理解できないからだ。
直方体を使った説明の何が問題かといえば、物体の大きさが有限(微小量でない)ということにある。では、きちんと圧力差で説明しようとするとどうなるか。本質的には静水圧平衡(静力学平衡)の概念が必要になる。
まず、水の密度をρ0とし、深さ水槽の底からの高さhでの圧力をP(h)とする。そこからΔhだけ上昇した点での圧力をP(h+Δh)≒P(h)+ΔPとしておく。当然、ΔP<0である(水面に近いほど圧力は減るので)。深さ高さhにおける流体素片の体積をΔV=SΔhとおくと、圧力差と重力が釣り合っているなら全体の力は(上向きを正にとる)、
F = P(h)S-P(h+Δh)S-mg = -SΔP-ρ0 ΔV g = -S ( ΔP + ρ0 g Δh ) = 0
となって、
ΔP = - ρ0 g Δh
が成り立つ。Δh→0 にとれば、
dP/dh = - ρ0 g
となる。平衡状態ではこうなっている。
さて、水中に沈める物体の質量をΔm、密度をρ、体積をΔVとしよう。ここで微小体積を問題にするので、水の場合の流体素片と同様に、物体を微小な高さ方向に対称な形状とし、底面積をS、高さをΔhとする。
この物体についての運動方程式をたてると、
Δm a = P(h)S - P(h+Δh)S - Δm g = -SΔP - ρSgΔh = -S ( ΔP + ρgΔh )
= -S ( -ρ0 g Δh + ρgΔh ) = SgΔh ( ρ0 - ρ)
となって、水の密度との差だけ軽くなることがわかる(密度が水より大きいと加速度が負、つまり沈もうとする)。
あるいは、同じ体積の水の質量を上で書いたように m と置いておくと、
Δm a = mg - Δmg = -(Δm-m)g
となって、まさに物体が押しのけた水の質量 m だけ軽くなっていることが示される。
というわけで、直方体での説明は、力を及ぼす実体のイメージを持たせつつ、微分が使えない高校物理での苦肉の説明だと思う。直方体の大きさを微小としさえすれば水中での圧力を深さの関数として表すことが可能となり、一旦それを認めてしまえば、あとは「物体が押しのけた水の量だけ軽くなる」というのを示すのは容易であるし、なにより水が力を及ぼすことで(上からも下からも、あと今回は省略したけど横からも)浮力が働くというイメージを持ちやすいのではないだろうか。
もちろん、話の入口としてのガモフの説明は大いに結構であると思う。それは、「だってそうじゃなかったら色々矛盾しておかしいじゃん」という、今まで学んできたこと同士の整合性を取り、論理的に非自明なことを導くという良い訓練になっていると思うから。でも、そこで留まるのはどうかなあ、と思うのであった。
あ、notation が妙なのはすんません(mとΔmが並ぶのはキモチ悪いよなあ。でもHTMLだと添字をつけるの面倒だもんで…)。
あともう一つ、kikulogでもリンク先の方も、当然「どっちが悪い」という議論はしておりませんので、念のため。どちらも大切だけど、ガモフ的な考え方が軽視されているのでは、という趣旨です(と私は読みました)。それには賛成です。
ではなんでわざわざこんなエントリあげたかというと、極限操作の厳密性を抜きにすれば、この程度できちんと理解できるから、ということを示したかったわけです。まあ高校ではつらいかもしれんけど。でもさ、静水圧平衡を理解していれば、大気の構造とかも理解できちゃうわけで、コストパフォーマンスの良い教養だと思います。
***
追記。全然関係ないけど、平衡で思い出した。某福岡氏の「動的平衡」ってやつですが、最初見たとき、これって「非平衡定常じゃん」と思った。が、分野によっては「動的」でも「平衡」と言うんですかね。
メモ2
「メモ」
の続き。
もはや mzsms さんを中心としたやりとりは視野外です。だいたい Judgementさんの最近の一連のエントリ及びそのコメント欄での議論を見て考えたことのメモです。メモなのでまとまっていません。まだまとまらない。けど書かないとまとまらないので出します。すいません。たぶんとても当たり前のことです。あちらでの議論の筋からも外れていると思います。応答とかそんなんじゃなくて、ちょっとこういう論理はどうなんだろう、というあたりで考えたことを。
一言だけ述べておくと、「その後」の mzsmsさんのエントリを見てもわかるように(たぶん)、「科学」と「宗教」や「道徳」などとの「境界」についての分析がまだまだ大雑把なので、これ以上なにかを言う気はしません。どのあたりが大雑把と感じるかは前回のエントリに書いた。おそらくメタな視点があまりに強過ぎて、実際の現象でどうなっているかの分析が足りなくなっているのだと思う。抽象的に分けられるだの分けられないだの言ってても始まらなくて、具体的事例でもって検討を積み重ねていくことが大事だろう、とだけ指摘しておきます。
○戦場は選択できるか
たとえば家族が怪しいものにハマってしまって、それをなんとかしたいとでも言うのであれば、しのごの言ってるヒマはない。こちらに選択権はなく、完全なる防衛戦である。しかしそれだけではないだろう。巷に溢れるニセ科学のどれを批判するかは「優先順位問題」と言われるようにそれぞれの人が選んでいるのである。なぜ選択できるかといえば、逆説的に聞こえるかもしれないが全面的な防衛戦になっているからである。つまり、そこらじゅうが戦場なのであり、どこで参戦するか、どこで陣地を築くかは実に消極的ではあれ批判する人が選んでいるのだ。
優先順位問題の議論の仕方にもおそらくは色々あって、「○○の批判をしないのはケシカラン」的な主張はまったくもって非生産的ではあるが、「○○は批判する必要があるよね」「○○は興味のある人にまかせておいても当面は大丈夫かな」「○○を批判することは、社会的には□□という意味があるよね」という議論は意味があると思う。いやもちろん意味のある議論が可能だろうと思うだけだけど。ただ、たとえば学校教育における諸問題は「水伝」を通してあぶりだされるのではないか(全部ではないにしろ)、だとすると、「水伝」をキーとして教育現場の問題を批判していくことは重要ではないか、とか、そういう社会的な、あるいはある領域での「位置付け」としてどこに防衛戦の陣地を築くかということは議論する価値が(少なくとも原理的には)あることだと思う。
○「括る」ということ
本質は常に現象をまとって現れる。我々が見るのは常に現象である。我々は「ニセ科学」を見るのではなく、個別の問題、血液型性格判断や水伝やマイナスイオンや波動やEMや…を見るのである。これらに共通しそうな要素を持つものを、「ニセ科学」と括ったわけだ。そしてその括りが一面の本質を衝いていたということは、その一言で世の中に蔓延する様々な問題の関連が見えてきたということからもわかるだろう。
では、具体的にあるのが抽象的な「ニセ科学」ではなく個別の問題であり、批判は常にそれら個別の問題であるからと言って「ニセ科学批判」と括ることに意味はないのか?それは違うだろう。批判対象は「ニセ科学」として括られる「なにか」を持っているわけである。批判の内容は個別の問題に応じて違うのは当たり前で今更言うまでもないが、批判の対象はなんらかの共通点を持っているわけだ。だから、共通点を持っているものそれぞれへの批判を「ニセ科学批判」と括ることには意味があるだろう。
様々な人が様々な観点で批判しているわけだし、誰かが指揮を下して批判をしているわけでもない。必要な場合はそのことを強調しなければならないこともあろう。しかしそれは逆に言えば客観的にはニセ科学を批判するということがある種の党派性を帯びるということであり、それは避けられないだろう。
もっと言えば、「科学者」って一体なんだ、ということだ。「科学者」が行っているのは個別の課題についての研究であって、抽象化された「科学」をやっているわけではない。それでも「科学」や「科学者」と括ることには意味があるわけだ。そして、科学が重要であるという「価値観」はまるで常識のようになっているからなかなか気付かないが、それだって「科学が重要である」という「価値観」を我々は選択し、また科学を遂行するために「科学者」というものを雇うような社会の仕組みを作っているわけである。そのことは、論理的には科学に価値を見出す集団という党派性を持つわけである。
いや、このあたりは相対主義と議論する際には当然の前提としておかないと話が噛み合わないと思うのだが、あまりに「括ること」「括られること」への忌避を正面に押し立てるのは、かえって変な方向に進みかねないという気がするのだが。
各種のニセ科学を批判していくことに社会的な意味を付与しようというのであれば、そのようなニセ科学を対象とする批判を「ニセ科学批判」としてまとめるのは議論の出発点として大事なのではないかなあ。
科学を大事にする、そして科学的思考を大事にするというのは一つの価値観だ。そしてそれは(いちおうは)社会的合意とされているはずだ。問題は、それがないがしろにされつつあるのではないか、ということだろう。一般の人々についてもそうだし、そのような科学的思考を教育することの放棄を迫っているのではないかとさえ思われるような政策いおいてもそうだ。科学を大事にするべきだという立場はアプリオリには出てこないだろう。だとすれば、その発想自体は「道徳」などと同列に語られるものだと思う。無論、その「御利益」が莫大であることが(テレビが見れるとかネットができるとか美味しいものが食べられるとかの「御利益」を良しとする立場であれば)導かれるわけで、それは「根拠」にはならないが「判断基準」として重要なものである。
そして、そういう社会的なプロセスがあってこその「社会における科学」だという認識があればこそ、「科学ではない大事なもの」を大事なものとして認めようということにもなると思うのだが。
念のために言っておくと、優先順位は強制されるものではないし、誰かの批判の方法に準拠しなきゃいけないというのもおかしな話だし、基本的にやりたい人がやりたいようにやればいい話なのだ。ただ、これだけ色々なものが蓄積されてきたのだから、それこそ「戦略的に」動こうと思えば動けるのではないのかなあ、と思うわけ。戦略をたてるだけの議論は無意味だけど、現象に寄り添いつついま必要なものはなにか、という議論が深まるなかで、じゃあそれは自分がやってみましょう、という人が出てくるのが理想的だと思うのですけどね。どうでしょう。
# 考えがまとまらんうちに考えながら書くと、やっぱし無駄に長くなるな。(^^;;
もはや mzsms さんを中心としたやりとりは視野外です。だいたい Judgementさんの最近の一連のエントリ及びそのコメント欄での議論を見て考えたことのメモです。メモなのでまとまっていません。まだまとまらない。けど書かないとまとまらないので出します。すいません。たぶんとても当たり前のことです。あちらでの議論の筋からも外れていると思います。応答とかそんなんじゃなくて、ちょっとこういう論理はどうなんだろう、というあたりで考えたことを。
一言だけ述べておくと、「その後」の mzsmsさんのエントリを見てもわかるように(たぶん)、「科学」と「宗教」や「道徳」などとの「境界」についての分析がまだまだ大雑把なので、これ以上なにかを言う気はしません。どのあたりが大雑把と感じるかは前回のエントリに書いた。おそらくメタな視点があまりに強過ぎて、実際の現象でどうなっているかの分析が足りなくなっているのだと思う。抽象的に分けられるだの分けられないだの言ってても始まらなくて、具体的事例でもって検討を積み重ねていくことが大事だろう、とだけ指摘しておきます。
○戦場は選択できるか
たとえば家族が怪しいものにハマってしまって、それをなんとかしたいとでも言うのであれば、しのごの言ってるヒマはない。こちらに選択権はなく、完全なる防衛戦である。しかしそれだけではないだろう。巷に溢れるニセ科学のどれを批判するかは「優先順位問題」と言われるようにそれぞれの人が選んでいるのである。なぜ選択できるかといえば、逆説的に聞こえるかもしれないが全面的な防衛戦になっているからである。つまり、そこらじゅうが戦場なのであり、どこで参戦するか、どこで陣地を築くかは実に消極的ではあれ批判する人が選んでいるのだ。
優先順位問題の議論の仕方にもおそらくは色々あって、「○○の批判をしないのはケシカラン」的な主張はまったくもって非生産的ではあるが、「○○は批判する必要があるよね」「○○は興味のある人にまかせておいても当面は大丈夫かな」「○○を批判することは、社会的には□□という意味があるよね」という議論は意味があると思う。いやもちろん意味のある議論が可能だろうと思うだけだけど。ただ、たとえば学校教育における諸問題は「水伝」を通してあぶりだされるのではないか(全部ではないにしろ)、だとすると、「水伝」をキーとして教育現場の問題を批判していくことは重要ではないか、とか、そういう社会的な、あるいはある領域での「位置付け」としてどこに防衛戦の陣地を築くかということは議論する価値が(少なくとも原理的には)あることだと思う。
○「括る」ということ
本質は常に現象をまとって現れる。我々が見るのは常に現象である。我々は「ニセ科学」を見るのではなく、個別の問題、血液型性格判断や水伝やマイナスイオンや波動やEMや…を見るのである。これらに共通しそうな要素を持つものを、「ニセ科学」と括ったわけだ。そしてその括りが一面の本質を衝いていたということは、その一言で世の中に蔓延する様々な問題の関連が見えてきたということからもわかるだろう。
では、具体的にあるのが抽象的な「ニセ科学」ではなく個別の問題であり、批判は常にそれら個別の問題であるからと言って「ニセ科学批判」と括ることに意味はないのか?それは違うだろう。批判対象は「ニセ科学」として括られる「なにか」を持っているわけである。批判の内容は個別の問題に応じて違うのは当たり前で今更言うまでもないが、批判の対象はなんらかの共通点を持っているわけだ。だから、共通点を持っているものそれぞれへの批判を「ニセ科学批判」と括ることには意味があるだろう。
様々な人が様々な観点で批判しているわけだし、誰かが指揮を下して批判をしているわけでもない。必要な場合はそのことを強調しなければならないこともあろう。しかしそれは逆に言えば客観的にはニセ科学を批判するということがある種の党派性を帯びるということであり、それは避けられないだろう。
もっと言えば、「科学者」って一体なんだ、ということだ。「科学者」が行っているのは個別の課題についての研究であって、抽象化された「科学」をやっているわけではない。それでも「科学」や「科学者」と括ることには意味があるわけだ。そして、科学が重要であるという「価値観」はまるで常識のようになっているからなかなか気付かないが、それだって「科学が重要である」という「価値観」を我々は選択し、また科学を遂行するために「科学者」というものを雇うような社会の仕組みを作っているわけである。そのことは、論理的には科学に価値を見出す集団という党派性を持つわけである。
いや、このあたりは相対主義と議論する際には当然の前提としておかないと話が噛み合わないと思うのだが、あまりに「括ること」「括られること」への忌避を正面に押し立てるのは、かえって変な方向に進みかねないという気がするのだが。
各種のニセ科学を批判していくことに社会的な意味を付与しようというのであれば、そのようなニセ科学を対象とする批判を「ニセ科学批判」としてまとめるのは議論の出発点として大事なのではないかなあ。
科学を大事にする、そして科学的思考を大事にするというのは一つの価値観だ。そしてそれは(いちおうは)社会的合意とされているはずだ。問題は、それがないがしろにされつつあるのではないか、ということだろう。一般の人々についてもそうだし、そのような科学的思考を教育することの放棄を迫っているのではないかとさえ思われるような政策いおいてもそうだ。科学を大事にするべきだという立場はアプリオリには出てこないだろう。だとすれば、その発想自体は「道徳」などと同列に語られるものだと思う。無論、その「御利益」が莫大であることが(テレビが見れるとかネットができるとか美味しいものが食べられるとかの「御利益」を良しとする立場であれば)導かれるわけで、それは「根拠」にはならないが「判断基準」として重要なものである。
そして、そういう社会的なプロセスがあってこその「社会における科学」だという認識があればこそ、「科学ではない大事なもの」を大事なものとして認めようということにもなると思うのだが。
念のために言っておくと、優先順位は強制されるものではないし、誰かの批判の方法に準拠しなきゃいけないというのもおかしな話だし、基本的にやりたい人がやりたいようにやればいい話なのだ。ただ、これだけ色々なものが蓄積されてきたのだから、それこそ「戦略的に」動こうと思えば動けるのではないのかなあ、と思うわけ。戦略をたてるだけの議論は無意味だけど、現象に寄り添いつついま必要なものはなにか、という議論が深まるなかで、じゃあそれは自分がやってみましょう、という人が出てくるのが理想的だと思うのですけどね。どうでしょう。
# 考えがまとまらんうちに考えながら書くと、やっぱし無駄に長くなるな。(^^;;
七田眞氏死去
なんともいえないフクザツな気分である。『朝日』
より。
息子のほうがどれくらい超能力や波動に染まってしまっているのかわからないけれども、今後、あきらかにトンデモな部分を減らし、徐々に路線変更していくといいなあ、というのは単なる願望にすぎないかな。すぐには変わらないだろうし。
いずれにしても、七田式についてはまとまった批判があまりないので(散発的にはたくさんあるけれども)、いまのような「七田式」が続く限りはどこかできっちりやらんといかんのだろうなあと思う。私も何冊か古本屋で集めたけれども、なかなか手が回らないというのが実際のところ。
「超右脳革命」 七田式教育提唱の七田眞さん死去まあ息子が後を継いでやってくんだろうけど。能見親子みたいに。2009年4月22日21時33分
七田 眞さん(しちだ・まこと=しちだ・教育研究所会長)22日死去、79歳。葬儀は近親者で行う。社葬は26日午後2時から島根県江津市江津町1110の17の市総合市民センターで。喪主は次男の同研究所社長厚さん。連絡先は同研究所(0855・52・4803)。
七田式教育を提唱し、著書に「超右脳革命」「できる子の親がしている70の習慣」など。
息子のほうがどれくらい超能力や波動に染まってしまっているのかわからないけれども、今後、あきらかにトンデモな部分を減らし、徐々に路線変更していくといいなあ、というのは単なる願望にすぎないかな。すぐには変わらないだろうし。
いずれにしても、七田式についてはまとまった批判があまりないので(散発的にはたくさんあるけれども)、いまのような「七田式」が続く限りはどこかできっちりやらんといかんのだろうなあと思う。私も何冊か古本屋で集めたけれども、なかなか手が回らないというのが実際のところ。