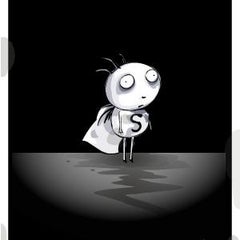For example…
https://en.wikipedia.org/wiki/X%2BY
上記HPより画像お借りしています。
↑皆の事が頭に浮かんでいる様子を表現しているようで、大好きな構図のポスター。
○僕と世界の方程式/X+Y(2014)
監督 モーガン・マシューズ
☆☆☆☆
出/エイサ・バターフィールド、ジョー・ヤン、サリー・ホーキンス
モーガン・マシューズ監督自身によるドキュメンタリー『beautiful young minds』(2007)を元にした劇映画デビュー作。本作は2014年製作。
そして劇映画デビュー作にしてライアン・レイノルズが出演してるのかと思ってみていると、その人はレイノルズじゃなくてレイフ・スポールだという事が徐々に判明していきます。『ライフ・オブ・パイ/トラと漂流した227日』で記者を演じていた人です。
あたいってば眼が悪くなったのかしら? てへへ(このふたり似てますよね?)。
えー、まずこの『僕と世界の方程式』を観まして、とても好きになったので本作の元となるドキュメンタリー映画を観たいなと。それで、知識がゼロだった自閉症スペクトラムについても調べつつ、『beautiful young minds』を観ました(youtubeに本編上がってます。中国か台湾の方が付けてくれたらしき字幕が大助かりです)。
さて。
……映画はドキュメンタリーまんまやな!!
マジそのままだったから逆に驚いたわよ。
いまのところ日本版という事では『beautiful young minds』を観られないので、こちらのドキュメンタリーのネタバレも挟んでいきます。あしからずです。
まずですね、自閉症は聞いたことあるけどスペクトラムって何ですかと。
何ですかと独り言をつぶやいても誰も教えてくれなかったので、ネットで読める紀要などを印刷して読んでみました(パソコン画面で読むのが苦手というね。目が疲れるんだもん)。
まず1本目は、<<アメリカ精神医学会の改訂診断基準DSM―5: 神経発達障害と知的障害,自閉症スペクトラム障害>>(2014)と題された宮川充司が書かれたものです。
こちらを読むとまず自閉症とかアスペルガー症候群とか周辺症状含めて多岐にわたっていたのを、DSM-5という診断基準の最新版(だから以前はDSM-Ⅳだった)を出す時にまとめたのが自閉症スペクトラム障害という呼称であると。スペクトラムとは連続体という意味。
その他の病気では、多くの病状でより効果的な治療を施せるように細分化が進められる中で、自閉症に関してはまとめられたというのは何故か、という話をされています。
もう一本は<<自閉症スペクトラム児と親の支援に関する調査研究 -親のアンケート調査から->>(2009)と題された前田明日香、荒井庸子、井上洋平、張鋭、荒木美知子、荒木穂積、竹内謙彰たちが書かれたものです。
こちらの論文で驚くのは、小さい頃に受けていた補助が、学校に通う年齢に達すると得られなくなる事が多いという話。アンケートや統計なんかでも、学習年齢に達してからの障害児の両親の負担は増しているのに、です。
何故かって、そもそもお年頃の方が大変なのは自明だし(難しい年頃って言葉があるでしょうよ)、学校という集団の中で立ち回る事が本人に要求され、子供が大丈夫である+上手くやれるかという心配が増える事になる両親も大変になるに決まってんじゃん。行政は馬鹿なの?
この『beautiful young minds』で印象深い場面が、ジョスという映画版でのルーカスのモデルとなる青年が、症状は様々あるのに同じ病名で呼ばれるから、「だから皆が、レインマン的な!って考えるんだろ」という発言を悲しそうにするところ。
同じ障害があるっていうだけで、十把一絡げにされてしまう。個性だ個性だと騒ぎたてる世界が、自分の事を見る前にまず障害を見てくる。俺はジョスであって、アスペルガー症候群って名前じゃねーから! そこんとこ夜露死苦!
ちなみにこの人が中心となってドキュメンタリーは進んでいくんだけど、途中で輪に加われない+性格が傲慢な事からオリンピック選抜キャンプの仲間たちから、ハッキリ言って虐められるというところまで関係が悪化していく(映画でもいじめの描写がありましたね)。そしてルーカスと同じように選抜には選ばれず、途中で消えてしまう。
話の中心はダニエルという青年へ移っていく。ダニエルは中国で出会った恋人がいたりと、エイサ・バターフィールド扮するネイサンのモデルとなっている人物。彼は一旦選抜から落とされるものの、敗者復活的にキャンプに呼び戻され、さらに数学オリンピック選抜6名に入り最終的には銀メダルに輝く。
ちなみに数学オリンピック=International Mathematic Olympiadという事でIMOと呼ばれます。
で、このダニエルの恋愛事情なんかもドキュメンタリーで大きく取り上げられます。というかほぼプロポーズみたいな「同居してくれる?」という問いかけに彼女が「…………(結構長考する)yes」って答える、身悶えのあまり観ているこちらがどうにかなってしまいそうな場面まであるんですよ!! ラブコメか!! リア充か!!
映画の方を観ていて、割と数学オリンピック自体はどうでもいい感じに話が展開するのですが(エディ・マーサンの感じ悪い先生含めてね)、それも納得の甘酸っぱさ。ちなみにドキュメンタリーのエンディングでは……(ダニエルとシュー・ヤンが結婚します! ッキャー♪)。
でもドキュメンタリーだと、ジョスが後半でも映されるんですよ。もうIMOの連中と絡んだりはないんですけれど、監督が彼の家を訪ねて「そういや今日IMOの結果発表じゃないのー」とか水を向けるとジョスが「え!? あ、ほんとだ。すっかり忘れてたわw」みたいな言い訳かましつつ速攻でネットの結果発表ページを開く。
……映画は、それしかない事の苦悩を描いていたけれど、ドキュメンタリーではそれしかない事のどうしようもないまでの情熱をも捉えていたと思います。
オリンピック出場の夢は断たれたけれど、ジョスも大学へ進学して数学の研究を続ける(本人曰く「本物の数学の」)。
で、ちなみに映画版の方も「たいがい『グッド・ウィル・ハンティング/旅立ち』ですなと思いましたが、ドキュメンタリーの時点でそうとうガス・ヴァン・サントしてますので、確実に意識はしていると思います(テロップが出る時の背景とか……数学を扱う映像作品はみんな似てるぞう)。
映画の話に映りますが。
同じように自閉症の彼の気持ちや、彼が両親から言われた言葉(同じ言葉)、それがわかる。だから父親以外の人の言葉にも大きな意味はあって、「愛する人を失うと悲しい」という言葉の集合には感情を説明する意味が込められていて、自分が愛する人を失った事故へと記憶が戻ったとき、他にも愛する人を失った人がいることがわかる。
自分と同じ思いをした人。お母さん。この思いをさせたくない人。チャン・メイ。どうすればいいかわからない人。僕。どうしたらいいか聞ける相手。お母さん。移動手段。車。運転できる人。お母さん。隣にいてくれる人。お母さん。隣にいたい人。チャン・メイ。
言葉に表せない気持ち。という言葉がありますし、その場合に言いたいことは多くの人には「言い表せない」と言えば伝わる。でも当てはまる言葉を探し続けても良いはずです。説明できる言葉を探し続ける人を、他人は「心で感じる事の出来ない人」と断ずる。事がある。
心で感じる事の出来ない人=変人。これが世界の公式になっている。だからあまりこの映画の邦題は好きじゃない。方程式で解を求めるのではなくて、言葉を尽くして説明しろと訴えている映画だと思うから。
答えはある。だからその問題を解く過程を楽しみましょうよっていう。だって証明できる場合もあれば、証明できない事が証明される事もあるから。
他者が自分を理解してくれないのは外国語を喋っているみたいな感じ、という冒頭で示される素晴らしい哲学が映画全編を支えています。言葉ですんで学べます。知らない言葉だったら教えてもらったり教えてあげたり。独りでも学べるし。本でも、映画でも、その辺にあるお店の看板でも。
言葉が増えると何が良いか? 人に説明する時のツールが増える。自分を理解する手段が増える。
答えはシンプルだと美しい、という考えもありますが、人の気持ちは形がないから多くの言葉で説明を試みた方がより伝わるはずです。相手は自分ではないし、心は不可視かつ無限大だから人それぞれ違う。それぞれ違う物を単純化して伝えても、それは元の形、伝えたかった形とは違うものかもしれない。一部で満足する必要はなくて、全部伝えようとし続けて良い。
この映画では主人公に何かを伝える時に、感情までも言葉によって説明する必要があります。夫が死んで悲しい時にも、悲しさの形を言葉で伝える必要がある。これが上手くできる人もいるし、下手な人もいる。
でも下手な人は言葉の数を増やせば良いだけだし、主人公だってどんどん感情の形や色を蓄積して理解が深くなっている。
人が時間をかけて成長する事、そのものを肯定しているんだと思います。
映画の原題はX+Yです。代数学ですね。何を代入しても良い。そしてこのタイトルは、「=」がついていない。解を求めているのではないんです。
お店の人に無理言ってエビを7つにしてもらってもいいし、8個入ってたから1個食べちゃってもいい。
XとYだから染色体の意味もあるのかな? だとすると、子供が生まれる仕組みって事かな。愛って意味だったら、X+XでもY+YでもY+X+Yでも良い筈ですからね。
自閉症スペクトラムは相手の気持ちがなかなかわかりづらいという症状がある場合もあって、友達が出来づらいと気に病んでいる方も多いそうです。
誰だって友達欲しいし、だからユーモアを勉強しようとして『モンティ・パイソンの空飛ぶサーカス』も暗記する。でもいくらイギリス人相手でも流石に古かった……という意味では無く、コミュニケーション手段に「不条理」ギャグを選んじゃったのでいずれにしろ理解できないという高度なギャグになってますね。もうそれこそモンティ・パイソン級の。
ちなみにこちらのスケッチは「The Parrot Sketch」という事で、「オウムのコント」ですね。実際にパイソンのスケッチをDVDにて再見しましたが、観ていると「不条理」で理解できない事を訴えるのではなくて「話がまったく噛み合わない」のがおかしいっていうコントでした。買った人はオウムが死んでいると言う。売った人はオウムは休んでいるだけだと言う。
あのー、芸術だと理解不能な事が賞賛されるのに、人間関係だとちょっとでも理解不能な部分があるってだけで排除されてしまう。
映画を1本も観た事ない人がシュールレアリズム映画を観たら「ふーん、映画ってこんな感じなんだねー」と思うところを、映画を観た事がある人だと「なにこれサイテー、意味わかんねー!」となる。
その人にとって面白いかどうかは別として、何かの価値を判断する時に人は通常、社会が作ったイメージを利用します。
例えば僕で言えば、「脚本が上手」というのを「伏線の張り方がよいので」みたいな説明でいつも書いています。ただしこれだと言葉を省いちゃってるんですよね。丁寧に直すと「この映画では後で重要な人物となるキャラクターがつねに明るい服を着ているなど伏線の張り方が目立たないながらも印象には残るため、脚本が上手に働いていると僕は感じる」ってところでしょうか。
これで言いたいのは、伏線の張り方がいいと上手な脚本、という社会的(映画業界的?)なイメージを無意識に僕が利用しているということ(映像を特に注視する人からすれば些細な事かもしれない)。こんな些細な文章であっても、人と社会とは切れない。
だから、その社会的なイメージが中々わかりづらい人へ何かを説明するというのは、いい訓練になるんだって事です。
1人の人間にとって大事な人の数なんてたかが知れてます。社会との関わりはその人たちとより良く生きる為の訓練です。
でも誰が自分の大事な人かは、その人を探しださない事には理解できない。だから社会に対してだって気持ちを砕く。あなたは僕の大事な人かもしれない。だから社会も僕に気持ちを砕いて欲しい。僕はあなたの大事な人かもしれないから。
僕が死んでるエビを起こそうとする意味が判らなかったら、「何それ」と聞いて欲しい。「どういう意味なの?」と聞いて欲しい。「モンティ・パイソンだよ」と僕が答えたら、スマホで検索して欲しい。Youtubeで動画を見て欲しい。僕だって死んだ鳥を起こそうとする意味なんて判らないって知って欲しい。友達になろうって言ってるんだよ。
一緒に勉強しようって、誘ってるんだよ。
でまあ、自閉症スペクトラムの症状ってまちまちだし、重度の人も軽度の人もいる。だから映画の中で、比較的重度の男の子(ルーカス)に対する「自閉症の症状だよ、やだねー」みたいな罵詈雑言を比較的軽度の主人公に対して仲間たちが発言する場面があります。
病気の症状である、という知識があっても対処できないのはまあ、高校生だしなとも思いますが、しょうがなくはない。
山登りだったらペースゆっくりな人を先頭に立てて歩くのが基本であり、それについて文句言う人なんてそう居ないでしょ?
なんだろ、色々な人の色々な立場を想像してみる。尊重できないならしなくたっていい、それはその人の勝手だし。でも「そういう場合どうしたらいいのか」という勉強はしてたっていい。もしかすると後年考えが変わった時にまたそういう場面や人に巡り会うかも知れないし。小説でも書くなら役にも立つじゃない。人前でかっこつけたい? なら知っておくといいんじゃないかな? 利用したっていいから関わり合いを断つのはやめてくれ。存在を無視しないで欲しい。
理解できなくていい。理解しようとして欲しい。
僕は辞書じゃなくて小説なんだよ。つまらないなら批評をして欲しい。面白い部分を見つけて欲しい。マーカーを引いて、しおりを挟んでおいて欲しい。読み終えたら題名だけでも覚えていて欲しい。
気がついて欲しい。この本はあなたが知っている言葉で書かれている事を。読める。誰だって、読めるんだよ。
大佐:(画面に入って来る)まったくだ、まったくだ。バカバカしいったらありゃしない。よし、次だ、さっさと次をやれ!
www.starkafterdarkonline.com/?paged=3
上記HPより画像お借りしています。