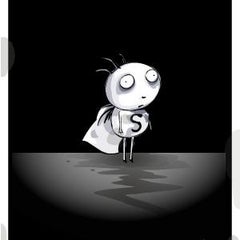言葉に色は着いてない。
https://twitter.com/greenbookmovie/media
上記HPより画像お借りしています。
監督 ピーター・ファレリー
☆☆
出/ヴィゴ・モーテンセン(太)とマハーシャラ・アリ(細)の天国二人道中
あの、スパイク・リーが噛みつきましたね。『グリーンブック』のアカデミー作品賞受賞に対して。曰く「俺は呪われてる!」(彼がアカデミーにノミネートされる度に白人運転手物に賞をさらわれる事に対して)
で、これに対して噛みつき返す人が結構いましたね。スパイク、またかよって。
彼は白人が黒人に関する映画を撮ろうとするととにかく噛みつく(映画内にひとり居ればサベツシテマセーンの証となると白人が言ってる黒人キャラクターことマジカル・ニグロなんて言葉も生み出しつつ)。
で、お前だって『サマー・オブ・サム』とか非黒人主演の映画撮ってんじゃん! みたいな返しをされる訳ですよね……。
これね、最終的には(人類の終わりとかのスケールでですが)どの人種が誰をどう撮ったって構やしない、現代はそういう日が来ることを待ってるところって感じです。
例えばスティーヴ・マックィーンとマイケル・ファスベンダーのコンビは最高じゃんすか。黒人監督白人主演でこれからもぼかすか傑作撮って下さいよと思いますよね。この2人だけを観ていれば「ほら、噛みつく前に手を取り合うことも出来るよ」的な思いも去来します。
でもスパイク・リーがとにかく噛みついている事に意味はあると思うんですよね。
今までがそうだったし、今もまだそうである事柄に対して声を上げ続ける。人種っていう言葉がこの世にある限りは、スパイク・リーがとにかく噛みついている事に救われてるぜって人も大勢いる筈です。
僕はスパイク・リーでも何でもないですし、黒人でもないですけれど、彼が続けている事がどれぐらい大変な事かはなんとなく想像できる。
「映画ファンからまたかよスパイクと呆れられる」「企画が気に入っても自分の立場を優先して断ることがある」「マスコミからはなんかイタい人扱い(新作が面白い場合は除く)」
自尊心すげえ傷ついてると思いますよ。
でも、隠すのが上手になった社会を変える為にはとにかく言い続けなきゃならない。被害妄想だなんだと言われても、映画という拡声器を持っている以上彼は責任を引き受ける。
頭じゃわかっているけど実行し続ける。いやー、格好良いわ。
冒頭。黒人の配管工が使ったコップを捨てるトニー。それを見つけて拾う、「賢明な」妻。
さて、これってトニーは凄い差別野郎って事なんでしょうか。
僕が観て感じた限りでは、彼は「黒人が使ったコップが何となく嫌」「周りの差別発言に同調して合わせる」な感じです。何が言いたいかっていうと、当時は多くの人がそんな感じなんじゃないかって事です。
それが自然な事だった。
差別というのが、全て土壌で醸成されるとは思っていませんが(言い換えればすべてを土地柄のせいにするなって事ですが)、時代やその空気(つまり政治)、歴史、友人関係や家族と言った要素が大きく絡んできますよね。だから……難しいんですけど……考えが偏ってしまう環境で生まれたならば、頭の中に差別が根付くのは避けられない。
でもそれは、変える事ができますよね。
映画の中でも示されましたけど、学ぶことで変えられる。
言葉によっても。
差別って、まずは周りにいる人間の声から自分の中に入ってくると思うんですね(現代ならインターネット含めて)。近しい人の言葉は自分の中に沁み込んでしまう。染みって中々取れないもんですよ。
たかが言葉ではあるんですけれど、言葉って人の心を傷つける武器にもなりますのでね。それだけ強力。
だからこそ、この『グリーンブック』の中に力が唯一の解決策、という場面が含まれてしまった。トニーが銃を撃つ場面がそうですね。
犯罪から身を守ったという理由付けと共に、「やっぱ持ってんじゃん!」というギャグとして描いて笑いも含まれていますが(マハーシャラ・アリのビックリしてる顔が達者過ぎる。この人完全なコメディもいけますね)、「銃を持っていて良かった」という暴力の肯定につながりかねない描写であると思います。
じゃあ暴力を振るわれて金を奪われれば良いんですか? という意見が聞こえてきそうですが、その前に警察呼んどけば良いんじゃないっすかね(警察沙汰避けたいのはわかるけども)。もしくは強盗の存在に気づいていたんだから、もっと時間を空けて車に戻るとか。暴力的に暴力をいさめるのではなくて、頭を使った解決がもっと出来たのでわ。
――これ本当に難しいんだよ。被害を受けそうな方が努力しなきゃいけないのかって問題でもあってさ。そりゃそうなんだけど。う~ん、でもそこから距離を置く事ってできるでしょう。あえて立ち向かうのだってもちろん必要なんだけど、時と場所を選ぶっていうか、自分から死にに行くなよっていうか。僕がよく使ってる、話し合えば分かり合える、っていう考え方と矛盾しちゃうんだけどさ。でも死ぬより矛盾してる方が良いよ。
スタンウェイ用意してなかった差別的オッサンにトニーがビンタかます場面で、とっても陽気な音楽が鳴り始めたって、構いません。スッキリして、でもオッサンはデブで皆に笑われ、多分給料も低くて家では妻にけなされしてるんだろうな、と後で想像してみる。しっかり相手を見ていれば、それぐらいできるはずです。
相手を敬えって話ですが。知らない相手の事は敬えないわけで。尊敬の念を持って誰にでも相対するというのは、僕には難しく思えます。でも、気をつかう事ぐらいはできる。
例えば、普段差別丸出し発言を友達としてる奴ならば、公共の場ではそういう態度を取らないとか。エレベーターで誰かおならしたら、知らんぷりするとか。誰かの失敗を、笑わないとかさ。それぐらいならできるよ。誰だってできるよ。なんでできるかっていうと、それをすると相手が傷つくって事ぐらい判るからです。誰だって判るからですよ。自分だって傷ついてきたんだから。
だからそれを関係ない人への攻撃に向けてしまうんじゃなくて、たまたま自分と同じ場所に居合わせた人への気遣いに向けたいですね。
ジャンル分けされた他人ではなくて、個人として知り合えばきっと変わるはずなので。
さて、肝心の映画の出来ですが……。
始まって少し経った辺りから面白くなります。具体的に言うと、マハーシャラ・アリ扮するドナルドが登場する場面からです。それまではヴィゴ・モーテンセン扮する主人公トニー・ヴァレロンガの紹介場面な訳ですが、これが結構退屈。
酒場の用心棒、という文字で書くと恐ろしく格好良い仕事をしているトニーですが、自身が出世する為にマフィアのボスへ渡りをつけようと「クラーク(コートとか受け取る係)の人が本当に殺されるかもわからない」世渡りテクニックを披露します。
……たかが帽子であんなに激昂しやがって、やっぱマフィアは頭おかしいわ。こんな感じの主張でトニーの行動を正当化しつつ(もともと残忍なマフィアだから何してもいい的な感じにしつつ)、世の中のルールについて描写していきます。
ルールの描写でもうひとつ大事なのは、トニーが自宅アパートの真ん前に駐車する場面です。彼はゴミ缶をひっくり返して散水栓に被せる。消防車のホースをつなぐ散水栓の前に駐車してしまうと消火活動の邪魔になる為、本来はもちろん駐車禁止です。
駐車禁止ってのはかなり明快で分かり易い社会のルールですよね。ルールに被せ物をして隠してしまう=世間的常識を無視する。
しかしトニーは世間的常識である、黒人を下に見る事に対して、思うところはあるものの(コップを捨てるまでに躊躇する時間がある)そのルールを破ったりはしない。
なんかこう書いていると非常に巧みにトニーという人物を紹介している感じがするんですけれど、全然作りが上手くないんですよ。
作りが上手くいってない事を象徴するように、「いつもと違うドッシリした構図」で映画全体をキメてる筈なのに、会話の際の切り返し編集が過ぎて(喋ってる人の顔が常に見えるようにしているので)結局チャカチャカ忙しなくなってしまっています。
ファレリー監督の良い点って、やっぱり脚本構成の巧みさ。特に伏線の張り方とか、いつもスゲー! って驚かされるんですけれども。
ところがどっこいで、今回はその伏線張りも微妙だし(後で出てくるってわかっちゃう感じ)、伏線を回収しているその瞬間も微妙です。ティッツバーグのネタとか何の意味があったんだよって。馬鹿話して仲良くなった表現だとは判るのですがね(他にも、知識が身についても振る舞いを変えないトニーって描写にもなってますな)。いつもならもっと上手だろ! って思っちゃった。やとわれ監督感漂う……。
まあでも、ドナルド登場の場面が最高だったからいいかな!?
チャップリンの『独裁者』とかにあったギャグが登場しますね。余の椅子は貴殿より高い所にあるぞよっていうね。もう爆笑。トニーが面接に挑む直前にアジア系の人とすれ違うのは、チャップリンの運転手や個人秘書を務めた高野虎市をイメージしてるのかな(ちなみに質屋の親父がチャーリーって名前なんですよね。チャップリンの短編映画に『質屋』っていうのがあって、ユダヤ人をステレオタイプ的に描いています……っていう紹介のされ方多いので僕の頭の中でも組み替えられちゃってたけど、実際にチャップリンの『質屋』を再見したら別に言う程ステレオタイプみたいな映画じゃないよなあ。脚立を使ったハラハラドキドキの凄いギャグがあって面白いですよ)。
部屋の中も象牙とかあって、金持ちの悪趣味な感じを強調してますね。ドナルドはドナルドで、首からぶら下げてるでっかい歯のアクセサリーが何の動物の歯なのか自分も知らねーという!
ようするに、後半に説明されるわけですが、彼にとって居心地の良くない部屋なわけですよね。孤独を象徴する。っていうか無茶苦茶神経質な人っていう描写があるからわかりますけど、あんなに物が溢れてる部屋は嫌だよな! いますぐこの部屋片づけてえ、というドナルドの叫びが聞こえてくる! でも「人に馬鹿にされる謂われは無いぐらい金持ってる」という、考えれば考えるほど辛いアピールの為だけにゴテゴテと部屋は飾られ続ける。
でまあ、フライドチキンの骨を道路に捨てるのは土に還るからいいけど、ジュースの紙コップ捨てるのは許しません! という場面なんかで、ドナルドはルールを守る人という描写がなされてルールに目を瞑るトニーと対比されます。
この映画が非常にスノッブで鼻持ちならない感じで気にくわない僕ですが(頭良いのの何が悪いのか? 僕も答えられないですが)、この対比が非常に上手くいっているのはわかります。
ドナルドは男娼を買うわけで、結局人は誰であれ自分がルールに目を瞑る事には甘いんだという。
ルールを破る時に、真面目な人はルールを破る理由を持っていると思います。ドナルドだったら「孤独」だから男娼を買ってセックスしても「仕方ない」。
で、本作が糾弾するのは「差別」ではなくてこの「仕方ない」の方ですよね。
伝統だからとか、みんなやってるからとか、法律だからとか。
トニーとドロレス夫妻のベッドの上には十字架が飾られています。信心深い。イタリア系だしね。
でもこの映画内で神について言及しない。
神に助けを求めるのはみんなやってる伝統ですが、法律(ジム・クロウ法)や慣習を打ち破る為にはそんな事したって仕方ない。
一緒に車に乗っている人間を、人は傷つけられる。車から降りる自由? あるよ。でも目的地は何十マイルも先だよ!
さて、ピーター・ファレリー監督と言えば「底抜けに明るい空模様」とかドギツイ下ネタとかが良く出来た脚本にのせられて物語られる作風ですが……『グリーンブック』では意識的に「真面目」な映画を作り過ぎて「メッセージ」を間違いなく観客に叩き付ける「ほぼ無味無臭」な映画を完成させてしまいました。
好きな方はごめんなさいよ。社会派とか、真面目とか、重厚な傑作とか……そんなんそれこそ皆が作ってる映画だよね? 途中でトニーがドナルドに言うじゃ無いですか。「お前さんだけのプレイを演んなよ」って。で、それを受けてドナルドが「私のショパンは私だけが可能なプレイだ」って答える。
早い話が「今回は王道ですいません」というファレリー監督の言い訳ですよね。
王道は悪くない。むしろ奇をてらい過ぎた映画の方が辛い場合が多い。それは僕もそう感じています。
でも車のトラブルで立ち往生している時に、農場で働く黒人労働者たちと目が合うドナルド……の姿に郷愁漂う音楽が被さって「ここポイントです。真面目に考えて欲しい場面ですよ」と強調してくるのはちょっとどうかと思った次第。
だってマハーシャラ・アリと労働者役の人たちの演技観てれば全部伝わってくるんだもの。「はいここポイント。テストに出すよー」って先生に言われなくてもちゃんとファレリー先生の授業聞いてましたから!
黒人酒場で弾くのがショパンの木枯らし。エチュードって練習曲って意味だそうで……。
練習曲ねえ。ショパン君、ちょっと校舎裏まで顔貸してくれる?(エド木はピアノ習ってました)
僕も実家にあったアップライトピアノであれこれ弾きましたっけ……猫踏んじゃった♪
ところでドナルドの演奏場面ですが、差別レベルの高い会場では「怒りを込めて弾く」といったような演じ分けがされていて非常に巧みですね。感情の乗った演奏場面を観ていると、マハーシャラ・アリはやっぱスゲーなと再認識。
単なる願望なんですけど、マハーシャラ・アリの吹き替えはトム・クルーズの声でおなじみの今は亡き鈴置洋孝が良かったなー。いまも洋孝VOICEで脳内再生されまくってます。
正しい綴り。
美しい文章。
ロマンティックな比喩。
……どれもうっとりする様な手紙には欠かせない要素です。でも手紙を完璧にするのは、「子供らにブッチューしといてくれな」の語りかけなんですよね。
で、最後に「手紙ありがとう」とお互いに是非お会いしたいと思っていた2人が出会う訳ですが(どちらも大変嬉しそう)、ここへ至るまでの道のりがちょっと駆け足。
ドナルドがトニーに文章の指示を出す楽しい場面がいくつもあるわけですが、その前段階であるトニーの手紙を盗み見して彼の家族に好感を抱くドナルド、という場面がほぼ無いんですね。ちらちら気にしてるっていう描写はありますが、トニーの人柄がにじみ出る手紙をじっくり読み込むドナルドという場面が、文章を指示する場面と同じぐらい欲しかった。
ゲイは男と見れば手当たり次第、というクソくだらない思い込みと同じで、孤独な人だから家庭的な雰囲気なら何でもオッケーとはならない。当たり前の話ですが。
性格の合う合わない。友人関係でもありますよね。
で、ドナルドがトニーの友達になったのは、差別しなくなったからとか差別野郎から守ってくれたからってわけじゃないはずです。
ファミコン時代のクソゲーを「ここが直れば名作なのになあ」なんてブツブツつぶやきながらいつまでもプレイしている時と一緒なんですよ。「気に入ったから直して欲しい」であり「直してくれたから気に入った」では絶対ないんです。
だのにこの映画は、「あくまでトニーが主人公」という姿勢で最後に車の運転を交代する場面までトニー視点で描いてしまう。
それでもトニー視点が徹底されていればそれで良いんですけれど、そのちょっと後でドナルドが自宅で孤独っていうトニーの視点を離れた場面があるんだもの!
結局スクリーンに映っているのは「変わる黒人」という事象であり、ドナルド・シャーリーという人じゃないんだよな。
この運転交代の場面ってさ、仕事での主導権が変わったとか、結局運転席に座る事になる黒人とかじゃなくて、友達のために夜を徹して車を走らせてるってだけの場面ですよ。
だから大事なんじゃないかよ。
この場面の前にある、警察に車を停められて云々が物凄い見せ場だとか小さな奇跡みたいに演出されてるけど、孤独な男が生涯の友を得たっていう場面になるはずの部分をどうしてすっ飛ばしちゃうんだよ。
「トニーはもう運転できない筈なのに車が動いている、何故!!?」みたいなちょっとした謎のオチに使ってる訳ですけど、真面目に作ってます映画だったら変にサプライズ風に演出しないで真面目に作ってよ!
あと字幕だけ追っているとわかりづらいのですが、どの蔑称を使っているかというキャラ分けもされています。ヴァレロンガ夫妻であればカラード。トニーにビンタされるおじさんとかはクーンを使っています。
クーンという言葉がどれぐらい侮辱かというのはテリー・ツワイゴフ監督の『ゴーストワールド』を観て頂ければわかるかと思います。
トニーの方もグリースボールとか呼ばれてましたね。
最後の場面は、トニーのファミリーがドナルド来訪に固まってしまう。でも間を空けて歓迎ムードになるというものです。
これって親戚たちから差別心が無くなった訳じゃなくて、トニーに気を使ったわけですよね。お前の友達なんだからって。
これ凄い大事だと思うんですよ。言葉を知る事と同じで、相手の事を知る第一歩になるから。
何となく嫌、を突き破る、かけがえのない一歩だから。
で、ドロレス事トニーの女房は「馬鹿」ではなかったという免罪符で爽やかに締めくくるんですが、映画のタイトルがグリーンブックってお前……「差別!」って書いてあるみたいなもんやぞ。
なんかパンフレットによれば、元々のタイトルは『Love Letters to Dolores』だったという事ですが、このトニーとドナルドが共作した手紙を題名としているのと『グリーンブック』では印象が丸で違いますよねー(ドナルド側遺族への配慮かもしれないけどさ)。
あとこれは技術的過ぎて正しく指摘できるわけではないのですが、Blu-rayで本作を再見していた際に「全然フィルム感ないぞ?」と感じたんですよ。ツルッとした画面でまったくざらざらしていない印象。
劇場で観た際にはそんな事思わなかった筈なので、Blu-rayソフトの作りの問題なのかも知れませんが……より人工度が高まっている気がしました。
P.S.ファレリー映画と言えばの障害者たちが出演している場面はどこへ消えたの? 60年代には彼らはいなかったの?(意地悪な発言でスミマセン。でも気になっちゃうんだもの! 差別心は心の畸形って事なのか?)
![]()
にほんブログ村https://blog.with2.net/link/?2015489