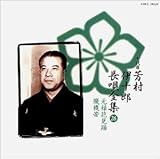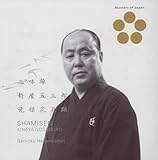花に遊ばば祇園あたりの色揃ひ、東方南方北方西方、
弥陀の浄土へひつかりひかひか、光輝く花揃ひ、わいわいわいとな。
浮世とは、浮いた騒ぎに浮かれて暮らす。
夜を昼なる全盛は、軒の燈火闇路も明く、花の街に土地一力の、広間につづく長廊下、
手の鳴る方とさんざめく、声にそやされうろうろと、酒にめんない千鳥足。
出会頭に手を取って。
「それ酒ぢゃ酒ぢゃ」
目隠しとって、これは失礼人違ひ、御免御免とたわいなき、体ぞ仲居も末社ども、手持無沙汰のきょろきょろ目、
酒はさめねど興さまし、こそこそ逃げて行く影を、ぢっと見送り侍達。
「大星氏、お頭お眼覚まされませう」
揺り起こされても心は空。
「東の出立はいつ頃でござるな」
「これは又きつい野暮、我等の相手は天の美禄」
(小唄)そもや神代の昔を今に、お神酒捧げぬ神はない
ちょっと銚つけとさし出すを、全く本心放埓と、袖振りきっておもて口、畳蹴立てて出でて行く。
更けて廓の粧見れば、閨の燈火うちそむき、浮き寝の床の夢の花。
散らす嵐の誘ひ来て、そっと呼び出す連れ人男の子、余所のさらばもなほ哀れにて
「是ぞ我等が虎の巻、大義であった」
うちも中戸を明けの鐘の音。
君に逢ふとて小簾戸に立てば。
月も推して雲がくれ、首尾はよいよいササよいやさ。
辛気辛気の胸の内、それと心もつくづくと、余所の恋路も羨ましうて、後ろへしょんぼり立ち姿。
「オオかるか、身の上の大事とこそはなりにけり」
と押し隠せば、繋ぎ染めたる色糸の、恋や浮気といふやうな。
ういた心の水色に、緑も浅黄の一夜妻、ただの馴染かなぞのやう、包むほどなや勝る、
胸の炎の萌木色、うち紫の女郎花、その模様さへ秋草と、いふもどうやら気がかりと、
卿ち涙に紅の、袖に露置くなまめきし、仇な姿にひとしほの、風情ぞまさる床の花。
いや疑ふな此中は、しんぞ命も打ち込んだ、そもじの姿夜昼を、丹精こめて描かせて、
君傾城の十二時、肱をまくらの転寝にも、肌身放さぬ絵巻物と、開けばひらく笑の眉。
門に小者が小提灯。
旦那のお迎ひうき様の、迎ひと叫ぶ声の下。
それお立ちぢゃと、家中が、下駄直すやら土下座やら、槌で庭掃く追従を、跡にのこして長縄手、
明日のうはさや京四つの、駕篭にゆられて。
頃も師走中旬とて、劔の風に打ちまざり、白き矢玉にさも似たる、巴とめぐる六の花、暮れてはいとど小止みなく。
銀延べし道もせに、更くるを待って亥の刻過ぎ、四十有余の人々は、皆一様の装束に、
手に手にえものいかめしく、忠義に神も余るなる、高の邸の裏表、門際近く詰め寄せて。
頭領大星良包が、やがて打ち出す山鹿流、川と答へる合言葉、
名に大鷲が大力の、かけやに砕く大扉、一度にどっと入り込みしは、勇ましくもまたすさまじい。
すはや夜討と宿直の武士、出会へ出会へと走り違ふ。
良包采を打ちふりて、逃ぐるを追わず只一と筋、師直一人目がけよと、踏み込む向ふへ小林が、両刀提げ仁王立ち。
され共人々鉄石と堅めし太刀先少しもひるまず、南の隅の雑部屋に、目指すお敵を仕留めしは、
雪の旦のしののめに、昇る旭と諸共に、名は末世まで高輪へ、苔なめらかに残す碑。