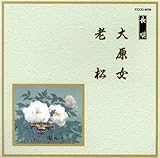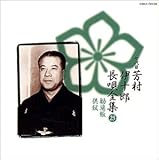| 年代 | 作曲 | 作詞 |
| 文政三年 (1820年) |
四世 杵屋六三郎 |
四世 杵屋六三郎(?) |
この曲は謡曲の「老松」を長唄化した曲。芝居用長唄ではなくて観賞用長唄として誕生した曲です。
作曲者の四世杵屋六三郎のお母様の「ます」を「まつ」に例えて、八十歳のお誕生日を祝ってこの曲を作ったそうです。
まあ、とにかく目出度い尽くし、この曲をプレゼントされたますさんは嬉しかった事でしょうね。
けれど、ちょっと祝い過ぎのようにも。。。きっと六三郎氏はお母様が大好きだったのでしょうね。
現在は八十歳はそう珍しい年頃ではありませんが、当時としては八十まで健在というのはすごっく珍しい事だと思います。ですから、これくらい大袈裟にお祝いをしても可笑しくないのかも知れません。
さすがに、謡曲を題材にしているだけあって、とってもしっとりと威厳のある曲です。
似たような曲に「鶴亀」という曲がありますが、「鶴亀」は眩い天上の美しさを感じますが、この曲はどちらかというと、静けさや威厳、燐としたものを感じます。
さて、この曲の終盤に「松風の合方」という三味線の見せ場があります。
この部分は、実は六三郎の作曲ではないようです。後になって十世杵屋六左衛門が六三郎の了承を得て合方を入れたそうです。
けっこうこの合方は聴き応えがあります。
演奏者によって色々な替え手が入るのですけれど、どれもとっても素敵です。
とっても構成がしっかりしていて、どの部分もとっても素敵です。
「松という、文字変われど~」あたりに笛の聴かせ処があります。
とっても素敵な旋律で、曲に引き込まれるという感じです。
私は、けっこうお笛の聴かせ処の部分はどの曲も好きです。
篠笛(竹笛)ってとても心の涙腺を緩めてくれるそんな音色がしますよね。
さて、涙腺が弛んで目頭が何故か熱くなるのもつかの間、次は神舞の二段目・三段目が入ります。
神舞というお囃子の手は色々な曲に使われています。「竹生島」とか「君が代松竹梅」とか。。。そうそう「常磐の庭」にもあったし。。。まだまだ考えればいっぱい入っていますよね。
どうも、この部分は天女が舞っているというイメージが強いです。
この曲も松の精が舞っているそんなイメージなんですよね。
実際は分かりませんけれど、個人的なイメージです。
この神舞が終わると、いよいよ大好きな太鼓地です。
「松の太夫~」の部分から曲の感じがガラッと変わって、とっても明るく甘く、可愛らしい感じに変化します。
そうそう、ちょっと暗めの照明から、パッと明るくなるそんなイメージです。
ここの部分の唄がとても好きで、お囃子をやりながらもついつい口づさんでしまいます。けれど、けっこうこの部分は忙しいのですよね。
太鼓と大小鼓の掛け合いですからね。。。唄に気を取られていると大変な事になってしまいます。