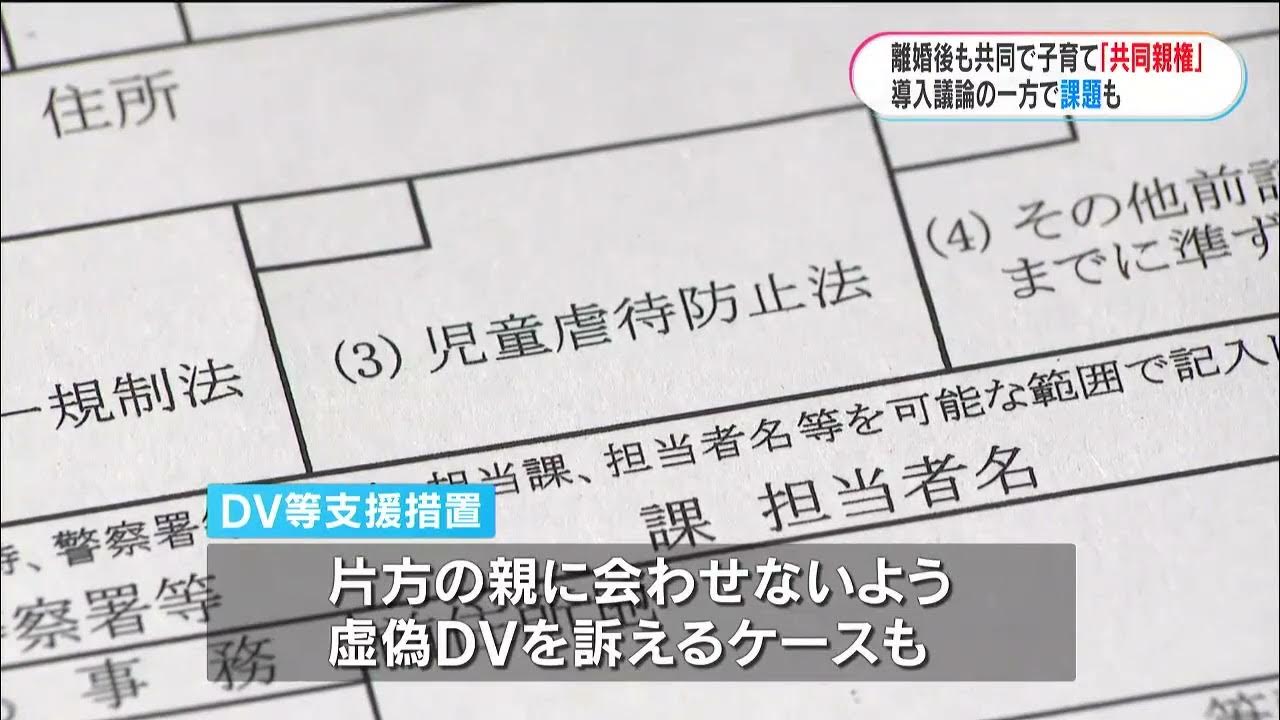【概要】
本当のDVと虚偽DVが混在してしまう理由があります。DV支援措置法における制度の欠陥があるからです。これについて解説していきます。
【この記事】
1.はじめに
虐待防止支援策法(DV支援措置法)は、被害者の支援を目的としていますが、残念ながら虚偽のDV申告による悪用ケースも存在します。虚偽のDV申告は、法的措置やサービスを不当に利用しようとする者がいます。例えば、離婚や親権問題の際に、配偶者に対して虚偽のDVを申告することで、自分に有利な条件を引き出そうとするケースがあります。しかし、虚偽のDV申告は一部の例に過ぎず、多くのDV被害者が本当に支援を必要としています。そのため、虚偽のDV申告を完全になくすことは困難であり、DV支援措置法の運用においては慎重な判断が求められます。虚偽のDV申告に対する対策として、関係機関や警察は証拠の確認や事実関係の検証を行い、不当な利用を防ぐ努力をしようとしていますが、この方針は明確に定まっているものでもありません。この問題を考慮しても、DV支援措置法は多くの被害者にとって重要な支援策であることは変わりません。今後も法律の改善や運用の工夫が求められるでしょう。
2.DV支援措置法とは
以下のとおりに補足します。
(1)措置の定義
住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付並びに戸籍の附票の写しの交付に係る支援措置について住民基本台帳事務処理要領について(昭和42年10月4日法務省民事甲第2671号・保発第39号・庁保発第22号。42食糧業第2668号(需給)。自治振第150号法務省民事局長・厚生省保険局長・社会保険庁年金保険部長・食糧庁長官。自治省行政局長から各都道府県知事あて通知。以下「住民基本台帳事務処理要領」という。)によると、市町村長は、 ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の加害者が、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付並びに戸籍の附票の写し等の交付(以下「住民基本台帳の開覧等」という。)の制度を不当に利用してそれらの行為の被害者の住所を探索することを防止し、もって被害者の保護を図ることを目的として、措置(以下「支援措置」という。)を講ずるものとされている。
(2)支援措置の申出について
市町村長は、住民基本台帳事務処理要領に則り、住民基本台帳に記録又は戸籍の附票に記載されている者で、次に掲げる者から支援措置の実施を求める旨の申し出を受け付ける。また、市町村長は、申出者が、その同一の住所を有する者について、申出者と併せて支援措置を実施することを求める場合には、その旨の申出を併せて受け付ける。なお、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市については、区及び総合区を市と、区長及び総合区長を市長とみなす。
(ア)配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止法」という。)第1条第2項に規定する被害者であり、かつ、暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがあるもの
(イ)ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第7条に規定するストーカー行為等の被害者であり、かつ、更に反復してつきまとい等をされるおそれがあるも
(ウ)児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがあるもの又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがあるもの
(工)その他(ア)から(ウ)までに掲げるものに準ずるもの
(3)支援の必要性の確認
(ア)当初受付市町村長は、申出者が、上記(ア)から(工)までに掲げる者に該当し、かつ、加害者が、申出者の住所を探索する目的で、住民基本台帳の開覧等を行うおそれがあると認められるかどうかについて、警察、配偶者暴力相談支援センター、児童相談所等の意見を聴取し、又は裁判所の発行する保護命令決定書の写し若しくはストーカー規制法に基づく警告等実施書面等の提出を求めることにより確認する。また、当初受付市町村長は、申出者と同一の住所を有する者で申請者と併せて支援措置を実施する申出を受けている場合には、加害者が、申出者の住所を探索
する目的で、同一の住所を有する者の住民基本台帳の閲覧等の申出を行うおそれがあると認められるかどうかについて、併せて同様の確認を行う。
3.DV支援措置法が通知されない理由
DV支援措置の存在を開示できないとする市町村側の考え方(法的見解ではない)を以下に示します。またこれによって家族に関する一切の情報にアクセスできなくなります。
①仮に実施機関が本件請求の申出書を保有しており、その内容を開示した場合、上記に記載したような情報が明らかとなる。支援措置はドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれに準ずる行為の加害者から被害者の保護を図る制度であるところ、未成年者である本人らが申出を行っているとすれば加害者欄に親権者の氏名が記載されていることは考えられるところである。例えば、加害者欄に請求人が記載されていない場合には存否を明らかにし、加害者欄に請求人が記載されている場合には存否を明らかにしないという応答をすれば、結果的に加害者欄に誰の氏名が記載されているかが推測され得ることになる。よって、本人らからすれば請求人を含めた親権者に支援措置申出書の存否を含めた内容が知られること自体が未成年者の利益に反するものと認められる。
②当該文書は不存在であると明らかにすれば、申出者が支援措置申出書を自治体に提出していないということが推測されることが明らかである。よって、支援措置申出書の存否を明らかにすること自体が、既に支援措置を受けている者や支援措置について相談をしようとする者からの支援措置の制度への信頼を損ね、支援措置の申出自体を回避または躊躇することが考えられ、結果として実施機関の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある。
4.相反するDV支援措置の利用
本当のDV(真正DV)と虚偽DV(刑事訴訟法または民事訴訟法ほどにはならないケースを含む)については、以下のように利用者の傾向が分かれることがあります。両者を比較すると、緊急避難に必要となるような支援措置の存在も把握できます。一方で、必要ではない可能性のケースも想定できます。
↑引用元
5.DV支援措置を行政不服審査法で見直しを求める
●行政不服審査法を活用しようでも少し触れていますが、個人情報の過保護となってしまっているケースがあります。ここで確認しておきたい文章があります。住民基本台帳事務処理要領に関連して「DV等被害者支援措置における「加害者」の考え方について」以下の記述があります。DV等被害者支援措置における加害者は、認定事実にもとづかないで対処されているということです。
そうなると●行政不服審査法を活用しようによって得られた処分庁の弁明書については、さらに新たに反論書を提出することができると考えます。以下の(a)~(i)について弁明を求めるのができるのではないかと思います。
『(a)被害者からの疎明資料が出されないとしても市町村は、保護を図ることができることは認める。しかし、措置の必要性を判断するまでに確定を待つまでに保護が図ることができたとしても、措置の必要性を判断するための継続的なプロセスが一般的な手順として明記されておらず、また判断基準が曖昧となっている。もし開示請求に関わる存否すらも伝えないことがあれば、措置の必要性があるかどうかの釈明ができる機会を失うことから、真に措置が客観的に必要かどうかという判断をする機能があるとはいえない。したがって不利益を受ける。
(b)(a)を踏まえると「国又は公共団体の統治行動に対して個人の基本的な自由と平等を保障する目的に出たもので、専ら国又は公共団体と個人との関係を規律するものであり、私人相互の関係を直接規律することを予定するものではないと解される(最高裁昭和48年12月12日大法廷判決)」ことに照らし合わせると、公共団体において推測の域であるDV支援措置では、個人の保護法益が過剰に制限されてしまうため、不利益性がある。
(c)さらに(b)を鑑みると、最高裁平成25年(オ)第1079号同27年12月16日大法廷における「親子法が子の福祉の保護のために運用されることが求められる旨の判示」から逸脱した解釈となりうる。つまり措置を適用する段階で、「双方からの聞き取り調査」や「事実を立証すること」というプロセスがない限り、親子の迅速な自由な面会交流権すらも実現できないことから、子の福祉という観点から子の利益を考慮した点を見出すことができないため、不利益性がある。
(d)内閣府男女共同参画局(平成26年 府共第 645 号)「母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第1項第3号又は同条第2項第3 号に該当する旨の証明を求める者が配偶者からの暴力を受けた者である 場合に係る証明書の発行について」の通知によれば、保護に関する証明書は、配偶者からの暴力を理由として保護した者に対して婦人相談所等が発行するものであり、配偶者からの暴力があった事実を証明するものではない点が述べられている。そうなれば処分の理由を理解するということは事実上困難であり、都度開示請求をしたとしても根本的な不利益処分の理由を知ることができないという状況にある。
↑引用元
(e)(a),(d)の裏付けとして大阪市における令和3年度諮問第24号の答申書によれば、「相談機関等の意見」欄について口頭のみの確認であり、過去にどのようなDV等の被害を受け、また申出時点においてどのような危険性があるかについて、判断を行うに足りる十分な情報を把握したとは考えらないとしたことから推測すると、処分庁の行政調査は不十分なものであるという判断されたという経緯があり、事務処理要領からは一意的に必要性があるとは必ずしも特定できないということがある。よって不十分な情報をもとに行われた支援措置実施決定を理由とするリスクがあるため、必ずしも「不当な目的によることが明らか」とは言い切れないのである。さらにいえば、第三者からの請求ではなく、子の監護や扶養を目的とするものであることからすると、保護者として正当な情報開示を必要とする場合は十分に考えられる。すなわち正当な弁明理由がない限り、支援措置自体がこれらを制限することになる可能性がある。しかも正当ではない支援措置が図られていることを子が知るとなれば、結果として審査請求人だけに留まらず養育を受ける子どもの個人利益を害することを否定できない。本人の「権利利益を害するおそれ」は、当該保有個人情報の性質、開示請求に至る状況や経過などから、開示請求者と本人の利益が相反するおそれがあると客観的に認められること、すなわち単なる抽象的な可能性では足りず、当該おそれが見込みどおりに起こると思われる程度が、確実ではなくとも、ある程度確かであろうと認定できるべきであると解される 。
※行政不服データベース
(f)すると処分庁として存否を開示しない対応であれば、子の養育という権利としての人格的利益の享受の点で差異が生まれることになり、事実を知らない支援措置対象者としては弁明の機会がない。そうなれば先に申請したほうが有利という特権制度となり、かえって親子断絶するときの手法として用いられてしまうことが容易に推測される。よって子の連れ去りをするときに、保護者としての認定地位を実効上において妨げる手段となりうることから、制度の濫用されてしまうことにより加害者として取り扱われることによって実施機関から(a)~(e)という点で不利益を受ける立場となりうる。しかし、弁明書の処分内容及び理由をみても、特にこれに対処できる仕組みが見当たらない。そうすると、子の扶養、監護に第一次的な義務を負う(民法818条、820条)ことからすれば、生命、身体、財産などを守る予防的な措置としての目的とは違う効力を発生することになり、合理性を欠く制度であるといわざるをえない。したがって、現行の運用制度の見直しが必要ではないとは言い切れない。すなわち基準が明確に定まっていないことにより、親子に関するの各種法令の権利利益を長期にわたって制限されるよって生じる損害がないとはいえない。
(g) 仮に(f)正しいとされ、弁明の機会がないとすれば、手段を問わずに子の連れ去ることによって用いることができるとなれば、父母の同意がなき行政手続きも行われたとしても知ることがなく共同親権下における利益が害されるおそれがある。もし、そのような手続きが行われているのであれば、民事訴訟法における子の監護者指定においては子の監護の継続性による期間が評価基準の一つとなりうることから、親権を失いかねないという大きなリスクを含んでいることになる。
(h) (g)という存在が妥当ならば、これは共同親権下においては父母の意見調整をするための機会が義務として保証されている法律が見当たらないことから、子の居所指定権や財産管理権などの行使ができないという事実となりうる。
(i) (g)の点が仮に論点にならないとしても、児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第2条4項「児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと」として虐待定義があるが、同居する家庭における配偶者および不知の交際相手からの暴力があったとしても、適切に保護することが困難になるというリスクが高まる。よって基本的人権として守られる親子関係を維持する利益を失いかねないことから、やはり事実関係からの経緯を把握することによって妥当性を1ヶ月程度の期間で継続的に再評価する機会が求められる。
以上、(a) 〜(i)で述べたとおり、行政不服審査法1条により、国民の権利利益の救済を図るとともに、適正な運営を確保するためのフィードバックを要望する。また弁明書において不知と言う点がある場合には、総務省、法務省、文部科学省、子ども家庭庁など各官庁に必要に応じて確認することで、全国的の自治体の運用について見解を深めることができる余地があることを付言しておく。
▼動画解説(外部サイト)
日本は、虚偽DVとして申請しても、何ら罰則がないため悪用するようなことを一部の弁護士、左派系、男女共同参画系が伝えているケースがある。
▼補足主張
虚偽DVによる支援措置だと子の情報取得が難しくなる。仮に夫婦間の問題であって親子関係に問題がなくても、同居親について回る措置のため、子の情報が不明となる。
↑引用元
▼補足主張2
DV支援措置の存否が分からないという視点が認められるのであれば、仮に実際に退園(転校)していないのであれば、保育施設や教育機関において私立であって無償化の上限を超える支払いをしなければならないという市政制度になる。逆に退園しているのであれば、部外者になっているのにも関わらず保育施設や教育機関に訪問することによって不法侵入に問われる可能性を否定することができない。よって存否を知らないことで受ける不利益性があることは明白である。
▼補足主張3
仮に根拠がなくても加害者と被害者の距離を確保する必要がある場合、支援措置を知らないまま偶発的に接近する機会があればに、かえって当事者間において緊張状態になる。存否を知れば、一時的に柔軟な対応を取る配慮ができる自力救済の手段にもなるケースが考えられるが、そのケースを失うことは不利益性が無いとは言い切れない。
▼虚偽のあるDV支援措置
▼虚偽DVが増える理由
過剰なメリットを活用しようとするため、虚偽が増える。
↑引用元
奨学金の優遇を受けるために、事実かどうか確認されなくとも支援措置を認定を受ければ、対象となりうる。虚偽としても悪用される可能性が高い。文部科学省はどのように対策しているのだろうか。
↑引用元
▼東京都三鷹市
虚偽DVが起きる理由が簡単。申請用紙に丸するだけ。これでは不利益が生じる。
↑引用元
▼住民基本台帳事務支援システム(令和2年11月8日告示)
双方から事実確認がされない制度だが、ようやく申請様式について「加害者」から「相手方」という表記に変更された。
↑以下参考元をもとに画像作成。
▼横浜市
2019年11月
↑引用元
▼総務省の様式変更の通知
令和6年1月30日にようやく遅れて掲載された。
↑引用元
▼総理大臣も認めた悪用事例
↑引用元
▼相続にも悪用される支援措置
↑引用元
▼えん罪(冤罪)
日本では、性犯罪対策としても利用される保護制度がある。ただ虚偽DVが離婚事由として悪用されている。住民基本台帳に関する支援措置、子どもの居場所の秘匿、給与証明などの非開示、不正的なひとり親の助成金申請など、多くの精査すべき課題がある。
:
↑引用元
↑引用元
↑引用元
▼トンダ
↑引用元
一時避難のはずが、根拠なく転居できる仕組みになっているのではないかと思われる。またこの手続きがあったことの認否は、他方親に知らされることがなく進むことから、親権や監護権の強奪に悪用されると思われる。なぜなら、すっとぼけて虚偽かどうか分からないけど指導したとする弁護士も出てくることは十分に予見される。
▼行政職員の偏見対応
益城町の刑事告発案件である。
↑引用元
▼大阪の審査請求で有力な点
国家賠償請求事件の裁判例においても、支援措置の適法性については、①被害者要件と②危険性要件に分けて要件充足性の判断を行っていることが認められる(名古屋高裁平成30年(ネ)第453号同31年1月31日判決・判時2413・2414号41頁、その下級審判決である名古屋地裁平成28年(ワ)第3409号同30年4月25日判決・判時2413・2414号55頁参照)。よって、少なくとも処分庁が上記意見付与機関に確認するに際しては、①被害者要件に該当する事実、②危険性要件に該当する事実を確認する必要がある。そして、仮に警察等の意見付与機関が①被害者要件、②危険性要件を判断するに足りる十分な事実関係を把握していないことが判明した場合には、処分庁は、意見付与機関に対し、処分庁が判断するのに足りるだけの根拠を提示するよう求めるべきである。
↑引用元
↑引用元
▼司法手続きの弊害
↑引用元
▼DV支援措置の利用者が真の加害者
痛ましい事件が起きた。支援措置をおそらく悪用していたと思われる自称?被害者が、同居している子どもへの加害を行い、子どもは死亡した。支援措置制度の欠陥のせいで命が救えなかった。
↑引用元
▼酷い自治体対応
↑引用元
●行政機関(市役所、区役所、町役場、小学校、中学校、保育園、幼稚園)に相談した情報が守られる権利