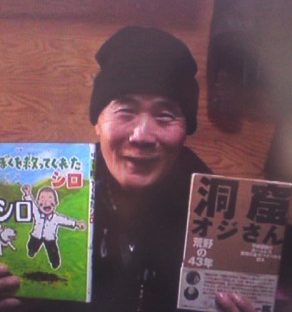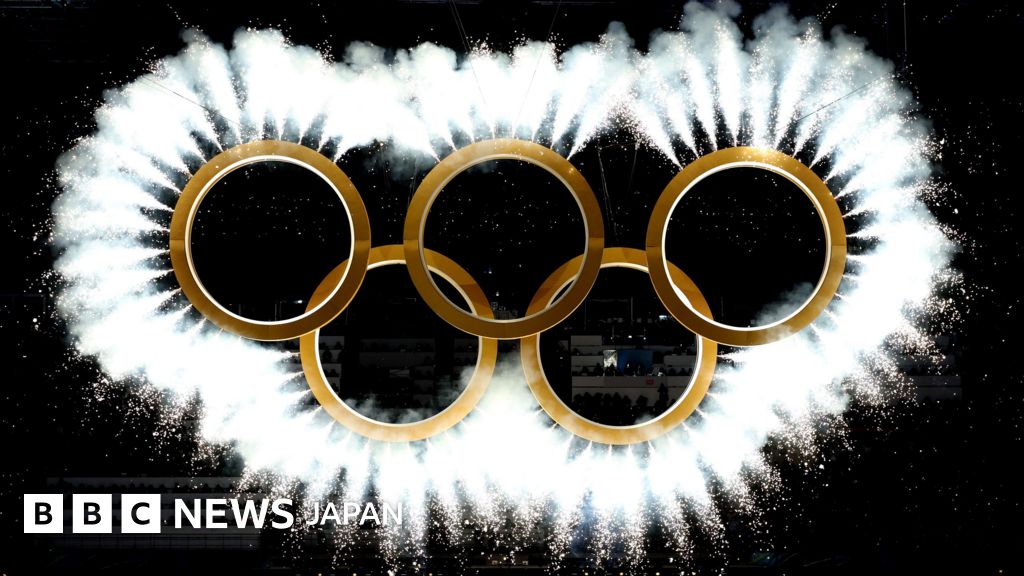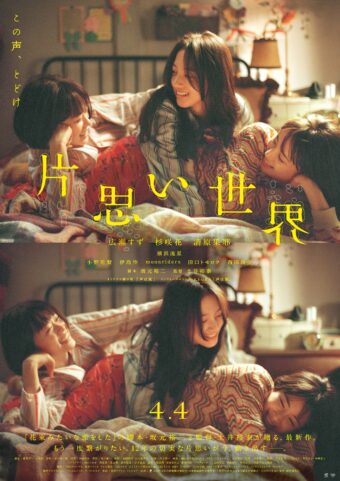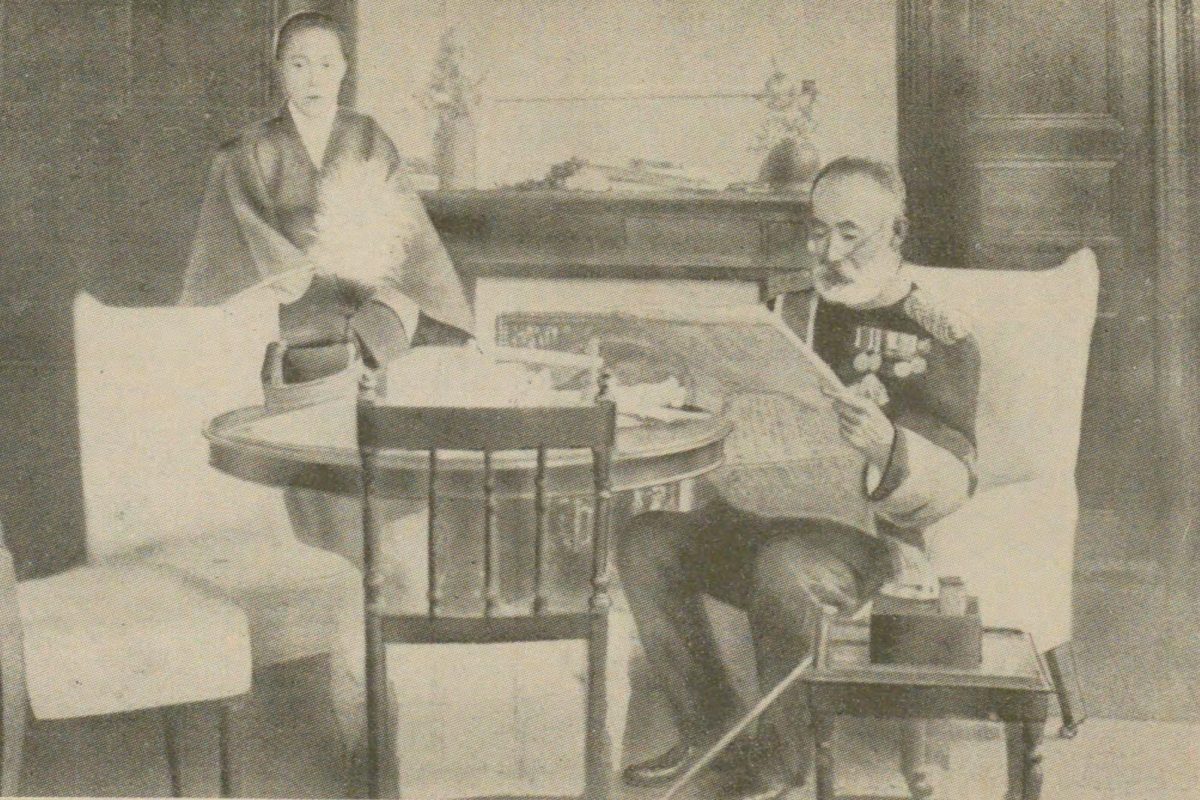どうせ読むならば、ラフカディオ・ハーンの研究家である平川祐弘先生の訳でと思った。先生の訳が大半だが、牧野陽子さんなど、他の先生方の訳もある。字の小さい文庫本であるが、巻末には、解説のみならず、元拠も記載されている。小泉八雲の文章(と訳文)は彫琢を凝らしたみごとなもので、メモなど意味ないことだが、どういう話だったか忘れないために簡単に、個人的にメモしておく。
耳なし芳一: 原拠に比べてひじょうに物語を膨らませてある。下関壇ノ浦での源平合戦を物語る琵琶法師が、平家の怨霊により耳を引きちぎられるという話である。赤間神宮を訪れたことを思い出す(こちらのブログには写真がいっぱい)。
おしどり: ある猟師が一番のおしどりの雄を殺して食したところ、雌が猟師の夢枕に立ち、翌日沼で雌のおしどりが自害するのを目にした。
お貞の話: ある男のいいなづけが結婚前に病床にあった。事切れる前に、この世でまた会うと言い残した。その後、迎えた妻と息子が亡くなった後、旅先の伊香保で、かつてのいいなづけにそっくりな人を見つけ、名を尋ねたら故人と同じで、あの女の人の生まれ変わりだという。男はこの女を娶ったが、それ以来、その女は昔のこともその時に語ったことも何も思い出せないままであった。
乳母桜: ようやく授かった一人娘が病に臥した時、その乳母が、自分を身代わりに病気平癒の願をかけ、それが叶った。乳母は願をかけた寺の境内に桜の木を奉納してほしいと言い残して他界し、奉納された桜は毎年その乳母の命日(2月16日)に花を咲かせた。
策略: 打首になる男が恨み言を述べた。邸の主人は、その深い怨みの徴に、首が刎ねられたあと、あの飛び石に噛み付くよう言い、そうなった。誰もが怨念を恐れたが、主人は恐れなかった。男の怨念が、石に噛み付くという妄執により消えたと知っていたからである。
鏡と鐘と: 寺の鐘を鋳造するために女たちが古い青銅の鏡を寄進した。その中に、寄進したことを惜しんだ女がいた。その女の鏡だけはどうしても溶けず、その噂に耐えかね、その梵鐘を突き破る者がいればあまたの財宝が授かると遺言して自害した。
人々はそれを信じて鐘を撞くので、坊さんたちはそれを沼へ沈めた。だが人々は、青銅の手水鉢を梵鐘になぞらえて打ち鳴らし、三百両を恵まれるという例が出た。
さらに、ある自堕落な百姓が、泥で鐘をつくり叩いたところ、土の中から白衣の女が蓋をした甕を持って現われた。その甕に何が詰まっていたかは語られていない。
食人鬼(じきにんき): 夢窓国師は、旅の道中、庵室に住む老僧に宿を乞うたところ、近くの村へ行くように言われ、そこでもてなしを受けた。その家ではたまたま死者が出たので、皆別の村へ移るから、いっしょに行こう言われたが、遠慮してその家に残った。すると夜更けに現われた物影が死体をむさぼり食らうのを目にした。村人の話から、夢窓国師は例の老僧は既に死んでいたことを知り、食人鬼となった老僧の霊に施餓鬼の法会を営んでほしいと頼まれた。
貉(むじな): むじなはアライグマのことだが、ここでは、日没後に人気のない界隈(赤坂の紀伊国坂、弁慶濠の西側)に出没するのっぺらぼうとして語られている。
轆轤首(ろくろくび): ろくろ首には首が伸びるものと、ぬけて飛び回るものがあるようだが、こちらはぬける方である。
ある九州の侍が浪人となって剃髪し、僧となり、説法の行脚を続け、ある晩、木樵の家に泊めてもらった。夜中に目覚めると五人の家人の首がない。首たちは林の中で僧侶を食う相談をしていたので退治した。首が一つ袂に食らいついたままだったので、僧は逮捕されたが、袂の首には切られた跡がなく、放免された。後に追い剥ぎにあうも、その妖怪変化の首つきの着物を所望されて売り渡した。追い剥ぎは、悪霊の祟りをおそれ、そのろくろ首が出たあたりを訪ねて葬り、法要を営んだ。
葬られた秘密: 丹波のある商人の娘が嫁ぎ、子を産んでから他界した。だが、その娘は、腰から下は消えているものの、自分の部屋に出没した。きっと霊が気になるものを残しているのだろうということになり、僧侶に来てもらうと、僧侶のもとに霊が現われ、抽出しの敷紙の下から手紙が見つかった。それは娘が昔もらった恋文であり、僧侶はそれを焼き、誰にもその内容を話さなかった。
雪女: 二人の木樵は吹雪にあい、渡守の番小屋に避難した。若い方が目を覚ますと、白装束の女が年老いた男に息を吹きかけており、彼の上にもかがみ込んだが、不憫になったのでやめておくが、誰にも話さぬようにと言って消えた。老人は死んでいた。
翌年、男はお雪という娘と知り合い、嫁にした。十人の子供ができた時、男は、自分が若い時に会った、妻にそっくりな白い女の話をした。妻は、しゃべったら命はないと言ったのにと甲高い声をあげて煙出しの穴から姿を消した。
青柳の話: ある若侍が、越前から京への旅路、吹雪の夜、山中で一夜の宿を借りた。そこの青柳という娘に心を奪われ、嫁にしたく思い、道連れとしたが、細川の殿の手下の手にかかり館に拉致されてしまった。若侍はなんとか思いを伝えようと漢詩を送ったところ、細川の殿に呼び出された。死をも覚悟であったが、漢詩に感銘を受けた細川公は二人の婚礼を祝った。その五年後、青柳は死ぬ。切り倒された木の霊なのだという。侍は越前であの家を探すと、三本の柳の切り株があるだけであった。
十六桜: 伊予のある侍の庭に桜の老木があり、みごとな花を咲かせていたが、枯れ死んでしまった。その侍も年老いて、子供にも皆先立たれてしまうと、その木を蘇らせてほしいと、その木の下で切腹した。それから、その日、正月十六日になると、雪の季節だというのにその桜は咲くのである。
安藝之介の夢: この大和の郷士は、家の庭の古い杉の大木の下で一睡りした。その夢の中で、豪奢な宮殿に招かれ、その家の姫君の婿に迎えられ、婚礼式を挙げた。そして数日後、莱州の国司に任ぜられ、二十年統治した。そして妃が他界し、国王はその郷士を国もとへ送り返すこととし、海に乗り出した、というところで、目が覚めた。友人はその人の顔のあたりを飛んでいた蝶が蟻につかまり、穴の中に引き込まれたのを見たというので、杉の木の下を調べてみると、みごとな蟻の巣が掘り抜かれており、妃の墓とおぼしきものも見つかった。
宿世の恋: 江戸で、落語家円朝の人情噺「牡丹灯籠」の中から怪談を英語にしてみることにした。ある旗本には美しい儚げな娘(お露) がいたが、後妻と折り合いがわるかったので、女中をつけて別邸に住まわせた。病に臥したその娘を訪ねた医師が、美しい若侍(萩原新三郎) を連れていったところ、娘は侍に懸想したが、医師が、旗本の勘気を恐れて若侍を遠ざけたため、娘は思い詰めて焦がれ死に、女中も世を去った。
若侍は後で医師から話を聞くと位牌を仏壇に入れて念仏を唱えた。盆の入り七月十三日、若侍は死んだはずの娘と女中に出会い、家に招き、それから毎晩通ってくるようになった。その若侍の傭人はそれを見咎め、女の顔を覗くと、それは髑髏!! 隣家の老人に事を告げる。その老人は若侍に、幽霊と情を交わすならば死ぬと注意され、下谷の谷中の三崎を訪ねると墓が二つと牡丹灯籠。新幡隋院の良席和尚から死霊除けのお札とお守りをもらう。だが、入口を失った幽霊は、傭人を脅して金を握らせ、お札を外させた。こうして侍は死に、その傍らには女の骸骨が横たわっていた。
ハーンは友人とその墓を見に行った。それらはお露と女中のものではなかった。
因果話: [この話はおそろしかった!]ある大名の正妻が今際の際にあって、若い側室を呼び寄せ、正妻になるよう優しく話しかけ、最後に桜が見たいからおぶって欲しいと言った。背中に乗った正妻はその側室の乳房を掴み、事切れた。その手は取り除くことができず、切断した後も胸にぶら下がっていた。側室は出家し、托鉢に出たが、毎晩丑の刻(深夜の1〜3時)になると干からびた蜘蛛のような嫉妬の手に痛めつけられないことはなかったという。
天狗の話: 悪童にいじめられていた鳶を救った高僧が法師の姿になって現われ、恩返しに見たいものを見せるというので、天竺の耆闍崛山の大会で釈迦如来の説法を目にしたいと願った。それを目にした高僧は、禁じられていたのに、思わず簡単の声「あなかしこ」を上げてしまったがために、その鳶は羽を折られてしまった。
和解: 年若い侍が、主君を失い、職を求めて京を落ち延びるにあたり、妻を離縁した。二度目の妻は性格がよくなかったので、前の妻を思い出しては後悔した。離縁して京に戻り、前の妻のもとを訪ねると、あたたかく迎えてくれた。翌朝目が覚めるとしかし、傍らに寝ていたのは死骸であった。前の妻は、何年も前に、侍が京を離れた年の秋に死んでいたのであった。
普賢菩薩の伝説: 播磨国のある坊様が普賢菩薩にお目にかかりたいと思っていたところ、神崎にある「遊女の長者」の家へ行けという夢のお告げがあり、坊様は、六牙の像に乗った普賢菩薩の姿を見た。門を出た時に件の遊女が現われ、今夜見たことは他言無用と言った。
死骸にまたがった男: 離縁された女が憤死した。男は陰陽師に助けを乞うと、死骸にまたがり、女の髪をしっかり掴めと言われた。女の死骸が外へ出て走り、恐ろしい夜を過ごしたが、陰陽師はそれで救われたのだと言った。[?]
菊花のちぎり: 義兄弟の武士の1人が故郷に旅立つにあたり、9月9日に戻ると約束をした。だが尼子経久に捉えられ、その部下の家に監禁され、約束を果たすために自刃して魂となって立ち戻った。
破られた約束: 妻が死ぬ前に、夫は二度と結婚しないと約束した。妻は自分が庭の隅に鈴とともに葬られるよう頼んで死んだ。だが夫は若い娘と再婚した。果たして死んだ女は、鈴の音とともに現われ、新しい妻を脅かし始めた。人に話すと殺されると脅されていたが、打ち明けると、夫は見張りの侍を二人つけてくれた。だがその侍たちは眠らされ、若い妻は首をもがれて死に、墓の傍らに首を持って立っていた。ある武士が念仏を誦えてその化け物を切ると消えたが、肉の落ちたその右手はなおも血まみれの首を握っていた。
閻魔の庁で: ある少女が疫病にかかった時、親族が疫病神に熱心に祈ったところ、娘は、疫病神が同じ名の娘と命を入れ替えて救っくれるという夢を見て、快癒した。再び三日間臥せって目が覚めると家のことも両親のこともわからずにいる。身代わりに死んだ娘は一方で、閻魔大王に送り返され、魂は臥せっていた娘の体に戻った。そして駆け出して、自分の家に戻り、両親と再会し、事の次第を説明した。二組の両親はその娘を両家の子とみなし、娘は両家の遺産をつぐこととなったという。
果心居士の話: 果心居士は地獄の責苦を描いた掛け物を見せながら説法してお布施を集めていた。信長がその掛け物を所望すると、果心居士は金百両を提示した。信長の家来は果心居士を斬って絵を奪ったが、掛け軸を広げると真っ白で絵がない。しばらくしてから、果心居士は別のところで絵を見せていた。そして妖術使いとして捕えられ、取り調べられた。絵には魂が宿っているから百両払えば絵は戻るだろうと言い、実際そうなった。痛い目にあわされた侍の弟は果心居士を殺したが、また生きて現われて捕えられた。その間に信長は光秀に殺され、果心居士は光秀に呼び出された。そこで酒をふるまわれ、屏風絵の中の船と湖水を実現させて一同をびっくりさせた。そして果心居士はその船に乗り、沖合へと姿を消した。
梅津忠兵衛: この出羽の国の侍が夜勤番に当たっていた時、夜更けに女と出会い、赤子を預かってほしいと言われ、抱いていると、その子がどんどん重くなった。あまりの重さに南無阿弥陀仏とつぶやくと、腕はからっぽになり、戻ってきた女は、自分は氏神で、氏子の難産を救ってくれたから、その侍に剛力を授けると言った。この侍の子供たちもやはり剛力になった。
夢応の鯉魚: 近江の三井寺にいた絵の名手である僧が、夢の中で魚と戯れていた記憶を絵にした。死んだようになって七日過ぎてから蘇生し、夢の中で自分が魚になって釣られてしまい、調理されたところで目が覚めたと語った。その次第はまさしく事実であった。その僧が他界してからしばらくして、描いた魚が湖に泳ぎ去ったという。
幽霊滝の伝説: 麻取り場の女たちが、幽霊滝に一人で行ける人には取った麻をあげるという話になった。お勝という女が行くと言い、証拠として賽銭箱を持ってくることにした。果たしてお勝は戻ってきたが、おぶっていた子供の頭がもぎ取られていた。
茶碗の中: 江戸時代の話。ある若侍が茶屋で渇きをうるおそうとしたところ、茶碗の中に顔の影が写っていた。注ぎ直してもやはり現われる。それを飲み干してしまった日の夜、あの茶碗に写っていた男が現われ、にじり寄ってきたので、短刀で斬りつけたが手応えがなく、壁の向こうにするりと消えた。翌晩はその男の家来が三人現われ、主人は傷が癒えたら報復に来ると告げたので斬りつけたが、舞い上がって消えた。話はそこで途切れているとのこと。
常識: 京の愛宕の山に学僧がいた。学僧は猟師に、毎晩象に乗って普賢菩薩がお見えになると語った。寺の小僧も何度か見たという。漁師は寺に留まり、普賢菩薩を待ち、現われると弓矢を射た。翌朝、矢に射抜かれた狸の死骸が見つかった。
生霊(いきりょう): ある江戸の霊岸島の商人は、甥を店の手伝いとして入れた。よく働いたが、七ヶ月ほどした頃、からだの具合がわるくなった。聞いてみると、店のお内儀(あるじの妻) の生霊に苛まれているのだという。内儀は甥が優秀なのに、実子が才覚に劣るので、甥を呪っていたのだという。甥は支店を出してもらい、それからは生霊に悩まされることはなく、再び元気になった。
お亀の話: 仲の良い若夫婦がいた。妻のお亀は病に倒れ、再婚しないでくれと言って息絶えた。残された夫は日に日に衰えていった。母に打ち明けたところによれば、お亀が毎晩添い寝をしにくるのだという。寺の和尚に助けを乞うと、お亀の墓をあばくこととなった。その遺体はまるで生きているかのよう。和尚は遺体に梵字を書き付け、施餓鬼の法要を営むともう霊がやってくることはなくなり、夫は健康を回復することができた。
蝿の話: 商人夫婦のもとに玉という下女がいた。着る物を質素にして節約していたのは幼い時に亡くした両親の法要を営むためであったことを商人夫婦は知った。こうして両親の法要を営み、残りの三十匁を内儀に預かってもらった。そしてにわかに病床に臥し、死んだ。それからしばらくすると、冬だというのに家の中に大きな蝿が入ってきた。目印をつけると同じ蝿が何度も入ってきた。夫婦はこれは玉だと思い、預かっていた三十匁で、玉の法要を営んだ。
忠五郎の話: ある旗本の足軽忠五郎は人好きの良い若者であったが、この頃、毎晩家を抜け出して明け方まで帰らないようになった。顔色も悪くなり、仲間に誰何され、訳を話した。きれいな女に出会って、水の中に導かれ、宮殿に至ったと話した。そして忠五郎は意識を失い、診察した医師は、彼に血がなく、血管の中にあるのは水だと叫んだ。医師は前にも似たことがあり、その女の正体は醜い蛙なのだと話した。
鏡の少女: 足利時代、南伊勢のある神社の宮司は社を修復する助けを求めようと京に上がり、待つ間、一軒の家を借りた。屋敷の東北に井戸があり、多くの人が身投げした不吉な井戸だと言われていた。旱魃があった時、人々はそこに水を汲みにきたが、ある朝、若い下僕の死体が井戸に浮かんでいた。見ると水に化粧をする若い女の姿が見えた。引き込まれそうになったので、垣根を作って近づけないようにした。
それから一週間ほどして、井戸に見えたあの女が訪ねてきた。あの井戸には竜王が住んでいたことがあり、私を使って人の生き血を吸っていたが、今はいなくなったので、私の体を引き上げてほしいと言う。井戸を浚うと髪飾りと鏡が見つかった。
またしてもその女が現われ、鏡を足利義政公に献上してほしいと言う。さらに明日この家は破壊されるので留まるなと忠告したので、宮司は洪水にあわずに済んだ。しかも義政公は献上品を喜び、神社再建の資金をたっぷり与えたのである。
伊藤則資(のりすけ)の話: 六百年ほど前、宇治に美男の武士がいた。近くで宮仕えをしているという少女と会った。物騒だったので家まで送ることにした。そして屋敷に上がるよう誘われ、美しい姫君に引き合わせられ、婚礼をあげた。侍っている老女によれば、姫は平重衡の息女だという。ぞっとした。その人は何百年も前に人ではないか!! だが夜明けを告げる鐘が鳴ると別れの時だと告げられ、彫りの施された小さな硯を贈られ、十年後の再会を告げられた。その後、その場に戻っても館など何もなかった。侍はやせ細り、十年後、硯をいっしょに埋葬してほしいと告げて他界した。その硯には12世紀、高倉天皇の御代の匠の銘があったという[やはり平家の人は成仏できていなかったようですね]。
美は記憶なり: 人間の愛に関わる感覚、美に対する衝撃は、幾億という生命を通して蓄積された記憶なのだ、という説。なんだか神秘的哲学のような文。
美の悲哀: 美の感覚に伴う謎めいた悲しみは、数知れぬ前世の追憶の悲しみだ、という、やはり神秘哲学のような文。すべての美しいものは悲哀の感情を呼び起こす、それは無数の死者の感情がそう思わせるのだ、と。
薄明の認識: 超自然的なものに対する恐怖がいちばん怖い。それは遺伝的な恐怖の複合体だから。夢の中の恐怖についていろいろ[金縛りとか?]。
破片: 夕刻の暗闇の中、菩薩と巡礼が山を登る。まわりには髑髏ばかり。頂は遠い。それらの髑髏はすべておまえの髑髏だと菩薩は言う。
振袖: 250年ほど前の江戸の振袖火事について。ある娘が美しい侍にまた出会いたいときれいな振袖をつくらせたが、再会できず、恋焦がれて亡くなり、その振袖は寺に寄贈された。その着物は売りに出され、買って着た娘はやはり患って死んだ。これが繰り返されるに及び、住職は怪しんでその着物を焼いた。その炎が寺の屋根に飛び、大火となって江戸のあらかたを焼き尽くした(1657年の振袖火事)。美しい侍は人間ではなく、不忍池の主である竜の化身であったという説もある。[だから古着は気持ち悪いのよね。呉服屋の人が新しい反物を売りたくてつくった怪談かしら?]
夜光るもの: 夜の大空に沸き立つような星くずは、幽界の深淵[エレボス Ἔρεβος]にうずまく生命であった。[またまた神秘と夢想の話。]
ゴシックの恐怖: ハーンは、幼少期より、ゴシック建築に特別な恐怖を感じていたとのこと。巨大な恐竜の骸骨の中にいるように感じていた。椰子の木にも、恐ろしい美しさの感覚をおぼえた。ゴシックの尖頭アーチは椰子の枝のカーヴを示唆し、増強する力とエネルギー、脅かす悪意、魑魅魍魎と化すのだ、と。