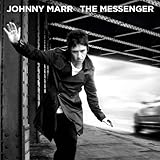あっというまの最終日。
フェスの最終日は、寝不足で朝グダグダなことが多い。
そんなこんなで、昼過ぎにホテルを出る。
海浜幕張の駅で、もう我慢できなくなり、ロッテリアの前でビールを買う。
これがキンキンに冷えていて、最高においしい一杯だった。
本州に居ると、ビールのありがたさがしみる。
まずはメッセでPEACEを見る。
ヴォーカルが白いサロペットみたいなのを着てる。
なんか、「時計じかけのオレンジ」っぽい。
Follow Babyからスタート。この曲好きです。ストーナーなグルーヴで一気に引きつける。
繰り出すどの曲もキャッチーでUK Rockの旨味に溢れている。
でも、その楽曲の良さに溺れることなく、実直なプレイを披露していた。
なんとなくあっさりした感はあったけど、まだまだ新人。
まずはちゃんとしたセカンドを作ってください。
その後はPalma Violetsを観ようかと思っていたけど、
マリンでスマパンを観ることにする。
自分の中でスマパンは、圧倒的に2ndサイアミーズ・ドリーム。
ちょこっとメロンコリーって感じで、あとはほとんど聴いていない。
最近のは全然しっくりこない。
そんな調子だったものだから、ライブも消化不良だった。
マリンにつく前に、Tonight Tonight,Chrub Rockやっちゃったみたい。
DisarmにSpace Oddityも・・・残念。
Todayは聴けたので、そこだけはよし。
ただ、今は完全ビリーのワンマンバンドなので、違うバンド観てるような気分になったのも事実。
ビリーもなんとなく落ち着いちゃったな。
イハ、ダーシー、ビリー・チェンバレンよりはずっと上手いバンドなんですけどね。
この頃が最高にかっこいいよ。