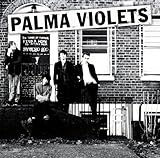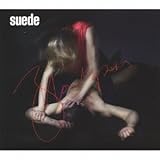- Stranger/星野源
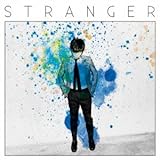
- ¥2,940
- Amazon.co.jp
愛すべきワーカホリック、星野源の3rd。
のほほんとした見かけとは正反対に、やりたいことをとことんまでやりきる。彼はそれを「仕事」と称する。大人が皆抱えていく「仕事」との向き合い方。生死の根本にある、人間の「生活」に並々ならぬ執着を持つ彼にとって、「仕事」は生活に直結した要素であり、仕事をし続けることが「生」を実感できる営みであるということを、著書「働く男」で知った。
いやぁ、おもしろいなぁ。というか、自分も元々すごく仕事をする人が好きで。でも、長い時間仕事をする人は嫌いです。「すごい」と「長い」は違うんです。ポジティヴなテンションでやりきってしまう人はかっこいいなと思うんです。明らかに面倒な、いやな仕事もうまく乗り越えていくような人。なかなか難しいことだとは思うけど、たぶん「仕事」が自分の好きなことじゃなくても、その中身を自分の感性でまっとうにやり遂げていくことが、その人の「生活」を豊かにしていくんじゃないかなと。そして、そういう人が増えていけばいいなと、漠然と思います。
話は少しそれたが、定期的にシングルを出し、一息つくのかと思いきやニューアルバムのニュースが流れたのが、今年の頭。体調を崩して春先のリリースとなったが、その目まぐるしいスピード感の中で作られた雰囲気が、アルバムにも色濃く感じられる。
とにかく、けたたましいマリンバから始まるオープニングの「化物」から「夢の外へ」までの流れがすごい。1st,2ndにはない怒濤のグルーヴ感。中でも2曲目「ワークソング」は圧巻。ブラス、ストリングス、あらゆる音が狂ったように鳴り響いている。この狂気のポップ感、何かに取り憑かれたような幸福感は、まさに新要素。
その後はシングル、タイアップ曲が多く、その流れがそこで終わってしまうのがやや残念であるが、独特の言い回しと親しみやすいメロディーラインを、素朴な音で紡ぎ出しているところは相変わらず。ジャズ、ゴスペル、フォークなど、リスナー的雑多な音楽性を自分のものに昇華させる才能は、見事としか言いようがない。
ただ、先ほど紹介した2曲と、「ツアー」「スカート」「レコードノイズ」が純粋な新曲というのは、わがままをあえて言わせてもらうと、少し物足りない。がっつり2枚組くらいのアルバムを作れるだけのポテンシャルは持っているので、少し間を開けて、「平成の怪物アルバム」を期待しています。
歌詞の世界はやや変化してきているように感じる。ストーリーテリングの要素は少なくなり、印象的な言葉を並べることによって、聴き手のイマジネーションを喚起しようとしているように見える。例えば、ラストの「ある車掌」は「どこに行くのか わからないのは 僕も同じさ」という歌詞で終わる。対象が何であれ、すべての人がアイデンティファイできる言葉を、感動的なメロディーと一緒に、すっとポケットに忍ばせてくる。僕なんかやっぱりこれを聞くと泣いてしまうのだ。今後の方向として、言葉のセンスはあるので、これからもっとスキゾフォニックに言葉を並べていくのもおもしろいと思う。
と、次への期待ばかり膨らんでしまうのだが、怖いくらいに着実に成長していることが感じられるアルバム。
再び会える日を、のんびりと待っています。武道館のチケット、まだ持ってますから!
(31/07/13)