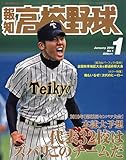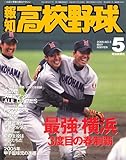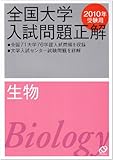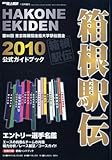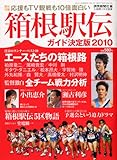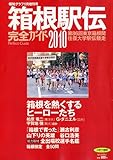あれから間もなく、河合塾から問題
と解答
が公表されました。
問題:http://nyushi.nikkei.co.jp/center/10/2/exam/432.pdf
解答:http://nyushi.nikkei.co.jp/center/10/2/answer/432.pdf
そこで改めて照らし合わせてみましたが、申し訳ありません、先程の自分の解答
は、2問間違っていました・・・ ただ、そのうち1問は、解釈によってどちらを答えるか迷ったのです。
ただ、そのうち1問は、解釈によってどちらを答えるか迷ったのです。
とりあえず、時間と体調の許す限りで、自分なりの解説をしてみたいと思います。
第1問
実験1は、酵母菌(菌類)の細胞分画法である事に注意(葉緑体はないが、細胞壁に似た構造は存在)。
∥
遠心力を上げるにつれ、密度の大きい(重い)細胞小器官から小さい小器官へと順に沈殿。
ア「その(酵母菌)最外層の構造物」:細胞壁(のようなもの)
イ「沈殿P1」:極めて多量のDNAを含んでいる。→核
ウ「沈殿P2」:酸素を活発に消費する性質。→ミトコンドリア(好気呼吸の場)
∥
酸素を用いて有機物(グルコースなど)を二酸化炭素と水に分解し、エネルギーを調達。
問1.「類似した構造物は植物細胞でも最外層にあり」=細胞壁…セルロースを主成分。→⑤
問2.核を複数個持つ細胞=骨格筋(多核)
核を全く持たない細胞=赤血球(哺乳類は無核)→⑥
問3.ミトコンドリアに関する説明は③
その他の選択肢:①中心体 ②葉緑体 ③ゴルジ体
問4.①植物の分裂組織は、根や茎の頂端分裂組織以外に形成層(木部と師部の間)がある。
②維管束組織は「維管束系」に含まれる。
③表皮系…植物体の外表面を覆う。
④動物の体表面・内表面を覆っているのは、上皮組織。
⑤筋組織:横紋筋(骨格筋、心筋)と平滑筋。
⑥神経組織:神経細胞(ニューロン=興奮を伝える)と神経膠細胞(ニューロンに栄養を与え、支える)
第2問
A
テッポウユリのつぼみ:長さ10~17cm→短いものほど若く、長いものほど成熟している。
問1.図1のグラフを読み取る問題。
①②葯での減数分裂 :つぼみ15cmで開始、30cmには終了(約15m分)。
胚珠での減数分裂:つぼみ50cmで開始(葯より遅い→①は誤り)、
170cmで終了(約120cm分=約より時間かかる→②は誤り)。
③分裂の時期はバラバラ。(つぼみ25cmでの葯、90-140cmでの胚珠 など)
→一斉に始まらない。
④葯内 :第一分裂=15-25cm、第二分裂25cmで見られる。
胚珠内:第一分裂=50-140cm、第二分裂90-140cmで見られる。
→共に第一分裂の方が長い。
⑤間期の存在は描かれていない。
第一分裂後は染色体の複製は起きず、ただちに第二分裂に入る。
問2.第一分裂 ・相同染色体の対合、二価染色体の形成。(前期)→①正しい。
この時、染色体の乗換え起こる。 →②は正しい。
・二価染色体が両極に移動。(後期) →③が誤り。
・染色体が半減。
第二分裂 ・体細胞分裂とほぼ同じ過程。→⑤は正しい。
④紡錘体の極は、1細胞あたり2つ。
第二分裂では、もとの細胞が2つに分かれ、各細胞に2こずつ存在するので、
2×2=4個
問3.2n=24(24本)の場合
第一分裂終期で染色体数が半減するため、第二分裂での染色体数がn=12本、一方
第一分裂で、各2本の相同染色体を別々と扱うか、二価染色体を1本として扱うかで迷いました。
解答によると、ここは後者の解釈なのですね。→②
B
問4.イ誘導……未分化の組織から、一定の器官を分化させる働き。
ウ「両生類」(カエルなど)では、植物極(真下)より動物極寄りで原口陥入が起こる。
エ原口背唇部(背側領域) が形成体の働きをする。 →④
問5.神経管→脳・脊髄・末梢神経・感覚器(網膜など)が形成。→①
問6.二次胚の形成
移植された原口背唇部(形成体)は、脊索に分化すると共に、
外胚葉に働きかけて神経管を
内胚葉に働きかけて腸管を誘導。
実験では、以下を用いた。
形成体―黒イモリ由来、宿主―色素を持たないイモリ
よって、
脊索―黒色素あり、神経管―色素なし→②
第3問
A
補足遺伝子(遺伝子の相互作用)
花の色に関する遺伝子2対:A>a、B>b
AとB両方を持つ場合、有色。
問1.AABb×AABb(自家受精)の次世代個体の遺伝子型。
A(a)について:AA×AA→すべてAA
B(b)について:Bb×Bb→BB:Bb:bb=1:2:1
これらを合わせ、AABb×AABb→AABB:AABb:AAbb=1:2:1
問2.自家受精してた場合、AとBを共に持っていると(ホモでもヘテロでも)、子は有色が現れるるため、
白色のみにしたい場合は、AかBの一方は欠くものを選ぶ。→⑤Aabb、⑥aaBb
問3.aaBB×白色個体X→白色:有色=1:1
個体Xの遺伝子型について
・aaBBがAを持たないため、子に有色が現れるには、Aを持つ事が必要。
・白色なので、AとBは共に持たない。→A_bb(AAbb又はAabb)
・ただし、AAbbでは、aaBBとの交配で生まれる子はAaBb(有色)のみとなる。
よって、Aabb→⑥
ちなみに、aaBB×Aabb→AaBb:aaBb=1:1
有色 白色
B
問4.DNAの形質転換
オ
S型菌(病原性)を加熱殺菌し、R型菌(非病原性)と混ぜると、
死んだS型菌により、R型菌がS型菌に変化。
エ
ハーシーとチェイスの実験
T2ファージ(タンパク質の殻で囲まれ、内部にDNAを持つ)を標識し、大腸菌に感染。
→ファージは、大腸菌内にDNAのみ注入して複製後、殻を合成して子ファージを作る。
→遺伝子の本体がタンパク質でなくDNAである事を証明。
カ
以上より、⑧
問5.染色体(真核生物)…DNAとタンパク質(ヒストン)から成る。→①
問6.DNAの二重らせん構造
ヌクレオチドが連なったDNA二本鎖がらせん状にねじれ、
内側に突出した塩基どうしがゆるやかに水素結合。
塩基は、A(アデニン)とT(チミン)、C(シトシン)とG(グアニン)が結合。→⑤
第4問
A
問1.跳躍伝導…有髄神経(軸索の周りを髄鞘が取り巻く神経)では、
髄鞘が電気を通さない絶縁体となっているため、
ランビエ絞輪(髄鞘の切れ目)だけで興奮が起こり、飛び飛びに伝導する。
1―③、2―②、3―⑤
問2.適刺激…ある受容器が受容出来る特定の刺激。
①光:受容器は目
瞳孔反射…虹彩を動かす筋肉の働きにより、目に入る光量の調節。
②化学物質(液体):味覚を生じる。
③血糖値低下→血糖値上昇に働く。=アドレナリン・グルカゴン・糖質コルチコイドの分泌。
④回転運動:受容器は耳の半規管→屈筋反射とは無関係→×
⑤気温低下=寒冷刺激
→体温上昇に働く。=立毛筋収縮、皮膚の血管収縮、心臓の拍動促進、筋肉・肝臓での代謝促進。
B
問3.ヘモグロビンの性質
・酸素濃度高、二酸化炭素濃度低(肺胞など)→酸素と結合し、酸素ヘモグロビンになる。
・酸素濃度低、二酸化炭素濃度高(組織など)→酸素を離す。
=酸素ヘモグロビンの割合は低い。→a×、b○
→c○、d×
→③
問4.①酸素濃度40~20にて大きく低下しているのは、酸素ヘモグロビン。
②グラフより、酸素濃度20の時―差は約65%。
酸素濃度40の時―差は約30%。
よって、正しい。
③50%が酸素と結合している時の酸素濃度
酸素ミオグロビン:約5
酸素ヘモグロビン:約35
④酸素濃度20の時、酸素ヘモグロビンの割合の方が高い。
問5.図1より、酸素ミオグロビン(筋肉中に含まれる)は、低酸素濃度でも、酸素と結合する割合が比較的高い。
これと、ヘモグロビンの性質を考えると、①は当てはまる。
②①と正反対。
③酸素濃度が高くなると、酸素と結合。
④筋肉(組織=低酸素濃度)では、ヘモグロビンが酸素と結合する割合はミオグロビンより低い。
第5問
A
問1.屈性…外界から来る刺激に対して、植物体の一部を一定の方向に屈曲させる性質。
傾性…刺激の方向とは関係なく、決まった方向に運動する性質。
①温度傾性 ②接触屈性 ③接触傾性
⑤光周性…生物現象が日長(実際には連続暗期)の長短によって誘導される性質。
問2.光屈性とオーキシン
マカラスムギなどの幼葉鞘は、光の方向へ屈曲する(正の光屈性)。
・幼葉鞘の先端でオーキシン(植物の成長促進ホルモン)を合成。
・オーキシンは、光の当たらない側へ移動。→光の当たらない側の伸長大。→②○
・オーキシンは下降して、その部位の成長促進。→①○
・幼葉鞘の先端に光が当たらない場合(不透明なキャップをかぶせる、先端切除など)
屈曲は起こらない。→③×、④○
B
問3.実験1:屈曲角が大きいほど、寒天に含まれるオーキシン濃度が高い。
・C(上側)の濃度が低く、D(下側)の濃度が高い。
AorBとCの濃度差と、DとAorBの濃度差は、ほぼ等しい。
・雲母板により、先端を完全に二分割した場合(E,F,G,H)、
中程まで差し込んだもの(A,B)に比べ濃度低い。
→上側から下側への移動が促進。→⑥
問4.①図1において、AとBの合計と、CとDの合計を比較すると、変わりはない。
→水平でも垂直でも、オーキシン合成量自体に差はない。
③図2cにおいて、水を含んだろ氏では屈曲を起こさない。
→オーキシンの作用がないと屈曲しない。
②正しいように思えてしまいます。
しかし図2cで、幼葉鞘の先端切除し、オーキシンを含んだろ紙を乗せたもが屈曲しているので、
「先端部はなくてもよい」という事ですか。。
④で、上記より「先端がなくても(オーキシンさえあれば)屈曲する」つまり
「基部も重力の方向を感知」という事になるのですかね。