
今日の一曲!KARAKURI「AMATERRAS」【2018年振り返り・ナナシス編】
【追記:2021.1.5】 本記事は「今日の一曲!」【テーマ:2018年のアニソンを振り返る】の第一弾『Tokyo 7th シスターズ』編です。【追記ここまで】
お知らせ & 趣旨説明
今回の更新分から年始までの「今日の一曲!」は、【2018年のアニソンを振り返るシリーズ】にする予定です。2016年と2017年の際には複合記事としてアップした本企画ですが、労力の割には検索エンジンからの流入に結びつきにくいため、今年は「今日の一曲!」を連続させるスタイルを試そうと思います。
記事タイトルには代表として一曲を表示し、レビューも基本的にはその一曲を中心に行いますが、墨付括弧内に【2018年振り返り・○○編】と記してあるように、目的はあくまでも通年のプレイバックです。従って、代表曲以外への言及も場合によっては多くなります。要するに本企画の趣旨は過去二年分と変わらず、「2018年にリリースされた○○の関連楽曲のうち、未だ当ブログで紹介していないものにフォーカスすること」であるとご理解いただければ大丈夫です。特に今年は半ばから「新譜レビュー」を実質封印したため、下半期ほどふれ損ねている作品が多くなっています。
―
ということで、この先の長い連載企画の記念すべき第一弾は【ナナシス編】です。2017年の時は【アニソン+ → 冬アニメ → 春 → 夏 → 秋】という順番で振り返ったので、これを踏襲して『Tokyo 7th シスターズ』をトップバッターとします。「アニソン+」についての詳細は、この記事の「2.3.2 リストCの説明」をご覧ください。
今年のナナシスは楽曲のリリースが多く、新ユニットが2組(臨時ユニットも含めれば3組)デビューしましたし、シリーズ全体の3rdアルバムも発売となり、豊作の一年だったと言えます。このうちCi+LUS『シトラスは片想い』(2018)と、Tokyo 7th シスターズ『THE STRAIGHT LIGHT』(2018)に関しては、過去に「新譜レビュー」としてアップした記事があるので、リンク先を参照してください。また、音楽大全本『Tokyo 7th シスターズ COMPLETE MUSIC FILE』(2018)の発売を記念した書いた特集記事も、内容的には「旧譜レビュー」ですが参考までにリンクしておきます。
―
さて、そんな2018年のナナシス史に於いて今回メインで扱うことにしたトラックは、KARAKURIの「AMATERRAS」(2018)です。同ユニット初のデジタルシングル曲で、The Queen of Purpleの「Clash!!!」(2018)に引き続き、配信オンリーでのリリースという新たな試みの一翼を担った曲でもあります。
ゲーム内実装では4thシングル曲;つまりKARAKURIの持ち歌として4作目にあたる本曲は、【1st「B.A.A.B.」(2014) → 2nd「-Zero」(2015) → 3rd「Winning Day」(2016)】と、ナンバリングが進むにつれて増していく楽曲の複雑性から否応なしに湧き出す期待に見事に応えた、ユニット史上最も高度な調和が披露されているキラーチューンであるとの認識です。
まずは歌唱の面から見ていきますが、最大の特徴はラップパートの存在だと言えます。区分すればサビ前のセクションがそれに該当しますが、続くサビもライミングの妙が光る言葉繰りとなっているため、部分単位ではなく曲全体として普段以上に韻律に気が配られているところを素敵に感じました。
偏見もあると前置きしておきますが、曲の一部にのみ登場するラップパートというものは、つなぎのメロディが思い付かなかった時や、似たような曲ばかりでネタ切れ気味になった場合など、換言すれば「作編曲者による小手先だけの誤魔化し」によって挿入されることも多々あるとの理解です。他アーティストの歌詞を引用して補強しますが、岡崎体育「Explain」(2016)の"突然のRap こういうRapの部分は2番のBメロ終わりにありがち"は、この手のらくらくサウンドメイキングを揶揄したものだと捉えています。
しかし、この批判は「AMATERRAS」には当て嵌まりません。なぜなら「ラップミュージック」という要素自体が、楽曲の目指す方向性のひとつとして既に根底に存在し、それゆえに全編を通してリリックとライムにこだわりが窺え、あとはそれが強く発露する箇所(ラップパート)と、部分的に見え隠れする箇所(サビ)とで、両者が巧みに使い分けてられていると分析可能だからです。
この点は作編曲面からも説明が出来、調性を薄めて非メロディアスな趣を宿しているのが前者で、バックトラックと主旋律とが同列に主張を強めている(詳細は後述)のが後者となり、これらを引き立てる役割としてA/B/Cメロがメロディアスなセクションとして据えられているとすれば、全てのパートに意味が見出せ、ラップの挿入が決して誤魔化しの類ではないことがわかります。
歌詞とメロディの橋渡し的ファクターとして次は譜割りに言及しますと、本曲を聴いた際に直感的に思う「この曲難しいな」といったような感想は、その理由を「譜割りの独特さ」に求めることが出来るのではないでしょうか。歌詞を追いながら実際に自分で歌ってみるのが理解への近道ですが、ラップがあるからという理由だけではなく、歌詞の頭と小節の頭が一致と不一致を繰り返しながら進行していくため、展開を正しく把握するのに時間がかかりますよね。
ここは「アウフタクト」でというか「拍」で説明したほうがベターな場面かもしれませんが、曲冒頭ではなく曲途中へのしかも複数回に亘る言及となるので、通念的な理解とズレてしまう可能性を考慮し、ざっくり「譜割り」と表現しました。僕の使う音楽用語はDTMerとしての独学が多く、楽典的な理解とは乖離していることが多いので、全く支離滅裂な内容になっていたらすみません。言わんとしているのは「旋律の緩急がアグレッシブで素晴らしい」ということであり、シンプルにこの点だけでも伝われば御の字です。
次はアレンジないしサウンド面を掘り下げます。立ち上がりはピアノの静けさとホワイトノイズの淡さが印象的で、アートワーク(ジャケ写)で二人を照らしているような青白いビジョンが脳内に浮かびますが、この静寂は電光の如き力強いシンセによって矢庭に破られ、空間全体が断続的に発光するイメージを伴いながら、性質の異なる鍵盤の応酬によって徐々に熱量が増していくという、緊張感に満ちたバックトラックの格好良さに文字通り痺れました。この衝撃はBメロ終わりまで続き、ラップパートに入るとキックが顔を出して俄にダンサブルな趣が強くなります。それ全体でライザーサウンドの様相を呈しつつも、ワンテンポ早い転身でサビへとなだれ込む意表の突き方は流石です。
サビまで進むとエレクトロの質感が一層先鋭化し、先に「詳細は後述」と記した分析;「バックトラックと主旋律とが同列に主張を強めている」が現出するので、続いてはこの点について解説します。悪い意味ではないので誤解なきようお願いしますが、サビはボーカルのラインに対してバックのシンセが浮いていると言いましょうか、両者を別々にはっきりと認識させるために敢えて調性を曖昧にしたように聴こえるんですよね。これをして「バックトラックと主旋律とが~」と形容したわけですが、このような「性質の異なる複数のラインを、ハーモニーに頼り切らずに強引に並行させる手法」は、ボーカルありのエレクトロナンバーでは顕著であるとの理解を経験上しているので、実は王道を歩むつくりになっているところを、ダンスミュージックフリークとしては高く評価したいです。
配信リリースゆえにオフボが今のところないのが残念ですが、4:03~はバックのシンセが奏でているラインが比較的聴き取り易いので、その主張の強さに傾聴してみてはいかがでしょうか。単純に音の性質だけを意識しても、「レベルメーターを振り切って音が歪んでいる?上等!」と言わんばかりのハイプレッシャーで、これまたエレクトロのマナーを弁えているなと絶賛します。
リファレンストラックとして、カナダのエレクトロユニットであるCrystal Castlesの「Concrete」(2016)を埋め込みますが、同曲のというか収録先の『AMNESTY (I)』全般に目立つような破壊的なシンセサウンドを、もう少しポップス寄りにしてマイルドにした雰囲気を「AMATERRAS」からは感じました。ここまで歪ませている極端な例と比較するのはどうかという気もしますが、普通は忌避されるであろうボーダーを軽々と超えてくるあたりで、KARAKURIをアイドルではなくきちんとアーティストとして扱っているのがわかり、非常に好感が持てます。ここでお利口に音を抑えてしまっていたら、アウトプットとして不満を覚えていたことでしょう。
あとはふれ損ねたツボを雑多に紹介しますが、1番サビ後間奏のチルアウトセクションや、2番ラップパート裏の2:33から独特のフレーズを刻み出すシンセ、Cメロバックの疾走感に、アウトロの昇天ギターソロも、それぞれ細かいこだわりが窺えて編曲上で好みのポイントです。
最後は歌詞解釈を披露します。KARAKURIの楽曲の歌詞は、これまでもシニカルな視点或いは孤高の厭世観が滲むようなクールなものが多く、本曲もその例に漏れずといった感じですが、「AMATERRAS」ではいつも以上に「呆れ」や「怒り」が前面に出ていると思えました。
とりわけラップのリリックが好例ですが、"怠惰もいわく平等/手柄はみんな 過失はお前だけ"だとか、"感謝を求め/されるのは当たり前/するのは当然 無料(ただ)じゃありません"だとかは、まさにサビで言うところの"心ない戦場"ですよね。そんな中でも"貴方"に"味方でいてね"と呼びかけるのが本曲のコアですが、それほどの強い存在を確固として自身の中に持たないと、これからの時代を「自分として」生きていけないぞという、警鐘めいたメッセージを読み取れました。これらの要素を全て引っ括めて音に変換すると、先に記したような「破壊的なシンセサウンド」につながるのではないかと推測します。他の表現をすれば「険しさと美しさが共存する音色」でしょうか。
更に歌詞解釈を続けますが、以降はイデオロジカルな向きが強くなるので、そういうのが苦手で楽曲に変な色を付けられたくないと思う人は読み飛ばしたほうが吉です。前の段落で読み終えてもレビューとしては完成しているため、蛇足でしかありません。全体を通していちばん好きなフレーズ;"未来仇/確証のない祭囃子"、これを「今の日本を象徴する一節」であると受け取った上で、批判的な論調を展開します。【追記:2019.2.11】アクセスが多いので補足しておきますと、「天照らす」ひいては「天照大神」を戴く曲名なので、「日本」と関連付けて語るのはそう的外れではないと考えています。建国記念の日に思うところありで書き足しました。【追記ここまで】
不特定多数の書き込みで見たので、誰が初出かはわからず恐縮ですが、「老人達のノスタルジーで国が動いている」といった類の絶望を今の日本に覚えている人は、決して少なくない数で存在しているとの認識です。僕はそれ自体を批判したいわけではありませんが(活気が必要なのは確かなので)、解決すべき問題が山積しているのに先送りにしてここまで来て、もはや取り返しがつきそうにないから見て見ぬふりをする的な、開き直りに近いロジックが背景にあるとすれば、それはあまり褒められたものではないと考えます。"逃げるが勝ち/新手札 手繰り寄せて"は、この種の盲目を皮肉っているのだと思いますが、当然いつまでも使える手ではないため、それは宛ら"確証のない祭囃子"であるとの解釈です。
このように見ていくと、"底抜けの正しさで/いま疼きだす哀し実にだけ宿る/愛しい形"にも共感が出来、"正しさ"を保とうとするだけでも苦しいような社会は確かに"哀し"く、作中年代の2034年は疎か、より直近でさえハッピーに迎えられるかどうか怪しくなって来ますよね。…敢えて色々とぼかして書いていますが、"遠き夏に未来はない/心ない戦場でも貴方でいてね"は、割と直球の風刺であると僕の目には映ったので、クリティカルな読み解きをしたくなってしまいました。なお、作中の未来設定を無視して現実に当て嵌めるという歪んだ時代考証に基いていることは自覚済みなので、あまり厳密に捉えないでいただけると幸いです。
―
通常の「今日の一曲!」であればもう記事を閉じている場面ですが、趣旨説明に記した通り「通年のプレイバック」が目的なので、その他のリリース作品にもざっとふれます。まずは先に曲名だけは出していたQOPの「Clash!!!」から。
来年にはミニアルバムの発売と単独ライブが決定しているQOPですが、本曲はそれに先駆けたプロモシングル的な意味合いもあったと推測します。「格好良い!」以外の感想は相応しくない直球のロックナンバーで、ガールズであることを一瞬忘れてしまいそうな本格硬派の路線は、後の新譜でも堅持してほしいですね。
―
お次は新ユニット・CASQUETTE’S(キャスケッツ)のデビューシングル『SHOW TIME』(2018)。ナナスタの大人組はいつかユニットになればいいなと予てから思っていて、そうなったらサウンドはラグジュアリー志向だろうなとも予想していたので、表題曲の「SHOW TIME」は「まさに!」という感じのナンバーでした。使用楽器の幅も大きく広がるので、ライブ的にも重宝することでしょう。
c/wの「マスカレード・ナイト」は一転してややチープなサウンドが懐かしさに寄与しているナンバーで、こちらはキャスケット帽から来る探偵要素を取り立てたのだろうと思います。関連するエピソードも潜入捜査でしたしね。素性を隠すのを仮面舞踏会に擬えているのでしょうが、アレンジの怪しさからは対となる怪盗的な雰囲気も連想出来ます。
楽曲レビューからは脱線しますが、大人組と言えどシサラがユニットに入ったのは個人的には意外でした。彼女は設定的に隠し玉としての側面があるので、ソロデビューもありなのでは?と考えていたんですよね。
―
最後に777☆SISTERSのメモリアルシングル『MELODY IN THE POCKET』(2018)を紹介します。表題曲の「MITP」は、同名を冠した日本武道館ライブへの「アンサーソング」で、シリーズの歴史を感じさせる切なさと爽やかさの混在が胸を打つ名曲です。3rdアルバムの記事の中では、収録曲の「スタートライン」(2017)と「STAY GOLD」(2017)に対してはやや批判的なことを書き、同系統とした「僕らは青空になる」(2015)は引き合いに出して絶賛したのですが、ここからの流れを直接汲んでいる「MITP」はやはりお気に入りとなりました。
c/wは括弧付きの新ユニット・SU♡SUTA(きゅうとな)のデビュー曲「ラブリー♡オンリー」。モロにシトラスを意識した対抗ソングで、同系統の可愛らしさにキュンとしてしまう一曲です。シトラスの記事の中には、NI+CORAとの対比で「片想い」にフォーカスした一考を載せましたが、これはムスビがスミレに変わっても同様に機能する内容なので、参考にはなるかと思います。ドラマトラック「SU♡SUTA、きゅうとなライバル」の中で、スミレがシトラスのことを「そもそもコンセプトがズルくない?ライブする度に告白してるようなもんじゃん!」と羨んでいましたが、この端的な分析には素直に感心しました。
シトラスは来年の春に2ndシングルの発売が予定されており、まだまだプッシュが続きそうな気配なので、両ユニット共に互いに負けじと頑張ってほしいです。
お知らせ & 趣旨説明
今回の更新分から年始までの「今日の一曲!」は、【2018年のアニソンを振り返るシリーズ】にする予定です。2016年と2017年の際には複合記事としてアップした本企画ですが、労力の割には検索エンジンからの流入に結びつきにくいため、今年は「今日の一曲!」を連続させるスタイルを試そうと思います。
記事タイトルには代表として一曲を表示し、レビューも基本的にはその一曲を中心に行いますが、墨付括弧内に【2018年振り返り・○○編】と記してあるように、目的はあくまでも通年のプレイバックです。従って、代表曲以外への言及も場合によっては多くなります。要するに本企画の趣旨は過去二年分と変わらず、「2018年にリリースされた○○の関連楽曲のうち、未だ当ブログで紹介していないものにフォーカスすること」であるとご理解いただければ大丈夫です。特に今年は半ばから「新譜レビュー」を実質封印したため、下半期ほどふれ損ねている作品が多くなっています。
―
 | THE STRAIGHT LIGHT <初回限定盤(3CD +DVD)> 4,098円 Amazon |
ということで、この先の長い連載企画の記念すべき第一弾は【ナナシス編】です。2017年の時は【アニソン+ → 冬アニメ → 春 → 夏 → 秋】という順番で振り返ったので、これを踏襲して『Tokyo 7th シスターズ』をトップバッターとします。「アニソン+」についての詳細は、この記事の「2.3.2 リストCの説明」をご覧ください。
今年のナナシスは楽曲のリリースが多く、新ユニットが2組(臨時ユニットも含めれば3組)デビューしましたし、シリーズ全体の3rdアルバムも発売となり、豊作の一年だったと言えます。このうちCi+LUS『シトラスは片想い』(2018)と、Tokyo 7th シスターズ『THE STRAIGHT LIGHT』(2018)に関しては、過去に「新譜レビュー」としてアップした記事があるので、リンク先を参照してください。また、音楽大全本『Tokyo 7th シスターズ COMPLETE MUSIC FILE』(2018)の発売を記念した書いた特集記事も、内容的には「旧譜レビュー」ですが参考までにリンクしておきます。
―
 | AMATERRAS 250円 Amazon |
さて、そんな2018年のナナシス史に於いて今回メインで扱うことにしたトラックは、KARAKURIの「AMATERRAS」(2018)です。同ユニット初のデジタルシングル曲で、The Queen of Purpleの「Clash!!!」(2018)に引き続き、配信オンリーでのリリースという新たな試みの一翼を担った曲でもあります。
ゲーム内実装では4thシングル曲;つまりKARAKURIの持ち歌として4作目にあたる本曲は、【1st「B.A.A.B.」(2014) → 2nd「-Zero」(2015) → 3rd「Winning Day」(2016)】と、ナンバリングが進むにつれて増していく楽曲の複雑性から否応なしに湧き出す期待に見事に応えた、ユニット史上最も高度な調和が披露されているキラーチューンであるとの認識です。
まずは歌唱の面から見ていきますが、最大の特徴はラップパートの存在だと言えます。区分すればサビ前のセクションがそれに該当しますが、続くサビもライミングの妙が光る言葉繰りとなっているため、部分単位ではなく曲全体として普段以上に韻律に気が配られているところを素敵に感じました。
偏見もあると前置きしておきますが、曲の一部にのみ登場するラップパートというものは、つなぎのメロディが思い付かなかった時や、似たような曲ばかりでネタ切れ気味になった場合など、換言すれば「作編曲者による小手先だけの誤魔化し」によって挿入されることも多々あるとの理解です。他アーティストの歌詞を引用して補強しますが、岡崎体育「Explain」(2016)の"突然のRap こういうRapの部分は2番のBメロ終わりにありがち"は、この手のらくらくサウンドメイキングを揶揄したものだと捉えています。
しかし、この批判は「AMATERRAS」には当て嵌まりません。なぜなら「ラップミュージック」という要素自体が、楽曲の目指す方向性のひとつとして既に根底に存在し、それゆえに全編を通してリリックとライムにこだわりが窺え、あとはそれが強く発露する箇所(ラップパート)と、部分的に見え隠れする箇所(サビ)とで、両者が巧みに使い分けてられていると分析可能だからです。
この点は作編曲面からも説明が出来、調性を薄めて非メロディアスな趣を宿しているのが前者で、バックトラックと主旋律とが同列に主張を強めている(詳細は後述)のが後者となり、これらを引き立てる役割としてA/B/Cメロがメロディアスなセクションとして据えられているとすれば、全てのパートに意味が見出せ、ラップの挿入が決して誤魔化しの類ではないことがわかります。
歌詞とメロディの橋渡し的ファクターとして次は譜割りに言及しますと、本曲を聴いた際に直感的に思う「この曲難しいな」といったような感想は、その理由を「譜割りの独特さ」に求めることが出来るのではないでしょうか。歌詞を追いながら実際に自分で歌ってみるのが理解への近道ですが、ラップがあるからという理由だけではなく、歌詞の頭と小節の頭が一致と不一致を繰り返しながら進行していくため、展開を正しく把握するのに時間がかかりますよね。
ここは「アウフタクト」でというか「拍」で説明したほうがベターな場面かもしれませんが、曲冒頭ではなく曲途中へのしかも複数回に亘る言及となるので、通念的な理解とズレてしまう可能性を考慮し、ざっくり「譜割り」と表現しました。僕の使う音楽用語はDTMerとしての独学が多く、楽典的な理解とは乖離していることが多いので、全く支離滅裂な内容になっていたらすみません。言わんとしているのは「旋律の緩急がアグレッシブで素晴らしい」ということであり、シンプルにこの点だけでも伝われば御の字です。
次はアレンジないしサウンド面を掘り下げます。立ち上がりはピアノの静けさとホワイトノイズの淡さが印象的で、アートワーク(ジャケ写)で二人を照らしているような青白いビジョンが脳内に浮かびますが、この静寂は電光の如き力強いシンセによって矢庭に破られ、空間全体が断続的に発光するイメージを伴いながら、性質の異なる鍵盤の応酬によって徐々に熱量が増していくという、緊張感に満ちたバックトラックの格好良さに文字通り痺れました。この衝撃はBメロ終わりまで続き、ラップパートに入るとキックが顔を出して俄にダンサブルな趣が強くなります。それ全体でライザーサウンドの様相を呈しつつも、ワンテンポ早い転身でサビへとなだれ込む意表の突き方は流石です。
サビまで進むとエレクトロの質感が一層先鋭化し、先に「詳細は後述」と記した分析;「バックトラックと主旋律とが同列に主張を強めている」が現出するので、続いてはこの点について解説します。悪い意味ではないので誤解なきようお願いしますが、サビはボーカルのラインに対してバックのシンセが浮いていると言いましょうか、両者を別々にはっきりと認識させるために敢えて調性を曖昧にしたように聴こえるんですよね。これをして「バックトラックと主旋律とが~」と形容したわけですが、このような「性質の異なる複数のラインを、ハーモニーに頼り切らずに強引に並行させる手法」は、ボーカルありのエレクトロナンバーでは顕著であるとの理解を経験上しているので、実は王道を歩むつくりになっているところを、ダンスミュージックフリークとしては高く評価したいです。
配信リリースゆえにオフボが今のところないのが残念ですが、4:03~はバックのシンセが奏でているラインが比較的聴き取り易いので、その主張の強さに傾聴してみてはいかがでしょうか。単純に音の性質だけを意識しても、「レベルメーターを振り切って音が歪んでいる?上等!」と言わんばかりのハイプレッシャーで、これまたエレクトロのマナーを弁えているなと絶賛します。
リファレンストラックとして、カナダのエレクトロユニットであるCrystal Castlesの「Concrete」(2016)を埋め込みますが、同曲のというか収録先の『AMNESTY (I)』全般に目立つような破壊的なシンセサウンドを、もう少しポップス寄りにしてマイルドにした雰囲気を「AMATERRAS」からは感じました。ここまで歪ませている極端な例と比較するのはどうかという気もしますが、普通は忌避されるであろうボーダーを軽々と超えてくるあたりで、KARAKURIをアイドルではなくきちんとアーティストとして扱っているのがわかり、非常に好感が持てます。ここでお利口に音を抑えてしまっていたら、アウトプットとして不満を覚えていたことでしょう。
あとはふれ損ねたツボを雑多に紹介しますが、1番サビ後間奏のチルアウトセクションや、2番ラップパート裏の2:33から独特のフレーズを刻み出すシンセ、Cメロバックの疾走感に、アウトロの昇天ギターソロも、それぞれ細かいこだわりが窺えて編曲上で好みのポイントです。
最後は歌詞解釈を披露します。KARAKURIの楽曲の歌詞は、これまでもシニカルな視点或いは孤高の厭世観が滲むようなクールなものが多く、本曲もその例に漏れずといった感じですが、「AMATERRAS」ではいつも以上に「呆れ」や「怒り」が前面に出ていると思えました。
とりわけラップのリリックが好例ですが、"怠惰もいわく平等/手柄はみんな 過失はお前だけ"だとか、"感謝を求め/されるのは当たり前/するのは当然 無料(ただ)じゃありません"だとかは、まさにサビで言うところの"心ない戦場"ですよね。そんな中でも"貴方"に"味方でいてね"と呼びかけるのが本曲のコアですが、それほどの強い存在を確固として自身の中に持たないと、これからの時代を「自分として」生きていけないぞという、警鐘めいたメッセージを読み取れました。これらの要素を全て引っ括めて音に変換すると、先に記したような「破壊的なシンセサウンド」につながるのではないかと推測します。他の表現をすれば「険しさと美しさが共存する音色」でしょうか。
更に歌詞解釈を続けますが、以降はイデオロジカルな向きが強くなるので、そういうのが苦手で楽曲に変な色を付けられたくないと思う人は読み飛ばしたほうが吉です。前の段落で読み終えてもレビューとしては完成しているため、蛇足でしかありません。全体を通していちばん好きなフレーズ;"未来仇/確証のない祭囃子"、これを「今の日本を象徴する一節」であると受け取った上で、批判的な論調を展開します。【追記:2019.2.11】アクセスが多いので補足しておきますと、「天照らす」ひいては「天照大神」を戴く曲名なので、「日本」と関連付けて語るのはそう的外れではないと考えています。建国記念の日に思うところありで書き足しました。【追記ここまで】
不特定多数の書き込みで見たので、誰が初出かはわからず恐縮ですが、「老人達のノスタルジーで国が動いている」といった類の絶望を今の日本に覚えている人は、決して少なくない数で存在しているとの認識です。僕はそれ自体を批判したいわけではありませんが(活気が必要なのは確かなので)、解決すべき問題が山積しているのに先送りにしてここまで来て、もはや取り返しがつきそうにないから見て見ぬふりをする的な、開き直りに近いロジックが背景にあるとすれば、それはあまり褒められたものではないと考えます。"逃げるが勝ち/新手札 手繰り寄せて"は、この種の盲目を皮肉っているのだと思いますが、当然いつまでも使える手ではないため、それは宛ら"確証のない祭囃子"であるとの解釈です。
このように見ていくと、"底抜けの正しさで/いま疼きだす哀し実にだけ宿る/愛しい形"にも共感が出来、"正しさ"を保とうとするだけでも苦しいような社会は確かに"哀し"く、作中年代の2034年は疎か、より直近でさえハッピーに迎えられるかどうか怪しくなって来ますよね。…敢えて色々とぼかして書いていますが、"遠き夏に未来はない/心ない戦場でも貴方でいてね"は、割と直球の風刺であると僕の目には映ったので、クリティカルな読み解きをしたくなってしまいました。なお、作中の未来設定を無視して現実に当て嵌めるという歪んだ時代考証に基いていることは自覚済みなので、あまり厳密に捉えないでいただけると幸いです。
―
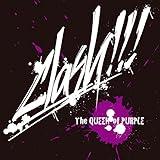 | Clash!!! 250円 Amazon |
通常の「今日の一曲!」であればもう記事を閉じている場面ですが、趣旨説明に記した通り「通年のプレイバック」が目的なので、その他のリリース作品にもざっとふれます。まずは先に曲名だけは出していたQOPの「Clash!!!」から。
来年にはミニアルバムの発売と単独ライブが決定しているQOPですが、本曲はそれに先駆けたプロモシングル的な意味合いもあったと推測します。「格好良い!」以外の感想は相応しくない直球のロックナンバーで、ガールズであることを一瞬忘れてしまいそうな本格硬派の路線は、後の新譜でも堅持してほしいですね。
―
 | SHOW TIME【初回限定盤】 1,944円 Amazon |
お次は新ユニット・CASQUETTE’S(キャスケッツ)のデビューシングル『SHOW TIME』(2018)。ナナスタの大人組はいつかユニットになればいいなと予てから思っていて、そうなったらサウンドはラグジュアリー志向だろうなとも予想していたので、表題曲の「SHOW TIME」は「まさに!」という感じのナンバーでした。使用楽器の幅も大きく広がるので、ライブ的にも重宝することでしょう。
c/wの「マスカレード・ナイト」は一転してややチープなサウンドが懐かしさに寄与しているナンバーで、こちらはキャスケット帽から来る探偵要素を取り立てたのだろうと思います。関連するエピソードも潜入捜査でしたしね。素性を隠すのを仮面舞踏会に擬えているのでしょうが、アレンジの怪しさからは対となる怪盗的な雰囲気も連想出来ます。
楽曲レビューからは脱線しますが、大人組と言えどシサラがユニットに入ったのは個人的には意外でした。彼女は設定的に隠し玉としての側面があるので、ソロデビューもありなのでは?と考えていたんですよね。
―
 | MELODY IN THE POCKET【初回限定盤】 1,944円 Amazon |
最後に777☆SISTERSのメモリアルシングル『MELODY IN THE POCKET』(2018)を紹介します。表題曲の「MITP」は、同名を冠した日本武道館ライブへの「アンサーソング」で、シリーズの歴史を感じさせる切なさと爽やかさの混在が胸を打つ名曲です。3rdアルバムの記事の中では、収録曲の「スタートライン」(2017)と「STAY GOLD」(2017)に対してはやや批判的なことを書き、同系統とした「僕らは青空になる」(2015)は引き合いに出して絶賛したのですが、ここからの流れを直接汲んでいる「MITP」はやはりお気に入りとなりました。
c/wは括弧付きの新ユニット・SU♡SUTA(きゅうとな)のデビュー曲「ラブリー♡オンリー」。モロにシトラスを意識した対抗ソングで、同系統の可愛らしさにキュンとしてしまう一曲です。シトラスの記事の中には、NI+CORAとの対比で「片想い」にフォーカスした一考を載せましたが、これはムスビがスミレに変わっても同様に機能する内容なので、参考にはなるかと思います。ドラマトラック「SU♡SUTA、きゅうとなライバル」の中で、スミレがシトラスのことを「そもそもコンセプトがズルくない?ライブする度に告白してるようなもんじゃん!」と羨んでいましたが、この端的な分析には素直に感心しました。
シトラスは来年の春に2ndシングルの発売が予定されており、まだまだプッシュが続きそうな気配なので、両ユニット共に互いに負けじと頑張ってほしいです。
■ 同じブログテーマの最新記事