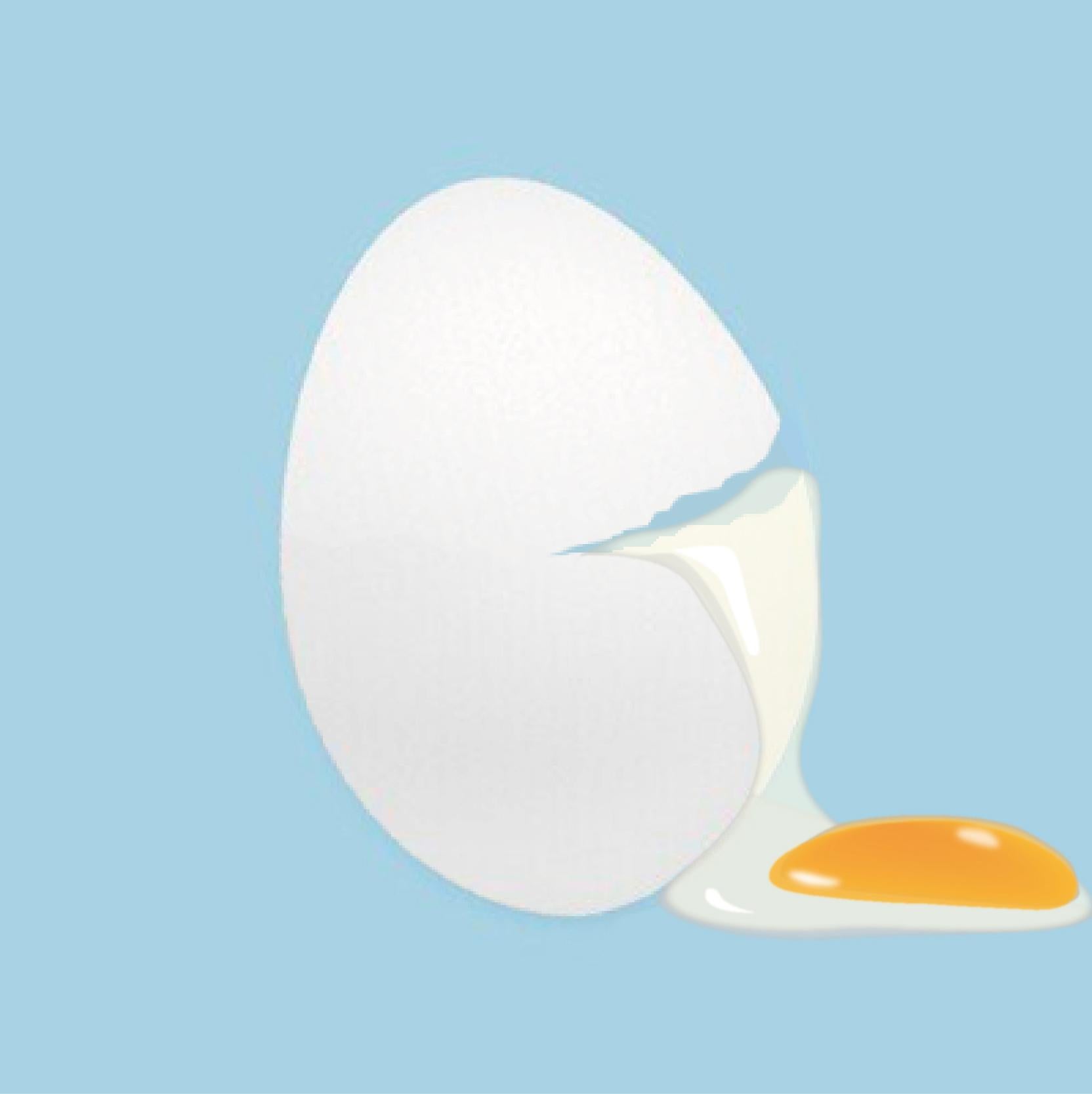2026年2月14日(土)NHKホール
コダーイ/ハンガリー民謡「くじゃく」による変奏曲
フンメル/トランペット協奏曲 ホ長調
ムソルグスキー(近衛秀麿編)/組曲「展覧会の絵」
指揮:ゲルゲイ・マダラシュ
トランペット:菊本和昭(N響首席トランペット奏者)」
最近、演奏会で寝てしまうので事前にコーヒーを飲んでみた。
コーヒーの暗示がかかり、寝ずに済んだ笑
さて、コダーイは何度予習しても頭に入らなかった。
生で聞いても同じく。
本日のメインはなんといっても菊本さんのトランペットでしょう!
すんばらしい演奏だった。
とても美しい。手本のような演奏で心が洗われた。
その後の展覧会の絵の長谷川さんの出だしも楽しみにしていたが、おいおい、、、近衛バージョンはヴァイオリンと合奏かい。残念。
というかフンメル、モーツァルト味がありすぎてパクリ過ぎでは……と思ったらモーツァルトの弟子だった。
特に第2楽章はピアノコンチェルト20番の第2楽章そのもの。
ここまでパクられると清々しい笑。
展覧会はまあ普通。
今日の主役はやはり菊本さんでしょう〜!