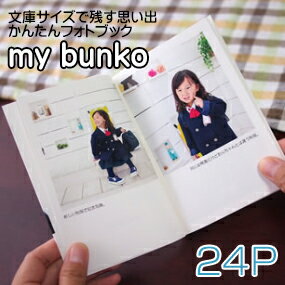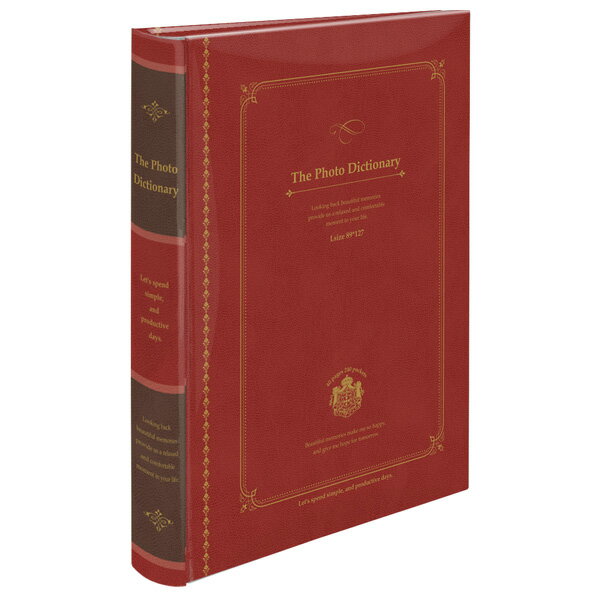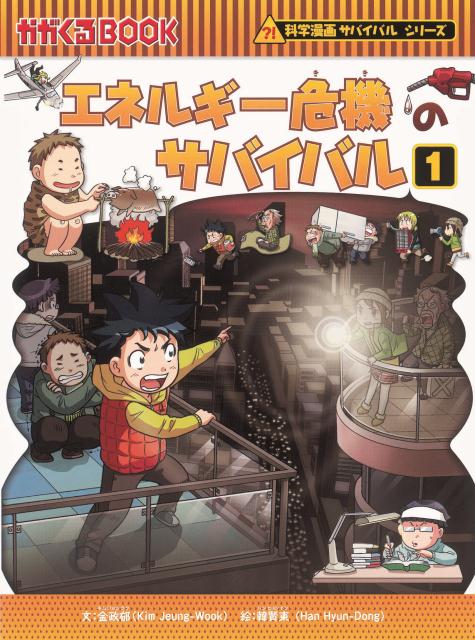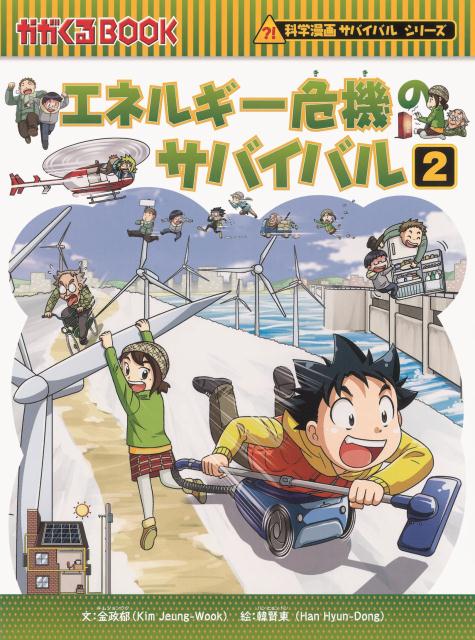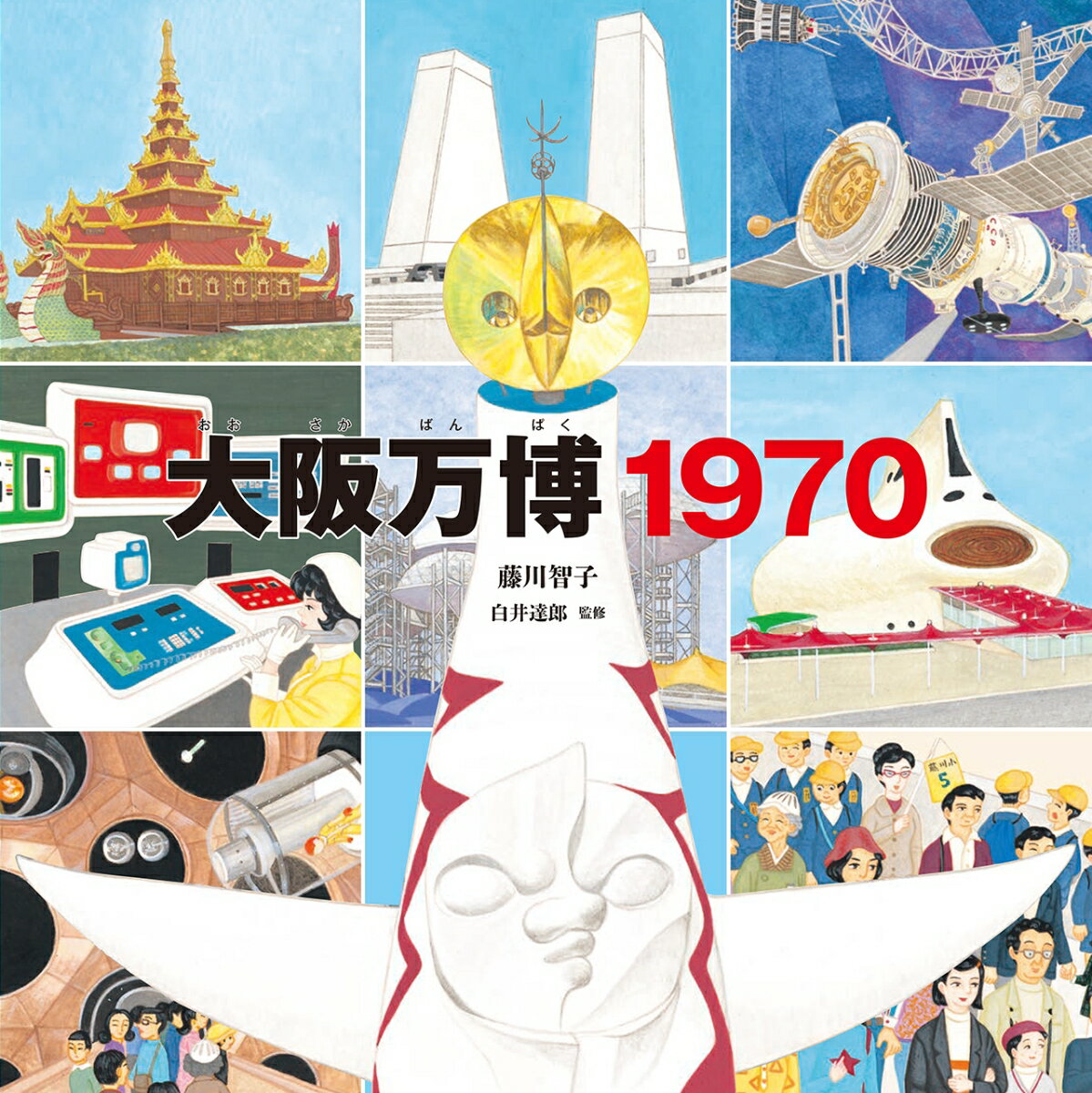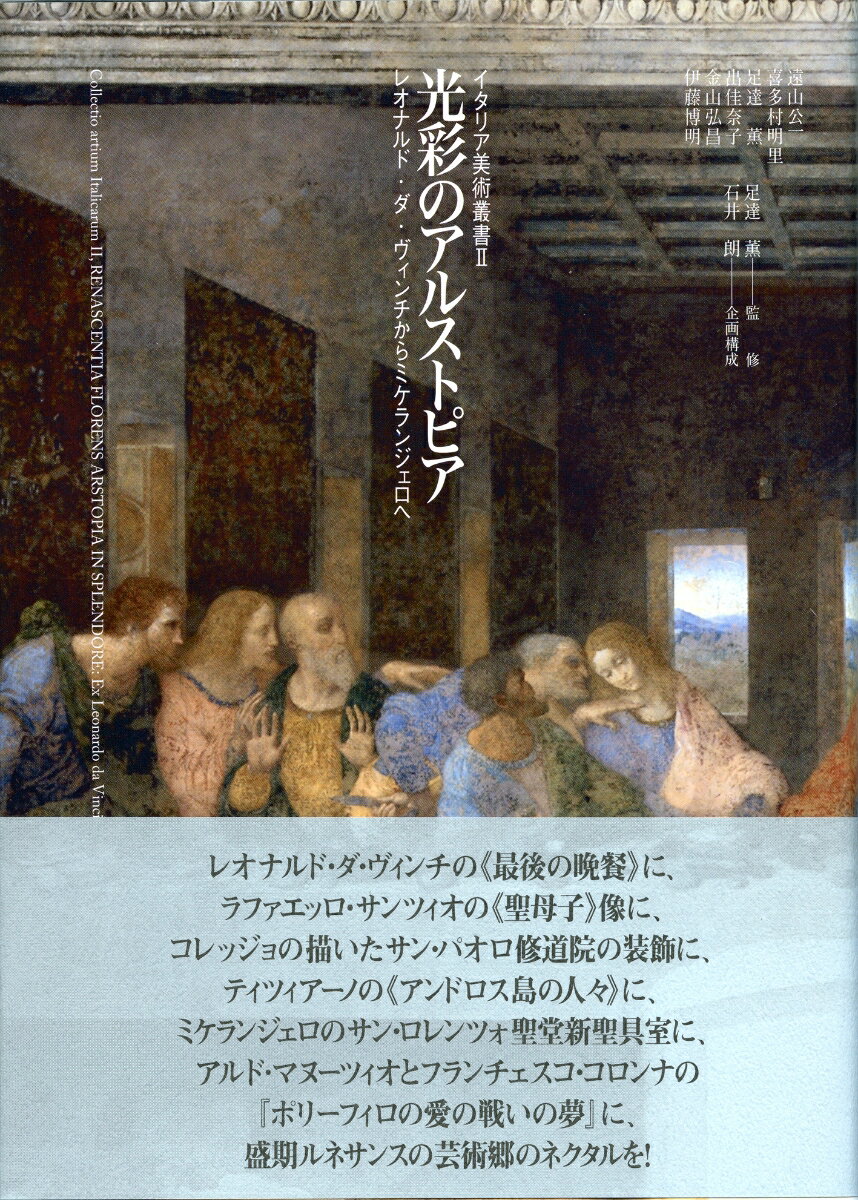万博の半年間、夢洲で撮った写真が本当に膨大で…。
Googleフォトに自動バックアップしていたのですが、無料プランではとても足りず、途中から家庭用のNASにどんどん移していました。
今はその写真を整理して、フォトブックを作ろうと思っています。
どうやって整理するか問題
最初は「日にちごと」にまとめようかと思ったのですが、見返してみると同じパビリオンに複数回行っていたり、外観だけ撮っていたりもするので、「パビリオンごと」で分類することにしました。
ただ、これが想像以上に大変。
パビリオン以外にも、
-
パブリックアート
-
イベントの様子
-
大屋根リング
-
トイレ・休憩所
-
空飛ぶ夢洲
…などなど、ジャンルが多すぎます。
でもNASに眠らせたままだと、きっと見返す機会も減ってしまう。
フォトブックにまとめれば、あとで気軽に眺められるし、思い出話にも花が咲くかなと思っています。
春の夢洲はガラガラで快適だった
4月の写真から見返していったのですが、今見ると本当に人が少ない!
あの静けさが懐かしいです。
夜だけの訪問でも5〜6館入っていたので、やっぱり春先が一番快適でしたね。
たくさんの人と盛り上がった夏も楽しかったけれど、あのゆるやかな空気の春もよかったなあと感じます。
👆こちらは「人が多いからやめよう」と並ばなかった、4月18日19時頃の中国館前。
この付近が後に「地獄通り」と呼ばれることになろうとは。
デジタルスタンプも思い出の一部
会期中は写真だけでなく、デジタルスタンプ集めも頑張っていました。アプリのサービス終了前に全スタンプをキャプチャして保存したので、フォトブックにも収録する予定です。
ただ、会場でQRコードを読み取った分とバーチャル万博で集めた分が混在していて少しややこしいうえ、会場のスタンプは発行数が一定数に達すると背景色が変わる(?)仕様だったように思います。
結果として、同じパビリオンでもバージョン違いが複数あったり、一方でなぜかフランス館だけ見当たらなかったり。
収集漏れに気づくと少し落ち込みますね。
失敗した…と思うのは「コモンズ」
写真を整理していて特に困っているのがコモンズの写真です。
国名と展示を一緒に撮っていなかったため、どの展示がどの国のものだったのかもう分からなくなってしまいました。
一部はネットで調べて判明しましたが、それでも不明なものが少し残っています。
それぞれに個性があったのに、最終的には「コモンズ」としてまとめるしかなく、ちょっと申し訳ない気持ちです。
見返していると、本当に一枚一枚に思い出がつまっていて、選ぶのも迷ってしまいます。“自分だけの万博アルバム”を作れるというワクワク感もありますが、いったい全部で何ページのフォトブックになるのか、そしていくらかかってしまうのか……。
14823枚(40.1GB)の写真を全部見て、ようやく一次選考を終えたところですが、まだ2200枚。せめて500枚以下にしなければ、と思いつつ、途中で投げ出さずに整理し終えられるのか、ちょっと心配になっているところです。