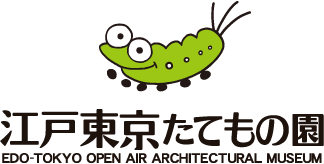現在、お出かけブログをお休みしています。
詳しくはこちらをご覧ください。
昨年11月に小金井市にある「江戸東京たてもの園」に行って来ました。
その様子を少しずつご紹介しています。
いままでの記事を順に載せますので、まだご覧になっていない方は順にご覧頂けたら嬉しいです。
すっかり間があいてしまい、申し訳ありません。
今回、ついに完結編となります。
少し長くなりますが、最後までお付き合いいただけたら幸いです。
江戸東京たてもの園の一番人気のエリア「東ゾーン」を散策しています。
前回はお風呂屋さんを見学しました。
江戸東京たてもの園は、小金井市の小金井公園の中にあります。
ここは、文化的価値の高い建物で、現地保存が難しいものを移築保存展示しているんです。
前回より、このたてもの園の中でも一番の撮影スポット、下町中通りを散策しています。
万徳旅館
江戸時代末期から明治時代初期の建物で、青梅市西分町の青梅街道沿いにあった旅館です。
建物は創建当初に近い姿に、室内は1950年(昭和25年)ごろの様子を復元しています。
でも、番頭さんとかいたんだろうなぁ。
青梅街道沿いにあったという事で、たくさんの旅人でにぎわったんでしょうね。
となりには、あの方のリサイタルが始まりそうな空き地がありました。
こんな空地は、ほとんどもう無いですからね。
一つは、西ゾーンにある「デ・ラランデ邸」。
そしてもう一か所がここ、「たべもの処 蔵」です。
1階が休憩所になっていて、2階が食堂です。
うどんを中心にしたメニューがあるようです。
次回はぜひ、うどんを食べてみたいなぁ。
長屋…という感じでしょうか。
今にも子供たちが元気に走り出てきそうです。
ずいぶん背の高い物干し台。
Y字になった棒で、物干しざおを下ろすんですよね。
またメインの通りに戻ってきました。
茶色い建物が「武居三省堂」、文具屋さんです。
小さなお店ですが、多くの人がひっきりなしに来ていました。
なぜなら、「千と千尋の神隠し」のなかの重要なシーンのモデルとなったと言われているからです。
では、中を見てみましょう。
そして、噂の場所が店内の左側なんです。こちら!
引き出しがぎっしり並ぶ場所、憶えていらっしゃいますか?
そう、千と千尋の神隠しの中で、釜爺がいたボイラー室。
あの時はいろんな薬草が引き出しに入っていたようですが、ここでは筆や墨などがぎっしり入っていたというわけですね。
とても狭い店内ですが、千と千尋の神隠しのモデルと知られているからか、ひっきりなしにお客様が訪ねてきていました。
その隣は花市生花店です。
1927年(昭和2年) 神田淡路町に建てられました。
壁には、牡丹や菊などの美しいレリーフが。
さすがお花屋さん。
1927年(昭和2年)に中央区新富に建てられました。
2階の窓の上にある装飾がとても凝った造りになっています。
中央のマークは、よく見ると「U」と「S」が組み合わされています。
これは、この建物を建てた「植村三郎」さんのイニシャルだという事です。
すごいな。
お隣は、乾物屋さんの「大和屋本店」です。
1928年(昭和3年)に港区白金台に建てられました。
3階建てで、間口が狭いのに背が非常に高い特徴があり、一見すると看板建築に合わせているように見えます。
珍しい建物なのだそうです。
するめや昆布など、乾物が並んでいました。
店内は戦前の乾物屋さんを再現しています。
一番奥の木の棚に並んでいる棒状のものは、かつおぶしでした。
そしていよいよ最後にご紹介する建物は、荒物屋さんです。
丸二商店(荒物屋)
昭和初期に建てられました。
小さい銅板を組み合わせて模様を作ってかざっているところが特徴的です。
店内は昭和10年代の様子を再現しています。
ここは、普通に買い物をしたくなるような、楽しいお店でした。
大きなやかん!
木の皮みたいなのは、経木かな?
鍋タワー、となりに釜タワー。
昭和レトロのお店で見たことがある、味のある水筒。
わっかはなんだろう。針金?
ネズミ捕りですね。
骨董市で私が買ったような小皿が(笑)
今でも東京の下町の何処かにありそうな、逆に西荻窪や代官山あたりにひっそりとありそうな(笑)
小物がずらりと並ぶ、楽しいお店でした。
本当に買い物が出来たらいいのにね。
さて、長々と続けてきた「江戸東京たてもの園」のご紹介は今回で完結です。
いかがでしたか?
もし、一緒に散策しているみたいとか、いつか行けるようになったら訪ねてみたいとか、そんなふうに思っていただけたらとてもうれしいです。
見学してみて、その時代の暮らしや空気を想像しながらその場にいられることがとても楽しかったです。
ハリボテではなく、忠実に再現されている所が素晴らしいなと思いました。
私はジブリ作品にそれほど詳しくありませんが、お好きな方にはその世界観も味わえる空間だと思います。
現在は、コロナ禍で臨時休園中ですが、またいつの日か再開される日が来たら、ぜひお出かけになって下さいね。
記事が長期にわたってしまい、バラバラになってしまったので、近々「まとめ」として記事を集めたいと思います。
そこに、今回載せきれなかった、江戸東京たてもの園の売店の様子などもオマケとして載せるつもりです。
「記事と記事の間があきすぎて、前の方忘れちゃったよ」という方は、ぜひご覧になって下さい。
最後までご覧いただきありがとうございました。
ランキングに参加しています。
下の「東京情報」のボタンを押して頂けると、明日からまたがんばれます!