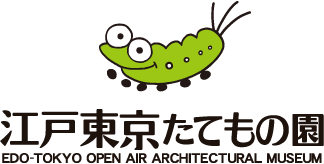コロナ禍でお出かけブログをお休みしておりましたが、少しずつ再開しております。
これからは、「小さな楽しみを見つけよう」と「東京街歩き」の両方を書いていきます。
https://ameblo.jp/mimimisuke/entry-12633760121.html
とぎれとぎれになってしまいましたが、11月に小金井市にある「江戸東京たてもの園」に行って来ました。
その様子を少しずつご紹介しています。
今回は3つあるゾーンの最後、東ゾーンの中を散策します。
まず最初はこちら!
万世橋交番(まんせいばしこうばん)
いつごろ造られたのか、正確な資料は残っていないようですが、デザインや建築様式から明治時代のものと考えられているのだそうです。
正式名称は、「須田町派出所」。
神田の万世橋のたもとにあったのだそうです。
移築の時は、これを丸ごとトレーラーにのせて運んだのだそうです。
運んでいるとき、見たかったなぁ!
中は簡易な感じで、流し台やガスコンロなどがついていました。
うーん、本当に最低限な感じだなぁ。
そのすぐとなりに、すごく重々しいゴージャスな街灯がありました。
皇居正門石橋飾電燈
皇居前広場から皇居に向かって左手前に見える石橋に設置されていた飾電燈です。
石橋は、その前に架けられていた木橋に替わって、1887年(明治20年)に架けられました。
飾電燈は、1886年(明治19年)に東京電燈会社へ発注されたことはわかっていますが、完成日、設計者、鋳造場所などはわかっていないそうです。
ちなみに、東京電燈(株)はかつてあった日本初の電力会社だったのだそうです。
次に目に入ったのは大きな農家。
※撮影 2020年11月28日
天明家(てんみょうけ)(農家)
江戸時代に、現在の大田区で重職を務めた旧家です。
長屋門や正面に千鳥破風をもつ主屋などに格式の高さを感じます。
たくさんの人が住んでいたんでしょうね。大きなお家です。
次に見えたのは、あれ?ムーミン?
上野消防署(旧下谷消防署)望楼上部
かわいくて、なんだかムーミンに出てきそうな建物じゃないですか?
でもこれ、名前の通り塔の上の部分だけなんです。
1925年(大正14年)に建てられたこの望楼は、高さ23.6mありました。
江戸時代からの「火の見櫓」の役割で建てられましたが、1973年(昭和48年)には、建造物の高層化や電話の普及のため、望楼の利用は取りやめとなったそうです。
この旧下谷消防署の望楼は、1970年(昭和45年)まで使用され、1977年(昭和52年)に解体されました。
てっぺんの部分だけだと、こんなにかわいいんですね。
次に見えたのは、黄色い電車!
都電の車両ですね。
都電7500形(1962年製造)
渋谷駅前を起終点として、新橋・浜町中ノ橋(神田)須田町まで走っていた車両です。
交通量の急増に伴い、都電は1963年(昭和38年)から順次廃止されました。
現在残っているのは、都電荒川線 三ノ輪橋~早稲田間(12・2㎞・30停留場)だけとなりました。
千と千尋の神隠しの中で、千尋が銭婆に会いに行くためにカオナシと電車に乗ったシーンは、この電車がモデルだったのではと言われているそうです。
さて、今回はここまでです。
次回はお風呂屋さんなどの中に入って見ようと思います。
何回にも分かれてしまってごめんなさい。
次のお出かけの予定が立たないので、せっかくのおでかけを大切にしようと思っています。
丁寧にゆっくりと進めますので、ぜひ次回もご覧になって下さいね。
ランキングに参加しています。
下の「東京情報」のボタンを押して頂けると、明日からまたがんばれます!