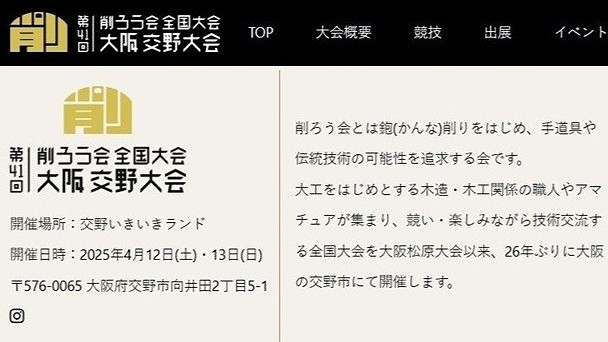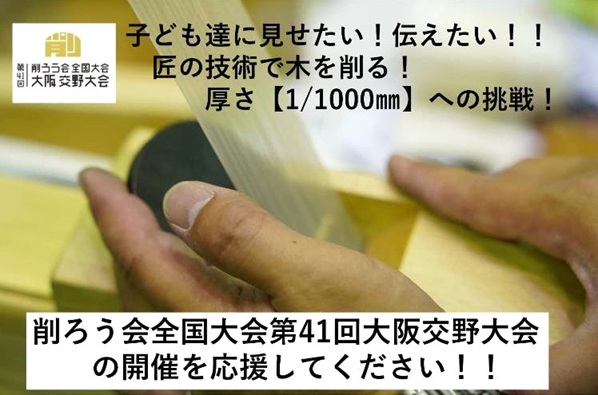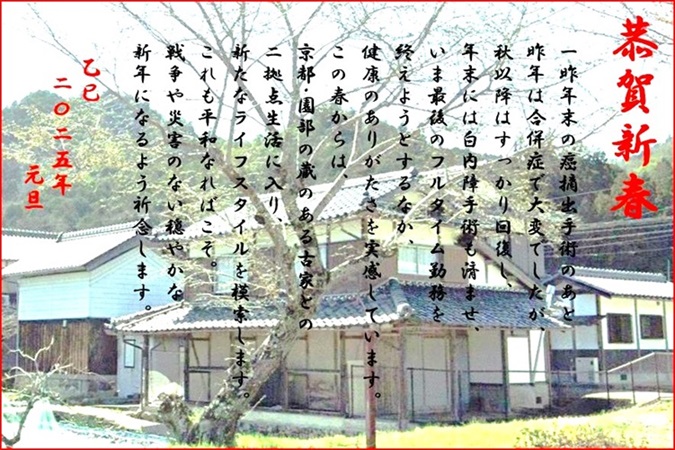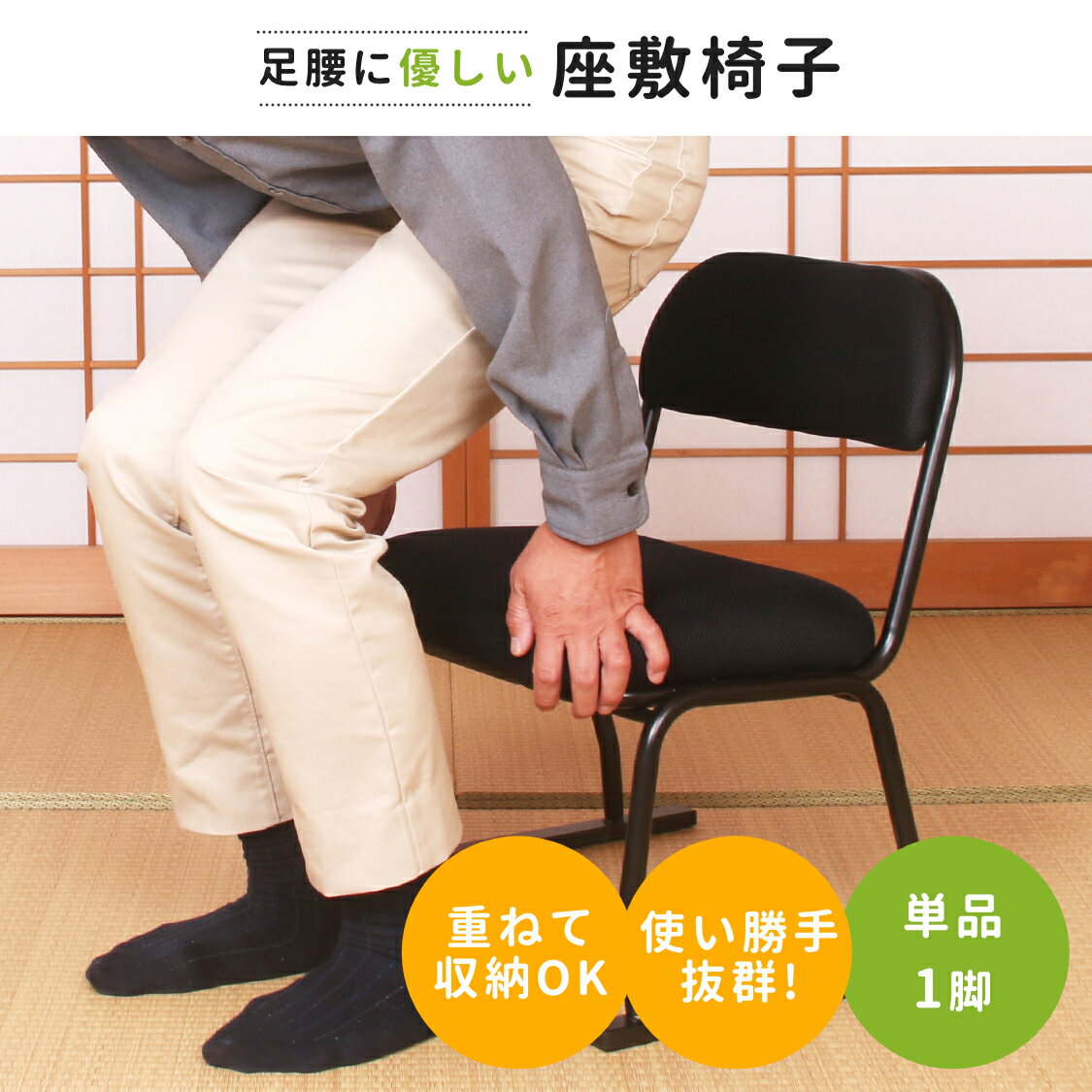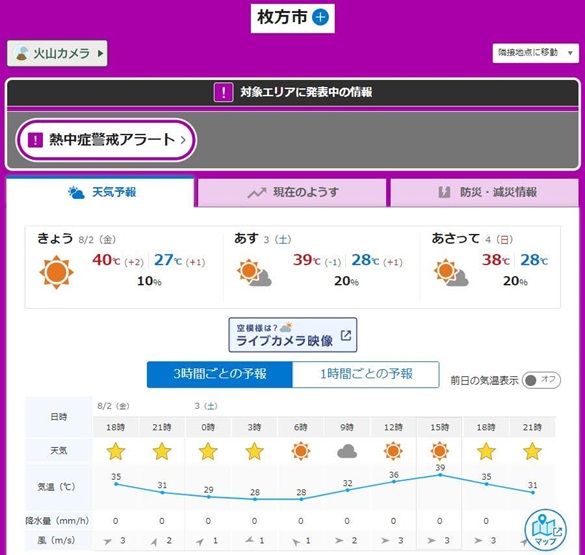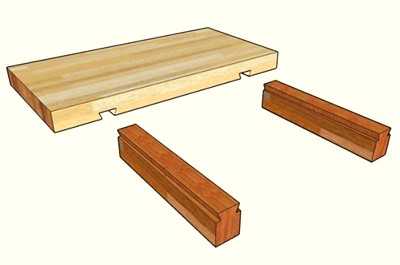大阪・枚方の石場建て伝統構法の家、
木と竹と土と紙の新居に暮らし始めてから、
早くも5度目のお正月を迎えました。
そして、京都・南丹市の築半世紀の古家との
二拠点生活を始めてから、丸1年が経ちました。
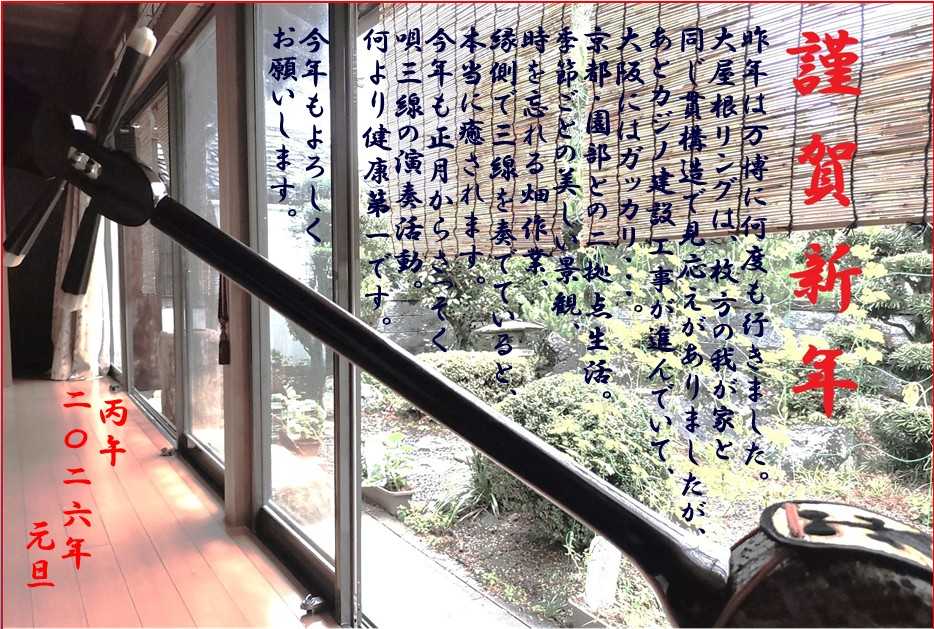
年末、南丹市のスーパーに行ったら、見たことのない注連縄?!
この地域独特の?・・・よく分からないまま、大は玄関、小は納屋に掛けてみました。…
地域の人が見たら、変かも?・・・こんど聞いてみよう!
年末は比較的あたたかめ・・・と言っても、南丹の朝は枚方よりずっと冷え込みます。
どんよりした冬空でも、家の周囲の景観は圧倒的に美しい!

それでも1/2の夜からは雪が降り始め、
あれよあれよという間に翌朝には積もりました。

元旦は、枚方の家に親族が大集合!・・・大人9人、子ども5人。
南丹の家なら余裕なんですが、
一応枚方の家が狭いながらも「実家」です。
枚方では毎年恒例、ことほきの素の注連飾りに、庭にあるものを適当に挿し足すんですが、
去年の1/1稿「the実家・・・」を見返してみると、今年はちょっとやり過ぎでした。

孫たちは、2階の畳の続き間で。

這いまわるので畳だと自由度が高いし、
何よりも床スレスレに顔、全身で畳を感じます。
つかまり立ちをするようになったので、飾り棚は危ないね!

まだ10ヵ月。でも畳の良さが分かるのか、どの家にお邪魔しても、
畳の部屋だと落ち着いてる気がするとは、息子の弁。
今日あらためて無垢無塗装の杉板外壁を眺めてみると、
5年も経つと経年変化でいい具合に侘びてきました。
雨が当たったり紫外線の直射を受けたりで、表情が生まれます。

2021.1.13稿「木組み土壁の家の快適性~冬季・・・」の
ほぼ同じ時間の写真と比べれば一目瞭然。
当初は均一で単調な感じだったなぁ・・・と改めて思い返されます。
枚方の住宅密集地では、南丹の家の環境の良さには及ぶべくもありませんが、
今日こうしてPCに向かってブログを更新しながら、
あらためて木と竹と土と紙の家の心地良さを実感しています。

去年の1/1稿「the実家・・・」には、
ネタが溜まってるから今年はせっせと投稿・・・と書いたのに、
結局1月と4月と10月に5回しか投稿できませんでした。
今年は月1の頻度をめざしたいと思っているところです。
今年もよろしくお願いします。