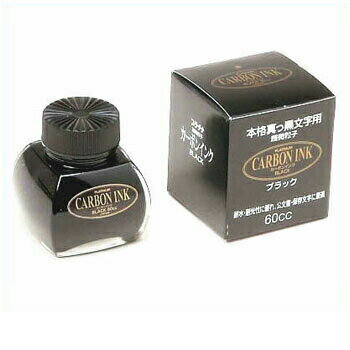先日の日曜日(6月23日)は、愛知県蒲郡市でトライアスロンでした
タイトル通り、第36回 蒲郡オレンジトライアスロン大会(2024)です
さて、その準備から
まずは大台ヶ原ヒルクライムで、劇坂仕様としたMAVICのキシリウムを外して
Tiagraティアグラグレードの11-34Tというドデカスプロケット(CS-HG500、10速)にしているので、さすがに蒲郡のド平坦コースには向かない
大台ヶ原後も、金剛山や、堀越観音など、山登り練習用にそのままにしているので、このホイールは使いません
そして、日曜日の蒲郡のお天気予報は雨!
終日、雨、雨、雨です
先週からずっと雨予報なので、ウェットレースを想定して機材準備
いつも、アルミのAC号(Athlete Companyアスリートカンパニー号)でトライアスロンに出場する時でも、ホイールだけはカーボンディープのFFWD F6C、あるいはF6Rを使うのですが、今回は雨レースの予感なので制動力に難のあるカーボンよりアルミリムの方が安全と思ったのと、蒲郡のバイクコースレイアウトが短い直線の折り返しの連続なのでTTバイクにするメリットも少ないし、ディープリムで風で煽られるのも嫌だったので、久しぶりにAC号と、このNOVATEC LASER(アルミチューブラー)で参戦することにしました
NOVATECノバテックは台湾メーカー、世界の2大メーカー、GIANTジャイアントもMERIDAメリダも台湾です
14、5年前にこのAC号を購入した時にアスリートカンパニーの店長さんがアッセンブルしてくれたのがこのホイールです
クリンチャーにするかチューブラーにするか訊かれましたが、トライアスロン用、レースバイクなので当然、チューブラーにしますと返答しました(ユーザーはチューブラーもクリンチャーも半々、好みですよ、と言われましたけど)
Nマーク入り、赤いアルマイトのハブ
タイヤはTUFOのS33 SPECIAL 28inch 21mm
チェコ製のチューブラータイヤ
当初はS33 PRO(260g)という、耐パンク層もない安価なタイヤでしたが、トレッドが硬く、チューブもブチルなので一旦、空気を入れるとほとんどエア抜けもなく、いつまでも走り続けられるくらい転がり抵抗も少なくて、マイナーながらいいタイヤ(ブランド、メーカー)でした
前回のタイヤ交換の際に、1グレード上の耐パンク層を備えたS33 SPECIAL(260g)に張り替えています
本当はもうひとつ上の、S3 Liteというタイヤにすれば更に軽量(お値段によって215g、165gなど重さが違う)で立派なレーシングタイヤになります(それでも価格はVittoriaの半額くらい、チューブはブチルです)
↓これでも立派ですけどね
NOVATECのホイールといい、TUFO(テュフォ、ツーホー、チューフォー、いろいろな言い方があります)といい、クラシカルな印象です
フロントも同じ
無理をして?いつもより(白いマーカー)5mmシートポスト上げてます(平坦、直線なのでより前傾姿勢、空気抵抗を減らすため)
単なる、見栄っ張りではないですよ!
タイバンドを巻いているのは、ゼッケンシールをカッコよく貼る為の工夫です(ゼッケンホルダー)
ステム回り
3T ARX TEAM -17° 90mm
ヘッドチューブ正面に○Aマーク(店長曰く、たしか、トライアスロンに因み、走る人と波〜と、ホイール○を現している、とのことでした)
なかなかカッコいいです!
ケーブルルーティングは、シフト、ブレーキとも左リア、右フロントのレーシングパターンです
これも店長さんの勧めで、自転車に乗り始めたときからこのセッティング
メインコンポを新車時の105から、数年してUltegraアルテグラにアップグレードした時に、全部自分でやり替えていますけど
ケーシングはシマノではなく、GIZAギザ?とかJagwireジャグワイヤーをよく使います
トップチューブとダウンチューブにAthlete Companyアスリートカンパニーのロゴ
トップチューブ、シートチューブは完全な円チューブ
ダウンチューブも真円ですが少し太めです
シートステー、チェーンステーは扁平加工がしてあり、この辺の造りは妥協なし、よく出来ています
トップ520、ヘッドチューブ120(TNI 7005 MkIIのLサイズと同じ、フォークのみカーボン、同色塗り)
スローピングフレームではありますが、このサイズだとほとんどホリゾンタルになるので、その辺も見栄えに影響します
これ以下のサイズ(Mサイズ以下)になるとスローピングがキツくなります(チープ感、キッズ感が強くなります)
520のフレームで、ステム90mm
自分は小柄なので、これがギリギリ乗れるサイズですが、プロでもやや大きめサイズのフレームが流行りだそうです
Cyclowiredで記事を読んだ、ホントの話し
クランクは大台ヶ原ヒルクライム仕様のまま
ROTOR INPOWER 3D+ 170mm(52−36T)
ホントはトライアスロンなので、ケイデンス重視で165か、160にしたいところですが、そんなに都合よく欲しいサイズのROTORクランク、特にROTOR POWERが入手できる訳ではないので、今回は使い慣れたこのクランクでいきます
チェーンリングも肉抜きされていて、エアロよりも軽量化重視のパーツです
リアディレーラーも大台ヶ原仕様、10速、105 RD-5701GS(デカいロー34Tティアグラスプロケ対応のロングケージ)のまま
そしてノバテックのスプロケは、10速Ultegraアルテグラ CS-6700 11-28Tでした
ボトルケージだけ豪華に、カーボン製
Blackburnブラックバーン!
もう何年も使っていますが、軽量、ボトルの保持力も良好で耐久性も問題ありません
赤いアルマイトのBBはROTOR純正
ローター3D+クランク(30mmアクスル)を使用するためのベアリング内径30mm、JIS-BSAフレーム互換用BBです(シマノクランクは24mm)
元々、セラミックベアリングでしたが、わざわざスチールベアリングに換装しています
さあ、リアセクションはこんな感じ
サドルはこれも長年愛用のFi'zi:k Arioneフィジークアリオネ R5 メタルk:iumキーウムシートレールモデル
ちなみに、前回レース、大阪城で使用したCervelo S5はこちら↓
前輪が、レース後、パンクしていました
いわゆるスローパンクチャーで、バイクピックアップ後、撤収時に気がつきました
チューブラータイヤを張り替えるのが面倒でまだそのままにしているので、とりあえず予備ホイールを嵌めてます
手前、パンクしているF6R、奥、S5に嵌めているのが予備のF6C
F6RはタイヤがVittoria Corsa CX 21-28ですが、F6Cは23-28です
ホイールの違いはほとんどありませんが、CはcontrolコントロールのCで、体重の重いサイクリストの為にハブのスポーク本数が多いモデルです
さて、ようやく自転車をクルマに詰め込んで、積め込んで
さあ、蒲郡に出発です!
といっても土曜日ですので午前中は仕事して、午後から半ドンで行きます
外した山岳仕様のキシリウムも、パンク対策で持っていくことにしました〜
機材の話はレース前にアップしたかったのですがサボって間に合わず
内容もついつい盛って長くなってしまったのでレースレポートは、次回に!!