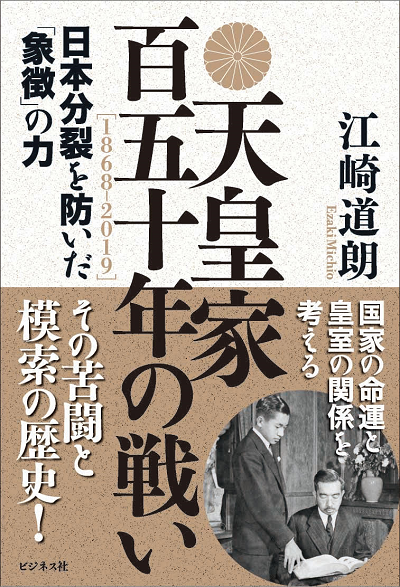嘉祥三年(850年)三月二十五日、文徳天皇の第四王子惟仁(これひと)親王が誕生しました。本日は旧暦では三月二十五日ですから今ぐらいの時期でしょう。(改暦は何度もあったため、単純に旧暦で考えています。)
惟仁親王の御母は、藤原良房の娘の女御明子(後の皇太后)であり、良房は摂政宣下を受け、皇族以外で初めて摂政の座に就き、以後藤原北家全盛時代を築いています。そのため、惟仁親王は三人の異母兄を超えて生後八か月で立太子されました。そして、天安二年(858年)十一月七日父帝の崩御により満年齢八歳で即位されました(清和天皇)。
そしてその翌年四月十五日、元号が貞観に改元されましたが、この貞観年間には様々なことが起きました。
貞観二年(860年)には勅命により都の西南の裏鬼門にある男山に石清水八幡宮が創建されています。これは南都大安寺(開基は聖徳太子)の僧、行教が宇佐八幡宮に参詣したおりに「われ都近き男山の峯に移座して国家を鎮護せん」との神託を受け、これを帰京して上奏したところ、すぐに創建の勅命が下りたのです。
同じ年、京都は長雨による大水に見舞われました。また京都をはじめ近畿地方は台風による洪水や、高潮が起き多くの死者が発生しています。
貞観三年四月七日(861年5月19日)、直方隕石(のおがたいんせき)が福岡県の武徳神社(現須賀神社)の境内に落下しました。これは確認できる世界最古の隕石といわれています。この翌日深くえぐられて土中から掘り起こした黒く焦げた石を桐箱に納め保存されたといわれ、その箱の蓋の裏には「貞観三年四月七日納ム」という墨書きがあります。これが、後に科学的鑑定もされて世界最古とされました。この隕石は5年に1度の御神幸大祭の時に公開されており、2021年10月がその公開の年でしたが検索しても出てこないのでコロナ禍によりこの年は公開されなかったのかもしれません。境内には隕石のレプリカが置かれており、北九州市にある「いのちのたび博物館」にもレプリカが展示されているそうです。
同じ年、大雨による洪水が起きています。
貞観四年(861年)、飢饉発生。
貞観五年(862年)、越中・越後地震発生。山崩れ、谷埋まり、水湧き、圧死多数。直江津付近の小島数島壊滅。
貞観六年(864年)五月二十五日、富士山の大噴火(貞観大噴火)が起きました。この時から貞観八年まで噴火活動が続きますが、この時が活動記録に残る一番大きな噴火で、この時富士山北麓にあった湖が埋没し、その時残ったのが現在の富士五湖のうちの西湖と精進湖で、湧きだした溶岩流の上に1100年の時を経て再生した森林地帯が現在の樹海の森青木が原です。
貞観八年(866年)閏三月十日、応天門(朝廷内での政務・儀式を行う場、朝堂院の正門)が放火される事件があり、嫌疑をかけられた伴善男父子が有罪となり流刑に処せられた事件がありました。これは藤原氏による他氏排斥事件の一つとされています。
貞観九年(867年)、河内で洪水、堤防決壊が起きました。
貞観十年(868年)は毎月のように地震が発生し、特に七月から八月にかけては連日発生していました。七月に発生した播磨国の地震では、官舎諸寺堂塔ことごとく倒壊したといいます。
貞観十一年(869年)五月二十六日、陸奥国で貞観地震が発生、地震に伴う津波(貞観津波)の被害が甚大で死者が約1000人ほど出て多賀城が損壊しました。これは東日本大震災とも酷似していると話題になった地震のことで、マグニチュード8.3以上であったとされています。
この時清和天皇は陸奥国と常陸國との国境が最大の被災地とする詔を発せられました。朝廷は死者を全て埋葬するよう命じ、被災民には租税や労役の免除をしています。
六月十五日には、貞観の新羅の韓寇が発生し、新羅の海賊が博多津に停泊していた豊前国貢調船を襲撃し略奪しました。以後承平五年(935年)まで約100年に亘って新羅の賊徒が日本各地を侵略することが続きました。国内の新羅人が内応していたという事ですから、現在の民族の構図と変わらないことがわかります。
十二月十四日、清和天皇は伊勢神宮に勅使を遣わして奉幣され、新羅の海賊や陸奥国の地震や津波で大被害が発生したことを報告し、御自身の不徳を詫びられて国家の平安を祈願されました。
貞観十三年(871年)四月八日、鳥海山(山形県と秋田県に連なる山)が大噴火を起し、土石流・泥流が日本海に達しました。また京都では大雨による洪水が発生しました。
貞観十四年(872年)、大和・因旗で台風による洪水が起き、稲が被害を受けました。
貞観十五年(873年)、伊勢で豊受神宮の層門倒壊、殿社と倉庫が流失しました。
貞観十六年(873年)七月二日、薩摩国の開聞岳が噴火しました。
同年、京都では暴風雨で御所が大きな被害を受け、大小の橋梁残さず流失し、京の集落では激しい水の流入による溺死者多数で、3000軒以上が罹災。
貞観十八年(876年)、清和天皇は在位十八年、満年齢二十五歳で、もうすぐ満年齢八歳になる第一皇子の貞明親王に譲位されました(陽成天皇)。この年は前年以来の旱魃により飢饉が発生していました。この時既に死去していた藤原良房の養子基経が史上初の関白に就任しています。
貞観十九年(877年)四月十六日、元号を貞観から元慶に改元。
元慶10月28日、相模武蔵地震発生、マグニチュード7.4と推定される。
元慶三年(879年)五月、上皇は出家され素真と号し、本気で修行僧になり、絶食をともなう苦行を行い、山野を跋渉したと伝わります。これは29歳という年齢だからできたことでもあったでしょう。しかし翌年病にて崩御されましたから、もしかしたらこの苦行が身体に響いたのかもしれません。
貞観年間はほぼ毎年大きな災害が続いています。
古来より天変地異は徳のない君主への天の戒めという考え方があります。こうした考え方があるため、譲位を迫られた天皇も江戸時代にはいらっしゃいました。しかし、日々日本の為祈りを捧げている祭祀王でもあられる天皇になんの咎もないと現代の私達は考えることができます。ただ、こうした考え方があった当時、災害の多い時代に時の天皇となられた重圧はいかばかりかと思うのです。
その一方で実際の政治を預かる方はどうか?ともいえます。
これは東日本大震災の時にも随分言われました。悪い政治が行われると良くないことが起きると。これは現代の民主主義でいえば、選挙により代表者を選んでいる私達自身にもいえることだともいえます。きちんと知り、讒言、プロバガンダに騙されずにいるのか?と。
清和天皇の時代では、有名な応天門の変が起きているのが象徴的であるかと思います。そして幼帝の摂政となった藤原良房から基経を経て藤原北家全盛時代となっていきます。そもそも清和天皇は満年齢八歳で即位され、貞観地震が起きて詔を出した時は満年齢19歳です。しかし、政治は藤原家が行いながら、君主の戒めだけ天皇にあり、ご本人もまた周りもそう考えていた時代なのです。
「FULL POWER」には、環境が人を作り、厳しい環境は人を成長させると書かれています。天災の多い土地環境で君主にならざるを得ないことから、御歴代の天皇には自らを戒め悔い改めようと努められた天皇が多く伝わるのだと思います。このように心を痛める天皇が代々いらっしゃったのが日本であり、それは今上陛下までお変わりがないのということは有難いことだと考えています。そのようなご心痛が少しでも少なくあればいいと願い、またきちんとした為政者を選ぶのが私たち務めではないかと考えるのです。そのためにはその為政者を選ぶ私たちが確かな目を持つ必要があります。換言に振り惑わされてはならない!と。
世界中が混とんとして激動の時代に入っているといわれる現在も、天皇陛下が日々日本と世界の安寧を祈られていらっしゃるだろうということは、本当にありがたく、私たちの日々の支えになることではないかと考えています。そのような国に生まれ、そう信じられる日本人として生まれたことは幸せではないでしょうか。その天皇と皇室を護るのは私たちにしかできません。しかし、ここのところ多くの人がなにか勘違いしているのではないか、とも思えるのです。
清和天皇が陸奥国と常陸国の国境が最大の被災地であるとの詔を発したことについては、正論SP2にも書かれています。
この貞観年間に生まれ育った宇多天皇により四方拝が儀式として定着していきますが、その四方拝は元旦の夜明け前の寒い時刻に四方の神々に祈るのですが、その祈りも災いを国民ではなく御身に受けようとする物凄い祈りなのです。
聖武天皇は疫病が発生したことを反省し、大仏を造りました。
御歴代の天皇の中で一番貧窮していたと伝わる後奈良天皇は、天災があるたびに御宸筆の般若心経を日本各地の社寺に奉納されています。(※明治時代以前は神仏融合の時代)
江戸の大火の後譲位された後西天皇は、清和天皇の異称の西院帝から後西院と追号されていますが、それも災害が続いて譲位されたことからなのでしょう。
皇室がなぜ長く続いてきたのか和歌によって解き明かされた「和歌で読み解く天皇と国民の歴史」。ここに登場する皇室の二つの家訓のうちの一つが「神武建国の詔」。二つの家訓がセットであるからこそ、皇室は長く続いてきた。そしてその一つが、「天皇は国民全体のための政治を行います。それが私の先祖のご命令なのです。私はここに都を造って一つの家のように仲の良い国を造りますから、みなさん協力してください。」と宣言していることは大きい。そしてそれを守ろうとしていたことが、清和天皇の行動からも読み取れるのです。そしてそうした意識が根底にあるらこそ、「国家」という言葉も生まれた。国が家であるという言葉は日本で生まれた言葉です。
一つ屋根の下仲良くという建国の言葉を歌にした「あめのした」
皇室がどうあるか?誰がふさわしくて誰がふさわしくないなどとおこがましいことをいうまえに、我々自身がどうあるか?が大切ではありませんか?
🌸🐎🐎🐎🐎🐎🐎🐎🐎🐎