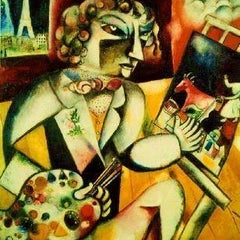モーツァルトの最高傑作と言えば、誰もがまず指を折るのがこの『レクイエム』。
若干36歳の人生を駆け抜けるように美しく生きたモーツァルト。
モーツァルトの音楽を聴くとき、筆者が強く感じるのはその音楽が常に死と隣り合わせであるということです。
具体的に彼がどのように「死」に直面したのかということは問わないことにするとして、彼の音楽からは瞬間毎に無の深淵から輝き出るような生の煌きと讃歌が聴こえてきます。
したがって、モーツァルトにとって「死」とはイメージの問題(しばしば恐ろしいものとして表象されるような)ではなく、自らの生の条件でありそこから生の輝き=音楽がほとばしり出てくる源にほかならなかったと思われます。だからこそ、モーツァルトの音楽はあんなにも美しいのでしょう。(モーツァルトの音楽は「作品」として個々に完結したものでは決してなく、むしろ個々の作品を超えて流れるモーツァルトの生があたかも(個々の作品において)鏡のように互いに映し出されているように思えてなりません。)
しかし、そのような生を生きたモーツァルトにとって、『レクイエム』はまさに文字通り自身の「死」を意味していた終焉の作品。ダンテの『地獄篇』を壮大な音楽絵図にしたようなパノラマ感があり、モーツァルトにしては音楽的な情動と共に絵画的な壮麗さも際立つ特異な傑作となっています。
もはや時間が直線的な軌道を描かず、無の深淵に渦巻き状に一切が投げ込まれていく様相はさながら地獄そのもの。おぞましい人間の呪われた欲望やそこから表裏一体となって現れる祈りの感情、聖なる光と浄化など、書き込まれているすべての音がこの天才の生の最後の輝きを湛えているのです。
その『レクイエム』が未完となってしまったことは人類にとっては確かに大きな損失であるには違いないでしょう。
現代においても尚、この作品の未完成をそのまま肯定したり、最初に補筆完成したジュスマイヤー版を尊重する向きは強いですが、ジュスマイヤーの手になるサンクトス、ベネディクトス、アニュスデイはそれぞれ生の爆発的な讃歌と優美、平安が描かれることになるはずであったことを考えると到底満足な出来栄えとは言えません。(ただし、ジュスマイヤー版はモーツァルトの当初の構想がどのようなものであったのかという点は正確に現代に伝えていると思われる。)
近年になってようやく、ジュスマイヤーの「功績」を土台としながらそれを音楽的にも満足の行くものに仕上げようという本格的な試みがなされるようになりました。それが今回ご紹介するロバート・レヴィン版です。
(ラクリモーサの末尾がアーメンフーガになっていることに注目! すごい音楽です。)
編曲者のレヴィンは音楽学者や古楽奏者としてだけでなく、有名な教育者ナディア・ブーランジェ女史を師に持つ華麗な即興演奏としても定評のある卓越した人物でこの世紀のチャレンジに最もふさわしい人物であるといえるでしょう。
彼が編曲の正当性の根拠とするのは、モーツァルトの残した多数の「スケッチ」が失敗作であるために破棄されたものではなく、注文などの種々の事情から適当な時期に完成を待つ「ノート」であったという点にあります。これが正しいとするならば、レクイエムについても残されたスケッチはすべてモーツァルトの意図を正しく反映したものとして受け取める必要があります。レヴィン版の基本的な趣旨はモーツァルトから直接指示を受けたジュスマイヤー版を十分に尊重しつつ、そこでは何らかの事情から破棄されてしまった「スケッチ」の価値を復興する点にあったと言えるでしょう。ですが、残された「スケッチ」はわずかばかりのもの。モーツァルトの様式を熟知しているレヴィンだからこそ、成し遂げることができた偉業にほかなりません。
実際、ジュスマイヤー版では破棄されてしまったラクリモーサのアーメンフーガはレヴィン版を聴くならばレクイエムの価値を再考させられるというほどの素晴らしい出来栄え。このような奈落の底に焼け落ちるようなものすごい音楽がセクエンツァの結末であったとは驚愕せざるを得ません。
レヴィン版の意義は単にそれが音楽的に高い水準であるというだけではなく、現代の私たちがどこまでモーツァルトの作曲様式を理解して演奏できるのか、という新たな問題提起を行っている点にあると言えます。
私たちは演奏するときモーツァルトの音楽を完成されたものと見做し、それをただ正確に演奏することだけを念頭に置きますが、真に彼の音楽を理解するとはそのようなことで良いのか、ということがレヴィンの問題提起なのではないでしょうか?
それは勝手に解釈することではなく、より深く楽譜を読み、研究する態度から生まれてきたものであるように筆者には思われます。
過去の音楽は失われ、モーツァルトは墓場から生き返ったりはしませんが、モーツァルトは死しても尚、あたかもガウディのサグラダファミリアがそうであるように、私たちに共に死と向き合い生が生である限り自らの生を生きるように呼びかけているのかもしれません。
モーツァルト自身の生を私たちが全く同じに体験することが不可能である以上、そしてレクイエムの後半部分が「スケッチ」にとどまった以上、完全な復元は有りえませんが、それでも私たちがこの音楽史上最も偉大な作品に数えられる傑作とどのように向き合うのかという問題にレヴィン版が一石を投じたことだけは間違いなさそうです。
実演の機会が増えることを心から願っています。
Requiem/W.A. Mozart
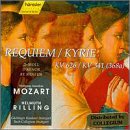
¥1,919
Amazon.co.jp
(初演者理リングによる名盤♪)
Mass in C (Great Mass)/Mozart
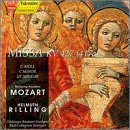
¥1,919
Amazon.co.jp
(モーツァルトのもう一つの大きな宗教曲である大ミサ曲の補筆完成版もあります♪ これも衝撃です♪)
若干36歳の人生を駆け抜けるように美しく生きたモーツァルト。
モーツァルトの音楽を聴くとき、筆者が強く感じるのはその音楽が常に死と隣り合わせであるということです。
具体的に彼がどのように「死」に直面したのかということは問わないことにするとして、彼の音楽からは瞬間毎に無の深淵から輝き出るような生の煌きと讃歌が聴こえてきます。
したがって、モーツァルトにとって「死」とはイメージの問題(しばしば恐ろしいものとして表象されるような)ではなく、自らの生の条件でありそこから生の輝き=音楽がほとばしり出てくる源にほかならなかったと思われます。だからこそ、モーツァルトの音楽はあんなにも美しいのでしょう。(モーツァルトの音楽は「作品」として個々に完結したものでは決してなく、むしろ個々の作品を超えて流れるモーツァルトの生があたかも(個々の作品において)鏡のように互いに映し出されているように思えてなりません。)
しかし、そのような生を生きたモーツァルトにとって、『レクイエム』はまさに文字通り自身の「死」を意味していた終焉の作品。ダンテの『地獄篇』を壮大な音楽絵図にしたようなパノラマ感があり、モーツァルトにしては音楽的な情動と共に絵画的な壮麗さも際立つ特異な傑作となっています。
もはや時間が直線的な軌道を描かず、無の深淵に渦巻き状に一切が投げ込まれていく様相はさながら地獄そのもの。おぞましい人間の呪われた欲望やそこから表裏一体となって現れる祈りの感情、聖なる光と浄化など、書き込まれているすべての音がこの天才の生の最後の輝きを湛えているのです。
その『レクイエム』が未完となってしまったことは人類にとっては確かに大きな損失であるには違いないでしょう。
現代においても尚、この作品の未完成をそのまま肯定したり、最初に補筆完成したジュスマイヤー版を尊重する向きは強いですが、ジュスマイヤーの手になるサンクトス、ベネディクトス、アニュスデイはそれぞれ生の爆発的な讃歌と優美、平安が描かれることになるはずであったことを考えると到底満足な出来栄えとは言えません。(ただし、ジュスマイヤー版はモーツァルトの当初の構想がどのようなものであったのかという点は正確に現代に伝えていると思われる。)
近年になってようやく、ジュスマイヤーの「功績」を土台としながらそれを音楽的にも満足の行くものに仕上げようという本格的な試みがなされるようになりました。それが今回ご紹介するロバート・レヴィン版です。
(ラクリモーサの末尾がアーメンフーガになっていることに注目! すごい音楽です。)
編曲者のレヴィンは音楽学者や古楽奏者としてだけでなく、有名な教育者ナディア・ブーランジェ女史を師に持つ華麗な即興演奏としても定評のある卓越した人物でこの世紀のチャレンジに最もふさわしい人物であるといえるでしょう。
彼が編曲の正当性の根拠とするのは、モーツァルトの残した多数の「スケッチ」が失敗作であるために破棄されたものではなく、注文などの種々の事情から適当な時期に完成を待つ「ノート」であったという点にあります。これが正しいとするならば、レクイエムについても残されたスケッチはすべてモーツァルトの意図を正しく反映したものとして受け取める必要があります。レヴィン版の基本的な趣旨はモーツァルトから直接指示を受けたジュスマイヤー版を十分に尊重しつつ、そこでは何らかの事情から破棄されてしまった「スケッチ」の価値を復興する点にあったと言えるでしょう。ですが、残された「スケッチ」はわずかばかりのもの。モーツァルトの様式を熟知しているレヴィンだからこそ、成し遂げることができた偉業にほかなりません。
実際、ジュスマイヤー版では破棄されてしまったラクリモーサのアーメンフーガはレヴィン版を聴くならばレクイエムの価値を再考させられるというほどの素晴らしい出来栄え。このような奈落の底に焼け落ちるようなものすごい音楽がセクエンツァの結末であったとは驚愕せざるを得ません。
レヴィン版の意義は単にそれが音楽的に高い水準であるというだけではなく、現代の私たちがどこまでモーツァルトの作曲様式を理解して演奏できるのか、という新たな問題提起を行っている点にあると言えます。
私たちは演奏するときモーツァルトの音楽を完成されたものと見做し、それをただ正確に演奏することだけを念頭に置きますが、真に彼の音楽を理解するとはそのようなことで良いのか、ということがレヴィンの問題提起なのではないでしょうか?
それは勝手に解釈することではなく、より深く楽譜を読み、研究する態度から生まれてきたものであるように筆者には思われます。
過去の音楽は失われ、モーツァルトは墓場から生き返ったりはしませんが、モーツァルトは死しても尚、あたかもガウディのサグラダファミリアがそうであるように、私たちに共に死と向き合い生が生である限り自らの生を生きるように呼びかけているのかもしれません。
モーツァルト自身の生を私たちが全く同じに体験することが不可能である以上、そしてレクイエムの後半部分が「スケッチ」にとどまった以上、完全な復元は有りえませんが、それでも私たちがこの音楽史上最も偉大な作品に数えられる傑作とどのように向き合うのかという問題にレヴィン版が一石を投じたことだけは間違いなさそうです。
実演の機会が増えることを心から願っています。
Requiem/W.A. Mozart
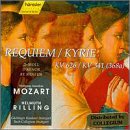
¥1,919
Amazon.co.jp
(初演者理リングによる名盤♪)
Mass in C (Great Mass)/Mozart
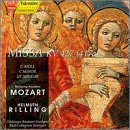
¥1,919
Amazon.co.jp
(モーツァルトのもう一つの大きな宗教曲である大ミサ曲の補筆完成版もあります♪ これも衝撃です♪)