日本一美味しいを目指す黒豆・レシピ・作り方/☆4
日本一美味しいを目指す黒豆・レシピ・作り方/☆4
黒豆を美味しく炊く!
日本一って事は、世界一って事です!!!
黒豆・レシピ・作り方。
御節料理に欠かせないであろう黒豆。

黒豆・レシピ・作り方/完成はこんな感じ。
自分の黒豆の炊き方は、濃い蜜、
砂糖で、豆をある程度脱水させて、
黒豆の風味と味を最大限に引き出すを目指すレシピです。
重曹を使わないので、重曹臭くないだろうし、
黒豆の黒い色のアントシアニンの淡くビターな後味も残します。
錆鉄は使いますが、鉄臭くないです。
醤油は入れません。塩も。
黒豆、砂糖、水だけので、豆を大切に調理します!
■材料
丹波黒豆(八木長本店)300g/2つ
上白糖(スプーン印)/1254g
白ザラ糖(スプーン印)/746g
南アルプスの天然水2L(サントリー)/6本くらい
錆鉄/南部鉄器822g
アルミホイル
リードキッチンペーパー
デジタルクッキングスケール
温度計・・・など。
※普通に作るなら、300gの黒豆で十分なので、分量は半分になります。
□砂糖について。
砂糖を2種類使うのは、上白糖だけだと甘さがくどくなり、
白ザラ糖だけだと、あっさりし過ぎて素材の風味を引き出さない物足りなさもあります。
□黒豆について。
黒豆の値は、ピンキリです。
自分が使ったのは、1袋300g入りで、1,905円(税抜き)
去年に引き続き、日本橋 八木長本店の丹波黒豆を使用しました。
黒豆は品種も有り、高いのは、100g800円以上、安いのは100g150円くらい。
デパートなどで取り扱う丹波産の黒豆は、100g600円位です。
黒豆の品種の中でも、高級なのは、丹波黒大豆です。
基本、大きければ大きいほど高値になります。
北海道産の品種は、大きくなく、真っ黒で、光沢が有りマンマル。
丹波種は、白い粉が吹いていて、光沢は無く、大きいです。
岩手、秋田、山形などの東北地方の
雁喰い豆(黒平豆)は、真っ黒で平たく潰れています。
黒豆の原種と言われているのが、
東北地方で栽培されている雁喰い豆(黒平豆)です。
そこから、人が手を加えて品種改良されて、丸い黒豆が出来たのでした。
なので、極論、雁喰い豆(黒平豆)以外、変異種(ミュータント)です。
今年は、雁喰い豆と丹波黒大豆を食べ比べようと思ったのですが、
平成26年度産は、乾物屋さんの話で、
今年のは皮が薄いので豆を戻すと破けてしまう。
と、言われたのでパスしました。
作物なので、気候にも左右され、
皮の厚みは年々違うし、中々難しいですよね。
って、事で、自分、ここまでマニアックになったよ!!!
わーわーわー!!!
な、解説から入っちゃいます!!!
■本題へ!
 1袋300g入りで、1,905円(税抜き)
1袋300g入りで、1,905円(税抜き)
2袋税込みの合計は、4,115円でした。
http://www.yagicho-honten.jp/shopping/502.html
ネットでは完売って表記だったのですが、店舗では売っていましたよ。
その他にも、北海道産の黒豆は、300g/900円台で売っていました。
岩手県産の雁喰い豆は、1200円台でした。
□錆鉄の準備。

縁の下にずっと眠っていた南部鉄の灰皿のふた。
洗って、焼いて、ヤスリで磨いて、外に出し霧吹きで毎日水をあげ・・・
1ヶ月くらいかけて錆付けした南部鉄。流水で柔らかく錆を洗い流します。

きれいに洗った手拭に包んで、準備します。
鉄が入ると、鉄イオンで黒豆の黒い色が皮に定着します。
鉄を入れないと、色が抜けて、最悪、茶色い斑になるので要注意です。
□黒豆の準備へ!
□22日黒豆を戻す準備をします。

黒豆は、ボールに水を入れ、良く洗い、
水から出ている時間を極力無くします。
 黒真珠なリッチな輝き☆
黒真珠なリッチな輝き☆
この段階で、皮が割けてる豆も有ります。
そういうものなので、しょうがないです。

南部鉄を手拭で包んで入れた鍋の中に。
南アルプスの天然水 3Lを入れて、蓋をして、24時間かけて豆を戻します。
この間、鉄イオンで黒豆の黒い色、アントシアニンを皮に定着させます。
サイエンスですわ。
◆メモ・後で調べたら。
熱湯から戻した方が皮が割れる率が少ないとの事。
次ぎに生かしたいと思います!!!
□23日
豆を戻して、24時間が過ぎた22時18分。
黒豆を戻すと、水は紫色になります!!!
□黒豆の炊き方
□22時25分。
前の行程、南アルプスの天然水 3Lを入れて、
蓋をして、24時間かけて豆を戻したら、落としぶたをして、
戻した黒豆の鍋を強火にかけ、灰汁を取り、沸騰したら弱火へ。
80℃付近でまずは1時間炊きました。

初めの強火。沸騰して来ると、灰汁が出て来ます。

火を弱火へ。こんな感じ。

灰汁が取れたら、鍋に温度計を噛ませ、弱火で80℃付近。
鍋は噛ませないとボコボコに沸騰してしまうので注意です。
終止、蓋を温度計で噛ませ、弱火で炊いていきます。
□23時25分。
水が減り豆が浮いたので、熱湯1リットルを追加。
最低な火加減で85℃
□0時30分、豆の味見。
ぐしゃっと柔らかくならないが、旨い!
目指すのはこの固さではないのです。
□1時30分。硬さ、極力変わらず。
□2時00分。500ccの熱湯追加。
□2時30分。硬さ、極力変わらず。アルデンテにうまい。
湯は、~90℃
湯が多いと温度が上がります。
□3時30分。少しほっくり感が出る。
ここまでで、黒豆を煮て5時間。
□4時30分。柔らかさを感じる。
熱湯500cc追加。
湯は、88℃くらい。
□5時30分。指で潰れる感じ。
指で簡単に潰れるまで火を通します。
□6時30分。後、一息って感じ。
湯は、85℃くらい
□7時30分。指でムニッと潰れる柔らかさに。

水分を含んでいるけど、粘りの有るような豆の甘み、風味が出ました。
※温度は、80℃以上、90℃以下を目安にしました。
ムニッと潰れたのは、24日クリスマスイブの7時39分。
炊いてから9時間後・・・
黒豆を茹で続け、9時間!
ずっと起きていました!!!
マジしねるw
□蓋をして、そのまま冷まし、24時間後。
□25日クリスマス。
9時17分調理再開。

豆を戻した時は、紫色でしたが、火を入れたら、黒くなっています。

落としぶたをしまま、黒い水を透明になるまで、
水をこぼしてすすぎます。

落としぶたのまま、ちょろちょろの流水で3時間さらし、灰汁を抜きます。
水量はこんな感じ。

豆の状態はこんな感じです。
皮があまりにも破けてる豆は取り出します。
この段階で、少し色が抜けるのですが、砂糖を加えて炊くと黒く戻ります。
□透明になるまで水を入れ替え、
落としぶたをしたまま、強火で沸騰してから、極弱火で1時間茹でます。
14時20分。

皮が破けた黒豆は浮いて来るので、取ります。
灰汁も取ります。

湯の色は、紫、黒、茶色と変化して行きました。
□常温になったら、透明になるまですすいで、流水で3時間さらします。
22時30分。
※常温に戻すのは、急激な温度差で黒豆の皮と実の収縮差を出さない為です。
熱々に冷水ぶっかけたら、全ての豆は脱皮をすると思う。

水の色は黒いです。
水量は、これよりもうんと細く。
この間、シロップを作ります。
□シロップを作ります。
流水に3時間さらしている間に、シロップを作ります。

乾物の黒豆600gで、最初のシロップの量は、
南アルプスの天然水・1200cc、
砂糖500g(上白糖・285g、白ザラ糖・215gで、57%と43%)にしました。
強火にかけ、かき混ぜながら、溶けたら火を止め常温にします。
□流水でさらした黒豆の水を、透明になるまで入れ替え、ザルにあけます。
あまりにも割れている豆は取り出します。
23時10分。
 去年は、錆鉄が少なく、茶色くまだらになったのですが、
去年は、錆鉄が少なく、茶色くまだらになったのですが、
今年はピカピカ、黒々と炊けました。
超大粒!!!
 あまりにも皮が割れてしまった黒豆を取り出します。
あまりにも皮が割れてしまった黒豆を取り出します。

初めの頃の錆鉄。
 調理後の錆鉄。
調理後の錆鉄。
錆が抜け、黒豆のアントシアニンが吸着して、
紫の入る黒い色へ変化しました。
毎年この鉄を使い、家の味にしたいです。
■流水で黒豆をさらすのは?
黒豆の灰汁、エグ味を抜く作業です。
煮直すのもその作業です。
重曹を入れれば、この作業は無くなると思うのですが、
どうしようか・・・次は重曹入れても良いかもな?
手間がヤバイ。
総じて日本料理は、大量の水を使うものだと思う。
だからそこ、綺麗な味に成るんだなって改めて思いましたよ。
■そして、メモ!痛恨のショック!!!
鍋底に焦げが・・・ステンレス鍋使ったからかも・・・
でも味にほぼ影響は無いので無視する・・・
次の課題です(涙)
笑ってよろいくてよw
ステンレス鍋はどうしても焦げやすいな。
それと、豆の量に対する水の量と、
鍋の大きさ、もっともっと鍋は大きくて良いです。
※ステンレス鍋の容量は、5Lです。
◆ここから、錆鉄を抜きで調理します。
ザルにあけた黒豆を、常温になったシロップの中に入れて、
一晩置き、甘を浸透させます。

シロップの中に入れた黒豆。
この段階でも、赤黒い感じ。砂糖で炊く事で黒が深まります。
 豆が浮いてしまうので、落としぶたをします。
豆が浮いてしまうので、落としぶたをします。
ステンレス鍋の反省を含め、アルミの雪平鍋で調理しました。
更に、蓋をかぶせます。
※3.5Lの雪平鍋です。
が、加糖すると容量不足。
なので、6Lのアルマイト鍋へ変更!!!
黒豆は、皮が破けてしまうものが出るのは、しょうがない。
し、そういうモノだと。
熱湯から豆を戻していれば、また違うと思うと、
このレシピはまだ完成度が低いです。
□26日は、加糖してから、火入れしたのは、合計3回。

初めのシロップで一晩経った黒豆。
色は抜けていません。砂糖の力で黒い色は水に溶けないのだと思いました。

13時30分、常温の鍋に、上白糖・171g、白ザラ糖・129gを入れ中火に。
沸騰する前まで、わりとこまめに鍋を大きく揺すり、上下の温度差を均一にします。
これをやらないと、上下で20℃くらいの温度差になり、
均一に炊けなくなってしまいます。
温度が上がって来て、黒豆に灰汁が出て来たので、
リードクッキングペーパーを落としぶたにして、細かな灰汁を取ります。

リードのペーパーの落としぶたをして、優しく鍋を大きく揺すりながら、
中火で90℃になったら、火を止め常温になるのを待ちます。
思うに、90℃まで到達させるのがベータかな。
※優しく鍋を大きく揺するのは、温度を一定にする為。
加糖すると、底と上面で温度差が大きくなるのを防ぐのと、焦がさない為です。
また、上面は、火から遠く、豆が浮いて外気、空気に触れるので、しわにさせない為です。

蜜は、透明で、黒い色は抜けません。
また、砂糖を加えると、黒豆は、より黒くなります。
□17時55分~18時12分
完全な常温から。
上白糖・171g、白ザラ糖・129gを入れ、
リードのペーパーの落としぶたをして、優しくかき混ぜながら、
中火で90℃になったら、火を止め常温になるのを待ちます。
□21時22分火入れ。~21時35分。
完全な常温から。
上白糖・171g、白ザラ糖・129gを入れ、
リードのペーパーの落としぶたをして、優しく揺らし、かき混ぜながら、
中火で90℃になったら、火を止め常温になるのを待ちます。

常温になって、リードクッキングペーパーを取り、絞り、
蜜を鍋に絞り、戻します。
綺麗な蜜になりました。
灰汁が取れたので、
落としぶたを、穴を所々あけたアルミホイルに変えます。
□この日1日の作業。
煮て冷まし、煮て冷ましを繰り返して、
薄蜜から、濃い密にして、甘さを十分に浸透させます。
□27日深夜2時30分~3時00分
常温になったので加糖します。時間が無かったので早めの調理。

黒豆に浸されたシロップ500ccを別鍋に移します。

上白糖・342g、白ザラ糖・258gを可能な限り火を入れ溶かして、(溶けにくい)
常温で黒豆が浸された鍋の中に、熱いまま少しずつ混ぜながら加えます。
その後、中火で黒豆の鍋を火入れします。
落としぶたは、穴を開けたアルミホイルを使用。
大きく優しく鍋を揺らし、90℃になったら、火を止め冷まします。
※白ザラ糖が濃い蜜で溶けないのを防止します。
蜜を合わせた黒豆はこんな感じに。
外気に触れないように、アルミの落としぶたをして下さいね。
その後、鍋ぶたもします。
□12時00~24分
 豆の状態はこんな感じ。
豆の状態はこんな感じ。

加糖無しで、火入れします。
常温の鍋から、中火で火入れ。
90℃になったら、火を止め冷まし、豆の状態を見ます。
□23時40~
 少しシワになった豆が有ったので、ここから調整な方向へ。
少しシワになった豆が有ったので、ここから調整な方向へ。

全体的には豆に張りがある感じです。
しわは、時間が経てば、もしくは、水を足せば、
もしくは、加熱すれば、戻ります。

加糖でシロップが増えて来たので、
シロップ600ccを、取り出しました。色はこんな感じ。

弱火で390ccになるまで煮詰めました。
鍋を中火で、途中何回も大きく揺らしながら90℃になったら、
黒豆の鍋へ、熱いシロップを徐々に足し、合わせます。
何故煮詰めたかと言うと、砂糖加えて密の量を増やしたく無かったのです。
これが、ちょっとネックだったかも。
□28日
16時~

崩れてしまった豆を取り出しました。

黒豆と、蜜の濃度、状態はこんな感じ。
蜜にとろみが付いて来ました。
そして、更に加糖します!

黒豆の鍋のシロップ300ccで、上白糖114g、白ザラ糖86gを溶かします。
アルミ蓋を取った黒豆の鍋をゴムベラでゆっくり混ぜながら、90℃に温め
砂糖を溶かしたシロップと合わせます。

合わせたのがこれ。蜜、トロントロンですよ。
ここから、3.5Lの雪平鍋で調理しました。

アルミホイルを被せ、蓋をして休ませます。
□29日
□10時
豆が少し堅く、口の中に少し残るのでどうしようかと!!!
時間を経たせ、様子見ます。
□17時10~
豆が締まって堅さが有るので、200ccの水を加え
ゆっくりかき混ぜながら、90℃になったら、火を止め蓋をして常温へ。
火を入れるとシロップはサラサラになり、
常温になると粘度が出ます。
□翌日、完成!!!

最終系はこんな状態。
7日間かかりました!!!
まー。去年作って、これは、予想通りな期間。
盛りつけはこんな感じ。

去年作った黒豆。上白糖50%、白ザラ糖50%でした。
途中、まだらに色素が抜けて赤茶気味な黒だったのです。

今年の黒豆。
黒々と大粒に炊けています。
■感想!!!
去年は、上白糖50%、白ザラ糖50%で、
品が良く、少し豆の抵抗感が無いなって思ったので調整しました。
今年は、上白糖57%、白ザラ糖43%で炊いたのですが、
去年の50%、50%の方が、味が良かったです。
でも、その時の物足りなさを補うのであれば、
上白糖53%、白ザラ糖47%くらいが次の課題かも。
何回か作らないと微調整難しいな。
計りながらやってるし、レシピアップの為、感覚で合わせてないのが、
味の欠落かもな。
数値決めて調理ではなく、調理した結果の数値が理想だけど、
そこまで計って出来ません~。
って事で、後一歩。
点数で言えば、70点。
納得いかねーーー!!!
超絶上手く出来ると、黒豆美味し過ぎて感動しますよ。
それと、贅沢を覚えます。
だからこそ、特別な料理なので、
時間も、素材の値も惜しみたくは無いのです。
料理、まだまだだなー。
精進します!!!
☆気になる最終的な加糖の割合!
豆600g
水1200cc+200cc
砂糖2200g(上白糖1254g、白ザラ糖746g)でした。
上白糖・285g、白ザラ糖・215g
上白糖・171g、白ザラ糖・129g
上白糖・171g、白ザラ糖・129g
上白糖・171g、白ザラ糖・129g
上白糖・342g、白ザラ糖・258g
上白糖・114g、白ザラ糖・86g
砂糖を加える分量の見直しと、
最初に白ザラ糖だけで味付けして、
溶けやすい上白糖を加えても違うだろうし、
シロップを煮詰めないで、途中、加水しないで、
純粋に加糖して行けばまた違うだろうし。
まだまだですわ!!!
■去年も参考にしたのが、辻調おいしいネット / レシピ です。
って事で、こんなレシピになってしまったのですが、
参考程度に見て下さい。
いつか完全なレシピにします!!!
世界一美味しい
黒豆を作る!!!
その日まで!!!
つづく!!!
コメント お気軽に☆
記事最下にコメント欄があります!
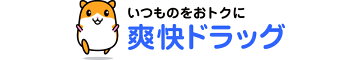

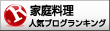


1日1回のクリックで投票されます!
料理系ブログが勢揃いのランキングです。

□レシピ・作り方・グルメ
□牛丼・レシピ・作り方 吉野家の再現率90%/☆5
□電子レンジで50秒!簡単温泉玉子・作り方/☆4
□焼き鳥とタレ・レシピ・作り方/☆4
□イタリアンピッツァ・ピザ・レシピ・作り方/☆4
□簡易デミグラスソース・レシピ・作り方/☆4
□輪切りのオランジェット、レモンコンフィ・レシピ・作り方/☆4
□シーザーサラダ・レシピ・作り方/☆4.5
□ローストチキン・レシピ・作り方/☆4
□鶏の唐揚げ・レシピ・作り方/☆4
□皮から作る焼き餃子・レシピ・作り方/☆3.5
□チーズソースのニョッキ・レシピ・作り方/☆4
□浅草グルメメモ!
□美味しい調味料、食材などなど。保存版!
→料理ブログ 料理の豆知識

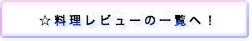






黒豆を美味しく炊く!
日本一って事は、世界一って事です!!!
黒豆・レシピ・作り方。
御節料理に欠かせないであろう黒豆。

黒豆・レシピ・作り方/完成はこんな感じ。
自分の黒豆の炊き方は、濃い蜜、
砂糖で、豆をある程度脱水させて、
黒豆の風味と味を最大限に引き出すを目指すレシピです。
重曹を使わないので、重曹臭くないだろうし、
黒豆の黒い色のアントシアニンの淡くビターな後味も残します。
錆鉄は使いますが、鉄臭くないです。
醤油は入れません。塩も。
黒豆、砂糖、水だけので、豆を大切に調理します!
■材料
丹波黒豆(八木長本店)300g/2つ
上白糖(スプーン印)/1254g
白ザラ糖(スプーン印)/746g
南アルプスの天然水2L(サントリー)/6本くらい
錆鉄/南部鉄器822g
アルミホイル
リードキッチンペーパー
デジタルクッキングスケール
温度計・・・など。
※普通に作るなら、300gの黒豆で十分なので、分量は半分になります。
□砂糖について。
砂糖を2種類使うのは、上白糖だけだと甘さがくどくなり、
白ザラ糖だけだと、あっさりし過ぎて素材の風味を引き出さない物足りなさもあります。
□黒豆について。
黒豆の値は、ピンキリです。
自分が使ったのは、1袋300g入りで、1,905円(税抜き)
去年に引き続き、日本橋 八木長本店の丹波黒豆を使用しました。
黒豆は品種も有り、高いのは、100g800円以上、安いのは100g150円くらい。
デパートなどで取り扱う丹波産の黒豆は、100g600円位です。
黒豆の品種の中でも、高級なのは、丹波黒大豆です。
基本、大きければ大きいほど高値になります。
北海道産の品種は、大きくなく、真っ黒で、光沢が有りマンマル。
丹波種は、白い粉が吹いていて、光沢は無く、大きいです。
岩手、秋田、山形などの東北地方の
雁喰い豆(黒平豆)は、真っ黒で平たく潰れています。
黒豆の原種と言われているのが、
東北地方で栽培されている雁喰い豆(黒平豆)です。
そこから、人が手を加えて品種改良されて、丸い黒豆が出来たのでした。
なので、極論、雁喰い豆(黒平豆)以外、変異種(ミュータント)です。
今年は、雁喰い豆と丹波黒大豆を食べ比べようと思ったのですが、
平成26年度産は、乾物屋さんの話で、
今年のは皮が薄いので豆を戻すと破けてしまう。
と、言われたのでパスしました。
作物なので、気候にも左右され、
皮の厚みは年々違うし、中々難しいですよね。
って、事で、自分、ここまでマニアックになったよ!!!
わーわーわー!!!
な、解説から入っちゃいます!!!
■本題へ!
 1袋300g入りで、1,905円(税抜き)
1袋300g入りで、1,905円(税抜き)2袋税込みの合計は、4,115円でした。
http://www.yagicho-honten.jp/shopping/502.html
ネットでは完売って表記だったのですが、店舗では売っていましたよ。
その他にも、北海道産の黒豆は、300g/900円台で売っていました。
岩手県産の雁喰い豆は、1200円台でした。
□錆鉄の準備。

縁の下にずっと眠っていた南部鉄の灰皿のふた。
洗って、焼いて、ヤスリで磨いて、外に出し霧吹きで毎日水をあげ・・・
1ヶ月くらいかけて錆付けした南部鉄。流水で柔らかく錆を洗い流します。

きれいに洗った手拭に包んで、準備します。
鉄が入ると、鉄イオンで黒豆の黒い色が皮に定着します。
鉄を入れないと、色が抜けて、最悪、茶色い斑になるので要注意です。
□黒豆の準備へ!
□22日黒豆を戻す準備をします。

黒豆は、ボールに水を入れ、良く洗い、
水から出ている時間を極力無くします。

この段階で、皮が割けてる豆も有ります。
そういうものなので、しょうがないです。

南部鉄を手拭で包んで入れた鍋の中に。
南アルプスの天然水 3Lを入れて、蓋をして、24時間かけて豆を戻します。
この間、鉄イオンで黒豆の黒い色、アントシアニンを皮に定着させます。
サイエンスですわ。
◆メモ・後で調べたら。
熱湯から戻した方が皮が割れる率が少ないとの事。
次ぎに生かしたいと思います!!!
□23日
豆を戻して、24時間が過ぎた22時18分。
黒豆を戻すと、水は紫色になります!!!
□黒豆の炊き方
□22時25分。
前の行程、南アルプスの天然水 3Lを入れて、
蓋をして、24時間かけて豆を戻したら、落としぶたをして、
戻した黒豆の鍋を強火にかけ、灰汁を取り、沸騰したら弱火へ。
80℃付近でまずは1時間炊きました。

初めの強火。沸騰して来ると、灰汁が出て来ます。

火を弱火へ。こんな感じ。

灰汁が取れたら、鍋に温度計を噛ませ、弱火で80℃付近。
鍋は噛ませないとボコボコに沸騰してしまうので注意です。
終止、蓋を温度計で噛ませ、弱火で炊いていきます。
□23時25分。
水が減り豆が浮いたので、熱湯1リットルを追加。
最低な火加減で85℃
□0時30分、豆の味見。
ぐしゃっと柔らかくならないが、旨い!
目指すのはこの固さではないのです。
□1時30分。硬さ、極力変わらず。
□2時00分。500ccの熱湯追加。
□2時30分。硬さ、極力変わらず。アルデンテにうまい。
湯は、~90℃
湯が多いと温度が上がります。
□3時30分。少しほっくり感が出る。
ここまでで、黒豆を煮て5時間。
□4時30分。柔らかさを感じる。
熱湯500cc追加。
湯は、88℃くらい。
□5時30分。指で潰れる感じ。
指で簡単に潰れるまで火を通します。
□6時30分。後、一息って感じ。
湯は、85℃くらい
□7時30分。指でムニッと潰れる柔らかさに。

水分を含んでいるけど、粘りの有るような豆の甘み、風味が出ました。
※温度は、80℃以上、90℃以下を目安にしました。
ムニッと潰れたのは、24日クリスマスイブの7時39分。
炊いてから9時間後・・・
黒豆を茹で続け、9時間!
ずっと起きていました!!!
マジしねるw
□蓋をして、そのまま冷まし、24時間後。
□25日クリスマス。
9時17分調理再開。

豆を戻した時は、紫色でしたが、火を入れたら、黒くなっています。

落としぶたをしまま、黒い水を透明になるまで、
水をこぼしてすすぎます。

落としぶたのまま、ちょろちょろの流水で3時間さらし、灰汁を抜きます。
水量はこんな感じ。

豆の状態はこんな感じです。
皮があまりにも破けてる豆は取り出します。
この段階で、少し色が抜けるのですが、砂糖を加えて炊くと黒く戻ります。
□透明になるまで水を入れ替え、
落としぶたをしたまま、強火で沸騰してから、極弱火で1時間茹でます。
14時20分。

皮が破けた黒豆は浮いて来るので、取ります。
灰汁も取ります。

湯の色は、紫、黒、茶色と変化して行きました。
□常温になったら、透明になるまですすいで、流水で3時間さらします。
22時30分。
※常温に戻すのは、急激な温度差で黒豆の皮と実の収縮差を出さない為です。
熱々に冷水ぶっかけたら、全ての豆は脱皮をすると思う。

水の色は黒いです。
水量は、これよりもうんと細く。
この間、シロップを作ります。
□シロップを作ります。
流水に3時間さらしている間に、シロップを作ります。

乾物の黒豆600gで、最初のシロップの量は、
南アルプスの天然水・1200cc、
砂糖500g(上白糖・285g、白ザラ糖・215gで、57%と43%)にしました。
強火にかけ、かき混ぜながら、溶けたら火を止め常温にします。
□流水でさらした黒豆の水を、透明になるまで入れ替え、ザルにあけます。
あまりにも割れている豆は取り出します。
23時10分。
 去年は、錆鉄が少なく、茶色くまだらになったのですが、
去年は、錆鉄が少なく、茶色くまだらになったのですが、今年はピカピカ、黒々と炊けました。
超大粒!!!
 あまりにも皮が割れてしまった黒豆を取り出します。
あまりにも皮が割れてしまった黒豆を取り出します。
初めの頃の錆鉄。
 調理後の錆鉄。
調理後の錆鉄。錆が抜け、黒豆のアントシアニンが吸着して、
紫の入る黒い色へ変化しました。
毎年この鉄を使い、家の味にしたいです。
■流水で黒豆をさらすのは?
黒豆の灰汁、エグ味を抜く作業です。
煮直すのもその作業です。
重曹を入れれば、この作業は無くなると思うのですが、
どうしようか・・・次は重曹入れても良いかもな?
手間がヤバイ。
総じて日本料理は、大量の水を使うものだと思う。
だからそこ、綺麗な味に成るんだなって改めて思いましたよ。
■そして、メモ!痛恨のショック!!!
鍋底に焦げが・・・ステンレス鍋使ったからかも・・・
でも味にほぼ影響は無いので無視する・・・
次の課題です(涙)
笑ってよろいくてよw
ステンレス鍋はどうしても焦げやすいな。
それと、豆の量に対する水の量と、
鍋の大きさ、もっともっと鍋は大きくて良いです。
※ステンレス鍋の容量は、5Lです。
◆ここから、錆鉄を抜きで調理します。
ザルにあけた黒豆を、常温になったシロップの中に入れて、
一晩置き、甘を浸透させます。

シロップの中に入れた黒豆。
この段階でも、赤黒い感じ。砂糖で炊く事で黒が深まります。
 豆が浮いてしまうので、落としぶたをします。
豆が浮いてしまうので、落としぶたをします。ステンレス鍋の反省を含め、アルミの雪平鍋で調理しました。
更に、蓋をかぶせます。
※3.5Lの雪平鍋です。
が、加糖すると容量不足。
なので、6Lのアルマイト鍋へ変更!!!
黒豆は、皮が破けてしまうものが出るのは、しょうがない。
し、そういうモノだと。
熱湯から豆を戻していれば、また違うと思うと、
このレシピはまだ完成度が低いです。
□26日は、加糖してから、火入れしたのは、合計3回。

初めのシロップで一晩経った黒豆。
色は抜けていません。砂糖の力で黒い色は水に溶けないのだと思いました。

13時30分、常温の鍋に、上白糖・171g、白ザラ糖・129gを入れ中火に。
沸騰する前まで、わりとこまめに鍋を大きく揺すり、上下の温度差を均一にします。
これをやらないと、上下で20℃くらいの温度差になり、
均一に炊けなくなってしまいます。
温度が上がって来て、黒豆に灰汁が出て来たので、
リードクッキングペーパーを落としぶたにして、細かな灰汁を取ります。

リードのペーパーの落としぶたをして、優しく鍋を大きく揺すりながら、
中火で90℃になったら、火を止め常温になるのを待ちます。
思うに、90℃まで到達させるのがベータかな。
※優しく鍋を大きく揺するのは、温度を一定にする為。
加糖すると、底と上面で温度差が大きくなるのを防ぐのと、焦がさない為です。
また、上面は、火から遠く、豆が浮いて外気、空気に触れるので、しわにさせない為です。

蜜は、透明で、黒い色は抜けません。
また、砂糖を加えると、黒豆は、より黒くなります。
□17時55分~18時12分
完全な常温から。
上白糖・171g、白ザラ糖・129gを入れ、
リードのペーパーの落としぶたをして、優しくかき混ぜながら、
中火で90℃になったら、火を止め常温になるのを待ちます。
□21時22分火入れ。~21時35分。
完全な常温から。
上白糖・171g、白ザラ糖・129gを入れ、
リードのペーパーの落としぶたをして、優しく揺らし、かき混ぜながら、
中火で90℃になったら、火を止め常温になるのを待ちます。

常温になって、リードクッキングペーパーを取り、絞り、
蜜を鍋に絞り、戻します。
綺麗な蜜になりました。
灰汁が取れたので、
落としぶたを、穴を所々あけたアルミホイルに変えます。
□この日1日の作業。
煮て冷まし、煮て冷ましを繰り返して、
薄蜜から、濃い密にして、甘さを十分に浸透させます。
□27日深夜2時30分~3時00分
常温になったので加糖します。時間が無かったので早めの調理。

黒豆に浸されたシロップ500ccを別鍋に移します。

上白糖・342g、白ザラ糖・258gを可能な限り火を入れ溶かして、(溶けにくい)
常温で黒豆が浸された鍋の中に、熱いまま少しずつ混ぜながら加えます。
その後、中火で黒豆の鍋を火入れします。
落としぶたは、穴を開けたアルミホイルを使用。
大きく優しく鍋を揺らし、90℃になったら、火を止め冷まします。
※白ザラ糖が濃い蜜で溶けないのを防止します。
蜜を合わせた黒豆はこんな感じに。
外気に触れないように、アルミの落としぶたをして下さいね。
その後、鍋ぶたもします。
□12時00~24分
 豆の状態はこんな感じ。
豆の状態はこんな感じ。
加糖無しで、火入れします。
常温の鍋から、中火で火入れ。
90℃になったら、火を止め冷まし、豆の状態を見ます。
□23時40~
 少しシワになった豆が有ったので、ここから調整な方向へ。
少しシワになった豆が有ったので、ここから調整な方向へ。
全体的には豆に張りがある感じです。
しわは、時間が経てば、もしくは、水を足せば、
もしくは、加熱すれば、戻ります。

加糖でシロップが増えて来たので、
シロップ600ccを、取り出しました。色はこんな感じ。

弱火で390ccになるまで煮詰めました。
鍋を中火で、途中何回も大きく揺らしながら90℃になったら、
黒豆の鍋へ、熱いシロップを徐々に足し、合わせます。
何故煮詰めたかと言うと、砂糖加えて密の量を増やしたく無かったのです。
これが、ちょっとネックだったかも。
□28日
16時~

崩れてしまった豆を取り出しました。

黒豆と、蜜の濃度、状態はこんな感じ。
蜜にとろみが付いて来ました。
そして、更に加糖します!

黒豆の鍋のシロップ300ccで、上白糖114g、白ザラ糖86gを溶かします。
アルミ蓋を取った黒豆の鍋をゴムベラでゆっくり混ぜながら、90℃に温め
砂糖を溶かしたシロップと合わせます。

合わせたのがこれ。蜜、トロントロンですよ。
ここから、3.5Lの雪平鍋で調理しました。

アルミホイルを被せ、蓋をして休ませます。
□29日
□10時
豆が少し堅く、口の中に少し残るのでどうしようかと!!!
時間を経たせ、様子見ます。
□17時10~
豆が締まって堅さが有るので、200ccの水を加え
ゆっくりかき混ぜながら、90℃になったら、火を止め蓋をして常温へ。
火を入れるとシロップはサラサラになり、
常温になると粘度が出ます。
□翌日、完成!!!

最終系はこんな状態。
7日間かかりました!!!
まー。去年作って、これは、予想通りな期間。
盛りつけはこんな感じ。

去年より大きく炊けたかも。ブレました・・・残念><

アップで。

理想、完璧な仕上がりではない!
豆を噛んだ時に、皮と実に隙間が出来て、蜜が入ってる豆もあるので、
そこをピタッと噛み合わせて、
皮と豆を一体化出来れば、より良い仕上がりでした。
もう少し水分を足して、豆を膨張させて・・・
後一歩、手間が欲しかったのですが、
御節色々と作った関係で、フィニッシュへ。

小皿に盛るとこんな感じ。
アップで。

理想、完璧な仕上がりではない!
豆を噛んだ時に、皮と実に隙間が出来て、蜜が入ってる豆もあるので、
そこをピタッと噛み合わせて、
皮と豆を一体化出来れば、より良い仕上がりでした。
もう少し水分を足して、豆を膨張させて・・・
後一歩、手間が欲しかったのですが、
御節色々と作った関係で、フィニッシュへ。

去年作った黒豆。上白糖50%、白ザラ糖50%でした。
途中、まだらに色素が抜けて赤茶気味な黒だったのです。

今年の黒豆。
黒々と大粒に炊けています。
■感想!!!
去年は、上白糖50%、白ザラ糖50%で、
品が良く、少し豆の抵抗感が無いなって思ったので調整しました。
今年は、上白糖57%、白ザラ糖43%で炊いたのですが、
去年の50%、50%の方が、味が良かったです。
でも、その時の物足りなさを補うのであれば、
上白糖53%、白ザラ糖47%くらいが次の課題かも。
何回か作らないと微調整難しいな。
計りながらやってるし、レシピアップの為、感覚で合わせてないのが、
味の欠落かもな。
数値決めて調理ではなく、調理した結果の数値が理想だけど、
そこまで計って出来ません~。
って事で、後一歩。
点数で言えば、70点。
納得いかねーーー!!!
超絶上手く出来ると、黒豆美味し過ぎて感動しますよ。
それと、贅沢を覚えます。
だからこそ、特別な料理なので、
時間も、素材の値も惜しみたくは無いのです。
料理、まだまだだなー。
精進します!!!
☆気になる最終的な加糖の割合!
豆600g
水1200cc+200cc
砂糖2200g(上白糖1254g、白ザラ糖746g)でした。
上白糖・285g、白ザラ糖・215g
上白糖・171g、白ザラ糖・129g
上白糖・171g、白ザラ糖・129g
上白糖・171g、白ザラ糖・129g
上白糖・342g、白ザラ糖・258g
上白糖・114g、白ザラ糖・86g
砂糖を加える分量の見直しと、
最初に白ザラ糖だけで味付けして、
溶けやすい上白糖を加えても違うだろうし、
シロップを煮詰めないで、途中、加水しないで、
純粋に加糖して行けばまた違うだろうし。
まだまだですわ!!!
■去年も参考にしたのが、辻調おいしいネット / レシピ です。
って事で、こんなレシピになってしまったのですが、
参考程度に見て下さい。
いつか完全なレシピにします!!!
世界一美味しい
黒豆を作る!!!
その日まで!!!
つづく!!!
記事最下にコメント欄があります!

1日1回のクリックで投票されます!
料理系ブログが勢揃いのランキングです。
□レシピ・作り方・グルメ
□牛丼・レシピ・作り方 吉野家の再現率90%/☆5
□電子レンジで50秒!簡単温泉玉子・作り方/☆4
□焼き鳥とタレ・レシピ・作り方/☆4
□イタリアンピッツァ・ピザ・レシピ・作り方/☆4
□簡易デミグラスソース・レシピ・作り方/☆4
□輪切りのオランジェット、レモンコンフィ・レシピ・作り方/☆4
□シーザーサラダ・レシピ・作り方/☆4.5
□ローストチキン・レシピ・作り方/☆4
□鶏の唐揚げ・レシピ・作り方/☆4
□皮から作る焼き餃子・レシピ・作り方/☆3.5
□チーズソースのニョッキ・レシピ・作り方/☆4
□浅草グルメメモ!
□美味しい調味料、食材などなど。保存版!
→料理ブログ 料理の豆知識







