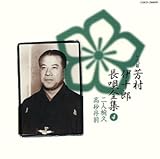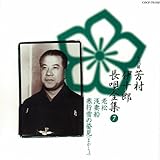丹前風呂に通う殿方は、独特な風体をしていたそうです。
それを歌舞伎的に表現したのが“丹前振り”というものだそうえです。
“丹前振り”・・・???
独特って何よ???!
独特な衣装に独特な歩き方。ここまでは分かった。
しかし、物事調べていて「独特な○×」という説明で終わってしまうのはなんて不親切。
仕方がないので、もっともっと調べてみましたよ。

衣装については、よく温泉旅館に行くと浴衣と一緒に、浴衣の上に羽織る『丹前』というのが置いてあるじゃないですか。たぶん、ああいったものを羽織ってというのがこの『丹前もの』に出てくる独特な衣装かと・・・。『丹前もの』の舞踊の写真や絵を見るとやっぱり、あの丹前のようなものを劇色化して派手にはしていますけれど着ています。
つまり和製ガウンのことですね。
はい。これで、衣装の謎は解明。
こんどは、歩き方・・・つまり、丹前振りの謎です。
いなせに肩でで風を切るように歩く。それも右肩を前に出したら右足を出す。左肩が前に出たら左足をだす。
…文では表現しにくいですが、つまり『ナンバ歩き』。
私たちの普通の歩き方は、右手が前に出ると左足が出ますよね。でもナンバ歩きは右手が前に出ると右足が出る歩き方です。
『丹前振り』とはこの『ナンバ歩き』を粋に気取った感じに歩く振りの事だったのです。
この、ナンバ…じゃなかった。『丹前振り』の時にお囃子は必ず締め太鼓で「豊後下り端・くせ」という手を打つそうです。太鼓の附けを確認。あったあった有りました!
そう言えば同じような手が「供奴」や「元禄花見踊」にもあったけど…。「供奴」に言ったってはその下りの歌詞がたしか『丹前好み~♪』という歌詞だったな?!
さて、この『丹前振り』でまた新たな発見が。
江戸時代までの人々の歩き方は、実は「ナンバ歩き」が普通だったというお話を発見。
日本の武道の動きで『ナンバ歩き』の形があるそうです。
ある武道家の方のサイトで、この『ナンバ歩き』は日本武道の独特の型ではなくて、日本伝統の文化と言っていました。
その方のお話では、日本人が今の歩き方が一般化したのは明治以降のお話で、西洋から軍事教育が導入されてそれが一般に浸透して今のような歩き方が一般化されたそうです。
つまり、行進の時に「右手を出したら左足を出す」という歩き方が教育された。それが一般に浸透したという訳らしいです。
「丹前もの」からこんな事まで分かっちゃった。
邦楽のお勉強ってけっこう楽しいですね。