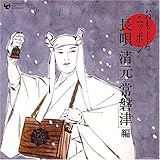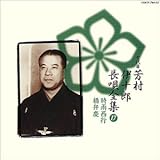| 1904年明治37年 | 五世杵屋勘五郎 |
お囃子の流派に望月流という流派があります。お囃子の流派としては最大の流派。
四世望月長九郎が七世望月太左衛門を襲名した際に、襲名の披露曲として発表したのが『島の千歳』です。
さて、この曲の誕生の馴れ初めは・・・
この七世太左衛門と作詞の如電氏はお互いに仙台出身だったそうです。同県人のよしみという事で、太左衛門氏が如電氏に作詞の依頼をしたのだそうです。
京都の飛鳥井家に『雨の曲』という雨乞いのような曲があるのだそうです。
この曲を奏でると七日の間に雨が降るのだそうです。
その歌詞が書いてある扇を如電は所有していたらしいです。
その扇には、月の出る夜空の大海に小さな岩があって、丹頂鶴が舞い遊ぶといった絵が書いてあり、如電はその図をヒントにこの曲の歌詞を作成したのだそうです。
こういう方々の想像力というのは、本当に凄い。扇の絵からこんな文学的な言葉がつらつら出てくるなんて・・・。
凡人の私には、その思考回路が不思議でたまりません。
“島の千歳”とは白拍子の元祖と言われる人の名前だそうです。
曲の題名は“千歳”と書いて「せんざい」と読んでいますが、白拍子の名前は“千歳”で「ちとせ」なのだそうです。
何故、「ちとせ」ではなく「せんざい」なのか。
これは、三番叟ものに由来していまして、翁・千歳・三番叟の「せんざい」のイメージを重ね、より目出度さを強調したのだそうです。
目出度さの象徴の一つに“鶴亀”がありますが、鶴は千歳まで生きる目出度い鳥とされています。
つまり、扇に書いてあった鶴から、千年生きる目出度い鳥だ。そうそう、千年生きる、つまり千歳・・・三番叟の千歳だ。そういえば、白拍子の元祖は千歳だ・・・。こんな感じに如電氏の頭の中はクルクルと膨大スケールのイメージが次から次ぎと思い浮かんだのでしょうね。
白拍子というと、私はすぐに義経の愛人である静御前や平家物語に出てくる祇王・祇女がすぐに浮かぶ。
白拍子の舞は、原点は巫女の舞なのだそうです。よく神前結婚式で巫女さんが舞ってくれますが、あれが元祖らしいです。
巫女さんたちの行脚で、方々布教活動として舞を披露していたのだそうですが、次第に、宗教から離れ芸能へと発展。当時の遊女が舞うようになったのだそうです。
つまり、白拍子というのは遊女なんですね。
後白河天皇は超白拍子オタクだったそうです。
結局、もとを正せば遊女ですから、悲恋とか悲しいストーリーのヒロインなんですよね。
あまり、白拍子がヒロインのお話でハッピーエンドを知りませんよね。
静御前も結局は義経と別れ別れになっちゃうし、祇王・祇女も悲しいストーリーのヒロインですし、、、そうそう、娘道成寺のヒロインの花子さんも白拍子ですが、、、清姫の霊にのり移られて大蛇に変身しちゃうのですものね。決して、ハッピーではありませんね。
さて、この曲は七世望月太左衛門氏のための曲ですから、望月流の秘曲というべき曲だと思います。
というか、発表されて二十年以上ほとんど演奏されずお蔵入りのような曲だったそうです。ところが、大正十二年頃、八世望月太左衛門が「あまり演奏されていない曲」の発掘を杵屋栄ニ氏に依頼。同年の夏にこの曲が再び演奏されたのだそうです。
これが現在、『島の千歳』が比較的メジャーになった由縁だそうです。
私自身もそうですが、小鼓のお稽古をする人は「いつかこの曲を演奏できるようになりたい」という目標の曲だと思います。何しろ、長唄と三味線。お囃子は小鼓一人のワンマンショーですから、舞台面としてカッコいいです。
けれど、それだけに難儀な曲。
普通、お囃子というのは伴奏に追従する役割がありますが、この曲は小鼓の為に作られた曲ですので、小鼓がリーダーシップをとって長唄や三味線をリードしなければいけない曲なのだそうです。
長唄のチームリーダーは一般的にタテ三味線なんです。その責任は並大抵ではないようです。まあ、三味線に限らず複数の人をまとめるリーダーというのは大変な役割ですよね。どんな世界でもリーダーはまとめられる力量が求められます。
つまり、単に小鼓が上手とかそういったレベルでは本当の『島の千歳』の演奏はできないのでしょうね。
亡くなった大皮の師匠が
「『島の千歳』は“許しもの”と言って、容易く教えてもらう曲じゃないんだ。“そろそろ、この曲を演奏できる力量が付いたかな”という段階になって、師匠にいきなり“『島の千歳』を打ってごらん”と言われて、まず師匠にその力量を試され、力が認められなければ演奏できない曲なんだ」と仰っていた事を記憶しています。
難しい曲というのは数知れなくありますが、中でも『島の千歳』は特別な曲という観念が私にはあります。
ああ、いつか大舞台でこの曲を演奏したいのです。また、この曲をきちっと演奏できるレベルまで精進したいものです。