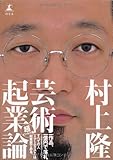1:電気を夕方までつけない
2:アパートの階段の照明は自動消灯
3:集合住宅では暖房器具の使用出来る期間が決まっている
4:アパートによっては棟ごとに暖房がつくので、個人の無駄使いは出来ない。
5:暖炉のある家が今も多くある
6:カーシェアリングの需要がある
7:ヨーロッパの家は組積造建築のため壁が厚く、夏にエアコンが無くても過ごせる
8:水を常温で飲むのに慣れている
9:夏は家族でバカンスに出かけ、公共の電力を使う。あるいは海外の電力を使う。
10:月に一回ストライキをして、公共の電力すら節約する。
11:月に一回 No Car Day があり、許可のある車以外は公道を走れない。
12:基本的に季節の野菜と果物しか買わない ハウス栽培は少ない
13:美味しいものは基本的に現地で食べる 輸送にかかるエネルギーが少ない
などなど。
自由に電気を使える環境で育った自分にとっては、イタリアでの生活は目から鱗でした。彼らは太陽光をうまく使い、出来るだけ少ない電力で生活する知恵があります。電気を共同で管理するシステムがあります。
少々ストライキがあっても、自分で暖房の調整が出来なくても、夕方まで電気がつかなくても、24時間のコンビニがなくても、日曜にスーパーが休みでも日常生活にはほとんど支障がないということに気付きました。暑ければ、涼しい街に行けばいいだけの話です。
イタリアは1950年代後半から原子力発電の研究開発を開始し、当時の世界原子力技術で最先端でした。しかし、チェルノブイリ事故以降、1987年の国民投票で原発全面停止を決定。1990年以降原発は停まったままです。この選択はまた、急激な経済発展は必要ないという民意であったともうけとれます。このような環境下で、様々な省エネの工夫がされてきました。
日本人もここから学ぶ事は多くあるはずですが、その前に私たちのメンタリティーも同時に変えていかなくてはなりません。
少々不便な事があっても、不都合なことが起きても社会は回ります。仕事も回ります。コンビニが無くても、日曜日スーパーが休みでも日常生活に支障はありません。
私たちが便利さや快適さを求めている限り、エネルギーの需要は変わりません。エネルギーの需要が変わらないという事は、原発も停まりません。
日本の経済発展は安いエネルギーの供給によって成し遂げられました。日本中にあるほぼ全てのサービスは原発からの安いエネルギー供給によって支えられています。
電気にそこまで依存しなくても生活できるジャン!って人がたくさんいれば、原発の需要は減っていくだけの話です。
電気に依存しない生活が進めば、もちろん既存のサービスも受けられなくなります。コンビニも減りますし、ツナおにぎりが一個300円になるかもしれません。ヨーロッパの美味しい食材も高額になるでしょう。そうなると、イタリアンやフレンチもなかなか食べれなくなります。美容エステにも通えなくなるかもしれません。テニスもナイター施設が利用出来なくなるかもしれません。そういった、側面を受入れる覚悟が日本人にあるかどうかになってくるのです。
クリック クリック↓
にほんブログ村