を読みました。今後アートやデザインの分野に興味がある、もしくは仕事として関わっている人に是非読んでもらいたい一冊です。
「世界ではこう戦え」と帯タイトルにもあるように、世界に通用するアーティストになるための具体的な戦略と方法論が書かれています。
この内容はアーティストのためのものではなく、デザイナーにもすっぽり当てはまる内容になってるので必ず生き残るためのヒントがえられる事は間違いないです。努力の方向性を間違えないためにも、早い段階で読んでおく事をお勧めします。
アートやデザインのルールの理解無しにもの作りをし続けるのは非常に非効率である事も述べており、
以前に村上隆の「芸術起業論」「芸術闘争論」を読みましたが、今回の「創造力なき日本」は前者で書いた内容にさらにビジネスの視点と、企業組織としての視点が加わり、集団でどのようにアートを作っていくべきなのかという部分にも触れています。
村上氏は、
”アートの世界も’企業の論理’と共通する、共同作業の中には一般企業と変わらない性格が生まれる” と述べています。
前2作も非常に面白いです。読むだけで村上隆のエネルギーが伝わってきます。かなりこってりに仕上がっていて、結構な破壊力がありました。お勧めです。今回のは言葉により磨きがかかり、要点も絞られてるのではじめのとっかかりとしては良い本であると思います。
「創造力なき日本」を読んで更に詳しく知りたい方は「芸術起業論」「芸術闘争論」を手に取ると良いかと思います。
面白いなと思ったところを少しまとめてみました。
”芸術には「大衆芸術」と「純粋芸術」に分けられる。例えば漫画やアニメが日本の代表的な大衆芸術。
大衆芸術は庶民の購買意欲を最大化する事に目的が絞られるのに対し、純粋芸術はハイヒエラルキーの人たちによって、お金で才能を買われる。純粋芸術の場合一般大衆に理解不能な事をしていても、ハイヒエラルキーの人たちの期待を裏切らなければよい。
だからこそ現代美術はその時代において評価を得られなくても”時代を乗り越えていく可能性”が出てくる”
デザインの場合は大衆芸術的な要素も含まれているので、線引きは難しですが、でもこれは自分がどの役割を果たしてゆきたいかによって決まっていくものだと思います。
「時代を乗り越える可能性」という言葉には勇気をもらいます。未来をどう導いてゆけるか、アーティストやデザイナーはその誘導者になり得る職業である。これは誇りを持ってよい事だと思います。
”まず、アーティスト(デザイナー)という職業は、社会的ヒエラルキーのピラミッドの最下層であることを自覚しなくてはならない。
純粋芸術の顧客は大金持ちであり、彼らがいてこそ制作が可能であり、要求に従わなければならない。また、仕事を頂くためにも自分からただただ歩み寄る事をしなければならない。
こうしたヒエレルキーから抜け出すには教授などの「教育者」という社会的立場が与えられ最下層から抜け出す事は出来る”
まず自分たちのおかれている立ち位置を把握することが大事なのだと気付きました。また、自分が最終的にどのポジションに着きたいかで、今やるべき事が変わっていますね。
自分がどこにいるかも分からず、ゴールも分からないまま闇雲に走り回るフルマラソンほど恐ろしいものはないです。。。
現段階で明確なゴールは分からなくても、大体あっちの方角ってぐらいはハッキリさせるべきなんだと思います。
”最初に問われるのは才能でなく自覚と覚悟。芸術家は覚悟と肉体を資本としたアスリートでなければならない。また絵の才能でなく”戦略”が現代美術の世界で戦う上で重要である。欧米の芸術の世界には”確固たる不文律”が存在し、日本の芸術家たちがほとんど欧米で通用しないのはそれらの理解がないからだ” と指摘しています
”確固たる不文律” ようは、言葉や文章で明確には体系化されていない教養の範囲の事を指しているのだと思います。このあたりを理解するには、キリスト教などの宗教や歴史、戦争や性の問題等の教養を身につけない限り見えてこない領域なのだと僕は考えています。
やはり宗教観、歴史観無しには芸術の奥にある背景は掴めないのではと感じます。また現代社会が抱える問題も見えてきません。
”本気でアーティストを目指している若い人には「寝るな!」といいます。ろくに睡眠を取らずに、意識が朦朧としようとも絵を描き続ける。そういった生活を3年程続けていると、絵を描く事はたいした事ではなくなる。その時にあらためてこれを続けてけていくのかと自問自答する。
~中略~
この業界で24時間寝られないと言った状況は苦しみのうちに入らない。死線をさまようのにも近いようなところまで自分を追い込む時期があってもいいはずだし、若くて体力のあるうちにそうした経験をすべきであり、自問自答してみる事も大事である” と言っています。
結構きつい言葉ですよね~。でも”若いうちは”です。出来てますか?
さらに面白かったのが、過去の歴史を振り返り、成功した芸術家は大きく分けて以下のパターンに分類されるという事です。
1:天才型 (ダヴィンチ、ピカソ)
2:天然型 (山下清、ピカソ)
3:努力型 (ダリ、狩野永徳、ウォーホル、陶芸家)
4:戦略型 (ハースト、ウォーホル、ダリ、北大路魯山人)
5:偶然型 (印象派の画家)
6:死後型 (パウルクレー、ゴッホ、ヘンリーダーカー、アウトサイダーアートの画家、山下清)
もちろん一つのパターンには限らず、いくつか組み合わさる人もいます。詳しくは本書に書かれています。
出来るだけ早い段階でこの本に出会っで欲しいと思い、記録も兼ねて書きました。興味が湧いた方は是非!
創造力なき日本 アートの現場で蘇る「覚悟」と「継続」 (角川oneテーマ21)/角川書店(角川グループパブリッシング)

¥820
Amazon.co.jp
芸術起業論/幻冬舎
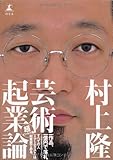
¥1,680
Amazon.co.jp
芸術闘争論/幻冬舎

¥1,890
Amazon.co.jp