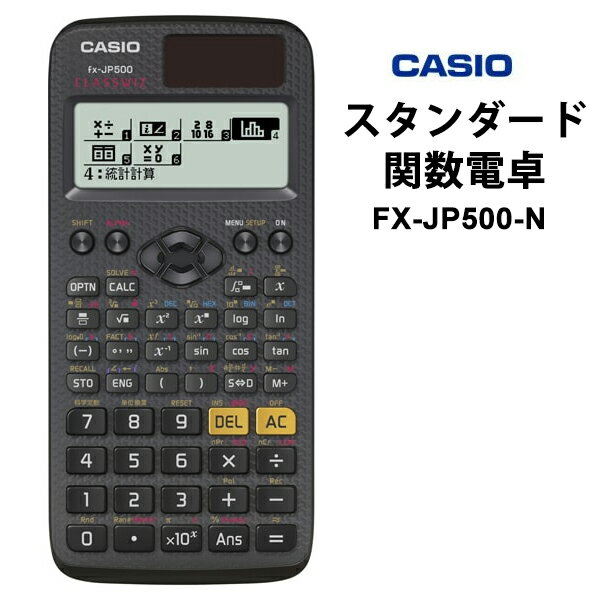阪急京都線の座席指定車両、PRiVACEが今年の夏にデビューするようです。
夏といえば7月の祇園祭(15,16日の宵山あたりに臨時列車が出る)や8月初めの淀川花火大会が沿線でのイベントでしょう。それらの突発的な需要を取り込むのか、それとも混乱を避けるのかに注目です。今更ながら予想してみます。
経緯として、10月06日のリリースから
神戸・宝塚線系統の2000系とともに2024年夏に京都線の新型特急用車両の2300系がデビューすることが発表されました。この時8両編成の大阪方4両目(4号車)に指定席車両が設定されることが判りました。指定席の定員は40人ですが、これだけでは京阪プレミアムカーのような2+1の1扉車か京急ル・シエルのような2+2の3扉LCカーなのかはわかりませんでした。
11月21日のリリースから
名前とロゴ、外観とデッキからのイメージが出てきました。
まず、名前とロゴについて、
↑ロゴ 公式サイトより
名前はPRiVACE(プライベース)でPrivateとPlaceの造語のようです。
「i」だけが小文字です。「アイ」と読ませたいことや、英語の一人称単数の主格「I」としてプライベート感を醸し出すこと、某スマホに影響を受けたなどが考えられますが、理由は分かりません。
ただ、英字表記がprivateやprivacyと1字違いであることが検索性に問題がないか心配です。
ロゴはPをかたどったものですが、巷では「ア」にしか見えないといわれており、名称も「ア」で通じてしまうようで面白いですね(このせいか、iを大文字する誤記もほとんど見られない)。また、ロゴに座っているポスターはドラえもんのコエカタマリンを彷彿させますね。
次に外観について
側面は車両中央に両開きの扉があり、両側に7つの窓があります。後述のデッキからのイメージと合わせて1列毎に窓があることがわかります。新造なので窓割りは合っているはずですが、1列ごとだとそこまで見える景色には影響は無いと思います(車両テーマの個に合わせたのか、そこまで沿線の景色が面白くないのか…)。扉横の窓の片方に種別・行き先・列車番号を表示する電光掲示板があります。はめ込み合成かもしれませんが、3000系プレミアムカー385x号車のinfoverreや東武N100系の彩Visionのような映り込みの少ない液晶が採用されると思われます。
↑大晦日終夜運転での急行
1列窓で横幅が狭いのと、常時(?)ロゴ表示がある分(385xは扉を閉めてから数秒後にロゴのアニメーション表示)3列表示になって窓の半分を占めますが、内装の写真と窓下部の棒のようなものがあることから座席ではなく、荷物置き場だと思われます。ですので景色には関係ないと思います。窓下には金色の線と4つ目の窓に車番と阪急マークがあります。ホームドアが整備されると見えない部分(扉と車番、阪急ロゴのところは3扉位置でホームドアが透明なので見えるのかな)なのであれです。ホームドア関連で車両端上にも車番があります。両隣の車両との違いがあまりないのが特徴ですね
↑側面 プレスリリースより
↑ドア付近 プレスリリースより
デッキからのイメージ↓プレスリリースより
外観からも分かる通り車両中央にデッキがある構造です。一般的に車両中央が乗り心地が良いですが、乗車時間が短いので気にしなくてよかったのでしょう。デッキの壁は下が木目調、上が漆喰というかアイボリーのような白色です。上の方に波線のような模様が入っています。デッキと客室を仕切る扉は無いようです。外との扉の窓は片側で三角形、両方で斜めの正方形です。
客室は壁が非対称なのを考えると2+1の配列です。これが7列ありますが、2と1の方で最前列までの奥行きが異なることから1の方のデッキ側は座席は存在しないこととなり、片側で(2+1)×7-1=20席になり、両側で40席とリリースの数と一致します。座席がない部分は外観では荷物置きと推測できますが、係員や車内販売のスペース、車椅子対応に広めの場所に使われるかもしれません。また、この部分に表示器を付けると思われるので、デッキを中心に点対称な座席配置(デッキから見て右が2列)だと思います。片方だけ荷物置き場だと他方の利用者はもう片方まで置いたり取りに行ったりしなくてはいけなく、荷物置き場側の乗客からは鬱陶しく感じられますが、両方付けると係員はデッキにいるのか?ということになりますね…。座席上の棚は透明のようです。客室床は黒無地のカーペットでしょうか?
椅子は緑で白の枕カバーが掛かっており、側面は茶色と阪急らしい色合いです。顔の高さの側面は前面に出っ張っており、プライベートな雰囲気を作り出しています。プレミアムカーのように座席の両面で色合いを変えることで出っ張りが強調された感じです。
↑プレミアムカーの座席
しかし、見た感じではバックシェル(近鉄ひのとりにある座席後ろの板のようなもの)が付いて無さそう(有るかもしれない)なので、リクライニングの際の気まずさは残ってしまうのではないでしょうか。リクライニングさせるときは声をかけてから倒しますが、イヤホンで音楽を聴いていると気付かれない場合があるのが嫌です(寝ているときはテーブルの物が落ちないようそっと勝手に倒しますが、寝てるのを起こすのもアレなので)。肘掛け部分は片側(1は通路側、2は真ん中か?)にコンセントとリクライニングボタンがまとめて取り付けているのでしょう。もう一つボタンらしきものがありますがおそらく暖房用のボタンかなと思います。
考察(適当)
既にある京阪プレミアムカーを参考に推察しました。
・何故扉が真ん中なのか?
プレミアムカーは3扉の端の扉の位置のみに扉があり、2+1の12列と端に2×2で40席です。
↑プレミアムカー座席と窓割り 公式サイトより
扉配置は2扉の8000系を改造したのでその1つをとって端に位置しています(3000系は新造ですが8000系に合わせたのでry)。プライベースは新造なので自由に設定できます。端に扉を設置すると狭い方は中途半端な広さの空間になりますが、4人分とグループや家族旅行に使いやすいセミコンパートメントと荷物置き場、乗務員・販売品スペースといった微妙に場所を使うものに割り当てられます。それでも中央にデッキを作ったのはやはり乗り降りに時間がかからないようにするためでしょう。特に朝ラッシュ(通勤特急も設定があるので朝も運行されるはず)では10両編成が廃止され(復活の見込みは無さそう)、さらに1両が定員84人減なので混雑は厳しいと思います。また、線路容量的に京阪線よりも本数が増やせないのが難点です(このせいかLC車説が濃厚だった)。比較的線形は良いのでデッキを中央に置いても問題無かったと思われます。
・同じところと異なるところ
同じ点…定員、扉の数、2+1配置、座席設備(たぶん)
似たような大きさの車両で1人席を設けようとすると2+1は当然であり、係員を乗せて採算を取ろうと座席を増やそうとすれば定員は40が限界でしょうか(JR東のグリーン車のようにダブルデッカーにすれば増えるが乗降に時間がかかる、あの中央東線でやるらしいが)。ちなみにJRのAシートは車両が大きいので話が違う。名前からしてバックシェルは付いていてほしい(願望)。
違う点…扉位置、扉の窓の形、窓割り、客室仕切り、色合い
扉位置は先述の通り、扉の窓の形がプレミアムカーは半円に対して四角なのは却って意識した感じもします。デッキと客室を仕切る扉はやはり必要ないと思われたのだと考えられます(乗降時間と個室感を天秤にかけたら)。しかし、窓が列ごとなのと仕切りが壁なのは個室のイメージでしょうか。プレミアムカーは窓割りは2列ごと(8000系は改造の為合っていない部分もある)、仕切りは暗いガラスに雲柄の模様入りで観光客もとらえようとしています。完全に隠れていない仕切りは衝立のような和の感じがしますね。逆にプライベースの壁は街並みを意識したように思います。
↑8000系 片開き
内装の色はプレミアムカーが白と黒のモノトーンを基調(8000系の方が若干白の割合が多い)、プライベースは茶と緑が基調で阪急らしい色合いです。外装の色はどちらもほぼ一色で金色の飾り帯がありますが、プレミアムカーの方が派手(特に扉付近)です。一般車の塗装が違うので比較しにくいですが、京阪は一般車が2色刷りの真ん中に帯で、プレミアムカーは上の色に金帯が太い線が窓下、上に細い線が引いてあり、扉付近は金色の市松模様です。対して、阪急は一般車が茶色(マルーン、栗色)に天井付近が白(アイボリー、象牙色)で(2300系では白の部分が減りましたが)、プライベースはこれの窓下に金色の線が入った程度の違いです(むしろ窓の方が違いがわかりやすい)。この外観の違いの無さも扉を中央にした理由の一つかもしれません(適当)