節分の工作 その3
陰干しがいいのですが風通しが良いところとなるといい場所が見つからず、エアコンの室外機の上で雨ざらしの直射日光にあてて数日放置していたところ、程よく乾いたので型から外しました。
これから縁を切り揃えて、いよいよ色塗りです。色塗りの前に一仕事しておくと仕上がりに差が出ます。
それは下塗りのジェッソ。いわゆる砥の粉と同じような役目をする地塗り剤で、これを塗るとムラなくきれいに発色します。お面くらいの作品のサイズに使う量なら一瓶400円くらいで手に入ります。
ジェッソを買ったら次の作業に入ります。
ニュートラルとスイッチ
- 図書館で見つけたDMの個展が今日からだったので、初めてのギャラリーで初めて見る作家さんの作品。あちこち住むならその土地土地に根付いた作品を見たいので、ちょうど良い機会でした。
ギャラリーにいた方の話を聞くと全国的な傾向で昔からある工房がよそ者の参入を拒み、粘土など製作に関わる条件を囲ってしまう結果、その土地とはゆかりのない材料(粘土など)で作品が作られ、本来の焼き物とは違う材質のものが一括りで「○○焼き」と呼ばれているそうです。
ただ素人目にはそれはわからないし、まぁその土地の作家さんが作ったものであればいいし、何より使いやすくて潤いを与えてくれる作品ならいいんではないのかと個人的には思います。誰かが作った作品がそばにあると、エナジーを感じ、同時にニュートラルからギアを入れる気持ちへの切り替えスイッチにもなります。ただ名産品としての品質は、自分で自分の首をしめているとは思いますが、それについては知りません。

だから買ってしまったカフェオレボウル。一晩水に浸けてから使います。友には鳥の箸置きを。
私の好みはシンプルなものと、鮮やかなものを好む2つの傾向があり、ハンカチやスリッパは目にも鮮やかな色を好み、食器やカバンはシンプルなものを好む傾向があります。本当はどっちが好きなんだろうと考えることもありますが、たぶんどっちも好きなんでしょう。たとえば今日ギャラリーでご馳走になったコーヒーカップも素敵でした。ヒビ模様の地に銀の不定形な面の継ぎと、糸底の部分は赤い漆塗り。一見不規則に指でひねられたカップの縁が口に当たったときの飲み心地と、銀とグレーがかった白と漆の赤、この3種のあやういバランスがたまらず、この作家の6月の個展が楽しみです。
そんな帰り道は本屋で「Pen
」の文房具特集(scos
が出ているので)を熱心に立ち読みし、エキスを吸い取り
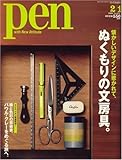
「ナガオカケンメイの考え 」を図書館に注文しようと決めて帰って来たのでした。

節分の工作 その2
水っぽい糊を使うので早めにとりかかろうと思っていたのですが、葬式に出ていたのでここ数日その空気を引きずり、低空飛行でした。「顔」のあるものを作るときは、なるべく気分がいいときにやったほうがいいと考えているのでしばらく様子を見てましたが、今朝は天気がいいので作業開始。
用意するものはコチラ
から。
 粘土細工にあれば便利なものとして、ヘラがあります。100円で売っているものがあればグーですが、もしなければ割り箸を削っても代用できます。
粘土細工にあれば便利なものとして、ヘラがあります。100円で売っているものがあればグーですが、もしなければ割り箸を削っても代用できます。
 油粘土を800g(2パック)くらい用意して、お面の土台を作ります。大きさの目安は被る人の「手の平の大きさ+3cm」くらい。節分の鬼のお面なので逃げる表情を想像しながら(ここがポイント。イメージすることが要なのです)どんどん粘土を盛りましょう。お化粧ではなくお面なのです。好き放題。
油粘土を800g(2パック)くらい用意して、お面の土台を作ります。大きさの目安は被る人の「手の平の大きさ+3cm」くらい。節分の鬼のお面なので逃げる表情を想像しながら(ここがポイント。イメージすることが要なのです)どんどん粘土を盛りましょう。お化粧ではなくお面なのです。好き放題。
ただし後から紙を貼るので細かい作業よりも、深く高く大きな作りが良いです(そうしないと能面になる)。ときどき真上や横から見て、盛り上がりのバランスやボリュームを見ましょう。低いところでも3cmくらいはあった方が映えると思います。 形が出来上がったら、ラップをふわりとかけて凹凸に合わせぴったり押さえます。
 ボールに1:10の割合で糊と水を入れ、よく溶かします。お面の凹凸にあわせられるくらいの大きさ(3~5cm)にちぎった和紙(半紙や薄い紙ならOK)を糊液に浸けます。
ボールに1:10の割合で糊と水を入れ、よく溶かします。お面の凹凸にあわせられるくらいの大きさ(3~5cm)にちぎった和紙(半紙や薄い紙ならOK)を糊液に浸けます。  ビタビタに濡れた和紙を土台にまんべんなく貼り付けます。端が重なるように隙間なくどんどん貼りましょう。窪みや出っ張りのラインは慎重に押さえます。油粘土の色が見えなくなるまで厚めに貼ります。また土台の縁の部分は薄くなりやすいですが、一番強度が必要な箇所なので意識して頑丈に厚く貼ります。
ビタビタに濡れた和紙を土台にまんべんなく貼り付けます。端が重なるように隙間なくどんどん貼りましょう。窪みや出っ張りのラインは慎重に押さえます。油粘土の色が見えなくなるまで厚めに貼ります。また土台の縁の部分は薄くなりやすいですが、一番強度が必要な箇所なので意識して頑丈に厚く貼ります。
ここまでが第一段階。出来上ったお面は完全に乾くまで陰干しします。作者は同じ要領でクスダマは作ったことがありますが、お面は初めての手探りです。どうなることやら知りませんが、それでは乾くまで。
※文中の「グー」はエド・はるみのそれとは関係ありません。
つづく
エコ
資本主義社会が回転するためには消費が欠かせないので、それを悪いとは言いませんが「エコ」と言う言葉がこれだけあふれてくると少々耳障りで、この一言が免罪符あるいはひっかけとして使われているようで、苦手です。
でも自分はわりとエコ生活に近いことをしているとは思います。生活で無理なく取り入れられる範囲で役に立てれば、くらいに考えているんですが、今年のどんと焼きは神職がいる神社が見つからず、サイクリングついでに往復20kmばかりチャリで走ってきました。寒い中、汗をびっしょりかいてお肌はすべすべになりました。
ゴミ箱がティッシュペーパーで一杯になるのがうっとうしいので、寒い季節の水っパナ程度ならハンカチで済ませることにしてみました。ゴミ箱がすっきりして、洗濯機に薄いハンカチを放り込むだけなので楽チンです。気に入った柄のハンカチならなおさら気分が良いです(きれいなままよりも使い込んでクタクタになった物に愛着があるので)。ただし、風邪の時はこの限りではありません。
古紙回収は徐々にたまっていくのを見るのが達成感があって好きです。
「エコな買い物」をするのではなく、身の回りのもので間に合うものはないか、探してみるのがいいのかな、と油粘土の「代用品」探しでふと思いました。というか、動機が個人的なものばかりなのですが、崇高な理想を持つことも大事ですがまずは「やってみる」ことがいいんではないでしょうか。
節分の工作 その1
怒涛のクリスマスから年末、お正月、七草粥もどんと焼きもイベントが一通りおわり、次は節分です。節分といえば鬼の面。これ、豆についている面が手軽ですが、作ったほうが断然面白いです。
というわけで、これから作り始めれば丁度2月3日までに出来上がるでしょう。
用意するもの
◇油粘土
◇ラップ
◇水に溶かしたでんぷん糊
◇和紙または薄い紙
◇ベニヤ板などの土台
◇アクリル絵の具(普通の水彩絵の具でも可)
あればいいもの
◇ジェッソ(地塗り剤)
◇ニス
油粘土に代わるものを身の回りで探しましたが見つかりません。近所で入手したら作業開始。ちなみに我が家は合理性を重んじる北海道方式で、豆は殻付ピーナッツを投げます。本州出身の旦那がなんと言おうと、節分はピーナッツです。ついでに言うと実家の母はチャキチャキの江戸っ子、佃の出身です。母は本来とは違うとブツブツ言いながらも、ピーナッツの節分をやってくれたものでした。
>>節分の工作 その2はコチラ
ヘッツェル
ベッドの上に荷物を出して、これから使うものと当面必要ないものを整理し始めた。ドロシーは再び本を読み、私はあれこれ仕分けをしながら、洗濯するものをよける。しばらくたったころ、この部屋の最後の一人がやってきた。
大きなブルーのキャリーバッグを引きずる快活なブロンドのヘッツェル齢60歳。とてもそうは見えない、というのは向こうも同じようで私の年を聞いてマジマジと見られる。部屋に入り調度品が気に入った様子を見せると早速巨大なキャリーバッグの蓋を開き、買い物が大好きなことを語り始めた。
「これは、経由してきたサンティアゴで買ったかばん、これはお買い得よ!どうこの革バッグ?ふふん。あなたはどこ経由で?ブエノスアイレス、あぁ~、バス!?それでこっちはカナダのトロントで…」といった具合。一息ついたところでヘッツェルはドロシーを誘い、2人は買い物と食事に中心街へ行くことになった。私はといえば、買い物にはあまり興味がない。むしろ、この部屋にある立派な、少なくとも私にはそう見えるバスタブが魅力的だった。
 何しろこれまでバスタブがあっても栓がなく、仕方なくビニールを詰めて無理やり低い水位の浴槽に浸かったり、途中から冷水修行に変わるシャワーばかり浴びていた。それが続くならそれで我慢するけど、私の場合アトピー体質でなかなか気まぐれな敏感肌。汚れはべつにいいのだけど、寒さが続くと人並み以上にゴワゴワのガサガサの突っ張った上に、もろいというオソロシイことになる。今目の前にあるのは、全てが用意された「豪華な」風呂。2人を見送ってから、いそいそと揉み手をしたくなるほどウキウキしながら湯船に勢い良く湯をためる。
何しろこれまでバスタブがあっても栓がなく、仕方なくビニールを詰めて無理やり低い水位の浴槽に浸かったり、途中から冷水修行に変わるシャワーばかり浴びていた。それが続くならそれで我慢するけど、私の場合アトピー体質でなかなか気まぐれな敏感肌。汚れはべつにいいのだけど、寒さが続くと人並み以上にゴワゴワのガサガサの突っ張った上に、もろいというオソロシイことになる。今目の前にあるのは、全てが用意された「豪華な」風呂。2人を見送ってから、いそいそと揉み手をしたくなるほどウキウキしながら湯船に勢い良く湯をためる。
もうもうと立ち込める暖かい蒸気で強ばった心身を伸ばし、大きな息を吐き出す。入浴は気分転換と言う人は多いと思うけど、このときの自分にとってはようやくとどいた明日への禊のような気持ちもあった。ついでに洗濯を済ませ、いよいよ明日は出港。この日は早めに床についた。
ドロシー
 中心街を抜け住宅街を通り過ぎ、湾に面した小高い丘の上にホテルはあった。チェックインを済ませると、フロントのカウンターには宿泊者名簿がある、私の泊まる部屋の番号を探した。3人部屋ということは、おそらく船室も同じメンバーなのだろうか。もしそうなら、その面子次第でこれから先の良し悪しは少なからず左右される。
中心街を抜け住宅街を通り過ぎ、湾に面した小高い丘の上にホテルはあった。チェックインを済ませると、フロントのカウンターには宿泊者名簿がある、私の泊まる部屋の番号を探した。3人部屋ということは、おそらく船室も同じメンバーなのだろうか。もしそうなら、その面子次第でこれから先の良し悪しは少なからず左右される。
「えーと、ドロシー…と、へ?ヘッツェル?」
オズの魔法使いの主人公とドイツ系らしき女性二人。若いのか、年上なのか、気が強いのか、のんびりしているのか、神経質だったら厄介だなぁと、どんな人なのか気になる。しかし想像ばかりしても始まらない。荷物はポーターが部屋まで運びドアを開けてくれた。広々と清潔で落ち着いた部屋が用意されてる。そして部屋の奥に開かれた明るい窓際の大きなベッドに一人、小さなお婆さんが膝を立て不釣合いなくらい大きく見える本を読んでいた。
「バッ…、婆さんかい…。」
これが正直な気持ち。
赤みがかった白髪のお婆さんは見たところかなりの高齢で、「おや、まぁ」と言った具合にこちらに気づくと本をたたみ、しゃがれた声のゆっくりとした英語で話しかけてきた。一通りの会話を交わすけど、しばらくスペイン語ばかり聞いていたので英語の会話に違和感がある。どちらにしろまともに話せないのでレベル的には大して変わらないけど、ついスペイン語の返事がでそうになり、頭の中はちゃんぽん状態で、これがドリーとの出会いだった。
移動
 storm in Africaを聴きながら、「アフリカに行きたいなぁ…」と掛け布団が半分落ちたベッドで思う。一晩経っても奥歯に挟まった生ハムの筋はまだ取れていない。
storm in Africaを聴きながら、「アフリカに行きたいなぁ…」と掛け布団が半分落ちたベッドで思う。一晩経っても奥歯に挟まった生ハムの筋はまだ取れていない。
MP3の再生順と音質を変え1年前のことを思い出していた。思いついたのが2006年10月の通勤電車の中。仕事の段取りは遅々として進まないことがあるのに、ことこういうことに関しては驚くべきスピードで算段が進む。動機はここで何度も書いているように、「南極がどういうところか見たいから」ただそれだけ。
それだけのことをするのにしがらみの多さに参り、それらを断ち切るようにして1ヶ月の旅に出てきた。もともとは南極へ行くのが目的で、憧れてはいたもののパタゴニアは「交通費がかかるついでくっつけてしまえ」と通り道なのを活かしてあちこち移動してきた。
そして旅とは物質的移動ではなく、精神的移動であるということを誰かが言っていた、それは長さに関係なくその人がどんな時をその中で過ごすかにあると思う。この先2週間、どういう時を過ごすことになるのかは自分次第。渦中にいるとその時その時をすごすのに夢中で、今こうしてノートを見返すと天井から自分を見ているようで面白い、時には当時の気持ちを思い出して笑ったり凹む。私は旅行ではなく旅をしたい、その話はまたいつかにするとして
いつものように防寒着と石で重い荷物を背負う。道端に生えている雑草は、故郷北海道と良く似ていて、サイズが1.5倍ほど大きい。タンポポもイネ科の植物もワサワサと短い夏を謳歌するように勢いよく生えている。
カフェで喉が熱くなるほどコニャックがきいた甘いチョコクレープを食べてはコーヒーを飲む。鼻から抜けるアルコールの熱さとチョコの香り、コーヒーのほろ苦さがたまらない。さらに中心街にある教会を訪ね、思い木の扉をゆっくり開き、静かな堂内の椅子に座りこむ。例によってにわか教徒でこの先の航海の安全をマリア様にお願いし、、ツアーのクォーク社が前泊で用意した街はずれの宿へ荷物を置くため、タクシーに乗り込んだ。
音楽
しばらく気のむくままに書いていますが、これもいいのではないかと思っています。さて、年齢とともに価値感や好みには変化があり、私はわりとランダムに聞くほうです。いろいろ試したいつまみ食いオムニバスを買うことが多いのですが、その中からお気に入りをMP3に入れては、そこかしこで聴いています。
そして、どこかで聴いた曲をメモっておかないと忘れてしまうんですね。たぶん気に入ったけどまだ手に入れていない曲がたくさんあると思います。思いついたことを書き留めておくノートは手元にあるのですが、音楽に至っては耳とアイデアは別な感じがして、耳の記憶だけに頼ってしまいます。

- 久石 譲 「おくりびと」 から「memory」
- 去年一番はこの曲でした。山﨑努がいぶし銀の渋い存在感で素敵です。
- オムニバスCD 「pure 」からアンドレ・ギャニオン 「めぐり逢い」
- 南極でずっと聴いていた曲でした。 このCD、真ん中あたりから選曲がメランコリックな曲が多く重いです。
と、しっとり系の曲を書いてみましたが先ほども述べたように、何でも聴きます。




