
出会いあり、別れあり・・・。
他のブロガーさんの記事を拝見しても、
悲喜こもごもという感じがします。
うちのチームは、昨日県南の一関に
遠征し、2試合を行ってきました

午前中は天気が良かったのですが、
午後から天気が崩れ、挙げ句
 が
が
さすがに雪中での試合は今まで
経験がありません

未だに雪が降る寒い岩手です

それにしても、子どもたちも寒い中
よく頑張りました


新学期も始まるし、風邪を引かない
ようにして欲しいものです

ちなみに、監督は午前の1試合目だけ
で、用事のため帰ってしまったので、2
試合目は自分が代行を務めました。
自分は、いつもではありませんが、基
本的にはサインは一切出しません。
いわゆる
”ノーサインベースボール
 ”
”です。
理由は嫌いだから。
子どもたちが、大人に操られてる感が
あって、とても違和感があるからです。
”どっち向いて野球やってるの
 ”
””キミ達が向くのは相手チームの子たち
の方だよ
 ”
”って思うくらい・・・。
でも、こんなことを子どもに言っても
仕方ありませんよね。
なぜなら、やらせてるのは大人だから。
このノーサインについては、当然賛否が
あることと思います。
確かに、サインに慣れている子どもたち
からは、サインを出して欲しいという声
も上がります。
でも、
”みんなの野球なんだから、みんなで
考えなさい”
って言います

とかく、
子どもたちは、大人の威厳で一方的に
支配しなければ統制が取れない。
子どもたちは、指示がないと動けない。
子どもたちのやりたいようにやらせたら、
緩くなり、締りがなくなる。
そう考える指導者も多いことと思います。
自分は、それについては否定しません。
一理あると思うし、それが必要な場合も
あるでしょう。
しかし、それは一つの考え方に過ぎない
のではないかと。
また、さらに言うならば、そんなの”迷信”
ではないかとさえ思ったりもするのです。
大人の威厳で
”いいから言う通りにやれ
 ”
”っていう、問答無用的スタンスは、単な
る大人の怠慢や逃げの表れにしか思
えません。
つまり、その方が何も考える必要がない
ので、楽だからです。
子どもたちがいかに集中して、楽しむよ
うにできるか。
それは指導者の、”持って行き方”次第
なのではないかと思っています。
指導者は力ずくで統制を取ろうとするの
ではなく、上手く子どもたちの心を乗せ
ることに腐心すべきだと。
ゆえに、一つだけではなく、たくさんの
アプローチが必要です。
それだけ指導者としての引き出しも必要
になるでしょう。
そういう意味では、子どもたち以上に、
”自分磨き”と”自己成長”が求められ
るのが指導者です。
自分は何も完全に子どもたちをほっと
けと言っているわけではありません。
”指摘するべきポイントと、そうでない
ポイントがあるでしょう”
と言いたいのです。
自分は、こんな場合は子どもたちに
対し、ビシッと指摘します。
礼節をわきまえない態度が見受けら
れたとき。
心が乱れていることが見受けられた
とき(道具がきれいに揃っていない、
大切にしないなど)。
チームの約束事を破ったとき。
(チームプレーに背いたとき)
仲間を大切にしない態度が見受けら
れたとき。
ケガになるような危険な行為に及ん
だとき。
以上の5つです。
こんなこと、改めて声高に言うことで
はありませんよね

当然のことですから。
要するに、反社会的な行為というのは
大人としては、決して見逃してはいけ
ないことは言うまでもないこと。
そして、決して感情に任せて”怒る”
のではなく、教育的視点を持って
”叱る”ことが大切だと思います。
確かに、上手く子どもたちの心を乗
せようとしても、緊張感がなくなって
きたような場合は、ビシッと締める必
要は当然あるでしょう。
でも自分的には、それ以外は子ども
たちの好きなようにやらせる。
子どもたちの創造性を掻き立て、自
ら感じ、自ら考える。
主役は子どもたちなんだと・・・。
そういう視点が大切なのではないで
しょうか

むしろ、自分たちで考える方が、ある
意味”厳しい”ことを要求しているとも
言えると思います。
なぜなら、指示を受けた方が全然楽
ですからね。
ノーサインベースボールは、あくまで
も子どもたちの力を引き出す、一つ
の”きっかけ”に過ぎないと思ってい
ます。
それに対応しようと考える子、それで
も考えない子はいます。
でも、とにかく大人はあの手この手で
きっかけを与え続けることが大切かと
思っています。
対応できないからといって、子どもの
責任にしてはいけません。
きっかけの与え方が不適切なだけだ
という自覚が必要だと。
要するに勉強不足なだけなんですよ。
その子によって性格も価値観も違う
わけです。
だから、一様な指導・指示はありえない
と思った方が賢明かと思うのです。
そして、大人も粘り強さ、我慢、研究
(勉強)が必要ということですね。
ちなみに、皮肉にも監督が指揮した
1試合目は快勝、自分が指揮した2
試合目は見事なまで完敗でした

でも、子どもたちの”笑顔”と”声の
連係”では、2試合めの方が明らか
に勝っていた・・・。
そんな感じがした、昨日の遠征でした













 と歓声
と歓声 です。
です。







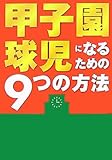









 ”
”