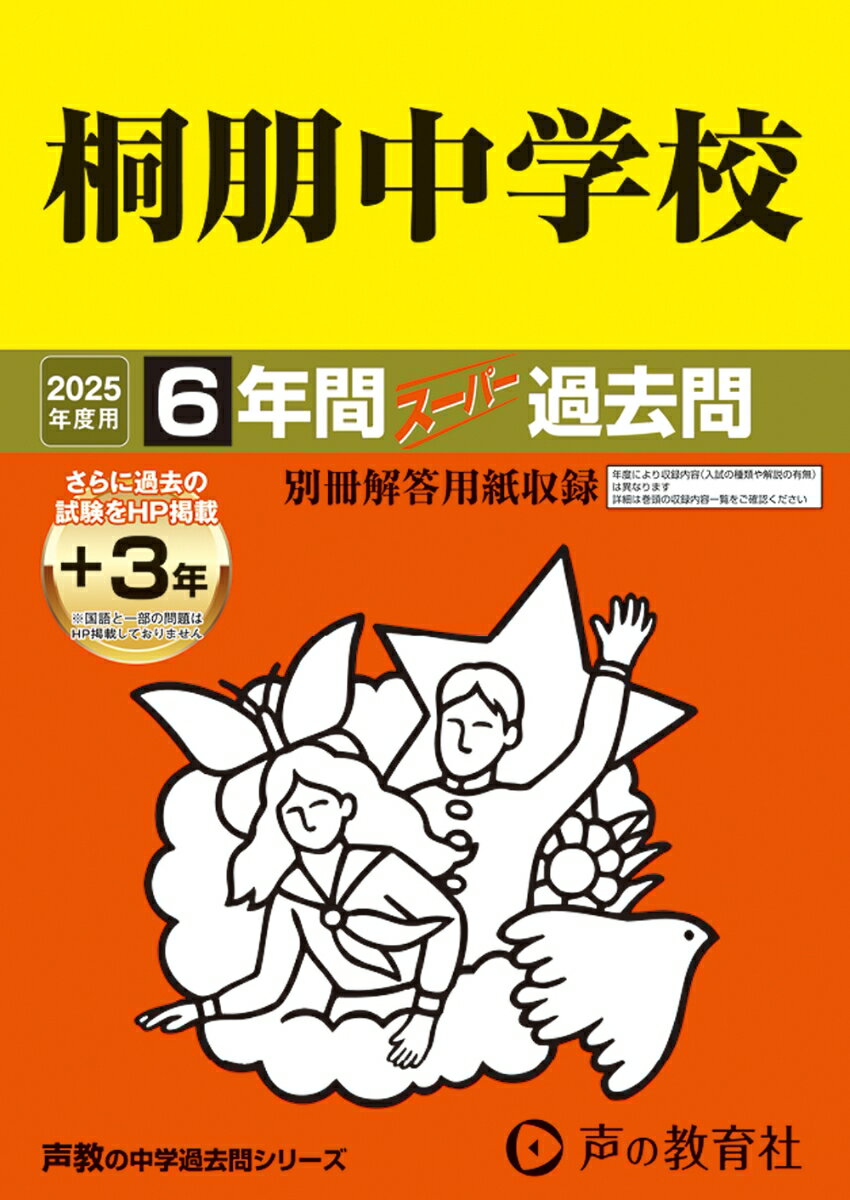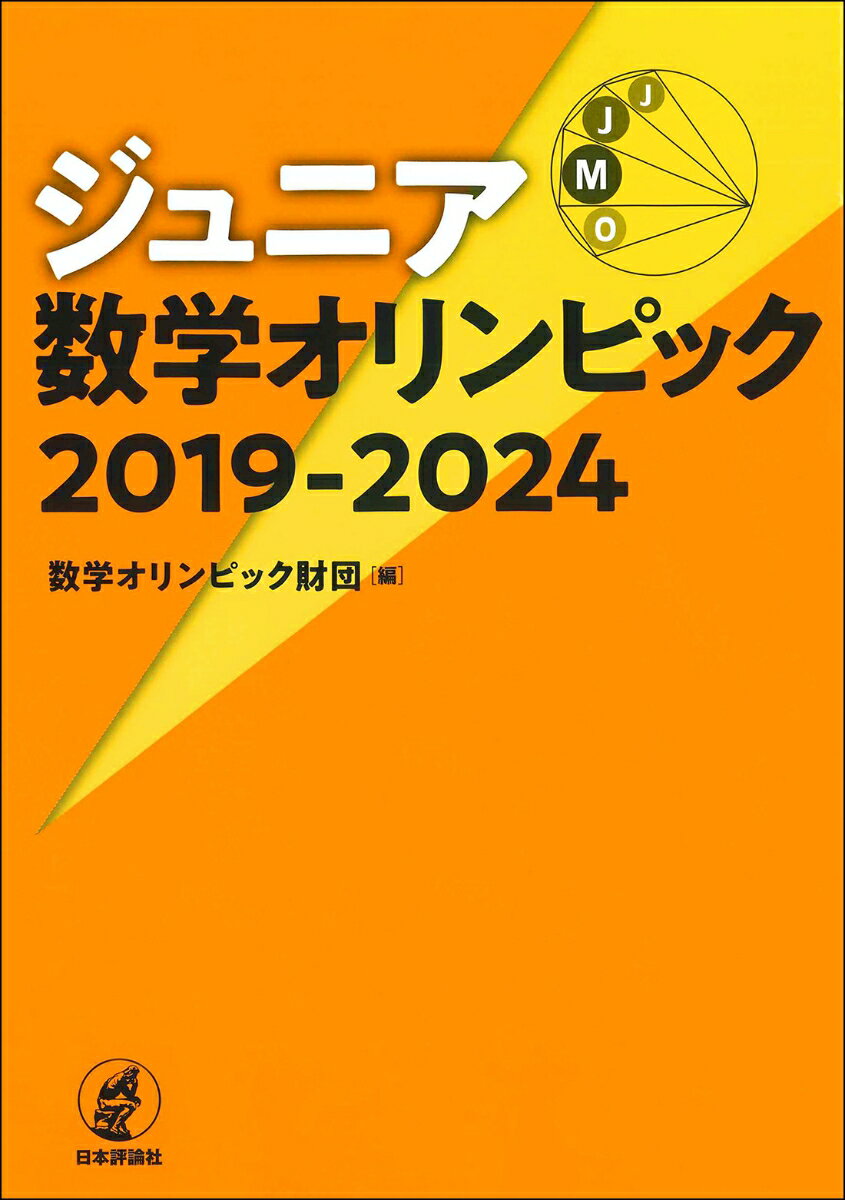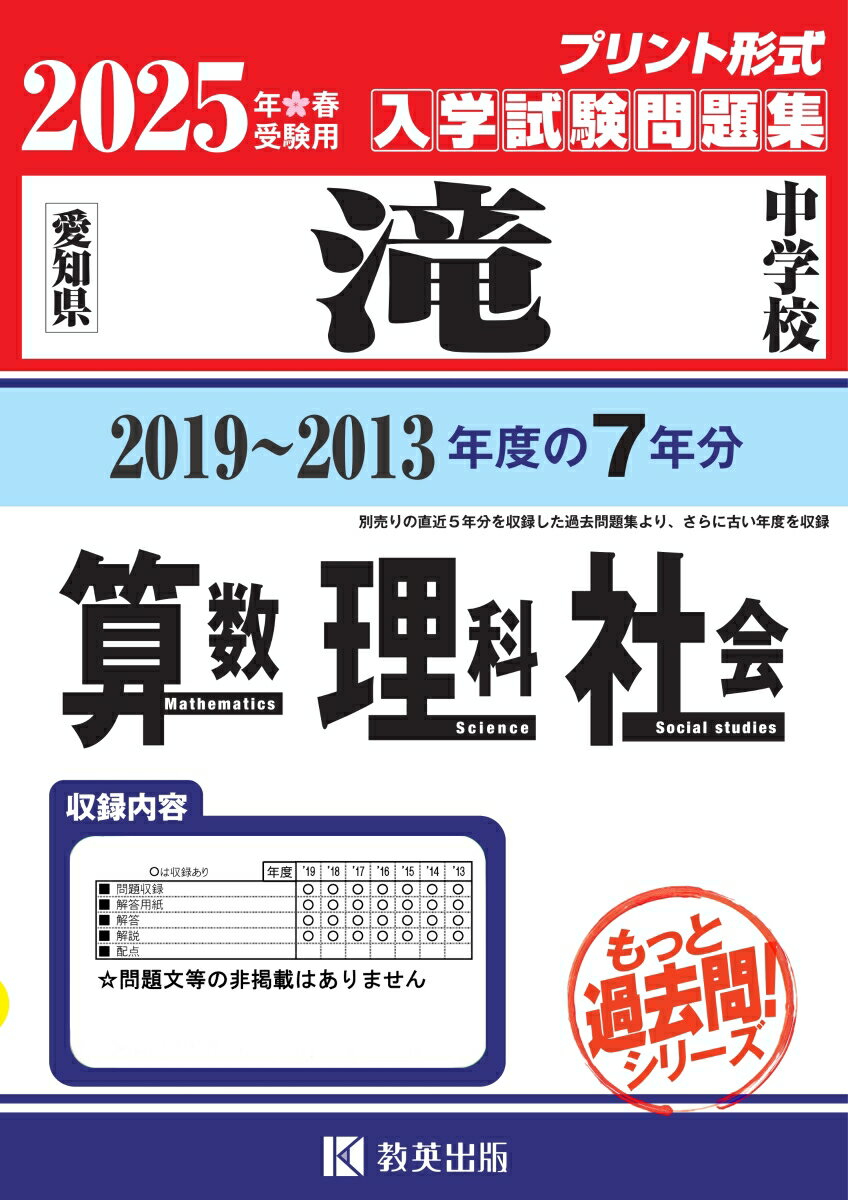次の□にあてはまる数を答えなさい。
(21×21-19×19)÷(1+4/(43×47))-20÷(1+□/(41×49))=21×21-(20×20×20+1)/21
一見すると厄介そうな計算問題ですが、それぞれの掛け算は暗算で計算できる(連続する平方数の差に持ち込む計算手法、〇△×〇□(〇+□=10)の計算手法(小学生でも解ける数学オリンピックの問題(日本数学オリンピック2011年予選第5問)の解答・解説を参照))ものばかりなので、実際にはそれほど面倒な計算はありません。
解説では、途中で消去算の手法を使うことによって、計算を楽にし、逆数に持ち込んで処理しています。
因みに、最難関中学校では、消去算の手法が使える計算問題がよく出されます(開成中学校2022年算数第1問(1)、灘中学校2022年算数1日目第1問など)。
因みに、上で言及した「連続する平方数の差に持ち込む計算手法」というのは、☆×☆と(☆+1)×(☆+1)の差が☆+(☆+1)となること(このことは下のような面積図をイメージすればすぐにわかります)を利用するものです。
例えば、99×99であれば、100×100-(100+99)=9801とできますし、31×31であれば、30×30+(30+31)=961とできますし、46×46であれば、45×45+(45+46)=2116とできます(最後の計算は、45×45=2025を利用しています)。
詳しくは、東大寺学園中学校2021年算数第1問(1)の解答・解説で。