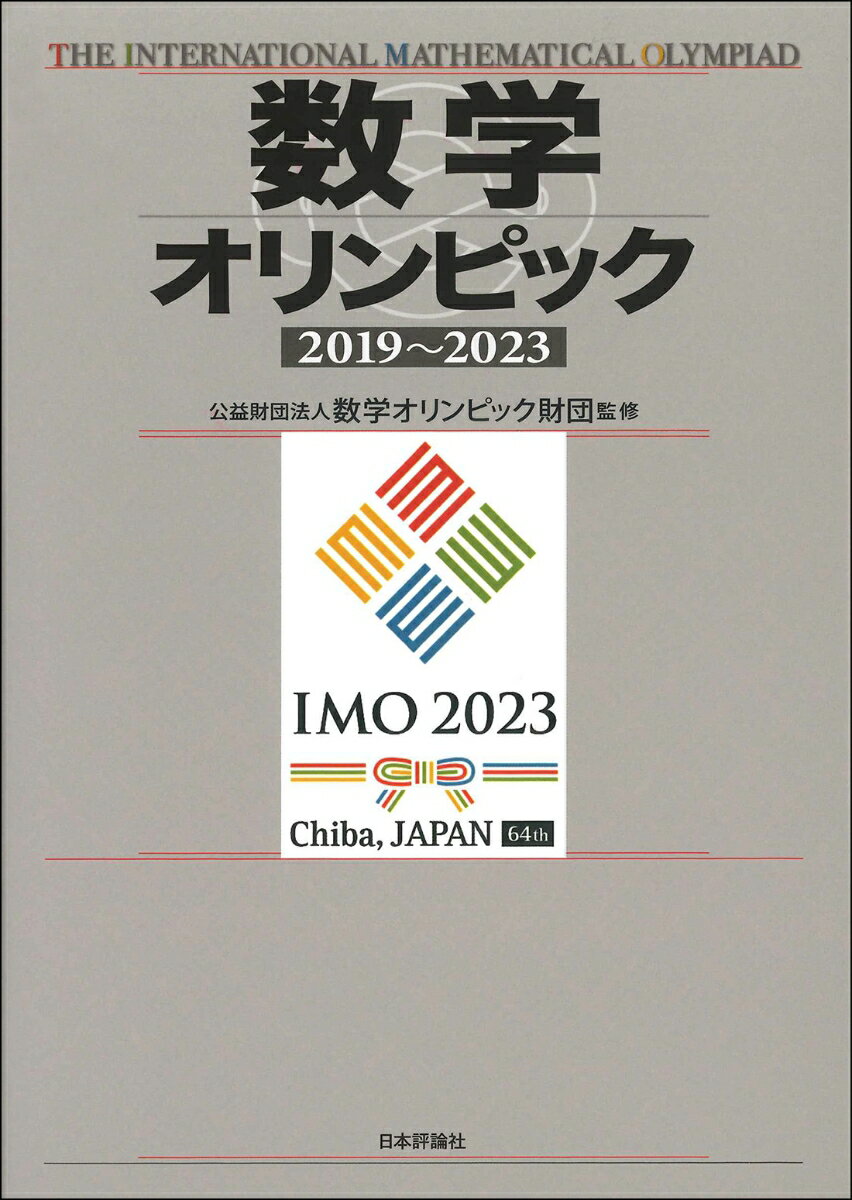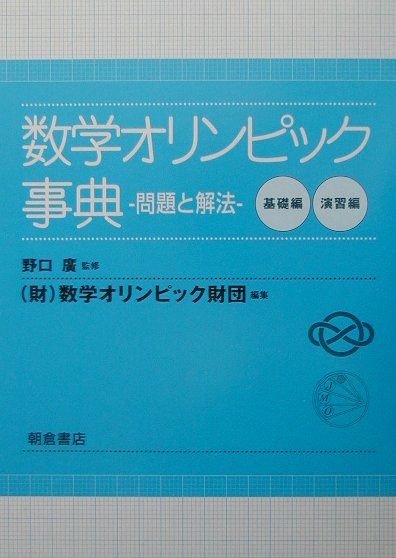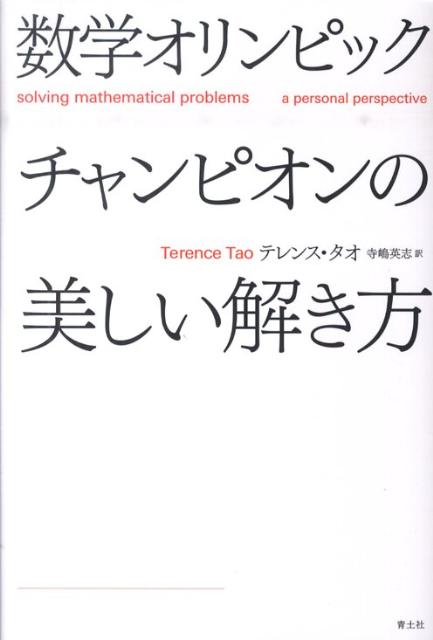今回は、日本数学オリンピック2011年予選第5問を取り上げて解説します。
十の位を求めるのだから、下2桁だけ考えればいいですね。
13×17、23×27、33×37、・・・、93×97の下2桁を考えることになりますが、(参考)で説明した計算の工夫を利用すると、いずれの下2桁も21となることがわかります((参考)の計算が使えるからこそ、小さい順に2個ずつセットにして考えようとするわけです)。
結局、一の位が3または7であるものを小さい順に2個ずつセットにしてかけ算したものを最後にかけあわせてXとすればよいから、21をかけあわせたときの十の位の周期性の問題にすぎないことになります(同じような問題は、中学入試にも出されています(白陵中学校2001年算数1次第4問、六甲学院中学校2023年A算数第3問など))。
X=(13×17)×(23×27)×(33×37)×・・・×(2003×2007)
→Xの十の位=21×21×21×・・・×21の十の位
21の個数は、4桁のデジタル表示(0007~2007)を利用すると、201個とすぐにわかりますね。
あとは21をかけあわせたときの十の位の周期性をチェックしていくだけです。
21
21×21=400+20+21=441→41
21×21×21→41×21=420+441→61
21×21×21×21→61×21=840+441→81
21×21×21×21×21→81×21=1260+441→01
21×21×21×21×21×21→01×21=21
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
となり、21、41、61、81、01の5個の数字の繰り返しとなります。
201÷5=40・・・1だから、Xの下2桁の数は21となり、十の位は2となります。
(参考)2桁の整数〇△×〇□(△+□=10)の計算について
〇×(〇+1)を百の位に配置し、△×□を下2桁に配置したものになります。
例えば、23×27であれば、2×3=6、3×7=21より、621となり、54×56であれば、5×6=30、4×6=24より、3024となります。
面積図を考えて、このことを確認してみます。

紫色の長方形を黄色の長方形のところに移動させると、計算結果は、縦が〇×10、横が(〇+1)×10の長方形の面積(〇×(〇+1)×100)と黄緑色の長方形の面積(△×□)の和となります。
算数オリンピック・ジュニア算数オリンピック・キッズBEE対策ならプロ家庭教師のPTへ
算数オリンピック・ジュニア算数オリンピック・キッズBEE対策のお申込み・ご相談