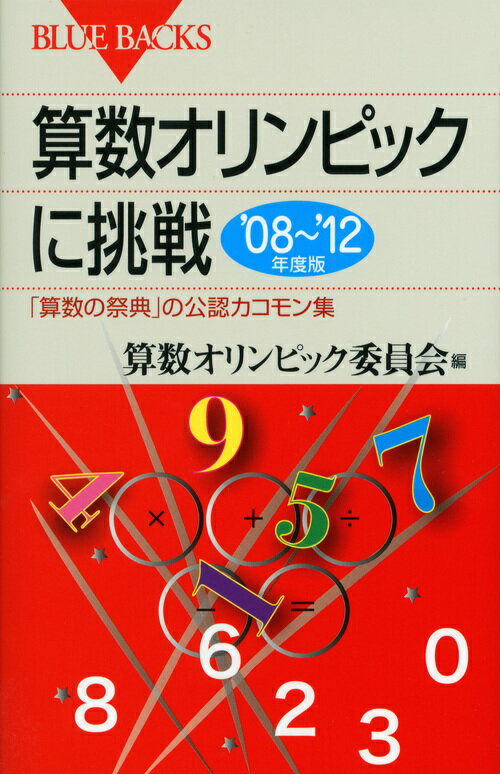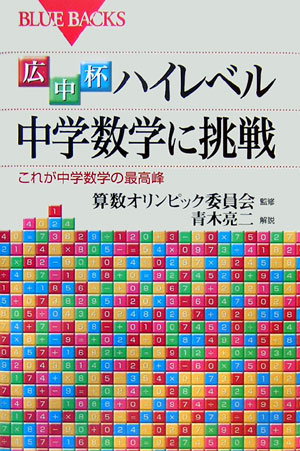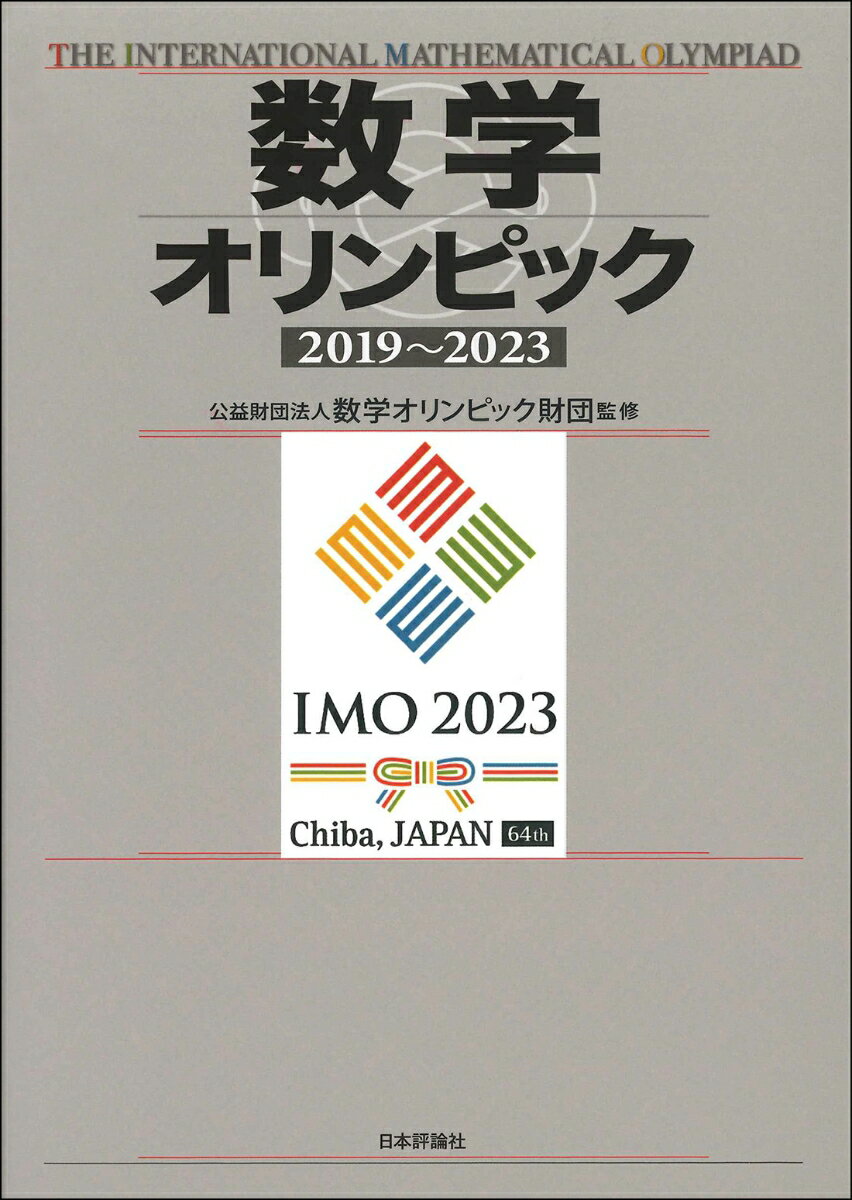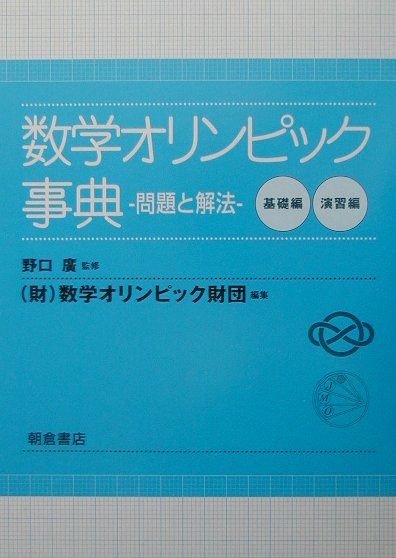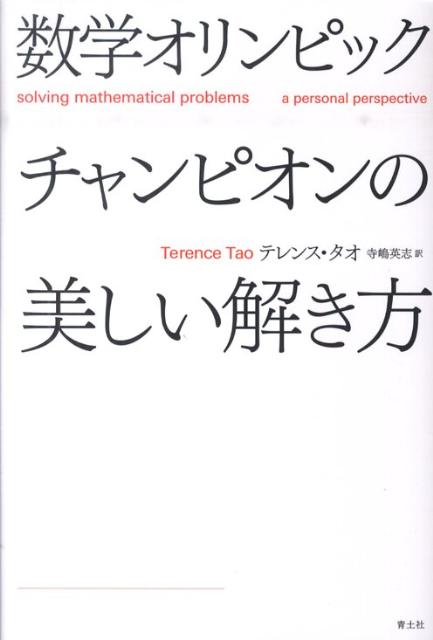日本数学オリンピック(JMO)2025年予選の問題
今回は、日本数学オリンピック2025年予選第2問を取り上げ、解説します。
正のというのは0より大きいということで、abcd、ab、bc、cd、daはそれぞれa×b×c×d、a×b、b×c、c×d、d×aということです。
4つの整数a、b、c、dは条件的に同じですね。
2025=45×45=3×3×3×3×5×5となります。
まず、素因数5(合計2個)の割り振りについて考えます。
素因数5を1つだけ4つの整数a、b、c、dのうちの1つ、例えばaに割り振ると、a×bが平方数であることから、bにも素因数5を奇数個(1個)割り振ることになります。また、b×cが平方数であることから、cにも素因数5を奇数個割り振る必要がありますが、素因数5は2個しかないので、無理ですね。
したがって、素因数5を1つだけ4つの整数a、b、c、dのうちの1つに割り振ることができず、素因数5を2個とも4つの整数a、b、c、dのうちの1つに割り振ることになります。
この場合、素因数5の割り振りについては、平方数の条件をすべて満たしますね。
結局、素因数5の割り振りの仕方については4通りあります。
次に、素因数3(合計4個)の割り振りについて考えます。
素因数3を1つだけ4つの整数a、b、c、dのうちの1つ、例えばaに割り振ると、a×bが平方数であることから、bにも素因数3を奇数個(1個か3個)割り振ることになります。
bに素因数3を1個割り振ると、b×cが平方数であることから、cにも素因数3を奇数個(1個)割り振ることになり、c×dが平方数であることから、dにも素因数3を奇数個(1個)割り振ることになります。
この場合、素因数3の割り振りについては、平方数の条件をすべて満たしますね。
bに素因数3を3個割り振ると、b×cが平方数であることから、cにも素因数3を奇数個割り振る必要がありますが、素因数3は4個しかないので、無理ですね。
説明すると上のようになるのですが、文章で書くのはさすがに面倒なので、以下では、省略します。
同様の議論により、素因数3の割り振りについては、結局のところ、
(あ)1個、1個、1個、1個
(い)2個、2個、0個、0個
(う)4個、0個、0個、0個
の3つの場合があります。
あとは、4つの整数a、b、c、dにどのように割り当てるかを考えるだけです(まず選び出し、次に並べるという場合の数の基本通りの考え方です)。
(あ)の場合
1通りあります。
(い)の場合
4つの整数a、b、c、dのうちどの2つの整数に素因数3を2個割り当てるかを考えればよく、(4×3)/(2×1)=6通りあります。
(う)の場合
4つの整数a、b、c、dのうちどの1つの整数に素因数3を4個割り当てるかを考えればよく、4通りあります。
結局、素因数3の割り振りの仕方については1+6+4=11通りあります。
したがって、正の整数の組(a,b,c,d)は4×11=44通りあります。
因みに、上の解説では、素因数3と5のそれぞれの割り振りについて一応調べていますが、いずれの割り振りについても偶奇が一致するように4つの整数a、b、c、d対して割り振る必要があることはすぐにわかります。
そのことを示しておきます。
a×b、b×cがともに平方数だから、a×b×b×cも平方数となりますが、b×bは平方数だから、a×cも平方数となります。
また、b×c、c×dがともに平方数だから、b×c×c×dも平方数となりますが、c×cは平方数だから、b×dも平方数となります。
結局、4つの整数a、b、c、dのうちどの2つの整数の積も平方数となります。
仮に、4つの整数a、b、c、dのうち、素因数3または5の個数の偶奇が異なるものがあるとすると、その2整数の積は平方数となりえず、矛盾が生じますね。
上の解説では、素因数3と5の個数に着目して解きましたが、(a×b)×(c×d)と(b×c)×(d×a)がともに2025である((a×b)と(c×d)が2025の約数のペアのうちともに平方数となるものとなり、(b×c)と(d×a)も同様となります)ことに着目して解いてもいいでしょう。
中学受験算数プロ家庭教師の生徒募集について
中学受験算数プロ家庭教師のお申込み・ご相談