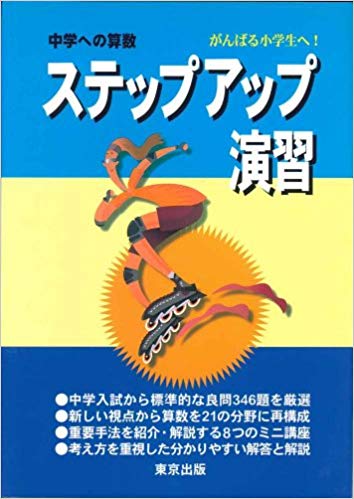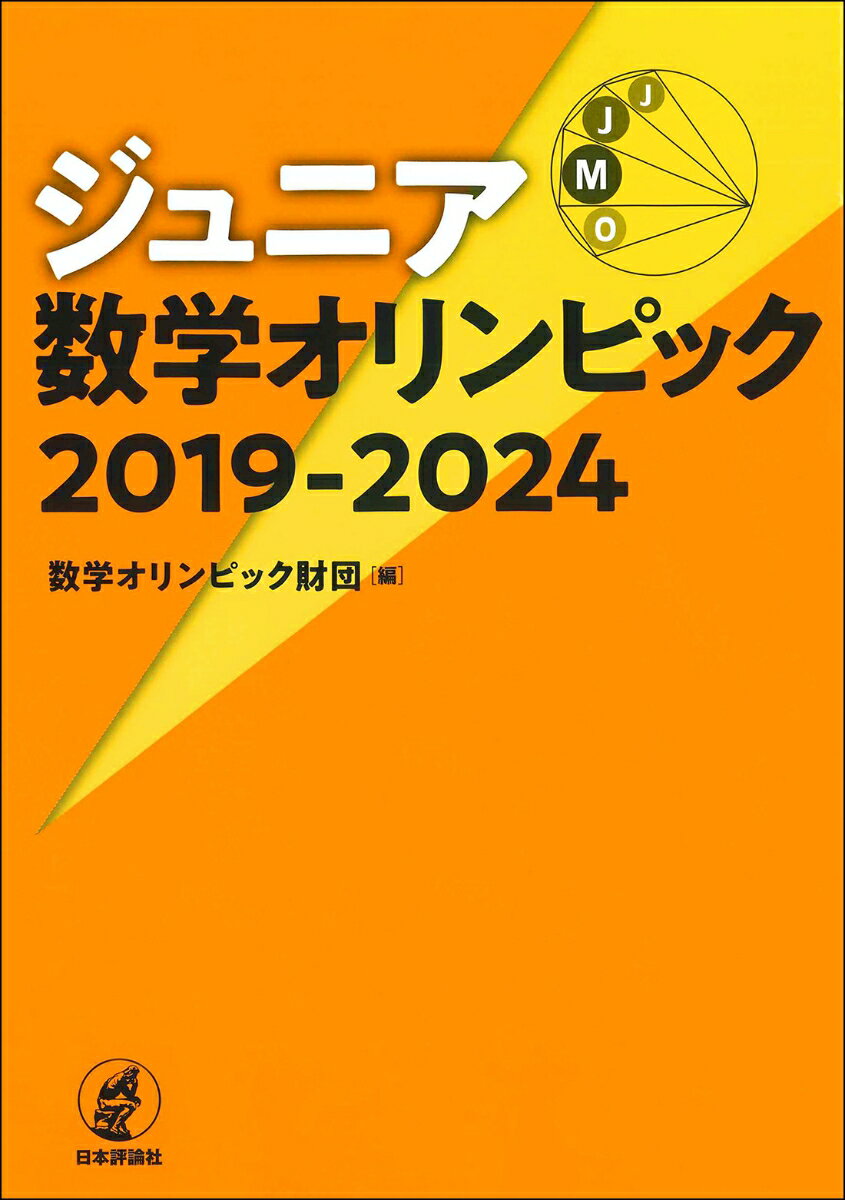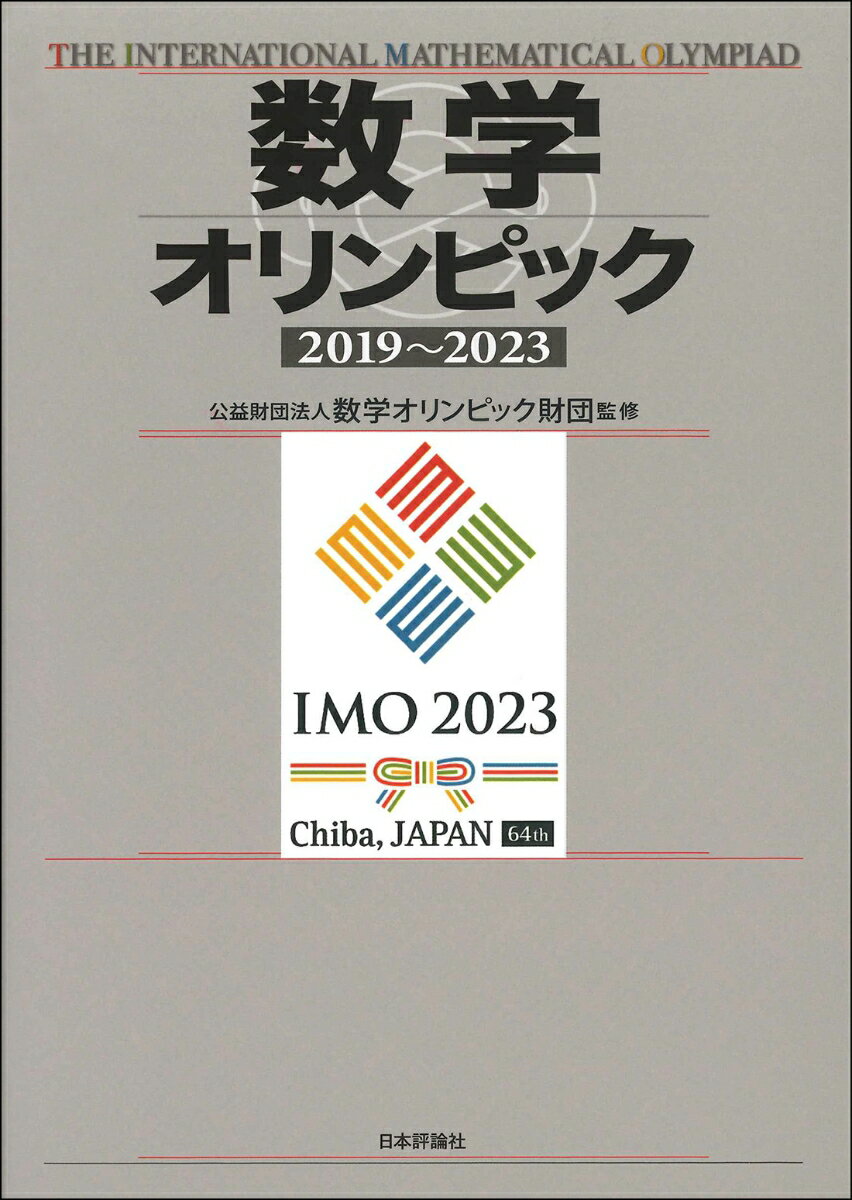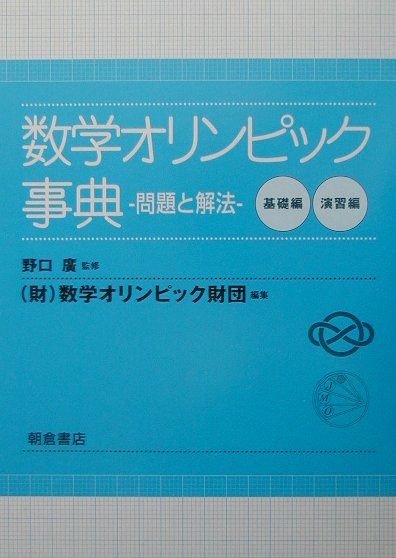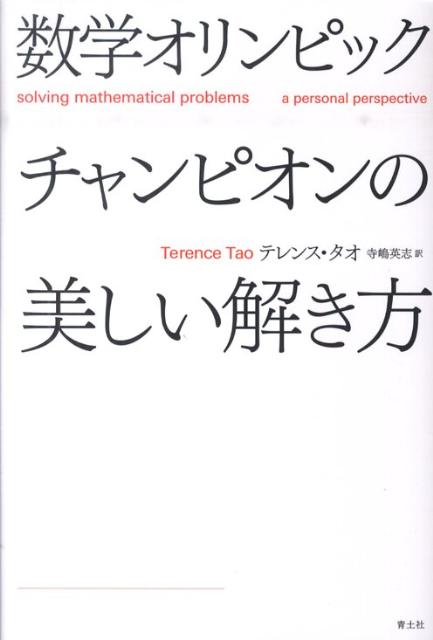3つの分数1935/129、4989/343、8929/593を小さい方から順に並べなさい。
分数の大小比較の問題です。
一見すると面倒そうな問題ですが、実際には面倒な計算は不要です。
3つの分数のうちどの分数に着目するかが最初のポイントとなります。
もっとも、この問題の場合、「何も考えない子」でも偶然うまくいく可能性があります。
「何も考えない子」の場合、分数を出てきた順に処理しますが、この問題の場合、たまたま、最初に出てきた分数に着目すればいいからです。
ただ、そういう子の場合、分数の並びを4989/343、8929/593、1935/129などとされると、まずいことになってしまいます。
きちんと考える子であれば、この並びであっても1935/129にまず着目します。
なお、解説にある大小比較の手法についてしっかり確認しておきましょう。
詳しくは、洛星中学校2016年前期算数第1問(2)の解答・解説で。