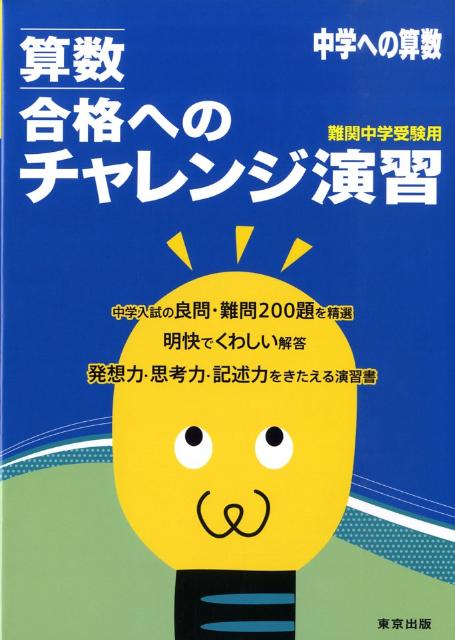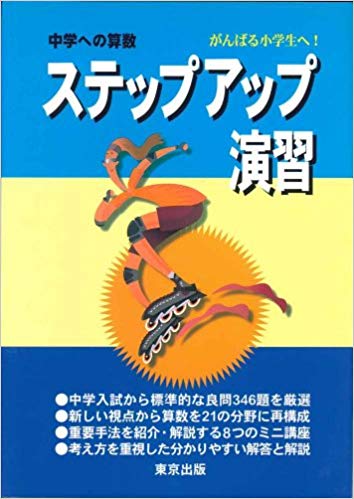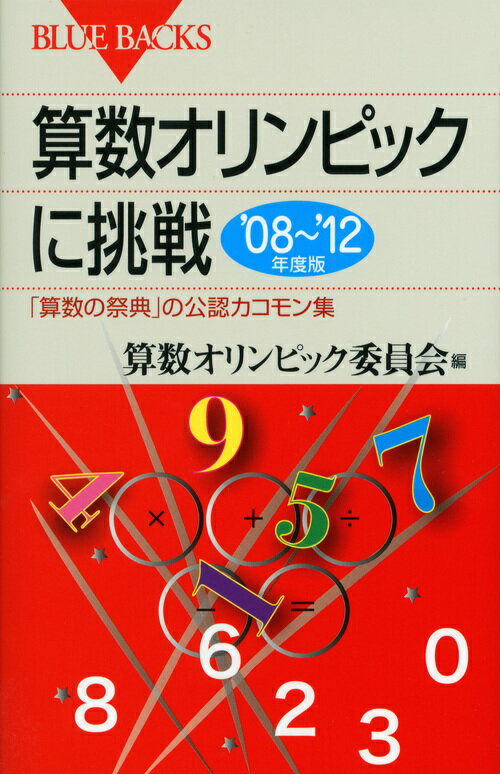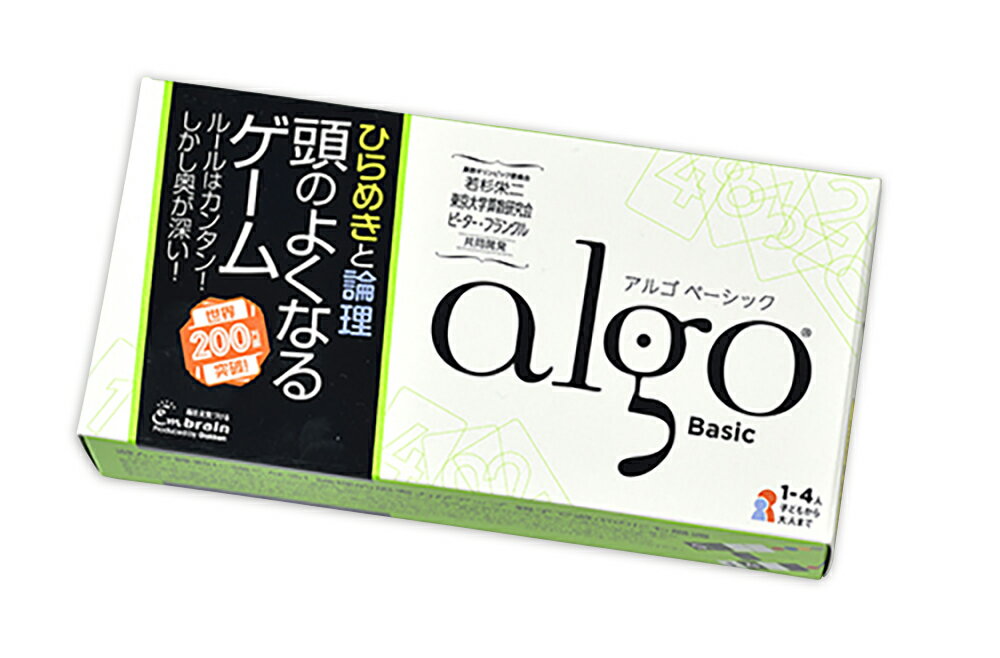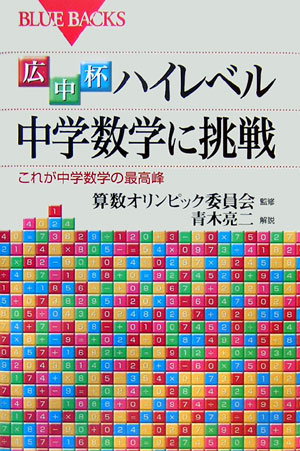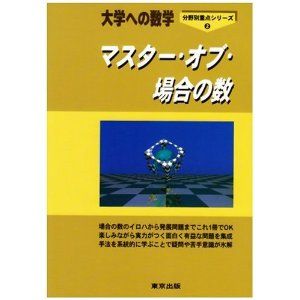いくつかの整数の和と積が等しくなるような数の組を考えます。
[例]和と積がともに8になるような数の組は2通りあり、それぞれの数の小さい順に並べると、
1、1、2、4と1、1、2、2、2
です。
1、1、2、4について調べてみると、
1+1+2+4=8
1×1×2×4=8
です。
1、1、2、2、2について調べてみると、
1+1+2+2+2=8
1×1×2×2×2=8
です。次の問いに答えなさい。
(1)いくつかの整数の和と積がともに12になるような数の組は3通りあります。それらの組をそれぞれ、例のように数の小さい順に並べなさい。答えのみを解答欄に書きなさい。
(2)いくつかの整数の和と積がともに210になるような数の組は全部で何通りありますか。
(3)いくつかの整数の和と
積がともに2310になるような数の組は全部で何通りありますか。
1を使わない積を考えた後、適当に1を加えて和が積と等しくなるようにするのがポイントです。
(1)はウオーミングアップの問題にすぎません。
(2)から本格的な問題になります。
210を素因数分解した後、素因数の割り振りを考えると計算で簡単に解くことができます。
(3)も同じ方針で解くこともできますが、(2)と同じ作業を繰り返しても時間の無駄なので、出題者が用意してくれた解法に乗っかるのがベストでしょう。
詳しくは、下記ページで。
和と積が絡んだ場合の数の問題を紹介しておくので、ぜひ解いてみましょう。