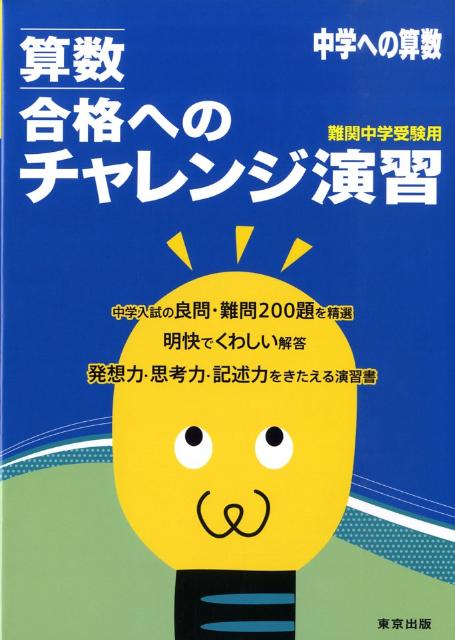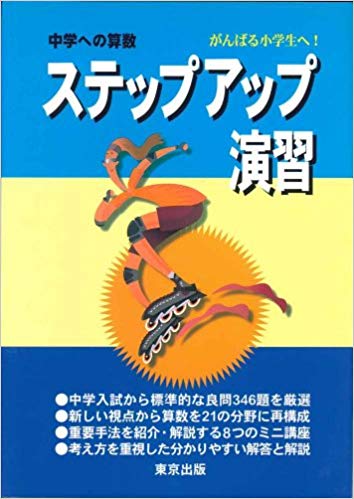直径12cmの円の周上に円周を12等分する点をとります。色のついた部分の面積の和は何cm2ですか。
神戸女学院中学部でほぼ同じ問題が過去に出されています(神戸女学院中学部2018年算数第5問)。
等積変形により2つの部分の面積をくっつけた後、相似比が18cm:12cm=3:2より面積比は(3×3):(2×2)=9:4となるから、女学院の(2)の問題の答えの52.515cm2を4/9倍すると、答え(23.34cm2)が得られます(ちゃんとした解き方は解説ページを参照)。
関西の某大手塾に通う生徒が復テでずっとこんな解き方をしていました。
記憶力のいい子でテキストの問題を解いたら答えを覚えてしまっていたので、数値を変更しただけの手抜き問題のオンパレードのテストでまともに解くのが馬鹿らしかったのでしょうね。
もちろんまともに解くこともできていましたが、程度の低いものに対してそれにふさわしいやり方をしていたわけです。
昔の大学入試センター試験の数学の問題などはまともに解くのがばかばかしいものが多かったので、できる子はまともに解けるけど適当に片付けるという感じでしたからね。
それと同じことです。
今の大学入試共通テストの数学は違う意味でまともに解いたらばかばかしいですが・・・
さて、話を元に戻します。
女学院の問題では、(1)を利用して和差算に持ち込んで解いていますが、ここでは別の解法を紹介します。
等積移動により2つの部分の面積をくっつけます(直径(ピンク色の太線)に関して折り返すイメージです)。
曲線上の点と円の中心を結びます。
三角定規(正三角形の半分のもの)の辺の比を利用すると、長さは図のようになります。
色のついた部分の面積
=(水色+黄色)+(黄緑色+紫色)-(紫色+黄色)
=6×6×3.14×1/6+3×6×1/2-3×3×1/2
=18.84+4.5
=23.34cm2
となります。