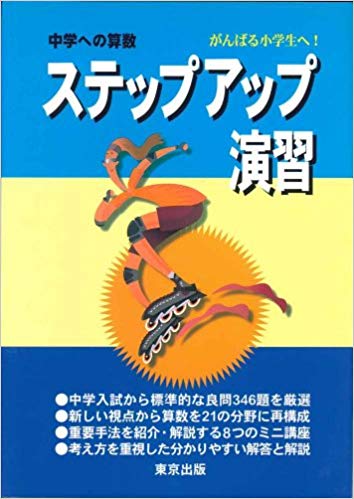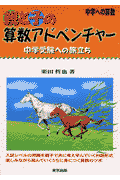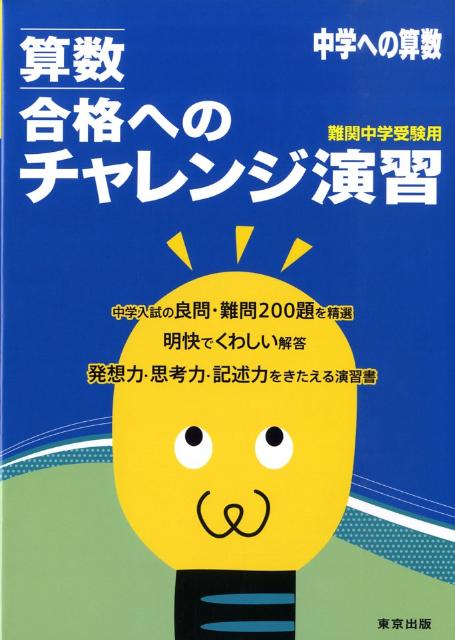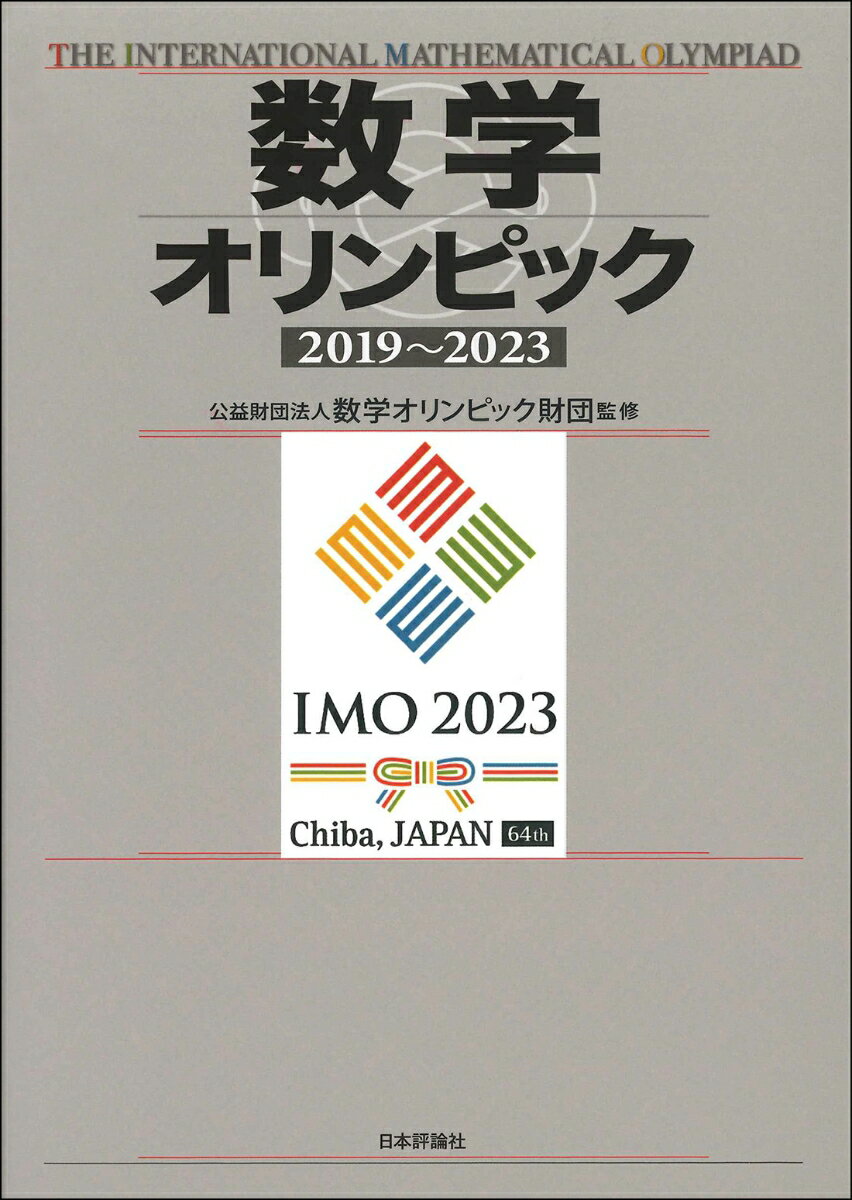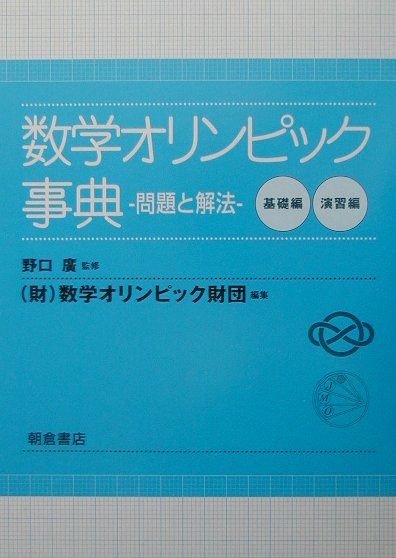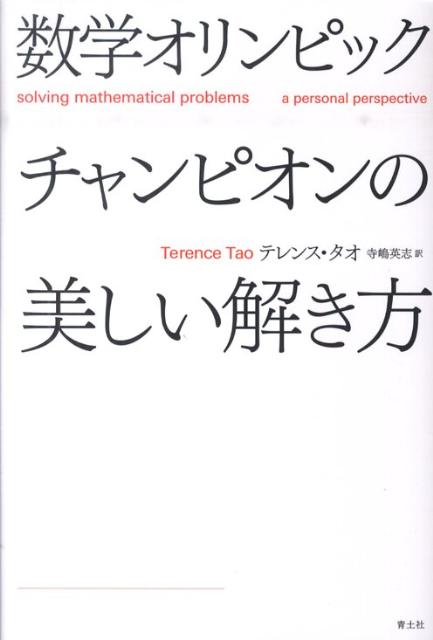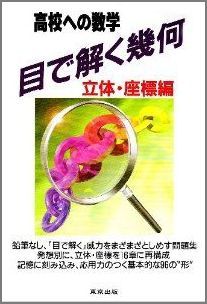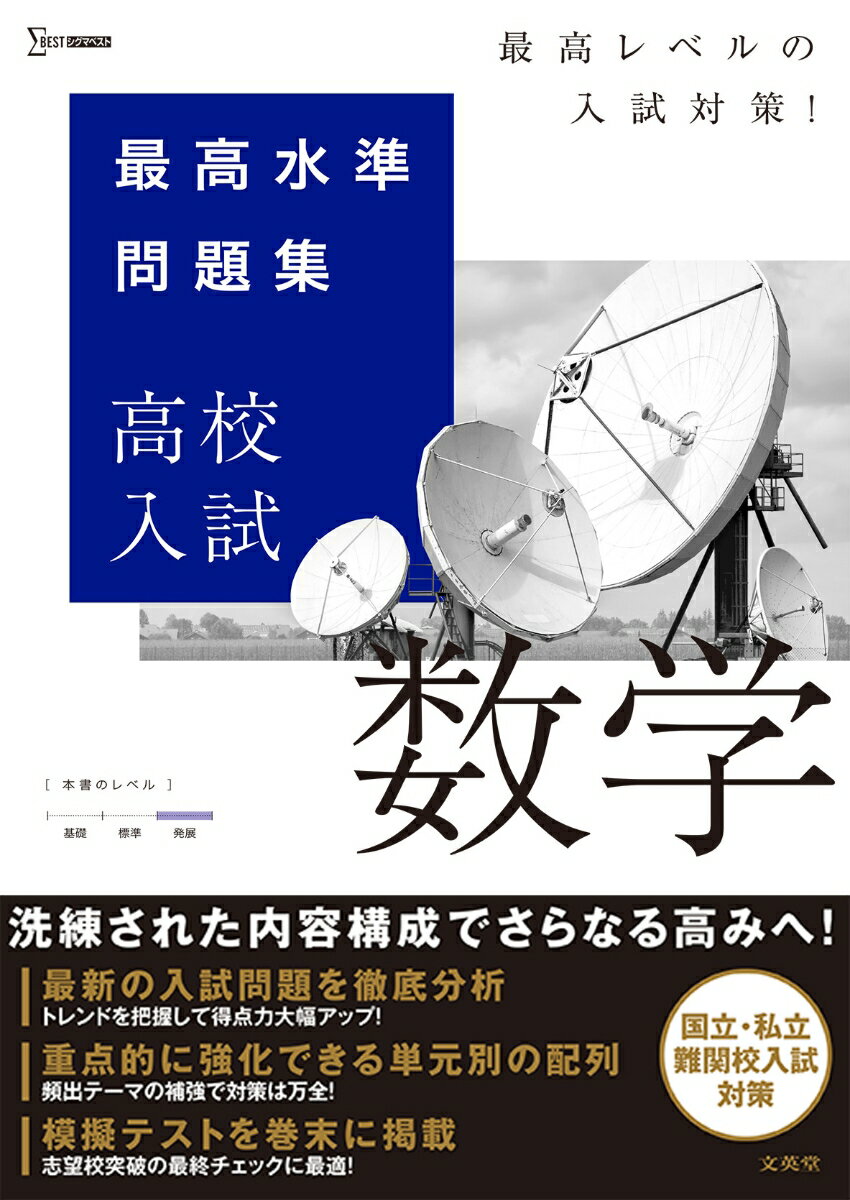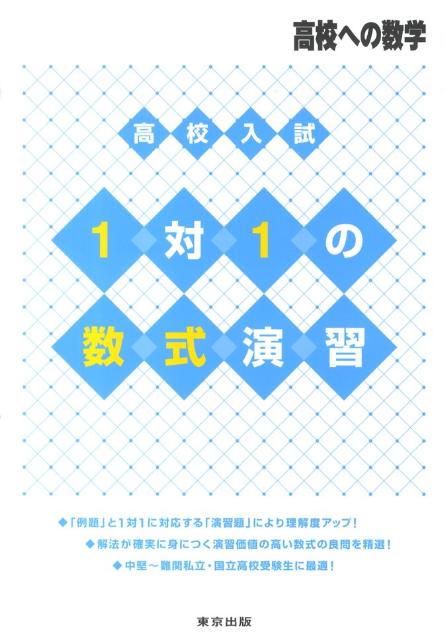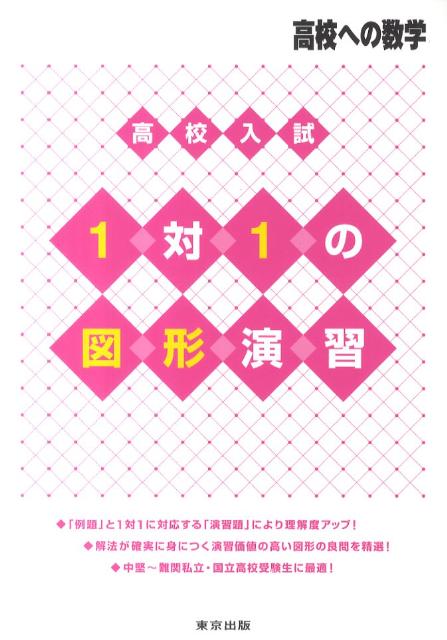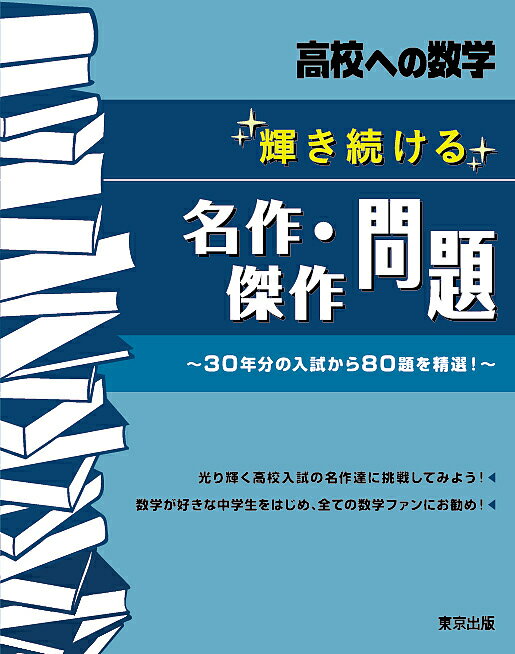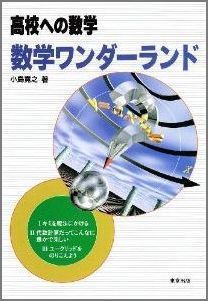日本ジュニア数学オリンピック(JJMO)2017年予選の問題
今回は日本ジュニア数学オリンピック(JJMO)2017年予選第7問を取り上げます。
「正の」というのは0より大きいということで、「2P(n)」は2×P(n)ということです。
倍数判定法をうまく利用すれば、小学生でも解ける問題です。
中学入試で出される条件不足のつるかめ算の問題の処理(神戸女学院中学部2009年算数第2問、武蔵中学校2009年算数第3問、神戸女学院中学部2014年算数第1問、渋谷教育学園幕張中学校2018年1次算数第2問などの解答・解説を参照)と同じような感じですからね。
nの百の位の数を〇、十の位の数を□、一の位の数を△(〇は1以上9以下の整数、□と△は0以上9以下の整数)とします。
与えられた条件から、
〇×100+□×10+△×1=2×〇×□×△+27
となります。
2×〇×□×△+27は奇数だから、△も奇数となります。
(あ)△=1のとき
2×〇×□×△+27
=2×〇×□×1+27
≦2×9×9×1+27(上限チェック!(以下同様))
=189
だから、〇は1となります。
このとき、2×〇×□×△+27=2×1×□×1+27≦2×1×9×1+27=45<100となり、条件を満たしませんね。
(い)△=3のとき
2×〇×□×△+27
=2×〇×□×3+27
≦2×9×9×3+27
=513
だから、〇は1~5のいずれかの数となり、さらに、
2×〇×□×3+27
≦2×5×9×3+27
=297
となるから、〇は1か2となり、さらにまた、
2×〇×□×3+27
≦2×2×9×3+27
=135
となり、〇は1となります。
このとき、2×〇×□×△+27=2×1×□×3+27≦2×1×9×3+27=81<100となり、条件を満たしませんね。
(う)△=5のとき
2×〇×□×△+27=2×〇×□×5+27の一の位の数が7となり、この場合はありえませんね。
(え)△=7のとき
2×9×9×7が1000を超えてしまうので、上限チェックをしても何の意味もないですね。
そこで、与えられた条件から得られる式をよく観察します。
〇×100+□×10+7×1=2×〇×□×7+27
〇×100+□×10=2×〇×□×7+20
〇×100、□×10、20はいずれも5の倍数だから、2×〇×□×7も5の倍数となり、(2と7は5と互いに素だから、)〇か□が5の倍数、つまり5となります。
〇=5のとき
5×100+□×10=2×5×□×7+20
480=□×60
□=8
このとき、n=587となります。
□=5のとき
〇×100+5×10=2×〇×5×7+20
〇×100+50=〇×70+20
となり、左辺が右辺より大きくなることが明らかだから、この場合はありえませんね。
(お)△=9のとき
〇×100+□×10+9×1=2×〇×□×9+27
n(2×〇×□×9+27)が9の倍数だから、nの各位の数の和(〇+□+9)は9の倍数となり、〇+□=9か18となります。
〇+□=9のとき
〇×90+(〇+□)×10+9=2×〇×□×9+27(分配法則の逆を利用しました。)
〇×90+9×10+9=2×〇×□×9+27
〇×10+10+1=2×〇×□+3(式全体を1/9倍しました。)
〇×10+8=2×〇×□
〇×5+4=〇×□(式全体を1/2倍しました。)
4=〇×□ー〇×5
4=〇×(□ー5)(分配法則の逆を利用しました。)
〇と□ー5は4の約数のペアで、その和が9-5=4となるから、〇=2、□ー5=2となります。
このとき、n=279となります。
〇+□=18のとき
〇=□=9となりますが、2×9×9×9+27>1000となり、条件を満たしませんね。
(あ)~(お)より、答えは587と279となります。
算数オリンピック・ジュニア算数オリンピック・キッズBEE対策ならプロ家庭教師のPTへ
算数オリンピック・ジュニア算数オリンピック・キッズBEE対策のお申込み・ご相談