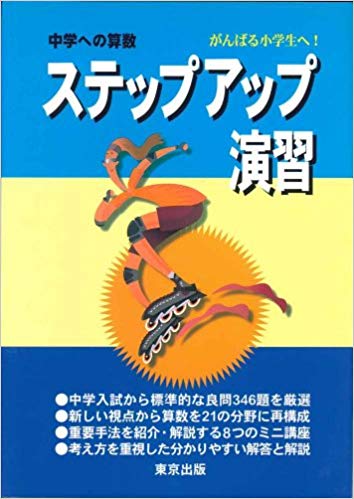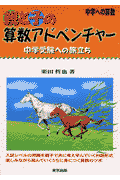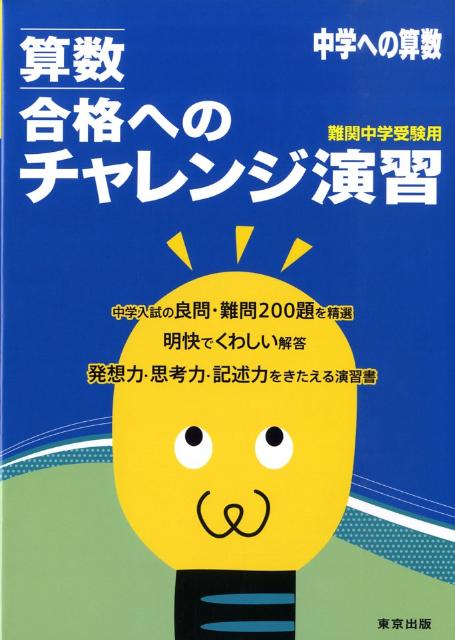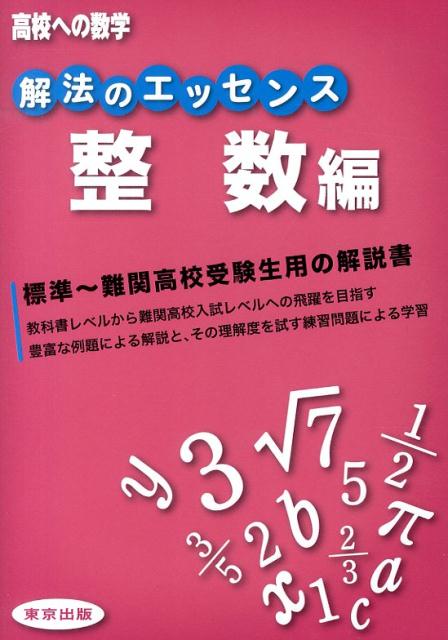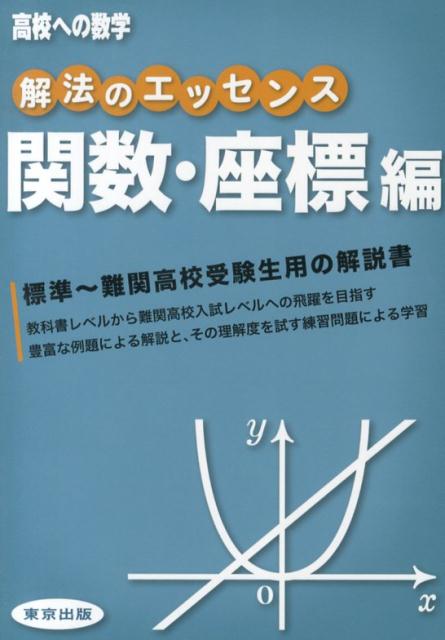図においてAB=3、AC=2、直線AEは∠BACの二等分線であり、AE⊥BEである。点Dは直線AEとBCの交点である。
(ⅰ)線分の長さの比AD:DEを求めよ。
(ⅱ)面積の比△ADC:△BEDを求めよ。

(注)
直線AEは∠BACの二等分線→直線AEが角BACの大きさを2等分するということです(図の2つの〇を見ればわかることですね)。
⊥→垂直
灘中学校や東海中学校など、レベルの高い平面図形の問題を出す中学校の受験生を教えるときに取り扱う問題の1つです。
直角三角形を2つ組み合わせて二等辺三角形を作り出す解法のマスターにちょうどいいですし、解説で紹介した2つの解法を確認すれば、いわゆる隣辺比、ベンツ切り、等高図形の面積比の確認ができますからね。
行き掛けの駄賃として、角の二等分線定理も確認できるので、この1問を通じて様々なことを学ぶことができます。
こういう学習は、志望校対策で過去問を取り扱う際にも大切なことです。
単に過去問を解いて、解けたとか解けなかったとか確認するだけでは不十分です。
すでに実力が完成してほぼ満点を取れるのであれば、時間を短縮して過去問に取り組み、解けなかった問題の解法等を確認する勉強でもいいでしょうが、そうでなければ、こんな学習をしても本当の実力はつきません。
過去問を学ぶのではなく、過去問で(様々なことを)学ぶことが肝要です。
詳しくは、下記ページで。
ラ・サール高等学校2010年数学第2問(2)(問題)
ラ・サール高等学校2010年数学第2問(2)(解答・解説)
中学受験算数プロ家庭教師の生徒募集について
中学受験算数プロ家庭教師のお申込み・ご相談