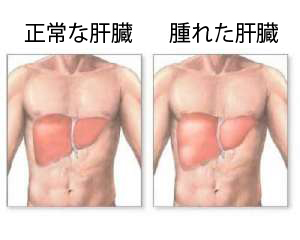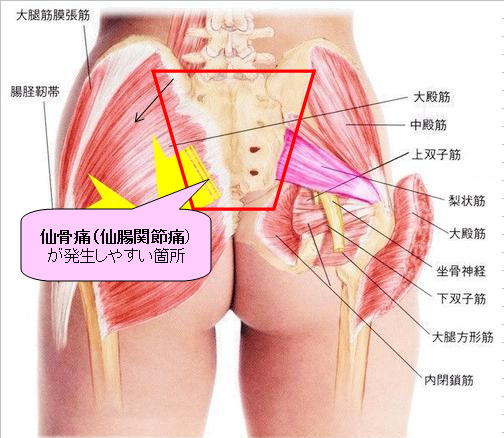長年の姿勢の悪さ(ストレートネック、猫背等)の結果、肋間筋の正面は縮まり、背面が広がる。
体軸が背骨より前に出てしまう結果でもあるけど、これを呼吸を意識に上げることで調整する。
わかりやすくは、
吐くことを強く意識し、背中をギューと収縮させる。
その際に胸は収縮させずに弛緩させる。むしろ肋骨を広げる意識。
肋間筋をメインとして収縮させる。
が、他の呼吸筋も限界まで使う。
■強制呼気筋(息を吐くときに使う筋肉)
・内肋間筋(横・後部)
・内腹斜筋
・外腹斜筋
・腹直筋
・腹横筋(補助筋)
・肋下筋(補助筋)
・胸横筋(補助筋)
・腰方形筋(補助筋)
・広背筋(補助筋)
そうすることで肋椎関節が大きく弛み、肋骨の可動域が拡張します。
背面の拘束が取れ、連動して腰の拘束も取れてきます。
==============
というのはおさらい(((uдu*)
昨日やっていたのは、
副腎まわり(第11,12肋骨まわり)の矯正呼吸(収縮)により、アドレナリン分泌をコントロールできるかどうかの実験。
背中のゾワゾワを感じ取れるかどうか(((uдu*)
以前も何度か書いてます。
【やる気スイッチ発見】アドレナリンコントロール
アドレナリンのプラス効果として
・お腹が空かない
・脂肪燃焼の促進(脂肪分解酵素:リパーゼの活性化)
・集中力のUP(興奮も増す)
・血行促進、脳内の酸素が増えて注意力が向上する
・筋肉内の血流が増え、爆発的な筋出力を発揮(火事場の馬鹿力)
※火事場の馬鹿力に関しては、オステオカルシンであるという説が濃厚ですが。
アドレナリンのデメリット
・副腎疲労を招く
・使わないと糖化の原因になる(肌荒れ、血管や骨が脆くなど)
・免疫力の低下
・消化機能の低下
・血圧の上昇、不眠
・中毒性がある
・イライラする、攻撃的な性格になる
・ビタミンの著しい消費(肉体の酸化)
昨日はやりすぎて、極度の疲労と眠気が生じました(◎_◎;)
弛めて回復させるということも同様に大事なことです。
弛めると言えばこれ。エプソムソルト。
 【Amazon.co.jp 限定】エプソムソルト 2.2kg イランイランの香り ビタミンC配合 計量スプーン付
【Amazon.co.jp 限定】エプソムソルト 2.2kg イランイランの香り ビタミンC配合 計量スプーン付
肉体の酸化に対して、電子を還元することが出来ます。
マグネシウムサプリもお勧めです。
 [海外直送品] ナウフーズ マグネシウムカップス 400mg 180カプセル
[海外直送品] ナウフーズ マグネシウムカップス 400mg 180カプセル
==================
【頭蓋骨改造問題】
ということを経て、姿勢が完全体になってくると、頸椎と頭蓋骨のバランスが正常化していまいます。
全然問題ではないのですが、背骨と頭蓋骨のバランスが正常化するということは、下図のように大きく顔のバランスが変わります。

※過去記事 首の付け根の認識と顔の大きさ
絶壁は無くなり、目線は斜め上を見ていた状態から正面へ変わり、眼筋が弛んだり、髪型を変えざるを得ないほどに角度が調整されます。
小顔になってしまう!ということではあるのですが、その際に22個の頭蓋骨の調整が必要になります。
勝手に調整されるとも思いますが、性格的にそれを許せないというのが問題(/ω\)
頭蓋骨調整の知識がないというのが問題なのです(((uдu*)w
ということで、(全集中の)呼吸の次は頭蓋骨のバランス、組み合わせ等を調整するという線が濃厚です(`・ω・´)
とはいえ、まだまだ肺が弱っちいので引き続き、いや多分生涯呼吸については常中を続けていくことになるでしょう(((uдu*)
なんらかの柱になりたいな\( 'ω')/