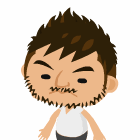
桜木町、
山上絋生氏の棒、オーケストラ・ラルゴ公演、済む、演目はドビュッシー《小スート》、マスネ《アルザスの風景》、っそしてサン=サーンス《オルガン》である、
午前は南千住で知己トロムボーン奏者さんのご指導なすっている高専の吹奏楽部の公演を聴いてくる、新入部員数名によって前回よりもパートが増えており、音色の幅も広がったようである、
山上氏は恆のとおり手堅い仕事ぶりでいられ、オケもまずまず、ルーシーとの相性もよかった、
桜木町への移動は急ぐ必要がなく、南千住でさいしょの乾杯には顔を出し、小1時間ほどいて中座す、っいま、っもうまもなく戻る、
っあすの旗日は、平林遼氏の公演で、マーラー《復活》である、
みずの自作アルヒーフ
《襷 ータスキー》(全4回)
https://ameblo.jp/marche-dt-cs4/entry-12351779591.html(第1回配本)
《ぶきっちょ》(全4回)
https://ameblo.jp/marche-dt-cs4/entry-12351806009.html(第1回配本)
《きりむすぶ》(執筆中・脱稿時期未定)
https://ameblo.jp/marche-dt-cs4/entry-12935343873.html(第1回配本)
ギロッポン2日目、
コバケンさんの日本フィルとの公演、済む、演目は、千葉清加、安達真理両女史のソロでモーツァルト《シンフォニア・コンチェルタンテ》、シベリウス《2番》である、午前のみ仕事をしてから出向く、
っきょうは、来年に2度もある井﨑正浩氏のマーラー《復活》の、っまず1団体目の公演の切符発売日で、音場はここサントリーであるが、ネット上では席を撰べない販売方法で、何度もペイジをリロードして申し込みをくりかえしてみたが、SもAも1階のおなじような席っきり当たらず、っよっぽどもうそれで妥協せむかとおもうが、待てよ、これからサントリーへ往くんだ、窓口では席を撰べるかもしらん、っとおもい直し、来てうかがうに、っちゃんと撰べて、っよろしくRCの前方を得るに及んだ、電話でも受け附けているのだろうか、っはじめから電話をしておけばもっと早くに安堵しえたかもしれない、っが、っぼくは電話をするのがいやな人で、仕事の連絡もメイルで済むのなら社外の方を相手にもそうし勝ちだし、っだいいち、っいまどきどんな小さな箱の映画館とかでもネット上で席を撰んで購えるのがあたりまえだというのに、枚数を選択しうるっきりで、席はぜんぜん撰べやしないなどという販売方法を採らないでくれたいものだ、っこの楽団は、前回はテケトというサイトで切符を売られていて、っそれがとても利用し易いので、っこんかいもそこで売ってくれたらよかったものを、
っさてきょうは、ってっきり2階の後方の席が取ってあるのかと早合点しており、っそれだと、RCやLCに聴く音量や音圧をただ水で割って薄めたような音響となってしまうので、往く前から一寸つまらないなあとおもっていたが、券面を見ると、っそうではなく、舞台を左っ肩から見下ろす位置であった、2階のSで良位置が得られないのならば、っそこより後方へ下がるよりも、相当度に偏った位置になるとしても、っむしろ舞台へ近附かむとするほうがよい、正面から聴けば、管打は絃で作る分厚いカーテンの向こう側で鳴るのだが、っきょうのような位置ならば、っいわばカーテンの裏側を覗く格好である、
っただ、っきょうの演目、奏楽の性格としてはどうだろうなあ、っあまり好条件とはしえなかった、っまずモーツァルトのソロおふたりは、っこちとら彼女等の背中側から聴いているので、っゆうべからすればだいぶん音像が不明瞭となり、殊にVaについては、え、いまそれどんな節を弾かれているんですか、っとおもわされる個所がしばしばあった、
大勢で弾くオケの音はその点、四方へ拡散するため、っまだしも快く、っゆうべより近い位置から聴いていることのたのしさもあった、シベリウス冒頭の木管など、目も覚めるばかりフレッシュに届き、っおもわずにうきうきとする、2楽章再現のオットー氏のラッパ・ソロは、全体をおおきなレガートで繫がれてはいるが、っよく聴くと、……たーら・たーらったー……、っとほんのかすかにフレイズをぷつぷつ切っていられるのがわかった、記譜のアルティキュレイションがどうなっているのかは識らない、
っいけなかったのはフィナーレか、っはじめの絃へ応えるトロムペット連とホルン連とのファンファールのうち、前者は、コバケンさんとしてはその音量にご不満のようで、提示の際には、彼等が吹かれる途端に手をぶらぶらさせて、や、もっと吹いてよもっと、っというふう、っにも拘わらず再現でもやはり音量が足らず、コバケンさんはまたおなじように、もっともっとっ、っというアクションをされていた、ったしかにぼくが聴いてもわずかに強勢に不足したようにおもうが、っゆうべも云うように、全曲に亙って遠大なる造形が達成せられているなかで、っこの上、金管の刺戟的の突出はなくもがなである、っところが信末氏以下ホルン連は、提示の時点ですでにしてかなりの咆哮、コバケンさんは親指と人差し指とで輪っかを作って、いいよっ、っというサインを送られていたが、っぼくにすれば、や、すこしく吹きすぎだとおもうがなあ、、、っというところ、っそして、っこちとらわるい予感がしながら再現が訪れるところ、っそこでは完全に臨界を振り切って彼等4人のみで他のすべての声部を塗り潰さむばかりの大絶叫、っまたぼくが、彼等の朝顔朝顔がこちとらへ向いている位置へ坐しており、っそれが余計にいけなかったかもしれない、っあれでRCあたりではどのように聴こえていただろうか、
っそれと、ティムパニも左側後方へおり、っやはりぼくに近かったのだが、っこれも同様、個所によっては、そこまでぼかすか打たないでよ、っとおもわせただろうか、
っさようにぜんぜん音響条件が違ったので判断に窮するが、演奏の仕上がりぐあいとしてはどうだろう、2日間でほぼ同水準であったのかと察せらる、っあらためて、サントリーはRCにかぎるとおもわずにいない、
っいままだ器の裏っ手へ立ち盡しているが、っこれからまた、桜田門から宮城へ首を垂れて有楽町まで歩き、っお高くとまった王将で食事をし、何軒か隣の喫煙スペイスを利用してから帰る、
っあすは、午后に桜木町で山上絋生氏の公演のみかとおもっていたが、知己トロムボーン奏者さんからご連絡をいただき、っこないだも伺ったご指導されている高専のささやかな吹奏楽部さんの公演がおありというので、っそれは午前であり、っぼくは聴いたあと横浜へ梯子、奏者さんは公演後、前回も他の来訪者さんとともにけっきょくよるまで呑んでいられて、っこんかいも同様なら、っご迷惑でなければ桜木町から取って返して呑み会へ途中参加しますと返信しておいたところ、その時間だとおそらく2軒目へ移動しているが、お待ちしています、っとのことで、忙しい休日になりそうだ、っで、っそのつぎの旗日もまた公演ね、
みずの自作アルヒーフ
《襷 ータスキー》(全4回)
https://ameblo.jp/marche-dt-cs4/entry-12351779591.html(第1回配本)
《ぶきっちょ》(全4回)
https://ameblo.jp/marche-dt-cs4/entry-12351806009.html(第1回配本)
《きりむすぶ》(執筆中・脱稿時期未定)
https://ameblo.jp/marche-dt-cs4/entry-12935343873.html(第1回配本)
ギロッポン初日、
コバケンさんの棒、日本フィル公演、済む、演目は、同団のアシスタント・ミストレスたる千葉清加女史、っおよびVaのプリンシパルである安達真理女史の両ソロになるモーツァルト《シンフォニア・コンチェルタンテ》と、シベリウス《2番》とである、
予報通りの雨で、っこれから多摩センへ戻って、室まで10分15分濡れて走らねばならないのは憂欝である、っしかも、っこのあと多摩センあたりは19ml/hとかという土砂降りになるとのことで、っあるいは、駅で喫煙しつ日附が変わるころまで雨宿りをするようかもしれない、っどこか店が開いているかなあ、晩餉でも摂っているとするか、、、っうむ、っいま調べた、ってっぺん以後まで開けている店がある、
今週のサントリーは魔性でも棲まっているのか、、、っなどと、っあすもあるというのに縁起でもないことを云うものではないが、っおとついも藤森氏が絃を切られたところ、っきょうも、モーツァルト開始からまもなく、1stのフォアシュピーラー氏のそれが派手な音を立てて切れ、っすぐ隣へ立たれる千葉女史も眼を円くして愕いていられた、
っそんなトラブルもあれ、っしかし、っなんという浄福の時間時間であったことだろうか、1楽章でも2楽章でも3楽章でも、聴いていて、ずっとこのひびきの裡へいたい、永遠に鳴り止まないでくれたい、っとおもわさる、っそこへはコバケンさんも千葉、安達両女史も日フィルもいない、っただただ無上の音楽が存るっきりだ、
《ドヴォ・コン》と違い、っまるで力む必要のないモーツァルトということもあろうが、っきょうの彼等のほうが、N響よりもずっとサントリーという音場、空間を味方へ附けていられる、N響は、っそれこそ藤森氏のああした奏楽に象徴せられるように、っしばしばみずからの音をキャラクタリスティックたれかしと弾かれ、っそれはなべて音のエッジをぐりっぐりに立てまくるという方法論で、っいきおい、っおとついも云うことだが、音の輪廓でのみ音楽を語り勝ちとなり、音色の多様多彩、間接音への信頼を欠くのみならず、鳴る音が楽曲の個所個所の妙味を伝えるよりも先に、N響の音ですっ、っと主張してきて、聴いていて必ずしも仕合わせではないと云ったのは、っつまりはそこである、っきょうはその点、モーツァルトでもシベリウスでも、演奏が篤く篤くおもい入れてゆけばゆくほど、上記のとおり、っしばしば指揮者も奏者も眼前から消え去ってしまう、っほんとうに、世に最もこころゆたかにしてくれる楽音がひびいている、
シベリウスにおく造形は、っここで札響を振られた広上氏や、っおとついの大友氏のほうがよい意味でずっと冷厳であり、っおふたりとも、っその共感がそのまま楽曲の構造を怜悧に解明してゆくかのようであられた、コバケンさんは、っとうぜんながらと云うべきか、っもっと歌と抒情とへ偏され、全曲冒頭からテムポはゆっくりだし、絃のリズムもしゃきしゃきと音を立てられない、っしかし、眞情も籠もる歌い口と、一節一節、刻一刻たる音色の豊饒とは他の誰にも敗けられず、っこの際、多少とも構造の見通しが甘くなることなぞ、っぼくはよろこんで看過したい、っともかく、一瞬一瞬の音色、っそのゆたかさなのである、っしかも、N響みたように特長附けが目的化した奏楽へは陥っていないため、っどんなにたっぷりと鳴っても、最後にはユニヴァーサリティ、っすなわち、オーケストラっていいなあ、オーケストラの鳴っている様って快いなあ、っとおもわせるその音の色の範疇へ留まっていられる、っこれが極まったときに、このまま、いつまでもいつまでも了わらないでくれっ、っとこちとら切望させらるのであり、っそれはまことに得難い体験である、
っさいきんではメイン・プロでもわりに淡々たる棒へ終始されることもあるコバケンさんだが、っきょうは、っとくに1楽章など、オケとともに唸り、燃焼せむという従前までのシャーマニズムを取り戻されるようなので、っぼくは、あんまりそうされなくっても、ただ拍を取っていられるっきりでも、オケはおおきによく弾いてくれるのじゃないか、っとおもったくらいだが、ファゴットの主題を楽章まんなかで全員で高唱する場面は、金管もティムパニも剝き出しの音力自慢へ堕さず、っゆとりと格調とがすばらしい、ロンドン・フィルとのマーラー《5番》音盤を聴いてもおもうことだが、っあそこまでの眞に穿ち切った音が出せていれば、っもはや音勢に勝る楽器楽器の刺戟的の突出はまるで要らない、全体にずっとなだらかな音響のままでよいというか、っそのほうがよいくらいである、
っそれにしても、っこの主部のテムポはぜんぜん迫らず、指定はアレグロであろうが、っとてもそれを叶えているとは云えない、大友氏は一気呵成に前進され、っゆるやかな冒頭部分との間にみごとな対照を附けられていたもので、アレグロなんだからきびきびとしているのがあたりまえというところかもしれないが、っつぎからつぎと息つく間もなく楽想楽想が連続する窮窟さというのは、っぼくごとき怠惰な人間には草臥れる音響体で、っきょうみたようにのんびりと、誰も彼も落ち着いて発音できている進行というのこそ愛しい、
2楽章は、っまあ奇異なほど遅いテムポを採ることの必然性もない音楽であり、コバケンさんの棒もいくぶんさくさくとされる、っけれども、歌の麗しさは変わらず、っそしてむしろ、コバケンさんとしては澹泊な音捌きが、っもはや心地よい、以前までの彼氏では、っおもい入れられるがあまりに、音も音楽も濁されたものである、
件のトロムペットによる主題の再現では、オットー氏は全体をシルキーなレガート、っおとついの大友氏には、新発見のよろこびと、論理的の整合性への納得感を與えられたが、コバケンさんにさようの冷眼を望むことができないのは、っもとより知れたことである、っそれに、っやはりこのラッパは、全体を纏綿と歌ってくれるほうが、遙かに様に成る、
3楽章は1楽章主部におなじ、っおっとりとして急がれない手筈には、っすでにして病み附きである、トリオの質朴を2度通過したのち、ラルガメンテのブリッジも、っけっして気持ちを逸らせられず、1歩1歩たしかめながら、っついにフィナーレへと到る、
っそのフィナーレは、っあれが㐧2テーマなのかな、低絃のアルコの上で管が口々に示す共通の動機、っちがうのか、っその前の高絃のアルコのはじめ頭が休符のやつがそうなのか、っいずれ、っその前者では、っあくまでもどこまでも音楽の経緯を見届けられるコバケンさんのじっくりとしたまなざしがことのほか印象的で、ロング・スパンでじわじわと漸増し、っいよいよトロムペット、トロムボーンの新しい動機を招来するその気宇の壮大なることは、っじたばたと無闇に音楽を煽動されぬことの結果である、
コバケンさんはシムフォニーは暗譜でいらしたが、っやはり、っいつザッツの乱れが起きるかとややはらはらさせるものがある、っじっさいには乱れらしい乱れは起きなんだのだが、っあすは、1日熟したことによるより落ち着き払った風格を聴かされたい、
晩餉を了えて、っちょうど日附の変わるころに退店す、食事中はインナー・ヘッド・フォンで耳を塞いでいたが、戸外は激しく降ったのだろうか、っほぼ予報通りで、っいまはほとんど止んでおり、濡れて走らずに済む、
っあすは午前のみ仕事をしてから出向く、っきょうはRCが購えているが、っあすは2階のまともなSへありつけておらず、左翼後方辺のAだかBだかだったとおもう、
みずの自作アルヒーフ
《襷 ータスキー》(全4回)
https://ameblo.jp/marche-dt-cs4/entry-12351779591.html(第1回配本)
《ぶきっちょ》(全4回)
https://ameblo.jp/marche-dt-cs4/entry-12351806009.html(第1回配本)
《きりむすぶ》(執筆中・脱稿時期未定)
https://ameblo.jp/marche-dt-cs4/entry-12935343873.html(第1回配本)
ギロッポン、
大友直人氏とN響との公演、済む、演目は、鳥羽咲音女史を招いてドヴォルザークのコンチェルト、っそしてシベリウス《2番》である、
大友氏の公演は、っきっといつかどこかでは聴いているのだとおもうが、ったしかにあの公演がそうだったといっていま想い出せるものはない、《ドヴォ・コン》のオケ・パートは、っあれがN響の演奏文化ででもあるのだろうが、攻めてゆかない大人しさがじつに鼻持ちならない、全曲がさいしょにトュッティへ達する部分は、Vnにぞんがい艶がなく、っきーきーいってしまっている、全体の音色も魅力に薄いし、1楽章のコーダなど、っいっさい力まない、っいっさいバランスを破らない安全運転に、率直に云って、っこちとら苛立たずにいない、っなんという覇気に乏しい奏楽であろうか、
鳥羽女史はといえば、繊細ななかにも音色に存在感がおありで、2楽章あたり、中間の〈あたしにかまわないでっ〉部を導くN響のトュッティはやはり本気の音がせず、綺麗事にすぎないが、ソロと木管とを主体とした中音量以下の部分など、っちゃんと薫風が吹きもする、
フィナーレも、っそうした多少とも魅惑的の部分とお高くとまっていてつまらない部分との斑模様で、っけっして全的には心身を預けえない、
シベリウスでの大友氏は、全曲に亙って苛烈な前進性をみせられる、っそのせいもあってか、N響はこんどは各パートとも力み勝ちで、セロの藤森氏など、っついにフィナーレ終局のピッツィの部分で絃をぶっ千切ってしまわれるばかりであったが、っそれにより、上に云う魅惑的であるよりはつまらない部分の、っすなわち音色の可能性のごく限局せられた、音の輪廓の明瞭さのみがものを云う性格の奏楽が、全曲全時間にぎゅうぎゅう詰めに詰め込まれる、演奏藝術としてある種おそるべき密度ではあるが、聴いていて必ずしも仕合わせではなく、全奏が完了し、満堂が沸いているなかでも、っぼくとしてはどこかこころ虚しい、
っしかし、大友氏があそこまで緊密な造形を示される方だとは、不分明のぼくは寡聞にして識らず、侮ってはならないというくらいにはおもった、
中1日置いてあさってしあさってと、っおなじくサントリーで、コバケンさんの日本フィルとの同曲である、っきょうの大友氏とは、テムポをはじめとして、っまったく好対照の造形が鳴るものと推知せられる、っおおらかな深呼吸はまったく結構だが、っただなんとなくなだらかに流れてゆくっきりでは、っぼくも満足できようはずがない、っやはりここで聴いた広上氏と札響とのものや、っきょうの大友氏も、っごく細部において相当度の彫琢を聴かせられた、長老のおひとりとしてのコバケンさんには、部分部分の手の込みぐあいについても、彼等に敗けない練達を期待したい、
っきょうの大友氏でなるほどとおもったのは、2楽章におくトロムペット1番による主題の再現である、吹奏は長谷川氏であったが、っそのフレイジングは、っぼくみたような半端者は、っぜんぶの音を綺麗にレガートで繫いで、孤高のバラッドとして歌い上げてくれたいなどと希んでしまうのだが、長谷川氏は、たーらーらーらーー・たーら・たーら・たったーらーらー、っというように吹かれた、っぼくはさいしょ、ん、巧く吹かれなかったのかな、っとおもったのだが、っそうではなく、絃に既出の同動機の、っそちらのフレイズに倣らうと、っそう吹くのが整合的というわけなのである、っまあそれでも、っどうしても、たーらーらーらーー・たーらーたーらーらーたーらーらー、っと吹いてくれたほうが切なく胸へ迫るようにおもうが、シムフォニーであるからには情緒よりは構成のほうを優先させているので、っかかる厳格は、コバケンさんに求めてもおそらく裏切られるだろう、っけれども、っくりかえす、っただ満々と全曲を歌で満たしたくらいのことで、っお客が納得して喝采を送ってくれるなどとは、夢おもわないでいただきたいものである、
公演事前のインターヴューでのコバケンさんは、チェコ・フィルとの同曲公演、録音時の故・ノイマン氏とのおなじみの挿話をみたびよたび語っておられる、っそのノイマン氏が病身を押して来訪し、ルドルフィヌムのオルガンの前の席から見下ろしていたという公演当日のプラハは、江崎氏によれば雨が降っていたとのことだ、っあさっての日フィル公演初日も、予報ではちょうどよるが土砂降りとなってしまいそうで、果たして、っそれは豊饒の時を惠む慈雨と成るであろうか、っぜひにそうあってくれたいものである、
みずの自作アルヒーフ
《襷 ータスキー》(全4回)
https://ameblo.jp/marche-dt-cs4/entry-12351779591.html(第1回配本)
《ぶきっちょ》(全4回)
https://ameblo.jp/marche-dt-cs4/entry-12351806009.html(第1回配本)
《きりむすぶ》(執筆中・脱稿時期未定)
https://ameblo.jp/marche-dt-cs4/entry-12935343873.html(第1回配本)
きりむすぶ 第3回配本
*本作は執筆中であり、不定期の投稿により、随時更新する。一定の文章量、ストーリー展開に達するまでには相当度(あるいは年単位)の期間を要する。以上をご理解の上、お見捨て置きいただければ幸甚である。各回配本の末尾には、次回配本を投稿し次第、そのURLを添付するものとする。
ハ.
英嗣は気にしている。ここ何ヶ月かの間にも彼は幾度も晴子に逢ったが、逢う度に、彼女が饒舌になってゆくようなのだ。自分の日常がいかに充実しているかを、彼女は力を籠めて話す。気のせいであればいいが、と英嗣はおもうのだが、それはほとんど、自身に云い聞かせるかのような、あるいは、叔父に嘴を挿ませまいとするかのような口調に聞こえる。晴子と別れたあと、あれはひょっとして、知らず知らずのうちに発せられる彼女のSOSなのじゃないか、そんな心配に駆られて、ひとりこころをはらはらさせている。以前までの晴子ならば、もっと叔父に水を向けて彼に話させ、熱心にそれへ耳を傾けたし、自身が話すときでも、彼にさかんに意見や助言を請うたものだ。
--(単に若気の背伸びみたいなものだろう。晴ちゃんだって、いつまでもこんな中年にとやかく云われたくはないさ。)
晴子相手に限らず、土台、それが英嗣の年少者への対し方だ。ありとある世代間で、目の上のたんこぶの疎ましさは、年少者たちによって掃いて捨てるほど経験されてきた。それがいついつまでも世の常だろうとも。しかし、せめて自分だけでも、誰かにとっての年長者となった暁には、彼等をおもうぞんぶん羽搏かせてやりたい。経験ある自分の目には、彼等の振る舞いは向こう見ずと映るだろう。もちろん失敗もたくさんするにちがいない。よいではないか。飛び立たせ、おおいに失敗をさせてやろう。尻を拭ってやるのが、年長者の仕事である。それよりも、彼等若者は、時代に遅れてゆく自分にはおもいも寄らぬ、おどろきの新発想を宿しているかもしれない。下手に小言を云って、その翼から羽根を毟るようでは、ひょっと一大損失になりはしまいか。
口で云うのは易く、じっさいにそれを実行に移せているのか、英嗣には自信がないが、彼なりにそうしてきたつもりである。こんなポリシーは誰か他人に口外するものでもないが、ほんのいちど、酒の力もあり、上司と部下として肝胆を照らし合ったとおもえる相手に英嗣は、自分はいつかはそうしたいのだと話したことがあった。そのときの上司の返答は、
--それは矢内のかんがえで、そうしたいならそうすればいいとおもうけれど、小言を云われて初めて羽搏ける奴も、若いのにはいるんじゃないのかな。
であった。こういう科白を聞けるからこそ、英嗣にとってこの上役は信頼に価した。しかも、大真面目を云ったのが恥ずかしさに、すぐさま相手は、
--ほら、ちょうどお前がそうだったじゃないかっ。
と英嗣の肩をばしばしどやして話を茶化しに掛かった。そのときの耳朶が真っ赤に染まっていたのは、アルコールのせいばかりではあるまい。英嗣はおもったものだ。かっこいい大人にはかわいげがある、かっこよさのために気難しくなるばかりではいけない、恥じらいを知り、かわいくいられなければ、かっこよくはないのだ、と。
晴子と逢うこの喫茶店で英嗣は、図らずもほぼまいかい聞き役に徹し、気が附くといつもこのかっての上司を想い出していた。晴子の話しぶりが、どうしても彼にそのことを想い出させた。そして、やはり云い知れぬ不安がその胸裡へ去来した。
--(いまは晴子をおもうぞんぶん羽搏かせてやるタイミングではないのかもしれない。首根っこを捕まえてでも、もうそれ以上飛ばなくていい、と云ってやるべきじゃないのか。おもい過ごしだろうか、取り返しのつかないことになってからでは遅い、おもい過ごしだろうか、取り返しのつかないことになってからでは遅い・・・・・・。)
もう何度、このふたつの感情の間を往復したことだろう。きょういまも、彼の脳裡にはあのときのあの真っ赤な耳朶が浮かんでいる、浮かんでしまっている。
晴子は、3年前に都内の私立大学を卒業し、大手の広告代理店へ入社した。何十と就職試験を受けることは、誰でもが通る道であるとはいえ、身近に見ていて、懸命に気丈夫に振る舞う晴子の姿は、英嗣の目にもときに痛々しかった。どうなるにせよ、いつかはその苦労も終わるのだから、どうか辛抱してほしい、そんな気持ちで見守っていた。喫茶店で相談を受けるとき、真剣に取り合ってやるのがよいのか、軽口でも叩いて気を紛らせてやるのがよいのか、まいかい慎重に思案した。その過程で晴子は、すくなくとも英嗣の前では、ただのいちども目に見えて取り乱すということがなかった。当の就職先が決まって、いつもは食べないイチゴのショート・ケイキなどを頼んでささやかな祝いをした際、英嗣がそのことを、偉いとおもったよ、と云うと、そこでやっと緊張の糸が解けて、晴子はぼろぼろと泪を落として泣いた。英嗣が会計に立つとマスターは、
--矢内さん、きょうはお代はけっこうですよ。
と云った。
--いえいえ、それはいけません。
--いえ、私のきもちですから。晴子ちゃん、よかったですね。
よかったと、もちろん英嗣もかんがえた。けれども、いまにしおもえば、その祝いをしているときにすでに、ある嫌な予感が、あるほんの嫌な予感が、彼の懐を掠めて行ったような気がする。そのときにはかぶりを振って即座に斥けた。しかしいま、たしかにあのときに嫌な予感がしたことを、彼は想い出さずにいられない。
晴子の両親はといえば、父、楠雄、2人兄弟の、5つ離れた英嗣の実兄だが、彼の喜びようたるや、まるでそれが我が事ででもあるかのようだった。英嗣はこの兄とは、晴子ほど頻繁には顔を合わせないが、晴子の就職が決まってからは、逢う度に自慢の娘だ自慢の娘だという彼のことばを聞いた。英嗣はそのいつかの機会に、上に云う嫌な予感がしていたこともあろうか、
--兄さん、それあんまり云いすぎてやるなよ、とくに晴ちゃん本人にはさ。
と云ってしまったことがある。想像に難くないだろうが、そのときの楠雄の激しようといったらなかった。
--なんだ英っ、その云い種はっ。云いすぎてやる、とはなんだよっ。あいかわらずお前は好かんことを云う奴だな。おう、そうだろうそうだろう。晴子は大手へ就職して、じきにお前より稼ぎのいいOLになるんだ。さぞかしおもしろくないだろうなっ。
それは楠雄宅でのことで、兄弟で話し始めたときには晴子はその場にはいなかったのだが、父が大きな声を出したことで心配そうにやって来て、上の最後の科白は彼女も聞いた。晴子は英嗣の方へ、叔父さんごめんね、との視線を送りながら、
--やめてよお父さんっ。
と窘めた。しかし楠雄は、
--お前は黙ってなさいっ。
とまるで取り合わなかった。
不貞腐れた楠雄はそのあとしばらく縁側で胡座を掻いていて、やがて、
--ああ不味いっ。煙草も不味けりゃ茶も不味いっ。
と、英嗣と晴子と、妻と、家内へ3人いる誰かへ聞こえよかしと吐き捨てて、玄関の扉もまた聞こえよかしとわざとらしくぴしゃりと閉めて、出て行った。その妻、つまり晴子の母、朱美も、夫が出て行ったとわかると英嗣を探してやって来て、
--ごめんなさいねえ英嗣さん。大きな声を出してあの人、大人気ないったらないんですから。
と腰を折って小さくなりながら詫びを云った。
--いえいえお義姉さん、止してください。頭を上げてください。ぼくのほうこそすみません。なにか癇に障ることを云っちゃったみたいで。
そう応じながら英嗣は、済まなさそうにする朱美の眼の色が、さきほどの晴子の、叔父さんごめんね、との視線とそっくりなのを認めて、可笑しいやら微笑ましいやらであった。
--不味いんならのまなきゃいいのに、あれで煙草を買いに出たんですから、いやですよまったく。いえね、あたしや晴子がなに云ったって聞く耳ひとつ持ちやしないんですから、押しつけるんじゃありませんけれど、英嗣さんからたまにお諫めのひとつも云っていただいて、それでちょっとかりかりするくらいがいい薬なんです。
--いえそんな。兄貴ですから、諫めだなんて滅相もない。
--いいええ。ほんとうですよ。
夫に聞かれていなければという条件附きで、いつでも本領を発揮できます、という朱美のこの生来のネアカなおしゃべり好きの感触に、英嗣もおもわずにほっこりとさせられた。
その朱美に云わせれば、夫の英嗣に対する態度が硬化したのも、就職した英嗣の稼ぎがどうやら自分よりもよいらしいと知れてからのことで、長年卑屈でいたものが、晴子が大手へ入ることができて、それで見返した気になっている、とのことだ。英嗣は、半分はそれを信じていないが、半分はさもありなんともおもっている。彼が、稼ぎくらいがなんだよ、という態度を取るときほど、兄のいらつきは高ずるようだからである。
むかしの楠雄はけっしてそのようではなかった。やや歳が離れていることもあり、英嗣には、兄に可愛がられた記憶しかない。就職が決まったときも、手放しによろこんでもらったことを、彼はよく憶えている。しかし、たしかにそれからしばらくして、そんな云い方をしなくたっていいじゃないか、という楠雄の科白を聞く機会が、ようよう増えてきたようだ。
以上のことから明々白々であるように、たとえば英嗣が姪っ子にずばり核心を訊き、彼女へなにか助け舟を出すとして、楠雄の存在は、高波も高波、大時化も大時化とならずにいないだろう。だからきょうも、喋りまくる晴子を前に、彼はただただ聞き役なのである。
(第3回配本 おわり)
西那須野、
井﨑正浩氏の棒、マロニエ響公演、済む、演目は、木下雄介氏を迎えてベルリオーズ《イタリィのハロルド》、っそしてホルスト《惑星》である、
っゆうべは、例によって作業着姿のまま居室の椅子へいて睡りへ堕ちてしまい、4時ころ目覚めて寝室へ移動し、っその格好で、頭も整髪料で固めたままで、枕の上へフェイス・タオルをかむせてもうすこしく睡る、7時半すぎに起きてシャワーを浴びるが、多摩センから、乗ろうとしていたものよりも1本遅い京王になってしまう、車中で検索するにしかし、新宿で4分でJRのホーム、、、ホームってプラットフォームだからホームじゃなくてフォームなのかしら、っどうかわからん、っへ移動できればほんらいの湘南新宿ラインへ乗り継げるとわかり、っただ京王の新宿着は1分から数分も後ろへ倒れることがざらだから、っあまり期待していなんだところ、っほぼ定刻通りに新宿へ着いたので、っときおり小走りでJR構内へ移り、4分後に湘南新宿ラインの車中へいた、宇都宮で乗り換えて西那須野着は12時すぎで、器までは東口のロータリーから延びる1本道、30分弱歩って開場の1時間ほど前に現着すると、順番待ちはおじいさんひとりっきり、2番目へ並んで1時間待ち、入場す、
2階正面最前列右寄りの列の端部へ背嚢を置いてすぐに喫煙へ出る、っもぎりの脇の戸外へ喫煙スペイスがあり、開演直前までそこへいたが、戻って着席すると、っややしくじった、席の前の通路の幅がかなり広く、っそうすると、壁面上部の手摺によって舞台の相当度が死角となる、っぼくの座高では、指揮台上へ立っている指揮者は視えるが、左翼は1st連、右翼は表へ出たセロ連の、プルト表の人たちのちょうど頭部附近がもろに手摺へ隠れてしまい、視覚的には悪条件で、1列後ろへ下がるほうがよかった、初めて行く器ではかようのことがある、っちゃんと席へ坐して視界を確かめてみねば、
っそれから、っきょうはお客の質がよくないのもかなりに気懸りであった、小さいお子を連れた人が演奏中に立って移動したり退出したりするのはやむないとしても、成人の客でもほとんど楽章間のたびに入って来たり出て行ったりで忙しく、入って来た人は、っもう演奏が開始しているなかでやっと席を定めて、っそれから落ち着くまでに手荷物の音をがさごそいわせていたり、っなかには、入って来たとおもったらすぐに他人様の眼前を堂々と横切って出て行ったりする人までいたりと、っいったいどういう料簡をしているのかと疑らずにいない、っちゃんと開演までに器へ来て、2時間の公演を最後まで大人しく聴いていられないのなら、演奏会へなど来るなと唾棄したい、っぼくのひとつ空けて右隣りの中年の女性ふたり連れも、演奏中に喋るわ、プログラムを捲って紙の音はさせるわ、足でぶらぶらリズムは取るわ、っせめてよっぽど、恐れ入ります、演奏中に話さないでいただけますか、っと云わむかとおもったが、不届者はそのばばあふたりだけじゃなくそこここにいたので、っもう云う気も失せてしまって我慢した、田舎の人は純情だから演奏会の場内では静寂を保てる人たちかとおもったが、栃木県人もダメですねえ、怪しからんよまったく、
っさておき、開演すれば、っやはりオケはとても巧くていられる、ベルリオーズのこの作はあまり聴いたことがなく、っこないだN響がヤルヴィ氏か誰かと演ったのの動画を単品購入し、っその音声を数回聴いた程度である、難解な作ではなく、トロムボーン連を加えたトュッティのとっぽい感触はいかにもベルリオーズだ、ヴィオラは音量が細く、っきょうくらいの音場でも2階正面までぎりぎり届くか届かないかの音勢で、っしかし、数年前まで大阪フィルのプリンシパルで、現在はフリーランス、棒振りもされることがあるという木下氏は、っおおきに闊達でいられる、
《惑星》は、偏愛する人もおおく、音盤はやれボールトのどれだとかカラヤンのどれだとかと巷間取り沙汰されているが、っぼくは夢中で聴いたことがなく、近現代の管絃楽曲としては、っべつにふつうというか、取り立てて壽ぐまでもない凡作のひとつかとおもう、っそういう曲は演奏においてかなりにへんてこであってくれるとうれしいもので、未聴だが、世評が高いということは、ボールトやカラヤンではその渇きは癒えないのだろう、っぼくが敢えてこの曲を聴くとすれば、数年前、トラムプの中共封じ込め政策の煽りを喰ったのだとおもうが、一挙的に閉鎖してしまった海賊盤市場で入手せる、っおそらく最晩年に近いロズージェストヴェンスキー氏が、ロシアのなんとかいう楽団を振られたライヴ盤である、海賊盤にしてはちゃんとクリアな音質で、オケもソフィスティケイトせられた鋭い音が出せ、っしかし棒は不細工なほど遅い、〈木星〉の開始など、っゆっくりと、っすべての音を明瞭に発音させむとするがあまりに、っかえってたどたどしいばかりになっており、っもちろんぼくはそういうのがうれしい、スマートでカッコいい奴等はみんなおとつい来やがれだ、
っあるは、っさいきんでは、公演へは行かなんだが、広上氏が日本フィルを振られた有料動画を購入して視聴せるところ、っもちろんロズージェストヴェンスキー氏ほどではないにせよ、広上氏も1音1音を大事に噛み締めたがっているテムポ感を示されており、恆のとおりすこしく無理をしてぐうぃっちぐうぃちに鳴りに行く日フィルの感触もたのしい、
井﨑氏はその点、〈火星〉から仮借のない前傾姿勢でいられる、っこないだの福井での彼氏の《オルガン》も同様の造形であったが、っあのときはもうひとつオケの精度に勝れず、不発に了わったところ、っきょうのマロニエ響はちゃんとその棒へ喰らい附かれる、全軍が全開すると、広くない、っよくひびく堂内は満々と充たされるが、っそのびりびりいう音響ですら大宇宙の神秘を音化したその効果音のごと、現実の楽器の物理音の集積であるとは信じ難い色調を発散し、っそうしたことは眞に勝れた合奏能力からでしか結果結實しないので、っまことにこの楽団にならばこのレヴェルの奏楽が期待せられた、っその期待通りの精華である、
っただし、後半ともなるとさしもの彼等とてわずかに息切れの気味で、っあれこれの綻びがみられた、前回のラフマニノフ《2番》では、フィナーレの最後の最後まで緊張の糸が切れずに繫がったので、綜体としてはその公演のほうがより上質であったようにおもう、器との相性としても、前回の宇都宮の音場のほうが、っやや乾いた感触がむしろ彼等のひびきの特質によくマッチしていたのではないか、
コーラスは少人数、ソプラノは、っいちばん高い音でいますこしく剣を抑えた発声ができるほうがより効果的であったかとおもうが、人声であって人声でないかのような、宇宙の彼方を漂う谺の感触はまずまず出来していた、っもっとも、眞空の宇宙空間へ音は伝わらなかろうが、作家が懸命に海王星の大気中を想像した、っその音響の具現であろう、
オルガンもいるというこの陣容でアンコールといえば、エルガー《威風堂々1番》と相場は定まっており、っそのとおりだったが、コーラスは、英国㐧2の国歌の部分を、っさいしょ静かなときはaの音でハミングというか、nとかmじゃなくaの音だとハミングとはいわないのか、っまあヴォカリーズ、あれ、歌詞は唄わないのかな、っとおもっていると、フォルテになってからは唄われていたようだ、っが、っほんの10と数人っきりいられないので、っざんねんながらぜんぜん聴こえない、
っいまは器から駅へ戻るとちゅうのコメダ、っもう19時を回った、4時間弱掛かるからな、っそろそろ帰らねば、
っお次は水曜、サントリーで大友氏がN響をお振りになる、大友氏にはあまり興味はないのだが、前プロで鳥羽咲音女史が、っあれ、《ドヴォ・コン》だったかな、ったしかそうとおもうが、っを弾かれるので、以前に読響がまいとし新星3名を招いてコンチェルトを3つ演る公演で彼女の同曲を聴き、頗る好印象だったもので、っもういちど聴きたいとおもった、サントリーでのN響でも、特別公演なら切符も取り易かったし、本プロはなにかしら、っひょっとしてシベリウス《2番》か、っそうとすると、っそのあとすぐおなじ音場で、金土とコバケンさん/日フィルの同曲を聴くこととなり、比較もたのしい、
鳥羽女史は、っお名をこれでなんと読ませるのかなあ、ったしかさくらだった気がするが、っぜんぜん読めませんね、っさいきんになって知って吃驚したのだが、彼女のご母堂は鳥羽泰子女史でいられる、っそのわりに咲音女史はそこまでもろにハーフ顔をされていないように見受け、っだから泰子女史のお嬢さんであるかもしれないなどともかりそめにも想像せなんだのだが、っご両親はあれかな、離婚されているのかな、っお母様もご帰国されて日本在住なのかもしれない、
っま、っともかく、
っさ、っこれからの帰途で、っもう景色もたのしめないし、っいくらかでも新作に手を染められるかどうか、一寸がんばってみましょうかね、
みずの自作アルヒーフ
《襷 ータスキー》(全4回)
https://ameblo.jp/marche-dt-cs4/entry-12351779591.html(㐧1回配本)
《ぶきっちょ》(全4回)
https://ameblo.jp/marche-dt-cs4/entry-12351806009.html(㐧1回配本)
《きりむすぶ》
https://ameblo.jp/marche-dt-cs4/entry-12935343873.html(㐧1回配本・執筆中・脱稿時期未定)
池袋、
大野和士氏の棒、都響公演、済む、先年に故人となられ、生前は同響と数多の公演、音盤制作をされたすぎやまこういち氏の作の特集で、開幕に新国立劇場唱を加えて《カンタータ・オルビス》、っすぎやま氏がだいぶん晩年に同響コン・マス矢部達哉氏のために書かれたというコンチェルティーノ《日本の風》、《神秘なる静寂》、っそして《イデオン》である、全曲、っきょうが舞台初演であったという、
前半3曲はいずれも10分に満たない小品、っぼくがすぎやまファンといっても、っほとんど《DQ》以外の彼氏のお仕事を識らない、《カンタータ・オルビス》はアニメ《伝説巨神イデオン》の劇中曲で、っすぎやま氏ご自身の手になるラテンの詞が唄われる、変拍子のセンスにすぎやますぎやました要素を聴く、コーラス・マスターは冨平恭平氏であられた、大野氏は、客席から観ているぶんには顔相は目に入らないし、振り姿はもっと澹泊な印象があったが、っねちっこい情念が垣間見える瞬間もあり、っぞんがいわるくないとおもった、不遜な云い種だが、都響は、極めてシャープな発音で、っぼくはやや濁った音色も交えた日本フィルの鳴り方のほうが手作りの味がしてすきだが、っごく上質なのは確かだ、
っつづく2曲はいずれも、っすぎやま邸を訪問された矢部氏へ作家が、はい、これ、っと事もなげにスコアを手渡されたという作、っうち《日本の風》が開始すると、途端におよそ名状に堪えぬ感懐に襲われ、一気に泪腺が弛む、音型が、和音が、リズムが、全体のひびきの感触が、っもうザ・すぎやまこういちなのである、嗚呼、この人の音楽が俺の青春だったなあ、、、っと、
表題通り、5音音階が聴かれるが、っいかにも日本の民謡風でございという聴こえよがしのフォルクローレを振り撒かないところがハイ・センスだ、ソロには難技巧もなく、矢部氏もその風采、挙措のとおり、嫋やかな奏楽で遙か故人を偲ばれるようであられた、
っこの曲へは管もいるが、《神秘なる静寂》は絃5部とソロと、主題は、矢部氏が作家に愛惜の意を伝えられたという《DQⅧ》の〈神秘なる塔〉のものをそのまま用い、っそれをVnのためにリライトしている、
《イデオン》は、っすぎやま氏のプロフィルに書されていたので、っぼくが《DQ》の音盤をあれこれ漁るようになったガキんちょのころから、楽曲の存在は知っており、小松一彦氏の棒になる音盤が出ていることも認識していた、っが、っその往時には当該音盤はかなりの稀少盤であり、っいまだネットもよく普及していない時分の田舎の高校生ではぜんぜん入手不能であった、っのち、Amazon.等を頼れば手に入れられるようにはなったが、っそのレヴューかなにかで、録音が鈍くてあまり聴けないという主旨の意見をみて、手を出しあぐねているうち、っついにきょうまでその音盤は購わないままだ、っぼくは当該アニメもぜんぜん識らないので、っどんな曲だか事前にはまったくわからず、っしかし、シムフォニーと銘打たれてはいても、っじっさいには劇中曲を繋いだっきりのチープな作だろうと侮っていたところ、っけっこう手の込んだ力作であり、っときおり、っのちに《DQ》各曲にも顔を出すすぎやま音型が聴こえるし、フィナーレについてはヴァリアシオンの形式を採用、ブラームス《4番》に範を求められたとのことで、ったしかに、同曲をおもわせる部分がいくらか聴かれた、
っそれが30分強、40分弱くらいの曲で、2時間にかなり満たないなとおもっていると、っふたたびコーラスが登壇され、開幕曲をアンコール、個人的にはもう1曲、《DQ》の〈序曲〉あたりを演ってくれたく、っそれを期待した人はぼく以外にも大勢いたとおもうが、っこれでハネた、
っいずれも、コンサート・ピースとして、堂々一公演を維持しうる良作佳作であったとおもう、《DQ》については、現在でも日本国中で頻繁に演奏せられているが、っどうしても、《DQ》のコンサートです、っという体裁での開催となってしまい、っおそらくどの団体の公演でも、スートを全曲通奏するのでなく、数曲毎に止めて指揮者がMCを入れたりしてしまっているのだろう、っそうじゃなくぼくは、っどこか楽団の定期公演の演目として、《DQ》でも、っほかの作品でもよいが、っそれを西洋古典とカップリングした演奏会が挙行せられてくれたいと、っずっとずっと以前から切望しているところだ、
、、、SIMが入っている方のiPhoneは、ったったいまバッテリーが落っこちる、っあさから取手くんだりまで無駄足で、モバイル・バッテリーも使い切ってしまった、コメダでこれを書いていて、っこの店舗は席毎にコンセントの提供がない、SIMなしで、音源を詰め込んでおくためだけに使っている方のiPhoneで店のフリーWi-Fiへ繫いだ、っいつ落ちるかとおもったのでまめに保存しており、書いた分が失われることはなかった、同iPhoneへはさっそくに、っおとついのカーチュン・ウォン氏の日フィル公演の動画から音声を抜いて、例によって音量レヴェルが低かったので、編集アプリケイションでゲインをいくらか上げて同期して来、っいまそのショスタコーヴィチのシムフォニーが耳で鳴っているが、っとても好い演奏だとおもう、カーチュン氏も、近来のマーラー《トラギッシェ》、ドヴォルザーク《新世界》、っそしてこのショスタコーヴィチとヒットつづきでいられ、勝れた画源音源が増えて、っこちとらうれしい悲鳴を上げている、
っさて、っお次はこんどの日曜、井﨑正浩氏を聴きに栃木まで遠出をする、っしかし栃木程度であれば新幹線など使わなくてよく、在来線なので、っそこまで多額の交通費は掛からない、例の2年に1度っきり公演を有たれない団体で、初めて聴いた前回は、吃驚するほど巧いリムスキー=コルサコフやラフマニノフにこちとら舌を巻いた、っだからこんかいもとても期待している、失礼に聞こえなければ、栃木の田舎にどうしてあんなにも全声部が均等に勝れるアマチュア楽団が存在できるのであろうか、っあの人たちはいったいぜんたい、っどこで誰に楽器と合奏とを教わったというのだろうか、っいずれ、井﨑氏も、っそのとくにラフマニノフでは、そんなによく弾けるんだったらここまでシヴィアな要求をするよっ、っという厳格なリハーサルもこちとら髣髴とするごと、入魂も入魂の造形を示され、終演後の、やったぜっっっ、っとメムバーメムバーと交歓される満足げな表情もつよく印象に遺っている、前回とは異なる器での公演であり、っそこもたのしみだ、
以下、っいつものごと自作アルヒーフのURLを貼るが、っこのiPhoneのメモへは新作分が反映していなく、加えるのも面倒なので、旧作2作分のみとしておきます、っすこしく間が空いてしまって、っだから云わんこっちゃない、怠惰をしないで、閑をみつけて書き継いでゆかんとな、
っあ、っそうそう、っいまICU構内で仕事をしており、っあすあさってには現場はカタが附くが、っこないだ井﨑氏は同大の学生オケと学内のチャペルだか講堂だかで公演を挙行されたんだよなあ、ったしかメインがフランクの《シムフォニー》で、っぜひ聴きたかったのだが、っなんだったかな、っどれか公演とバッティングして聴けなく、っまことに惜しいことをした、
っさ、っそろそろ帰ります、
みずの自作アルヒーフ
《襷 ータスキー》(全4回)
https://ameblo.jp/marche-dt-cs4/entry-12351779591.html(㐧1回配本)
《ぶきっちょ》(全4回)
https://ameblo.jp/marche-dt-cs4/entry-12351806009.html(㐧1回配本)
っなにーーーっ、
佐藤雄一氏の楽聖《㐧9》公演の切符、っすでにして配布を終了とのこと、、、数日前に配布を開始したばかりだとおもうのだが、周辺のじじばばが殺到したんだろうなあ、っこちとら平日は仕事をしているんだってのに、
取手まで来ちゃいましたよ、、、来て、器まで歩きつ楽団のHPを検索したら、っさようのわけで、っがっかりしちゃうよまったく、、、
っこの楽団は公演の音源を公開していられるので、っそれを聴くこととせむ、っただ音質は、っいまどきこんなにへぼなのかよというほど貧しく、貧しいというか、録るときの音量レヴェルの設定が高すぎるのだろうか、一寸トュッティのところがぜんぶばりっばりに音割れしているので、っそこがざんねんだ、
っじゃあまあ、っその日はなにかべつの公演を探してみるとしますかねえ、っやれやれ、、、
池袋へ向かいます、
みずの自作アルヒーフ
《襷 ータスキー》(全4回)
https://ameblo.jp/marche-dt-cs4/entry-12351779591.html(㐧1回配本)
《ぶきっちょ》(全4回)
https://ameblo.jp/marche-dt-cs4/entry-12351806009.html(㐧1回配本)
《きりむすぶ》
https://ameblo.jp/marche-dt-cs4/entry-12935343873.html(㐧1回配本・執筆中・脱稿時期未定)
ギロッポン2日目、
カーチュン・ウォン氏の棒、日本フィル公演、済む、演目は、小川典子女史と同フィルのオッタヴィアーノ・クリストーフォリ氏とのソロでショスタコーヴィチ《1番》コンチェルトと、同《11番》とである、
2日ともRCが購えていなく、っゆうべはRA、っきょうは1階前方の左寄りであった、っゆうべは小川女史のピアノの音は蓋の向こう側からしており、オットー氏のラッパもあさっての方角を向いていて、条件はかならずしもよくなかったが、っきょうはよりクリアな音響を見舞わる、殊にオットー氏については、っゆうべはもっと彼氏の音量バランスをつよく聴きたいという不満を有ったが、っきょうは、正面からやや右側を向いて楽器を構えられたその朝顔はちょうどぼくの席あたりと正対しており、っきのうの3倍も5倍もおおきな音量に聴こえた、吹かれ方はきのうと大差がなかったのだろうか、っいかになんでも位置ひとつであんなにも聴こえ方が変わるということもなかろうから、っあるいは、カーチュン氏と申し合わせの上で、全体にもうすこしく音量を出すこととされたのかもしれない、
同曲は、広島で角野、児玉両氏のソロで聴いたが、っとくに角野氏のピアノにはぜんぜんニュアンスの変転がなく、っただでさえピアノ以外は絃合奏にラッパのソロのみという異例のシムプルな編成であれば、ソロの質感に多彩を望めないのはつらく、曲の妙味を堪能するに及ばなんだ、っその点、小川女史は流石で、カーチュン氏の棒と同様に、曲想毎に当意即妙に音の表情が豹変せる、
っわずかに睡かったので、15分の休憩も外出しないで自席で瞑目しておくようにしたが、っそれでもシムフォニーではずっとやや睡かった、音響バランスは、っきのうより好転した面もあるが、舞台を右っ肩から見下ろしているきのうのほうが、管打の実在感が豊富で、っよりたのしかった、っきょうの位置は、っもっと全体がよく融け合っており、っかなり舞台へ近いにも拘わらず、っぞんがい大楽隊の奏楽による風圧というものも感ぜられなく、っそうすると、好音響がそのまま快眠に打って附けの揺り椅子さながらでもあった、
っきのうはもっと、っずっと静かに運ぶ1楽章の透徹に絶妙の緊張を味わい、っそこで緊と、、、っひしとねひしと、張り詰めていたからこそ、一転、音響上の頂点を迎える2楽章では、身体が文字通りくわっくわと、、、っこれで読むときにはくわっくわなどと読まずにかっかと読んでくださいね、活字で誰それはくわっと激したなんて書いてあったら、読むときにはかっと激したと読まなくてはだめです、熱くなるのが感ぜられ、銃撃の惨状も冷徹な音構築で通過すると、っいっさいの味附けなく単旋律として顕われる3楽章の既成歌は、日フィルの燻銀のVaを味わうのに、っこれほど好適の場面もまたとあるまい、っついにフィナーレも、っじゅうぶんに熱しながら、っしかし主情に感ける幼稚さがなく、っいつも全体が周到に見渡されている、
っふだんからあまり聴かない曲だからそうした演奏でもおおきに昂奮するのだろうか、ったとえば、先般の彼等のマーラー《5番》は、公演直後には厭事はあまり書かないようにしたが、っとくにフィナーレが全体に音の腰がかるく、っもっとどすんずしんと来る演奏がぼくのこのみである、っきのうきょうの2楽章やフィナーレあたり、っぼくにはまことに必要にして十分と聴こえたが、っもっとたくさんこの曲を聴いている人にとってはどうだったのだろう、
日フィルはやはり、っすでにしてとても巧くていられるのに、っしかし各位がすこしくずつ無理をなすって、全体にぐうぃっちぐうぃちのひびきを出して来られるところがほんとうに素敵だ、っこないだのマーラー《トラギッシェ》や今次のように、大所帯で複雑な楽曲を奏する際はとくにそうで、《5番》が既のところで不満を懐かせたのも、っじつにこのぎっしりと中身の詰まった手応えを出し切れなんだがためにちがいない、ハレ管のシェフも務められるカーチュン氏で、っきょう現在、手許にはマーラー《復活》、ブルックナー《9番》と、2曲で日フィルと重複する音源が存るが、録音の性質にも依るかもしらんが、っぼくはハレ管よりも日フィルの鳴り方のほうが断然すきであり、カーチュン氏の音楽性にもよくお似合いだとおもう、自分がイギリス人でなく日本人で、日本に暮らしていて常時、日フィルを聴ける人間で、っほんとうによかったとおもう、
っそうだ、同フィルの定期会員券の仕組について、事務局へ電話などせずとも、公演の際に器で訊けばよいのではないかと気附くが、っゆうべは帰りしな、っその窓口へは大勢の人が集っており、遠慮したところ、っきょうの退場時には誰も並んでいなかったので、2、3の不明点をうかがって、っよく理解できた、っこんかいのように同一プロ公演で2日ともRCを購えないなどというのはとてもイヤなので、っやはり来季は、東京定期の2日ずつのうちかたっぽ、金曜がよいかな、土曜はほかのめぼしい公演とバッティングしてしまう惧れがあるから、金曜の年間券を購い、2日とも聴きたい月は、ったほうは1回券を購うとせむ、会員になっていると、日フィルの主催公演の切符は1割引で購えるらしい、創立記念公演のマーラー《1千人》も最優先で売ってくれるというので、っそれももちろん2日とも行かねばならないし、っぼくももうだいぶんおじさんとなって、っいつまでも若くときのように行きたい人の公演へっきり行かないなどという幼稚なことはしていないで、聴かず嫌いをせずいろいろの人を聴くほうがよいし、っしかし、人生だなあ、っまさかにある楽団の定期会員になる日が来ようとは、っそれが来季の日フィルであるとは、っこれもまた時宜よろしきを得たりというものか、っそして、1年こっきりですぐに止してしまうというのもカッコわるいので、っできれば再来年度以降も継続したいところである、
っさてあすは、池袋で都響公演、物故せられたすぎやまこういち氏の作をあれこれと集めた意慾的のプロである、棒は同団の大野氏だが、聴かず嫌いをすまいと云ったその舌の根も乾かぬうちに白状すれば、大野氏ってねえ、っこんなこと云ったら怒られちゃうけれども、っお顔からしてもう仕合わせじゃないんだよねえ、っお客を悦境へ攫いますって相貌をされていないんだよ、っあれがイヤでねえ、っま、っその侮りが覆されることを期待しているけれども、
っそれは午后で、午前には、佐藤雄一氏が師走に楽聖《㐧9》を振られるのだが、繁多の来場者が見込まれるからだろう、事前に整理券を入手されたいというので、ネットでの配布はなく、っわざわざそのためだけに取手くんだりまで往って来なくてはならない、彼氏の同曲は以前、フィナーレのみを、っしかも晴海の、音場ではなくその階下の、一般の人もぞろぞろ歩っているフロアで演奏さるのを聴いたっきりで、全楽章をちゃんと音場で聴く機会のあらまほしきこととおもっていたが、っついにそれを聴けるならば、っべつに整理券をもらうためだけにでも遠出をするのは苦でもなんでもない、っが、彼氏は、っぼくが聴くようになったころに関係されていた団体のうち、っより腕の利くところほど活動を休止されてしまったりで、っこちとら正直に云って、当初ほど熱心には聴けなくなっているんだよなあ、っやはりあの音楽性は、っまず相当度に精妙に弾ける楽団を得ないことには、っほとんど客席で聴いている意味がない、指揮者の性向のなかには、っお客として楽団が拙いことには目をつむって、脳内補完して聴くというか、っそれすらしないでも、オケが下手でも下手なままぜんぜんうれしく聴いていられるというか、っや、下手なことはうれしいことではないが、っつまり下手なことがまるで気にならない人と、客としてのそんな妥協をいくらしたってほんとうのほんとうには音楽を聴いている味わっていることにならない人といて、佐藤氏はまちがいなく断然に後者の人だ、演奏会が始まってさいしょの1音が出たときに、あ、オケが下手だ、っとおもわせるその水準の楽団では、申し訳ないが眞には佐藤雄一の音楽を達成することはできない、っそんなこと、誰指揮者にとってもおなじだが、っとくに佐藤氏はそうで、っぼくは交響楽団CTKや、最盛期の慶應医学部管を聴いてしまっているだけに、数年以前から佐藤氏の現状については気の毒におもうきもちがつよい、っこのせっかくの楽聖の大作の公演にしても、っざんねんながら、っそれほど期待を高く有つわけにはゆかないのである、
みずの自作アルヒーフ
《襷 ータスキー》(全4回)
https://ameblo.jp/marche-dt-cs4/entry-12351779591.html(㐧1回配本)
《ぶきっちょ》(全4回)
https://ameblo.jp/marche-dt-cs4/entry-12351806009.html(㐧1回配本)
《きりむすぶ》
https://ameblo.jp/marche-dt-cs4/entry-12935343873.html(㐧1回配本・執筆中・脱稿時期未定)
ギロッポン初日、補遺、
半日ばかりだと仕事をしたようなしていないような、っはんぶん申し訳ないきもちだ、
っさてゆうべ、カーチュン・ウォン氏の棒、日本フィル公演で、小川典子女史と同フィルのオットー氏とのソロでショスタコーヴィチ《1番》コンチェルト、っおよび同《11番》であった、
カーチュン氏は作曲家でもあられるが、っきのう聴いていると、っありとある瞬間がコムポジションとしての主張を為すのがいたく実感せられる、シムフォニーは表題楽の性格を有つが、っさようの具体的の場面場面を想起せしめる念力よりは、音々の組み立てを飽くまでも克明に追う冷厳のほうが前面へ出ている、彼氏の演奏へ不満を云う声はごくたまに見られるが、っあるいは、っそうした点がかえって澹泊な印象を與えている可能性もないとしない、っぼくとしては、っいっさいの楽章において動機という動機が、っつよいもよわいも速いも遅いも、っすべて等しく扱われること、っそれにより、先行楽章の動機が後続楽章へ組み込まれたり、ダブル・タームになったりする經緯も明瞭に伝わる、和音や楽器の選択、特殊な楽器法も、っいつも発音が明晰であってこそ、作家がそのそれぞれの筆へいかなる効果を求めたかがよくよく諒解せられる、っさようにして多様の物理音が集い、っひとつの音楽が組み上がってゆく様をただただ見守り、っそしてその時間は無上にたのしかった、
日フィルは、っそれこそ各声部とも顔のある愛すべきアンサムブルであるが、っそれが極まることにより、っついに日フィルであることを止めて、っなにか夢に聴く不朽不滅の楽団のごとであった、
っきょうもこれから、っまもなくそれが始まる、
みずの自作アルヒーフ
《襷 ータスキー》(全4回)
https://ameblo.jp/marche-dt-cs4/entry-12351779591.html(㐧1回配本)
《ぶきっちょ》(全4回)
https://ameblo.jp/marche-dt-cs4/entry-12351806009.html(㐧1回配本)
《きりむすぶ》
https://ameblo.jp/marche-dt-cs4/entry-12935343873.html(㐧1回配本・執筆中・脱稿時期未定)