前回、なぜゆうちょさんに日本人は預けるのか?
そしてデメリットは消費税増税分の話やコンビニATMを利用した際の手数料の方が
預貯金に預けた際の利息よりも多いじゃん?
の内容にとても分かりやすいとの声をいただき嬉しい限りです。
読んでない方はこちら
https://ameblo.jp/kms2/entry-12455196034.html
今日のテーマは『個人金融資産の日米比較』と称して
金銭教育にたけていると言われるアメリカの国民はどうなのだろうとみてみましょう。
【日本とアメリカでは預け先が全く違う!?】
日本では多くの方がお金を都市銀行や郵便局(ゆうちょ銀行)に預けていることはすでに書きました。
しかし、実際にどれくらいの資産を預貯金として預けているのでしょうか?
日本銀行調査統計局が2017年8月にまとめた資料があります。

日本人は現金と銀行への預貯金が資産のうち、
半分以上を占めていることがわかります。
対して「金融先進国」といわれるアメリカでは、なんとたった13.4%!
アメリカ人は現金や銀行預金をほとんど持っていないのです。
代わりに多く持っているのが「株式」。日本と比較すると3.5倍になります。
ほかにも「債務証券は日本の4倍、投資信託も日本の2倍多く、
金融資産として保有しているのです。
「保険・年金・定型保証」に関しては、保険大国と言われる日本とはほとんど差がありませんね。
ただし、じつはその中身には大きな差があると言われています。
日本では資産を作る際に、養老保険、学資保険、個人年金といった定額保険と言われる積立保険などが人気なのに対し、
アメリカでは変額保険を活用した積立保険が人気。
つまり、資産運用としての保険の中身が大きく違うのです。
(どう違うのか詳しくはまた別の機会に記載しますね)
【預け先が違うから、増えかたも違う!】
日本人とアメリカ人では資産の預け先(運用先)がまったく異なることがわかりました。
しかし、いくら両者が違うといっても、日本人の資産の方が増えていれば、アメリカ人のことを気にする必要なんかありませんよね。
2017年3月末現在、日本の家計の金融資産合計は1809兆円で、アメリカは77.1兆ドル。
ややこしいので、1ドル=100円として、7710兆円としましょう。
では27年前、1990年の両国の金融資産合計はいくらだったのでしょう?
日本 982兆円(1990年)⇒⇒⇒1809兆円(2017年)
アメリカ 1740兆円(1990年)⇒⇒⇒7710兆円(2017年)
つまり1990年から2017年の27年で、日本人は資産を1.84倍に増やしました。
対してアメリカ人は4.43倍に増やしているのです。
これこそが預貯金に頼る日本人と、株式や投資信託を活用し、
資産をうまく運用するアメリカ人との大きな違い。
このままでは、預貯金で眠らせているだけのあなたの資産も、
きっと増えないままとなることでしょう。
では、どうしたらお金を増やせるのでしょうか?
海の向こうの方々は我々日本人と何が違うのか?
一緒に考えていきませんか?
近藤正樹プロフィール
IFA
お金の小学校代表
チーム★ライフプラン研究会 認定講師
キッズ・マネー・ステーション 認定講師
昭和50年6月18日生まれ
神奈川県川崎市出身。早稲田大学社会科学部卒業
学生時代に好きだった小劇場のパワーあふれる舞台俳優の影響を
受け20代を舞台俳優の活動に専念する。
多くの金融機関の方が専門知識を難しい言葉で話す姿に違和感を覚え、
舞台俳優・落語で得た知識と経験を元に、誰もが悩むお金と人生の関係を、
だれもが知っている昔話「桃太郎」を使って
人生とお金の関係をわかりやすく紐とくなど、親しみやすいマネーセミナー講師として活動。
近年では親子向けのお金の教育にも力を入れている。
家庭に帰るとスキー指導員の資格も持つ、10歳と3歳の父親。
著書:「お金の小学校」(一間堂)
「誰か教えて!一生にかかるお金の話」(中経出版)
記事掲載:新日本保険新聞・「美的」「DIME」など
マネーセミナー「お金の小学校」随時開催中
次回開催 6月5日19時~お金の小学校・6月12日19時~お金の中学校
お得なクーポンは以下から
ホームページ https://www.okanenoshougakkou.com/








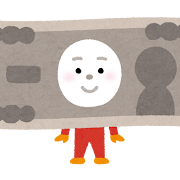





 」や「お金は難しそう
」や「お金は難しそう 」って思い込みを捨ててご自身のお金と向き合ってみてくださいね
」って思い込みを捨ててご自身のお金と向き合ってみてくださいね



