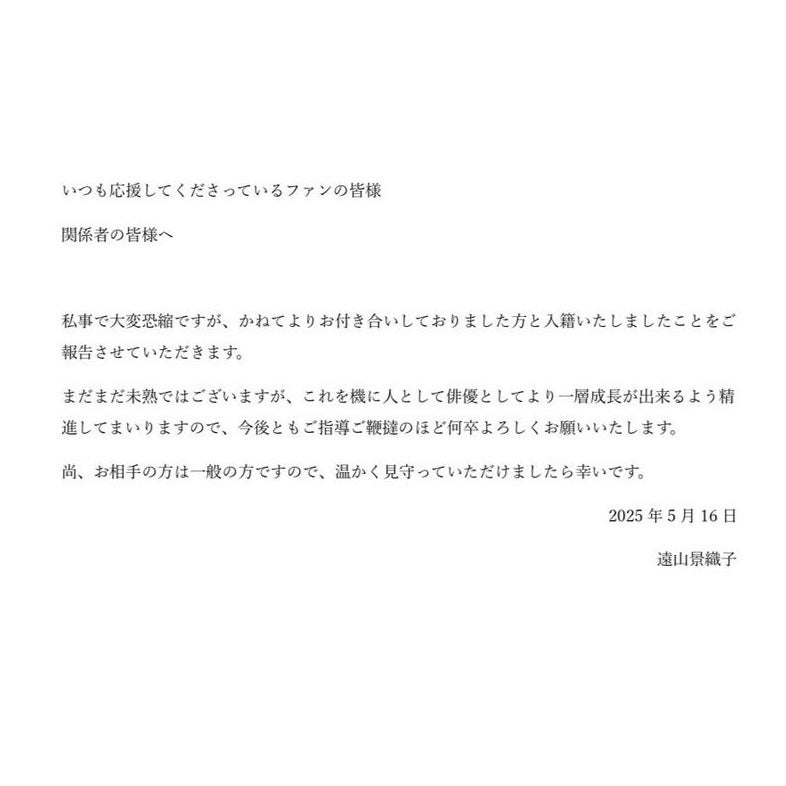*既に多くの「いいね」を頂いていますが、大幅に改定を施すため改定記事として再UPします。
■表記
「勘注系図」 … 建田勢命
「先代旧事本紀」 … 建田背命
「丹後舊事記」 … 神服連海部直(カムハトリノムラジアマベノアタヒ)
*海部直、海部直命と表記されることも多い
■概要
彦火明命の六世孫。海部直・丹波国造・但馬国造・神服連などの祖。初代「丹後国王」とも言われる建諸隅命(由碁理)の父。
◎「勘注系図」には以下のように記されています。
━━大日本根子彦太瓊天皇(孝霊天皇)御宇、丹波国丹波郷に於いて宰(みこともち、=国造)となり奉仕した。山背国久世郡水主村に移り、山背直等の祖となり、更にまた大和国に移る━━
つまり大和国から派遣され丹波国造(丹後国が分離する以前)となり、山城国久世郡水主村を経て、また大和国へ戻ったというもの。「山城国久世郡水主村(みずしむら)」については現地に水主神社が鎮座しています。
◎建田勢命が丹波(丹後)で拠点としたのは、熊野郡海部郷(海士郷)。読みは「海部(かいべ)」「海士(あま)」。現在の京丹後市久美浜町「海士(あま)」。おそらく古代は「海部(あま)」であったかと思います。
海部氏が與謝郡へ移る前の拠点であったと思われます。
◎「丹後舊事記」(文化七年・1810年成立)には、主要な神名が列記される中で2番目に記載、1番目は子の笛連王。
━━王代任国入館跡の事
神服連海部直
古事記や先代旧事本紀には、神服連海部直は皇孫(彦火明命)六世孫で、丹波国造・但馬国造の祖とあります。第7代孝霊天皇(大日本根子彦大瓊尊)の御世の時の館跡が今もなお、丹後国熊野郡「川上庄海部」の里に「殿垣六宮廻(ろくのまわり)」という田地の字があると、細川忠興の「順国志」にあります。王代が住んだ地を我が名とする例は多くあります。川上庄は丹後国の国府の始まりです━━(大意)
(→【丹後の原像】第58回の記事参照)
「殿垣六宮廻」とは上記の通り、式内社 矢田神社の境内または北隣とされます。
◎続いて記される子の笛連王にも関連する記述がみられます。
━━笛連王
「古事記」が言うには、神服連海部直の子であると。母は櫛名櫛媛。孝元天皇(大日本根子彦國章尊)に仕え奉り、父の国府跡を領有し、與佐(吉佐、与謝)の「比治山」の麓の「笛原」を国府としました。細川忠興の「順国志」が言うには、「比沼眞名井ヶ原」の辺り「五箇」の「本庄本ヶ村」に、「砂山」という高山があり、麓に磯砂山(いさなごやま)笛寺という真言宗の伽藍があります。「和哥名所志」に「笛の浦」と記されます。山中に海部の名がある名所としています。これは笛連の館跡です━━(大意)
(→【丹後の原像】第59回の記事参照)
◎父は建斗米命、母は中名草姫。「先代旧事本紀」によると兄弟は以下の通り。
建田背命・建宇那比命・建多乎利命・建彌阿久良命・建麻利尼命・建手和邇命・宇那比姫命
*「勘注系図」は建田勢命・建田小利命(建多乎利命)・宇那比姫命のみ
◎建田勢命が山城国へ移住。すると丹後の長は次男の建宇那比命が継いだのであろうと思われます。その子の笛連王が丹波郡五箇庄に国府を営んだとされています。「五箇庄」は豊受大神が降臨したとされる「磯砂山(いさなごやま)」の地。現在の京丹後市峰山町「五箇」。
◎神名、後裔の神服連という氏族名から、機織を職掌としていたものと思われます。
丹後には天女が機織を伝えたとされます。大陸からの玄関口でもあり、弥生時代には早くも伝わっていた可能性もあると考えています。後の天平十一年(739年)に竹野郡鳥取郷から貢上されたという「絁(あしぎぬ)」や、「丹後ちりめん」もこの素地があったからではないかと。
◎建麻利尼命は山邊御縣坐神社(天理市別所町)、山邊御縣坐神社(天理市西井戸堂町)で祀られています。山邊縣主の祖。
◎宇那比姫命は第5代孝昭天皇皇子 天足彦国押人命の妃または后で、和珥氏の祖。
■祀られる社・関連社(参拝済み社のみ)
[丹後国熊野郡] 矢田神社(京丹後市久美浜町海士)
[山城国久世郡] 水主神社
[但馬国] 海神社(豊岡市小島)
*関連社
[丹後国熊野郡] 陵神社
*境内社等
[越後国] 彌彦神社(境内摂社 勝神社)
[美濃国] 伊富岐神社(不破郡垂井町)(境内社)
[丹後国熊野郡] 陵神社

[但馬国] 海神社(豊岡市小島) 境内磐座
*誤字・脱字・誤記等無きよう努めますが、もし発見されました際はご指摘頂けますとさいわいです。