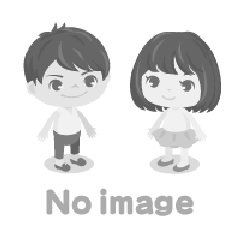動詞の活用の種類についてつづき。
日本語を母語とする人が国語の授業で学ぶ「国語文法」では、「動詞の後ろに『ない』をつけた時、その直前の文字が『アの段』だったら『五段活用』と習うことがあると思う…というのは既に書いた。
日本語の母語話者なら、「飲む→飲まない」「書く→書かない」のように、無意識かつ自動的に、なぜそうなるのか考えずに「飲む→飲ま」「書く→書か」に変換させることができ、「ま」「か」が「アの段」だから「飲む」「書く」は「五段活用」と知ることができる。
でも、日本語を母語としない人は、この「自動変換」ができないから、動詞を学ぶ際にはグループも一緒に覚えないといけない。ドイツ語やフランス語の名詞を学ぶ時に性別も一緒に覚えるような感じかな。
日本語を母語とする人でも、この見分け方を忘れてしまって、社会に出てからふとした時に「『食べれる』『変えれる』は『ら抜き言葉』だから、『帰れる』も『ら抜き』だっけ…??」とか悩んでしまうことがある。この時に、「食べる」「変える」は「下一段」で、「帰る」は「五段」ということを思い出すことができれば、悩みが解決する。
で、この「後ろに『ない』をつけた時…」の見分け方なんだけど、実はこれよりわかりやすい見分け方がある。
辞書に載っている形(国語文法では「終止形」、日本語文法では「辞書形」)の最後の文字が「る」以外の動詞は全て五段活用(グループ1)
五段活用(グループ1)の動詞には、「買う」「書く」「話す」「持つ」「死ぬ」「呼ぶ」「飲む」などがある。このように「る」以外の文字で終わるものは全て五段活用(グループ1)。このルールを知らない人が意外と多い。私自身も、国語の授業の時に聞いた記憶はない。先生は言ってたけど私が覚えてないだけかも…だとしたらすみません…。
でも、実際、手元にある国語文法のテキストの「五段活用」の説明の部分にも
「『話す』の活用語尾が『さ・し・す・せ・そ』と変化するように、五十音図の五段にわたって語形が変化するもの。」
と書いてある。これはたしかにそうなんだけど、「『る』以外の文字で終わるのは全部『五段活用』」というのもわかってると、活用の種類の見分けにものすごく役に立つと思う。
このルールを知っていれば、「飲む」「書く」は、どちらも「る」以外の文字「む」「く」で終わってるから五段活用(グループ1)とすぐにわかる。後ろに「ない」をつけるとかそういう作業は必要ない。
ただし、注意が必要なのは、
「『る』以外で終わる動詞は全て『五段活用』」は、「『五段活用』は全て『る』以外で終わる』を意味しない。
ということ。つまり、「る」で終わる五段活用(グループ1)動詞も存在する。代表的なのが、上に書いた「帰る」。日本語学習者も早い段階で学ぶ基本的な動詞だ。
簡単にまとめる。
グループ2(上一段、下一段)と、グループ3(カ変、サ変)は全て「る」で終わる。
グループ1(五段)は、「る」で終わる動詞と、「る」以外の文字で終わる動詞がある。
だから、日本語母語話者が五段活用の動詞を判定する際には、
1.「る」以外の文字で終わる動詞の全て
2.「る」で終わる動詞のうち、後ろに「ない」をつけた時に直前が「ら」になるもの
というのが目印になる。便利なのでよかったら使ってほしい。
ちなみに、日本語を母語としない人は、1のルールは使えるけど、2は使えない。彼らには、「『ら』で終わるグループ1動詞」と「グループ2の動詞」の見分けがつかない。見かけ上同じだから。例えば、同じ「かえる」でも、「帰る」はグループ1で「変える」はグループ2。これの見分けがつくのは母語話者だけ。
じゃあどうすればいいか?つづく…。