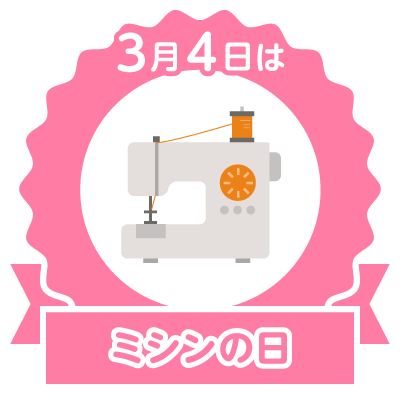ミシン持ってる?
▼本日限定!ブログスタンプ
今日はミシンの日
すっかり忘れてました。
就活で長いことブログを開かないうちに。。。
仕事柄私は家庭用ミシン二台と職業用ミシン一台、ロックミシン三台、工業用ミシン一台所有してます。
昭和の時代はどの家庭もホームソーイングは当たり前でお母さんが家族の服を作るのは当たり前、町には生地屋さんが必ずありました。
ミシンは嫁入り道具の一つでした。ミシンは一生モノです。
長い昭和の時は流れ、昭和の終わりにはミシンをかけれる女子もかなり減って嫁入り道具には含まれなくなっていました。
さて
時々これからミシンを買いたい人から相談を受けるのですが、
少しミシンのアドヴァイスを。
ミシンの相談のタイミングは2つあるような感じです。
一つには赤ちゃんが生まれる前。
妊娠期間、自分で赤ちゃんのお洋服や小物、ママバッグ的な袋物など作りたいのでミシンが欲しい。
二つには子供が幼稚園に上がる前に色々作らねばならない課題ができた、という相談で。
何を作っていきたいのか、
どのくらいの頻度で利用したいのか、
細かいこと言うと、(主には)どんな生地を頻度高く使うのか、
などなど
ミシンを買う前に自分の希望や理想を書き出してポイントを押さえてみましょう
上にあげた二つのきっかけで購入する人が多くて、そのきっかけだと刺繍の機能を求めている人が多くて、家庭用ミシンだとアルファベットやひらがな、カタカナなどの機能がついているものもありますね。
それ以上にディズニーのキャラクターや写真のトレースを刺繍に出来るようなかなり高級なミシンも店頭のデモンストレーションで見たこともあるでしょう。
結構、相談の時にこのン十万もするコンピューターミシンを欲しいけれど高すぎて悩んでいる。と言うことを必ず言われます。ほぼ必ず。
まぁ店頭で見ると面白そうだし、自分の手によって簡単にこんな凝ったものができるなんて使いたくなる気持ちは私にもあります。
が!本当に正直な話、コンピューターミシンを買って、購入後もずっと使っていると言う話は一度たりとも聞いたことがありません。
買った時は盛り上がる、って言うのは何にでもある話ですがそれにしても1回使ってもうやらないと言うには高すぎる買い物です。出すにもべらぼうに重いのもあって余計使わなくなってしまう、と言う負の相乗効果もあります。
ミシンを買うときのポイントは、「余計な機能はいらない、コンピューターミシンでなくていい。」と言うことでしょうか。
子供の手提げだけでなくミシンにはまってしまって自分のスカートやワンピースも縫うようになった。なんて言う人は自ずとロックミシン欲しくなりますね。
ロックミシンも高価なものですし、頻度や出し入れ、置き場など考えたらすぐには買わないでミシンのジグザグ縫い機能を使うとか、私の友達が持っていたのですが家庭用ミシン一台の中にロックミシン機能がついたミシンがあって、それが見つかると場所も取らないし出し入れの手間も一つ減っていいですよね。
結論はミシン買うのであれば直線縫いとジグザグ縫いの二つの機能で十分です(あと一台にロック機能があるものが見つかれば)そもそもいろんな機能がついてるのは家庭用ミシンだけで職業用も工業用も直線縫いのみです。
プロの人から見るとシロウト向けに色々買わせちゃう魂胆にしか見えないと言う。。。
刺繍は大概買った時だけで使いません。そして通常機能のミシンの10倍くらい高いので押入れの肥やしになるには「・・・」です。
本気でミシンにハマろう、って人は値段は高くなりますが職業用ミシンならおすすめです。形状は家庭用ミシンと変わらないですが馬力が違うので厚手のデニムや革なども縫えてしまいますし縫い目がとても綺麗です。
ここにはったブラザーのヌーベルはとてもいいですよ!
ではもうすぐ4月。春に向けて通学グッズや軽やかなお洋服を作りましょう!