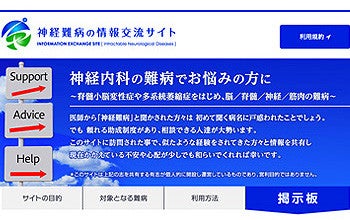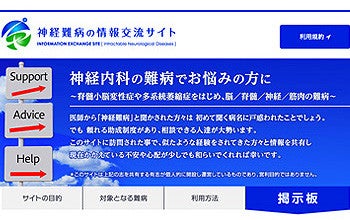長らく抱いていた疑問。
それは、
『何故、性善説社会の日本(やまと)民族が、地球上で生き延びて来れたのか?』
性善説社会の民族が性悪説社会の民族に勝てるわけが無い(少なくても個としては)のに、日本(やまと)民族が今日まで生き延びられた理由が知りたい、ということである。
日本(やまと)民族は、島国という立地故に、典型的な、そして世界でも稀有で純粋培養的な「性善説社会」を形成した。
それに対する極端な「性悪説社会」なのがアラブ遊牧民。
他の民族は、日本(やまと)民族とアラブ遊牧民の間の何処かに位置する。
そのことは、歴史背景も文化も生活環境も極端に違う極限の民族とも、生活を共にすることで最後には分かり合い信頼関係を築けた、と言う感動のルポルタージュ(「カナダエスキモー」および「ニューギニア高地人」)で有名になった本多勝一氏が、それらの成功体験を引っさげて新たな極限の民族に挑んだ「アラビア遊牧民」の中にも記されている。
ここで本多勝一は手痛い挫折を経験することになる。
その失意を、(無理やり?)日本人の特殊性の発見と位置づけて、極限の民族に対するボロクソな批判(悪口?)と共に綴った1冊となってしまった。
アラブの大学に2年間も留学していた経験のある私にはよく理解できる。
「悪く見える瞬間が有っても人間の本質は善良(性善説)」と考えている人と、「人間の本質は悪。良く見える時は何かを企んでいる(性悪説)」と考えている人とが、分かり合えるはずがないことが。
性悪説側が性善説側に良くしようと接するのは、例外なく何らかの悪企みを持っている時で、性善説側が性悪説側に少しでも近づくために相手に良くしようと思えば思うほど、性悪説側は疑心暗鬼になるのだから取り付く島がない。
(ご興味をお持ちの方は以下投稿もご参照下さい。)
・アラブ の対局にある 日本
・ベドウィンの誇り
・アラブとの対比に思うこと
個人対個人の戦いを想定すると、どう考えても性善説側に勝ち目はない。
何故なら、常に相手を疑うことを是として、心のなかに(時には物理的にも)ナイフを秘めた相手に対して、精神的にも物理的にも丸腰で無防備に戦いを挑むのと同じだから。
それと分かりつつ性悪説一辺倒の相手と戦うならまだ手段もあろうが、性善説のふりをして信頼を勝ち取った後に性悪説の牙をむく、そして個々人が拳銃を所有しているような民族に対しては勝ち目がない。
前述の私の疑問は、こうした背景の中で、
『そんな純粋培養的な性善説社会にどっぷり浸っていた日本(やまと)民族が、日本よりも性悪説的な国々ばかりの地球上でどうやって生き延びて来れたのか?』
ということ。
「集団(組織)」がキーワードだと考えていたが、その科学的裏付けがこの本の中にあった。

『「シャーデンフロイデ」とは、他人を引きずり下ろしたときに生まれる快感のこと。成功者のちょっとした失敗をネット上で糾弾し、喜びに浸る。実はこの行動の根幹には、脳内物質「オキシトシン」が深く関わっている。オキシトシンは、母子間など、人と人との愛着を形成するために欠かせない脳内ホルモンだが、最新の研究では「妬み」感情も高めてしまうことがわかってきた。なぜ人間は一見、非生産的に思える「妬み」という感情を他人に覚え、その不幸を喜ぶのか。現代社会が抱える病理の象徴「シャーデンフロイデ」の正体を解き明かす。』
(本書裏表紙から転用)
著者は脳科学者の中野信子氏。
「愛情」が脳内物質の分泌で説明がつく、という著者の主張は何とも味気ない話だが、そう考えると納得できる部分もある。
詳しいことは本書を読んでいただくとして、子宮頚部への刺激や射精によって分泌が促されるとされる脳内物質「オキシトシン」は、「幸せホルモン」とも「絆ホルモン」とも呼ばれ、人間同士の信頼関係を構築するために必要な脳内物質なのだそうだ。
肉体的に恵まれていなかった人類が他の動物にジャングルから追い払われて、平原で巨大生物との戦いを制して生き残れたのは、集団の力のおかげと言うのは定説である。
それを助けたのが「オキシトシン」の働きだという。
更に、肉体的に圧倒的に勝っていたネアンデルタール人が肉体的に劣るホモサピエンスに淘汰されたのは、ホモサピエンスがより集団行動に秀でていたからと言われている。
即ち、「オキシトシン」の働きがより活発なDNAが生き残った、と考えられる。
日本(やまと)民族は、多民族より「オキシトシン」の分泌が多いDNAを持っていたことと、恵まれた自然環境を要因として、他人との信頼関係を築き易く、それ故に集団を形成し易い、性善説社会を構築したと思われるが、それだけでは弱点にもなりうる。
忘れてならないのは、集団を保つための優れた制度を確立していたことだろう。
集団を保つためには内部崩壊を避けなければならない。
内部崩壊を避けるためには、その集団固有の秩序の形成と保守の仕組みが必要で、現在も残っている典型が官僚制度だ。
官僚が所属する組織の維持しか考えていないのは改めて言うまでもない。
官僚の優先順位は、① 組織の存続、② 利権(≒予算)の確保・拡大、③ 天下り先の確保・拡大、で、それらに対する貢献度によって在任中も退任後も人生が180°変わる。
時にはそれらに命すらも賭けるが、本来尽くすべき納税者のことなど歯牙にも掛けない。
上の言うことは絶対で、パワハラが当たり前の世界。
官僚に限らず、一般企業でも、仕事上は大した実績も上げていないのに出世する輩が大勢いる。
大抵は上司に媚びへつらうだけが取り柄のような輩で部下からは軽蔑されている。
だが、見方を変えると上意下達こそが組織維持の要とも言えるから、その観点から言うと当然の人事ということになる。
集団を維持するために必要なことは、集団を内部崩壊させる可能性のある異端児候補が顕在化する前に排除することである。
出る杭は打たれる。誰かが突出した活躍をすると、必ず大したこともしていない誰かが足を引っ張る。
企業などで下手に手柄を立てて発言力を持っている異端児には、その組織内での出世の目は無いのである。
コロナの女王と言われる岡田女子が突然叩かれ始めているのもこの一環だろう。
ホリエモンを始めとしてその犠牲になった人は数え切れない。
半沢直樹など、実在し得ないからこそドラマになるのだ。
もう一つ集団を崩壊させないために必要なことは、集団の構成員に公平感をもたせておくことであり、能力の差はさておいて自分だけが割りを食っているとか、誰かだけが得をしているとか言うことが無いようにすることである。
それを達成しようとすると、低い方にレベルを合わせる悪平等と、損得帰属情報の隠蔽が発生する。
この結果、優秀な人材が育ち難い上に、仮に育っても集団には居辛いために国外に流出してしまう。
本書では、自分自身で意思決定したいと考えている人が、ヨーロッパでは60%近くなのに対して日本人では僅かに27%しか居ない、と指摘している。これにはドーパミンが深く関与しているようなのだが、説明は本書に譲るとして、自らの意思ではなく集団の指導者の意思に従うことで集団を維持し易くするDNAの所持者が日本人には多い、と言うことでそれが日本に集団の秩序を根付かせた。
従順で盲目的な秩序の特性は、新型コロナウィルス対策にも効果的かも知れない。
更に、集団の正義をかざした人間がどれほど冷酷な攻撃者に変貌するか、それも自らの意思を持たない人間の方が極端であることの実験結果が提示されている。
宗教が戦争を生み出す数々の歴史的な事実や、過激なネットバッシングなどを引き合いに出すまでもなく、実感に近い実験結果である。
「村八分」、「村十分」、「出る杭は打つ」、「平等」、など集団の秩序を守るための制度が、「いじめ」、「(ネット)集団バッシング」、「出る杭は打たれる」、「悪平等」、「隠蔽体質」、等の副作用と思しき事態を生んでいる状態は、
『「シャーデンフロイデ」自体は忌むべき感情だが、それが人類が生き延びるための副産物だったとは皮肉である。』
との本書の趣旨と符合してしまう。
さて、これまではこうして生き延びてきた日本(やまと)民族だが、これからも同じやり方で生き延びられるとは限らない。
また、副作用のデメリットが、情報技術の進化にも後押しされて、メリットよりも大きくなってきているような気もする。
数十万年を掛けて人類が培ってきたDNA特性を短期間に変えられるとは思わないが、DNAの呪縛から理性で逃れることは出来るかも知れない。