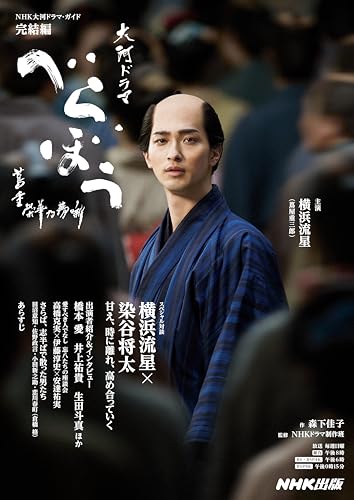3年ぶりの上演

東京バレエ団 『ドン・キホーテ』
つくづく思ったんだけど バレエの『ドン・キ』はやっぱり
ロシア系が、よろし。

変にこねくり回してなくて、
純粋に パワフル & エネルギッシュ & エキサイティング
見たぁ~ って感じがするっ
って感じがするっ
このプロダクションが初演されたのは 2001年6月。
それまで 男性ダンサーが充実したバレエ団なのに 何でレパートリーに入っていないんだろう? て思っていたから “満を持して” てな印象だった。

しかも、ボリショイバレエ団 レジェンドのウラジーミル・ワシーリエフの演出。
彼は もう、バジルを踊るために生まれてきたバレエダンサー
出来上がったプログラムは勿論だけど、その過程 -どうやって作品を創り上げていったか― ていうのも、スゴく気になる。実際
「初演らしい気迫と初演らしからぬ周到さ」
「日本のバレエもついにここまで来たか」
と、初演時に大絶賛されたんだって。
最初に観たとき(2004年再演時) ドン・キホーテの夢の場面の淡い青を基調とした美術がとっても綺麗なのがすごく印象に残った。

あと 広場や酒場の群衆たちの一体感となった盛り上がりがホント、ヤバい。
大抵(特に海外のバレエ団とか)舞台上の演者が 思い思いにお芝居していて、それはそれで楽しいけど 観てる方は 目が二つじゃ足りなくてあちこちキョロキョロしちゃうのよ。
だから、みんなが一斉にタンバリンを叩きながら 主役の二人をはやし立てて盛り上げる踊りにはとっても高揚する。
子役ダンサーも大活躍。
夢の場面のキューピットの場面が凄く可愛かった。
キューピットのバリエーションの間、ちびっこキューピットたちが 舞台奥で腹ばいになって肘をつきながら 音楽に合わせて足を交差したり 手をひらひらさせたりしていて。
子どもならではの魅力の演出。
前に観た時、こんな場面あったっけ???
全2幕(通常3幕)にまとめられているから、スピーディーで集中力も途切れず楽しめた。
そして 今回、ゲスト・プリンシパル 上野水香さんが東京バレエ団における最後の『ドン・キ』になるんだとか。
滅多にない バレリーナの国内バレエ団移籍から いつの間にか 20年以上。
移籍後 初の全幕主演が海外公演での『ドン・キホーテ』だったって。
おきゃんな元気娘;キトリは彼女によく似合っている。
このワシーリエフ版、幕開きからいきなり主役の二人が登場して 床屋のバジルがドン・キホーテ宅でお仕事して、近くでキトリがちょっかい出しているような演出。
これじゃ、広場の場面で それぞれが登場したときの盛り上がりがうすれちゃんじゃない?とか、
ドン・キホーテが広場でキトリを見て 憧れのドゥルシネア姫と思い込んでしまうストーリーの辻褄が合わなくなっちゃうじゃん、て ツッコミ入れたくなっちゃう。
そうしたら、おもむろに キューピットが登場して(ドン・キホーテにしか見えていない? ← 幻覚??)ハートを射抜かれて キトリが憧れの姫になっちゃった、ということらしい。
プロローグで姿を見せていても、第1幕の広場の登場の場面では、やっぱり プリマ参上! 的にひときわ大きな拍手が沸き起こっていた。
男性の片手で持ち上げられるリフトでも 客席にニッコリ笑顔を向けて余裕綽々。
バジル役は 当初予定されていた キミン・キム(マリインスキー劇場バレエ)が怪我で降板してしまって、ヴィクター・カイシェタ(ウィーン国立バレエ団)になったけど、お調子者で飄々としたいかにもラテン系のダンサー。
まるで 二人でおしゃべりしているみたいな息の合った踊り。
やっぱり 『ドン・キホーテ』はこうでなくっちゃ 

11月19日 東京文化会館大ホール所見
振付:マリウス・プティパ、アレクサンドル・ゴールスキー、カシアン・ゴレイゾフスキー、ウラジーミル・ワシーリエフ
新演出・振付:ウラジーミル・ワシーリエフ
音楽:レオン・ミンクスほか
美術:ヴィクトル・ヴォリスキー
衣裳:ラファイル・ヴォリスキー
キトリ/ドゥルシネア姫:上野水香
バジル:ヴィクター・カイシェタ
ドン・キホーテ:高岸直樹
サンチョ・パンサ:後藤健太朗
ガマーシュ:樋口祐輝
メルセデス:政本絵美
エスパーダ:柄本 弾
ロレンツォ:岡﨑 司
【 第1幕 】
2人のキトリの友人:三雲友里加、中川美雪
闘牛士:生方隆之介、安村圭太、鳥海 創、中嶋智哉、南江祐生、本岡直也、陶山 湘、小泉樹聖
若いロマの娘:平木菜子
ドリアードの女王:中島映理子
3人のドリアード:加藤くるみ、中沢恵理子、長谷川琴音
4人のドリアード:金子仁美、涌田美紀、工 桃子、安西くるみ
キューピッド:足立真里亜
【 第2幕 】
ヴァリエーション1:三雲友里加
ヴァリエーション2:中川美雪
指揮:アントン・グリシャニン
演奏:東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
協力:東京バレエ団OB・OG、東京バレエ学校
~上演時間~
第1幕 19:00~20:10
休憩 20分
第2幕 20:30~21:20